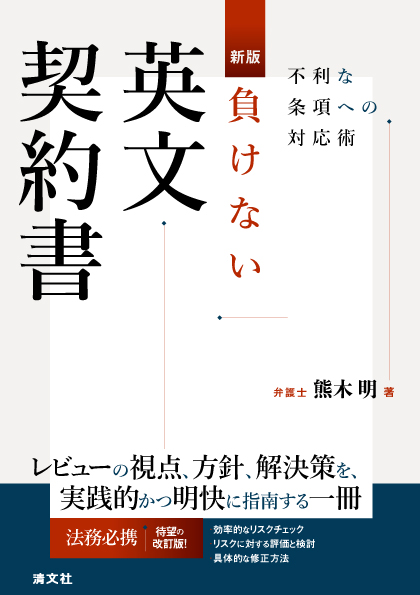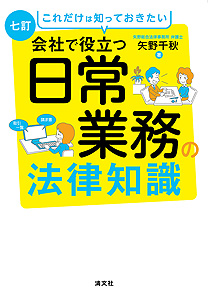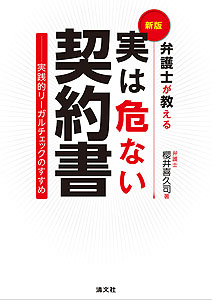コーポレートガバナンス・コードのポイントと
企業実務における対応のヒント
【第1回】
「はじめに」
~コーポレートガバナンス・コード(原案)の確定と企業への影響~
あらた監査法人 パートナー
公認会計士 小林 昭夫
〔コーポレートガバナンス・コード(原案)の確定〕
2014年12月に金融庁から公表された「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方(案)コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために~」(以下「コーポレートガバナンス・コード原案」または「コード」という)が、パブリック・コメント期間を経て、いよいよ最終版として確定することになった。
コーポレートガバナンス・コード原案の策定のために、2014年8月から金融庁と東京証券取引所を共同事務局とする有識者会議が開催されていたが、2015年3月5日に開催された第9回において、コードの最終稿が示されている。
昨年12月から本年1月にかけて実施されたパブリック・コメントでは、国内・海外から合計121の団体・個人からのコメントが寄せられたが、その大部分は肯定的ものであったとのことである。公開草案からは修辞的な修正がいくつか入ったものの、概ね草案どおりの内容のまま確定することになる。
本シリーズでは、コーポレートガバナンス・コード原案のポイントをわかりやすく解説するとともに、企業実務における対応のヒントを全10回シリーズにてご説明したい。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをお断りしておく。
〔上場制度の整備状況〕
このコードは2014年6月に閣議決定された政府の成長戦略(日本再興戦略 改訂2014)を受けて導入されようとしており、序文にも記載されているとおり、企業の「稼ぐ力」の向上をその狙いの一つとしている。「攻めのガバナンス」という言葉が象徴的に使われているように、経営陣の健全なリスクテイクを後押しすることが期待されている。さらに、企業と投資家との建設的な対話を促進することによって、企業の持続的成長を促すことが意図されている。
コードの最終化と並行して、上場企業が実際にこのコードの要求事項を実行に移すために、東京証券取引所の上場制度の整備が検討されている。既に2015年2月24日に東京証券取引所から上場制度整備案として「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備について」が公表されており、2015年3月26日までがパブリック・コメント期間とされている。
上場制度整備案では、
① コードを企業行動規範の「遵守すべき事項」に位置づけること
② 新興企業向け市場(マザーズ・ジャスダック)については、コードの基本原則部分についてのみ実施しない場合の説明を求めること(翻って原則および補充原則部分については説明を求めない)
③ 「コードを実施しない場合の理由の説明」のために、現行のコーポレート・ガバナンス報告書に欄を新設すること
④ コーポレート・ガバナンス報告書は初年度に限り定時株主総会後6ヶ月後までの提出とすること
⑤ 独立役員の独立性に関する情報開示の整理(従前の「要説明」の類型(いわゆる開示加重要件)を廃止し、「要開示」の類型に統一)
などが記載されている。
〔企業はどう対応すべきか〕
コードおよび上場制度整備案では適用時期を2015年6月1日としており、3月決算上場会社はあまり時間のない中で、本年の株主総会時期に向けた対応準備を行う必要があるが、コードが原則主義(プリンシプルベース・アプローチ)やコンプライ・オア・エクスプレインといった、日本企業にあまり馴染みのないコンセプトを採用していることもあり、対応方法について模索している企業も多いように思われる。
コードの要求事項に関しては、独立取締役2名以上の選任(原則4-8)について取り上げられることが多いが、その他にも体制整備や開示などを求める事項が多岐にわたって記載されている。
これらのコードの要求事項を個別に捉えて、実施しない説明を避けることに注力するあまり、拙速な対応になってしまうことはコードの趣旨に沿っているとは考えられない。むしろ、自社の状況、すなわち業種、規模、事業特性、機関設計、環境を考慮して、自社のあるべきガバナンスの方向をあらためて考える機会とすることが期待されていると捉えるべきであろう。自社が目指すガバナンスの姿には、すぐに到達しない場合も考えられるので、数年をかけて実施を目指す事項が出てくることもあり得ると思われる。
さらに、コードへの対応は、取締役会や監査役会に加え、企業の様々な部署(法務・IR・総務・企画・財務経理・内部監査等)に関連した取り組みになるものと想定される。実効性のあるガバナンスへの取り組みには、経営陣の主体的な関与が不可欠であることは言うまでもない。
本コードの策定・導入に際しては、国内外の企業や投資家からの高い関心が示されている。日本企業のコーポレート・ガバナンスの向上と企業価値の向上に向けた、企業と投資家との建設的対話を促すための取り組みに対し、これまでは概ね肯定的で高い評価が得られているようである。
コードを実際に適用していく企業には、コード導入の趣旨を忖度し、企業価値の向上とガバナンス向上のために実効性のある取り組みを進めていくことが期待されている。
(了)
「コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント」は、隔週で掲載されます。