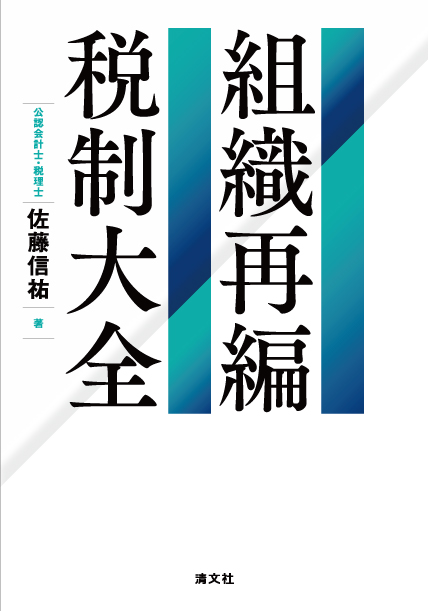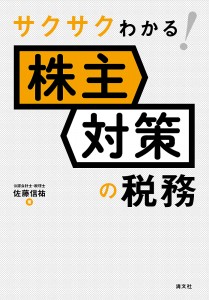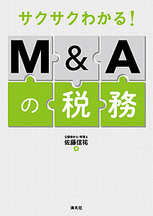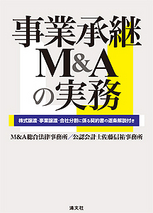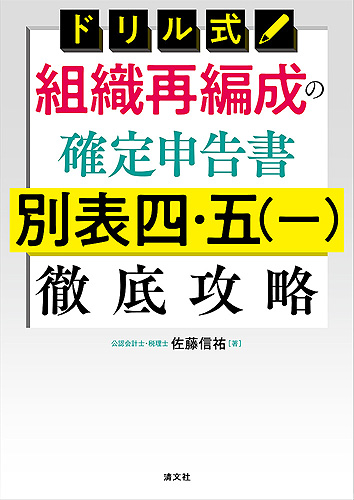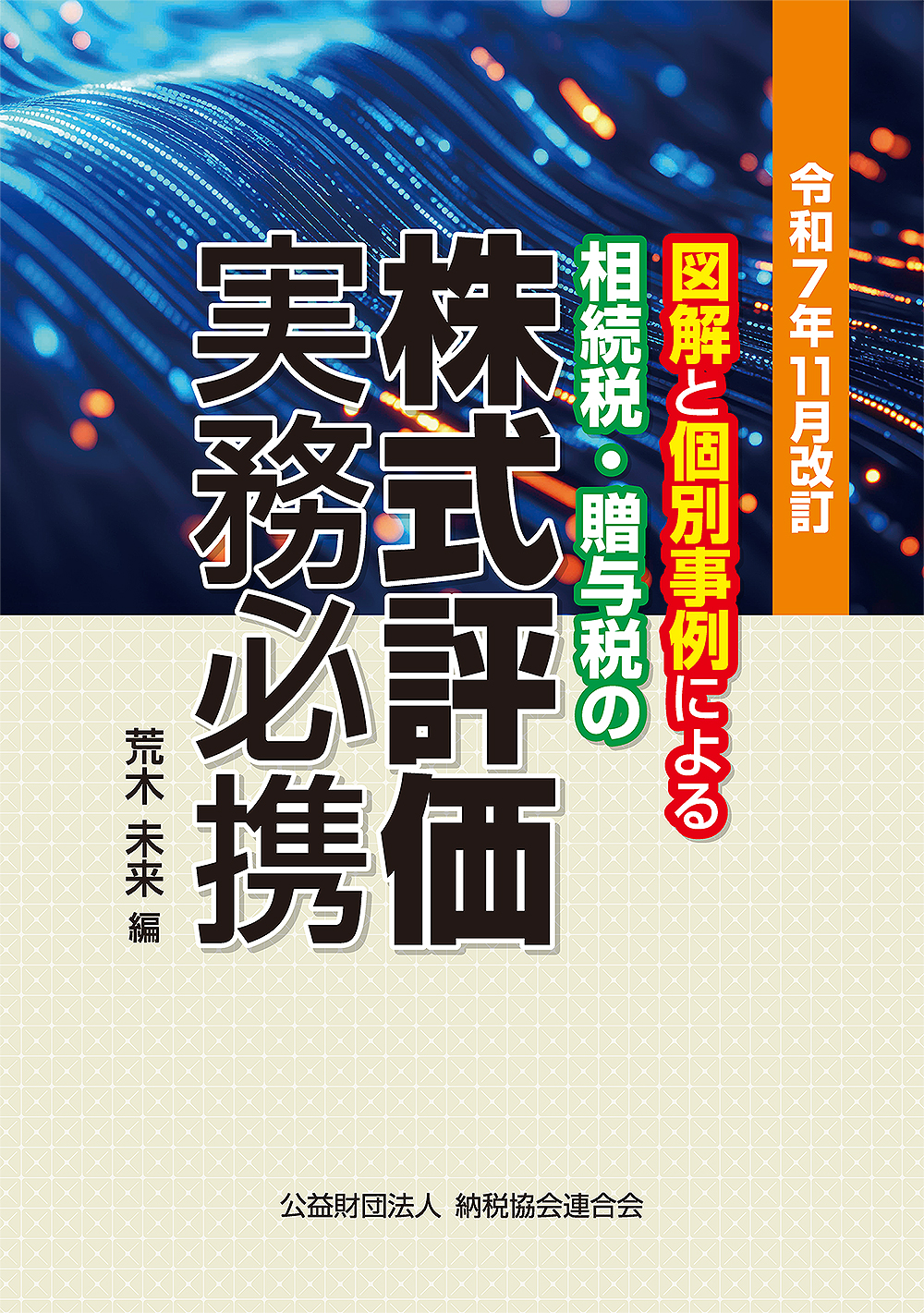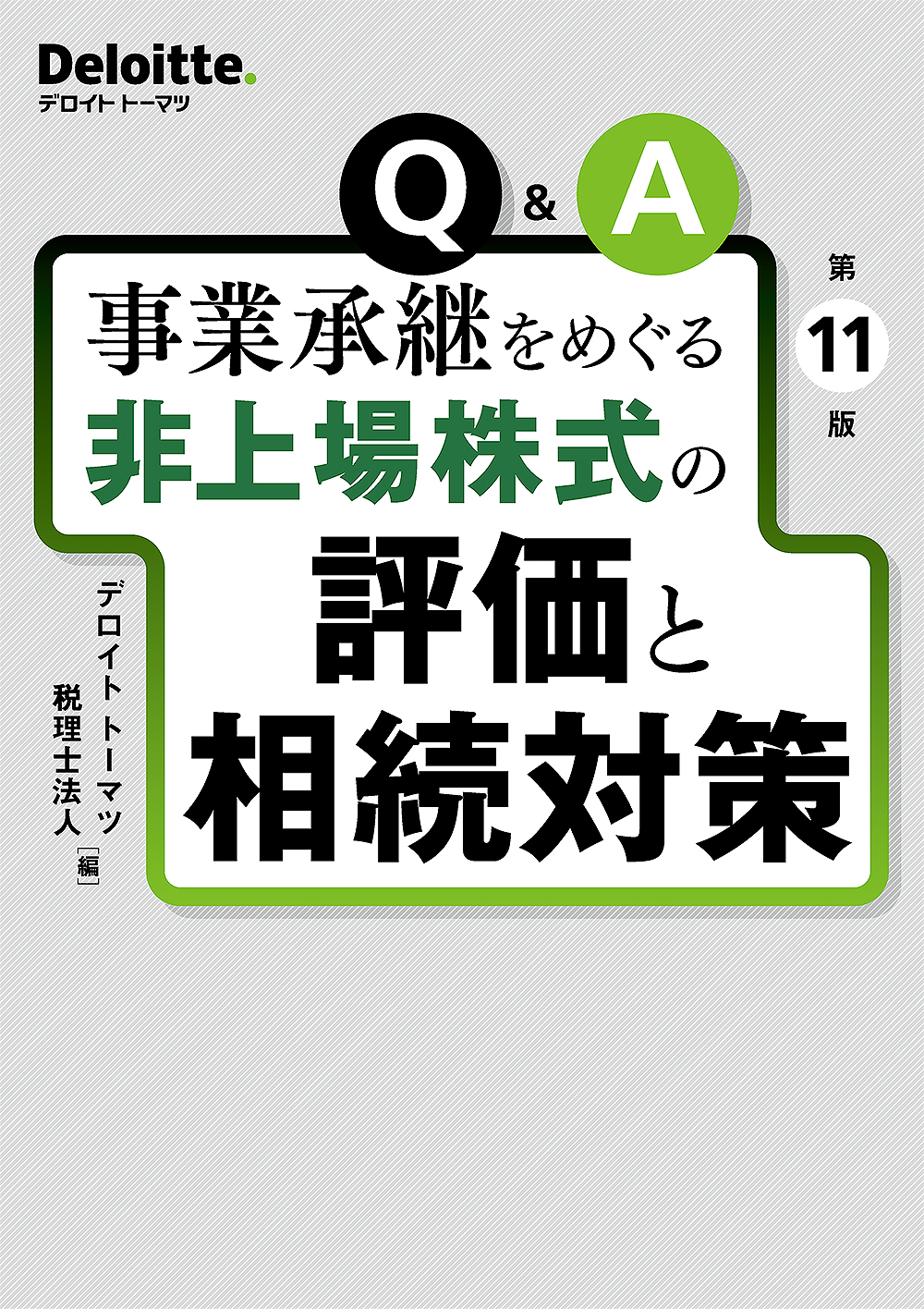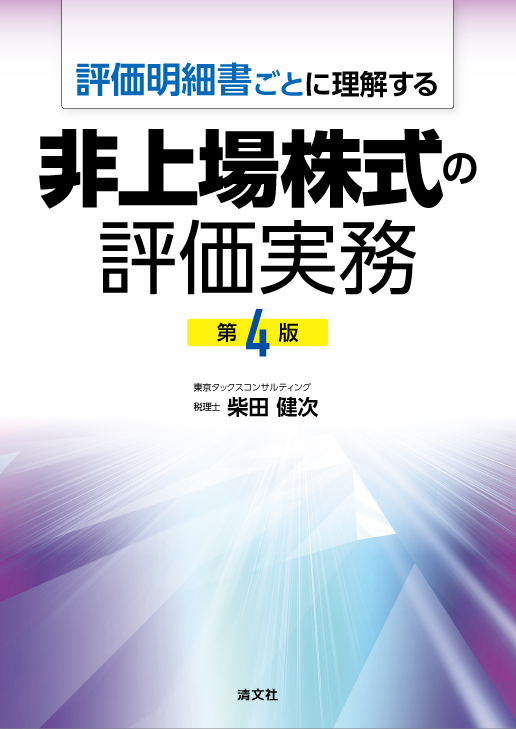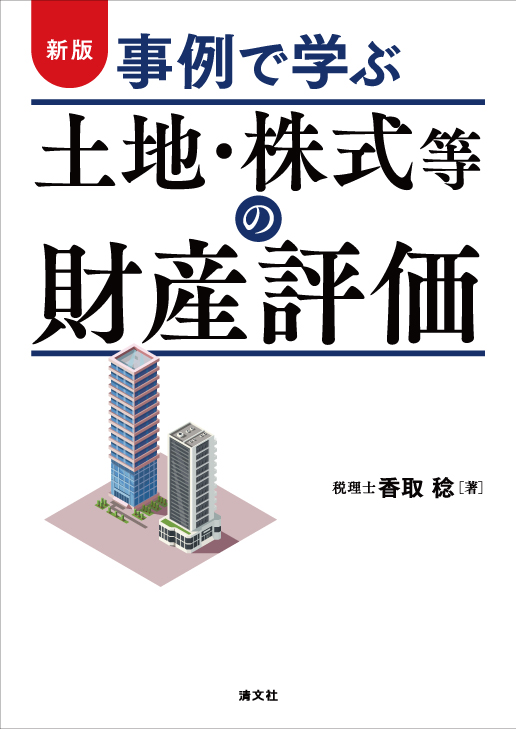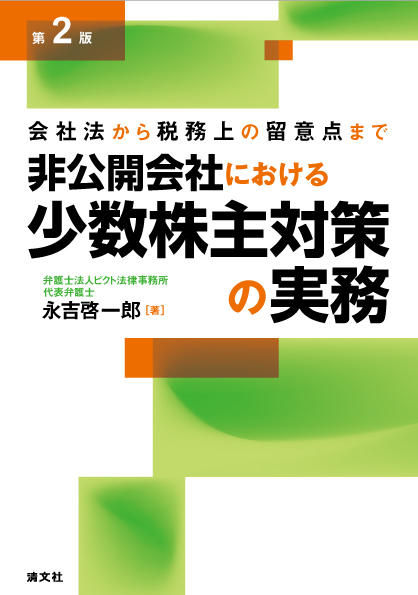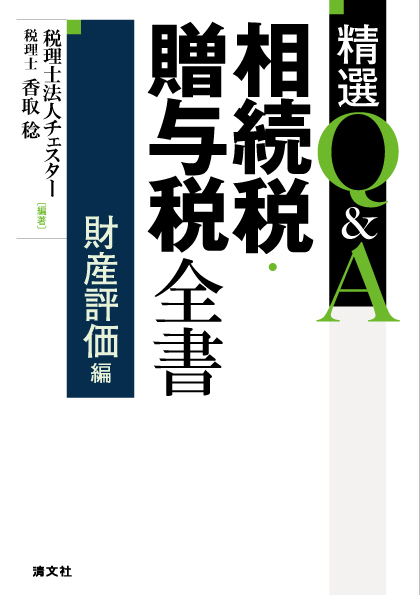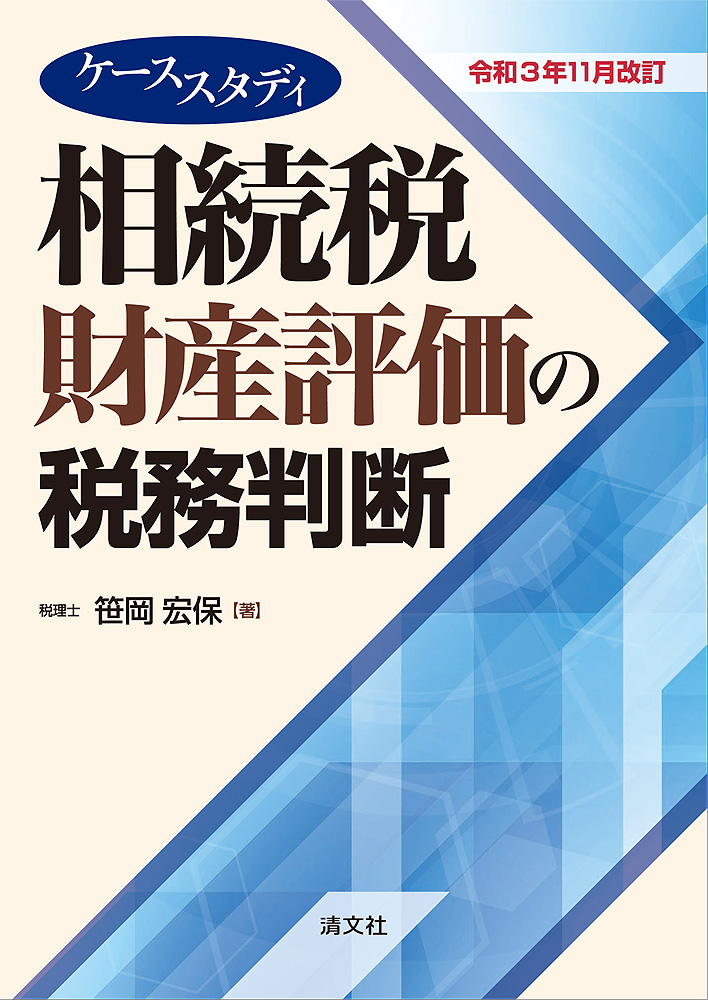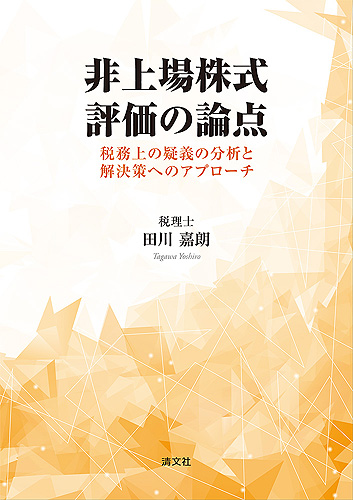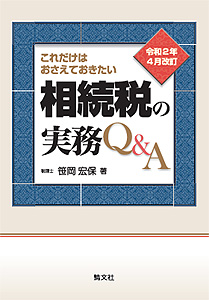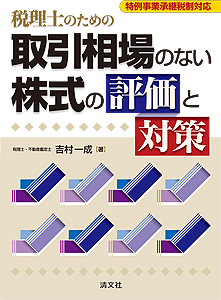裁判例・裁決例からみた
非上場株式の評価
【第18回】
「租税法上の評価②」
公認会計士 佐藤 信祐
連載の目次はこちら
本稿では、東京高裁平成12年9月28日判決について解説を行う。本事件は、同族株主以外の株主であっても、純資産価額による買取りが保障されている場合には、純資産価額方式による評価をすべきであると判断された事件である。
2 東京高裁平成12年9月28日判決・TAINSコード:Z248-8734
(1) 事実の概要
本事件は、平成5年11月24日死亡した能沢十太郎(以下「亡十太郎」という)の共同相続人である原告らが、フォーエスキャピタル株式会社の株式(以下「本件株式」という)を特例的評価方式により評価して相続税の申告をしたところ、純資産価額方式により評価すべきであるとして、被告が原告らに対して平成7年7月31日付けで更正及びこれに対する過少申告加算税賦課決定(以下「本件各処分」という)を行ったのに対し、原告らが申告額を超える部分に係る本件各処分の取消しを求めた事件である。
なお、第一審判決文には、以下の事実関係が記載されており、その背景を理解すると裁判所の判断も分かりやすい。
【判決文抜粋】
本件会社は、杉山が代表取締役を務める日本スリーエス株式会社(以下「日本スリーエス」という。)を中心とするグループに属し、ベンチャービジネスに投資することを目的として資産家に対して投資を呼びかけていた。
そして、日本事業承継コンサルタント協会の会員である税理士等からの紹介で本件会社への出資の申込みがあった場合には、日本スリーエスが窓口となり、まず、出資希望者に対し、本件株式が将来公開された場合には、出資者はキャピタルゲインが得られること及び出資者は常に少数株主となることから出資者の所有する本件株式は相続税及び贈与税の課税価格計算上、配当還元方式で評価することができ節税になることを説明し、出資希望者の資産状況から自己資金あるいは借入金により、いくら出資できるかを検討して出資金額を決定し、次に出資金額を出資時の前月末現在の本件株式の時価純資産価額で除して出資可能株数を算出し、本件会社がその株数に相当する増資を行い出資希望者に割り当てていた。なお、増資を行うことによりセムヤーゼの本件株式の保有割合が本件会社の発行済株式総数の50パーセント未満になる場合には、本件会社が劣後株式を発行し、そのすべてをセムヤーゼが引き受けることにより、セムヤーゼの本件株式の保有割合が50パーセント以上になる状態を維持していた。
日本スリーエスは、出資希望者に対し、出資者が、本件株式の売却を希望するときに購入希望者がいない場合には日本スリーエスグループの関連会社で買い取るか本件会社が減資する等の方法により必ず希望に応じ、その際の売買価額は、原則として取引日の前月末現在における本件株式の純資産価額であることを出資申込みの際に説明していた。
(2) 第一審(東京地裁11年3月25日判決・TAINSコード:Z241-8368)
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。