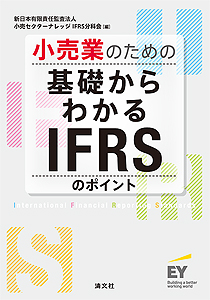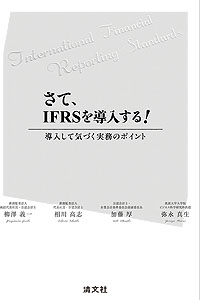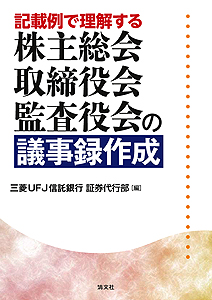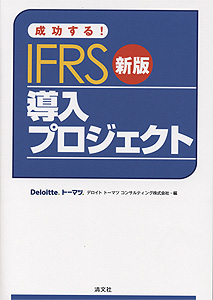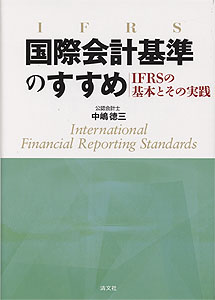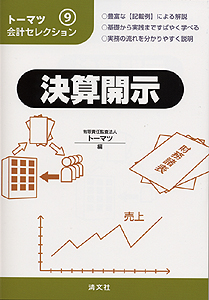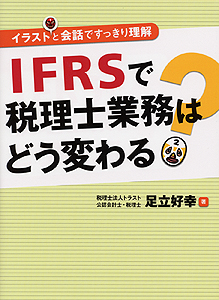『単体開示の簡素化』の要点をおさえる
【第1回】
「制度改正の背景と簡素化の範囲」
公認会計士 中村 真之
1 はじめに
平成26年3月26日に、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年内閣府令第19号、以下「改正府令」という)が公布され、平成26年3月期に係る有価証券報告書の作成から、単体開示に関して簡素化が図られている。
【参考】 金融庁ホームページ
「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」(平成26年3月26日)
現在までに1,500社を超える会社において簡素化された単体開示が採用されており、その実例や実績を踏まえて、有価証券報告書の作成を今後に控えている会社や当期は採用を見送ったものの、今後の簡素化を検討される会社もあると思われる。
本稿では、改正府令のうち、財務諸表等規則の改正内容を中心に、改正の背景や狙いについて2回にわたり解説を行う。なお、文中の意見に関する部分は私見であることをあらかじめ申し添えさせていただく。
2 単体開示の簡素化の概要
(1) 改正の背景と狙い
本改正府令に先立ち公表された「当面の方針」においては、「IFRSの任意適用の積上げを図ること」が謳われているが、IFRSの導入に当たっては、会計基準を変更することに伴って生じる調整や準備のために過大なコストが生じることが予想され、これがIFRS以降の障害になっているという指摘があった。
【参考】 金融庁ホームページ
「「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」の公表について」(平成25年6月20日)
また、金商法における開示制度として連結開示を主、単体開示を従として以来十数年が経過し、現在では多くの財務諸表利用者が、連結における情報を中心に投資判断を行うという実態が定着していると考えられる一方で、連結開示を主としながらも単体開示にも一定の作成負担があることや、会社法と金商法という2つの開示体系が要求する開示内容が異なることに起因して、財務諸表作成者である企業にとって二重の負担となることが指摘されていた。
そこで、金商法における単体開示の在り方について検討し、投資者保護という金商法の趣旨を損なわない限りにおいて、一定の条件を満たした場合には、一部の開示を免除することや開示要求を会社法とあわせるなど、企業の負担軽減・コスト削減につながる単体開示の簡素化を主旨とする改正を行うこととした。
(2) 対象となる会社
今回の改正では、改正後の財務諸表等規則(以下「新財務諸表等規則等」という)の第1条の2において、金商法における単体開示の簡素化の対象会社として、「特例財務諸表提出会社」という新たな概念を規定した。
ここで「特例財務諸表提出会社」とは、以下の2つの条件をいずれも満たす会社とされている(ただし別記事業を営む会社等を除く)。
① 連結財務諸表を作成している会社
② 会社法第2条第11号で規定する会計監査人設置会社
したがって、上場会社であることは特例財務諸表提出会社の条件とはされておらず、「当面の方針」において、IFRSの任意適用について、非上場会社であっても任意適用が可能としていることとも整合させている。
連結財務諸表を作成している会社には、日本基準に基づく連結財務諸表を作成している会社はもちろんのこと、指定国際会計基準又は米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成している会社も含まれていると解されている。
また、会社計算書類規則第98条によれば、会計監査人設置会社と非設置会社とでは、会社法の計算書類において要求される注記項目が大きく異なる。そのため、有価証券報告書提出会社であるものの、会計監査人を設置していない会社を特例財務諸表提出会社とした場合に、単体開示の簡素化の基礎となるべき会社法における注記が存在せず、その結果、金商法における注記が開示されないという事態が想定される。そこで、金商法の要請である投資者保護の主旨を損なわないようにするため、会計監査人設置会社であるという要件を設けている。
3 本表に関する改正の概要
「当面の方針」において、
本表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)に関しては、大多数の会社が会社法の計算書類の作成に当たって経団連のひな型を使用している状況を踏まえれば、会社法の計算書類と金商法の財務諸表とでは開示水準が大きく異ならないため、会社法の要求水準に統一することを基本とする
とされており、今回の改正では、これに則り、新財務諸表等規則第127条第1項第1号から第3号までにおいて、経団連のひな型を参考とした新様式を規定した。
また、これまで、貸借対照表の区分掲記および販売費及び一般管理費の主要な費目の開示に当たり、個別財務諸表の方が連結財務諸表よりも低い基準値が設定されていたが、今般の改正により、連結財務諸表規則と同じ基準となっている。
この重要性の変更については、特例財務諸表提出会社以外にも適用され、単体開示のみの会社に対しても一定の負担軽減が図られている。
4 注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容に関する改正の考え方
「当面の方針」において、
注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容に関しては、会社法の計算書類と金商法の財務諸表とで開示水準が大きく異ならない項目については会社法の要求水準に統一することを基本とする。また、金商法の連結財務諸表において十分な情報が開示されている場合には、金商法の単体ベースの開示を免除することを基本とする
とされていることから、注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容(以下「注記等」という)について、連結財務諸表を作成している場合には単体での開示を要しない項目を整理している。
まず、連結開示で十分な情報が開示されている項目については、金商法の単体開示を免除することとした。次に、金商法の連結開示のみでは十分な情報が開示されていないために単体開示を免除できない項目についても、金商法の開示水準と会社法の開示水準が同程度であると認められる場合には、金商法の単体開示に関する規定を会社法の単体開示の規定に合わせることとした。
その一方で、
上記以外の項目については、その有用性、財務諸表等利用者のニーズ、作成コスト、国際的整合性、監査上の観点等を斟酌した上で、従来どおりの開示が必要か否かについて検討すべきである
単体開示の簡素化に当たっては、単体開示の情報が少なくなることへの懸念に対応しつつ、金商法の単体財務諸表と会社法の(単体)計算書類の統一を図る観点から、例えば、連結財務諸表のセグメント情報の充実や、注記等の記載内容を非財務情報として開示することなどについて検討すべきである
とされていることを踏まえて、
① 金商法の単体開示を免除する
② 金商法の単体開示の水準を会社法の単体開示の水準に合わせる
③ 現状の単体開示を維持する
④ 有価証券報告書の非財務情報(有価証券報告書の「経理の状況」以外の記載箇所)に移行する
のいずれかの対応を行っている。
* * *
次回(2014/7/31公開)は具体的な免除項目の確認と本制度導入に当たっての留意事項について解説する。
(了)