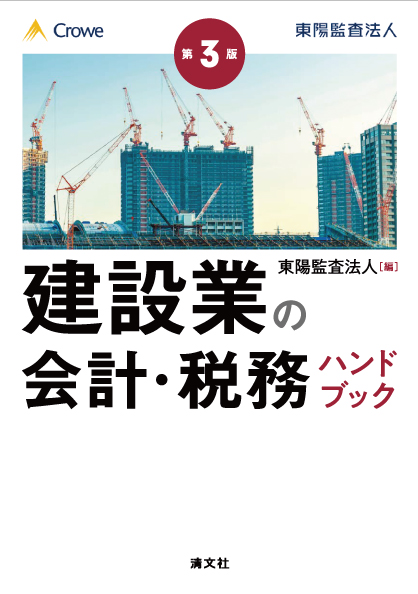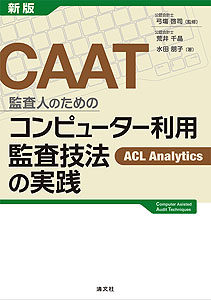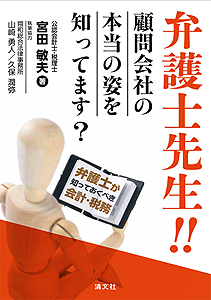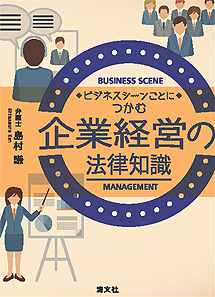なぜ工事契約会計で不正が起こるのか?
~東芝事件から学ぶ原因と防止策~
【第1回】
「工事原価総額の見積りの信頼性」
公認会計士・税理士 中谷 敏久
Ⅰ はじめに
東芝は2003年に委員会等設置会社に移行し、企業統治改革の先駆者としてこれまで国内外から高く評価されてきた。にもかかわらず順守できなかった「工事契約会計」とはいったいどのような会計制度なのか、また日本を代表する企業がその会計制度を使ってどのように会計不正を行ったかを明らかにしたい。
Ⅱ 工事契約会計とは
わが国では長い間、長期請負工事に関する収益は工事完成基準又は工事進行基準のいずれかを選択して計上することが認められてきた。工事完成基準は、工事が完成し、その引渡しが完了した日に工事収益を計上する方法であり、工事進行基準は、決算期末に工事進行程度を見積もり、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する方法である(企業会計原則注解7)。
この結果、同様の長期請負工事であっても、企業により収益の計上方法が異なることになり、財務諸表の比較可能性が損なわれるという弊害が生じていた。この弊害を解消するため、民間団体である企業会計基準委員会が2007年に公表した会計基準が「工事契約に関する会計基準」(以下、「会計基準」という)である。
会計基準によると、工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する(会計基準9項)。今までは、成果の確実性が認められるか否かにかかわらず、企業が任意に両基準を選択適用することができたが、それができなくなったのである。
ここで「成果の確実性」とは何か。会計基準は、
(1) 工事収益総額
(2) 工事原価総額
(3) 決算日における工事進捗度
まず(1)工事収益総額については、信頼性をもって見積もることは容易である。なぜなら、施工者は注文主との間で工事請負契約を締結し、請負額、決済条件及び決済方法を明確に定めるのが一般的であるからである。
これに対し、(2)工事原価総額については信頼性をもって見積もることは難しい。工事原価総額は、工事契約に着手した後も様々な状況により変動することが多いため、信頼性をもって見積もるためには、当該工事契約に関する実行予算や工事原価等に関する管理体制の整備が求められるからである。
(3)決算日における工事進捗度を見積もる方法としてはいくつかの種類があるが、原価比例法を採用する場合には、工事原価総額が信頼性をもって見積もることができれば、工事原価発生額を工事原価総額で割ることによって工事進捗度も信頼性をもって見積もることが可能となる。
したがって、成果の確実性は主に(2)工事原価総額の信頼性に左右されることになる。
-具体例-
「工事収益総額:100、工事原価総額:80、工事原価発生額:60」のケース
① 工事進捗度・・・60÷80=75%
② 工事収益計上額・・・100×75%=75
Ⅲ 工事契約から損失が見込まれる場合
ここで気をつけなければならない点が1つある。
それは、「工事収益総額<工事原価総額」の場合には、成果の確実性が認められるとして工事進行基準を適用していても、また認められないとして工事完成基準を適用していても、必ず工事損失引当金を計上しなければならないという点である。
会計基準に沿って正確に述べると、工事原価総額等(工事原価総額のほか、販売直接経費がある場合にはその見積額を含めた額)が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、その超過すると見込まれる額(以下、「工事損失」という)のうち、当該工事契約に関してすでに計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損失を計上する(会計基準19項)。
今後見込まれる工事損失を事前に工事損失として計上する会計技法が引当金の計上であり、工事損失引当金を計上するということは、工事損失を事前に計上するということである。
-具体例-
「工事収益総額:100、工事原価総額:120、工事原価発生額:60」のケース
① 工事進捗度・・・60÷120=50%
② 工事収益計上額・・・100×50%=50
③ すでに計上された損益の額・・・50-60=損失10
④ 工事損失引当金計上額・・・120-100-損失10=10
上記のケースでは、工事損失引当金が10計上され、当該工事契約に関して今後見込まれる損失の額を示すことになる。
Ⅳ 東芝での会計基準適用状況
第三者委員会調査報告書(以下、「報告書」という)によると、東芝では、工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度を信頼性をもって見積もることができる状態であるという要件を満たす案件のうち、
- 見積工事収益総額が10億円以上、かつ、工事期間が1年以上の長期請負工事
- 見積工事収益総額が10億円以上で工期が3ヶ月以上1年未満の工事のうち、着工事業年度中にその目的物の引渡しが行われない請負工事
については、工事進行基準適用案件として取り扱うこととし、見積工事収益総額が10億円未満であっても、成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用することができるとされている。
また、東芝においては、工事進行基準の適用の有無にかかわらず、当期末において2億円以上の損失が発生することが見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることができる案件については、翌期以降の損失見込額を、工事損失引当金として計上することとされている。
* * *
次回は上記報告書で指摘された工事契約会計に係る不正内容とその原因を整理してみたい。
(了)
「なぜ工事契約会計で不正が起こるのか?~東芝事件から学ぶ原因と防止策~」は、隔週で掲載されます。