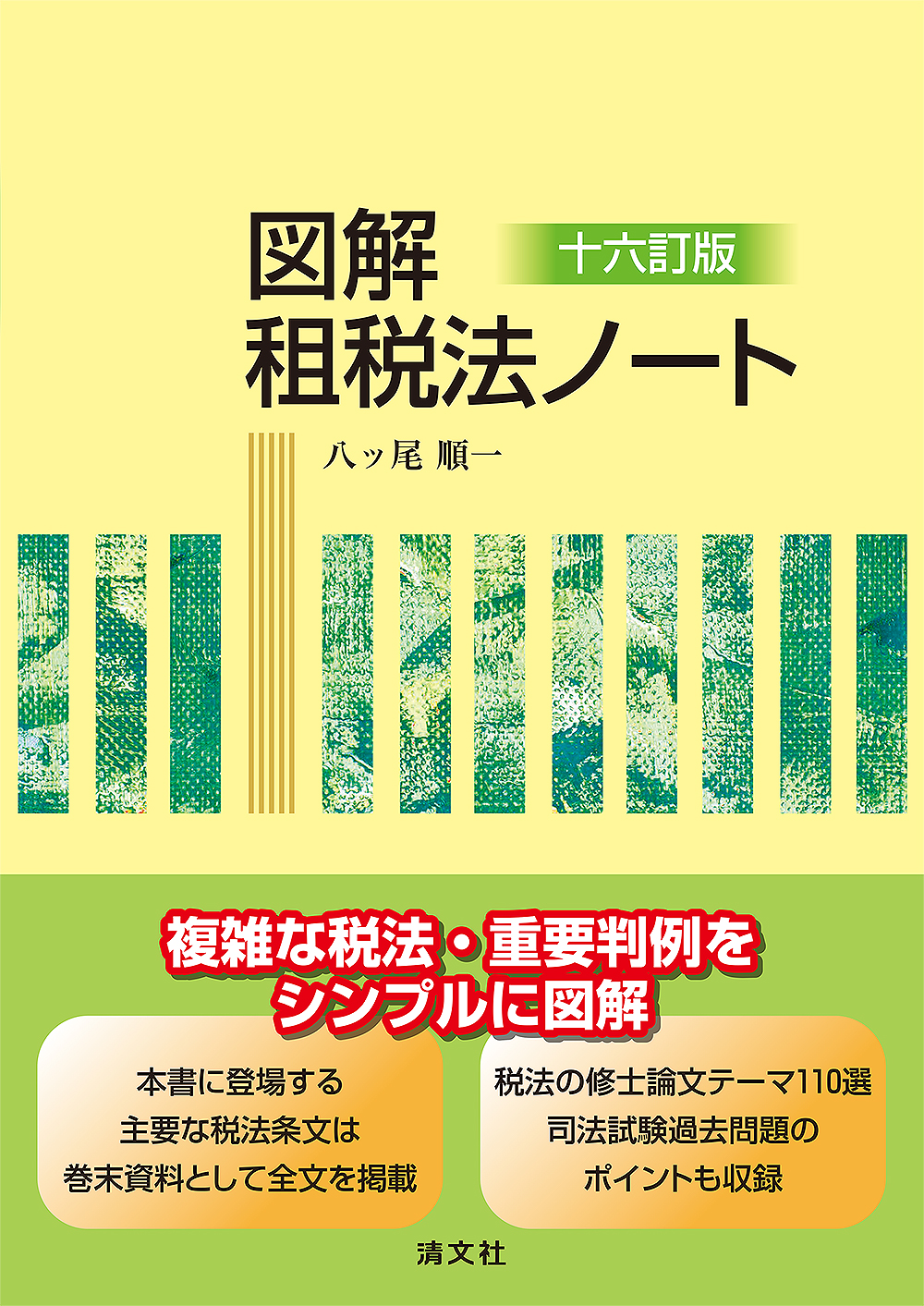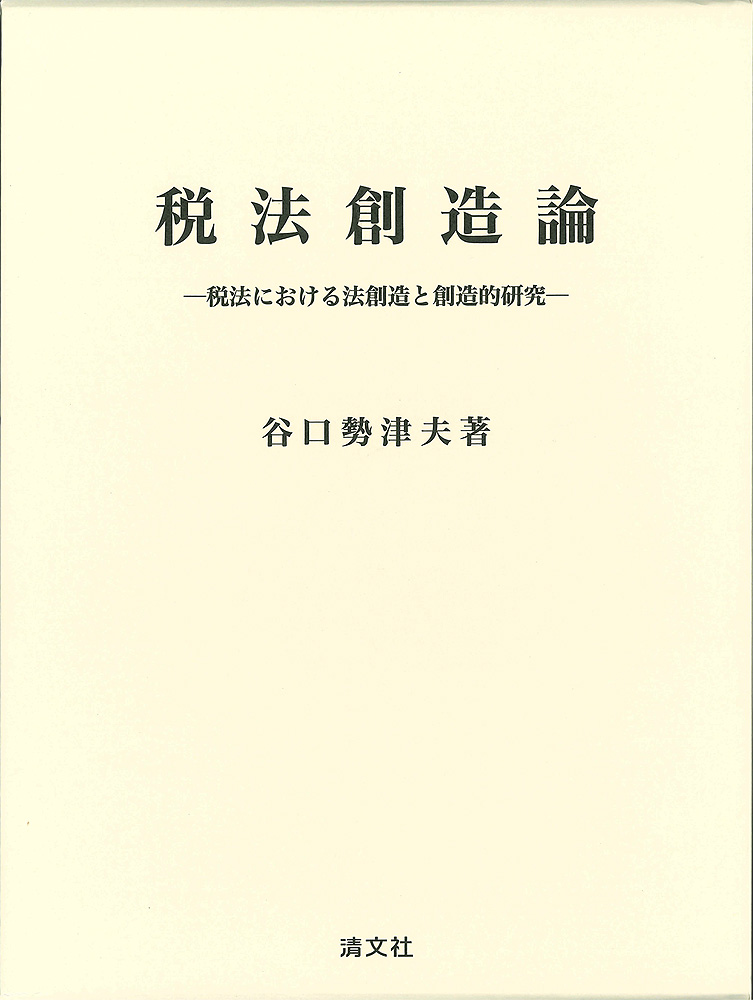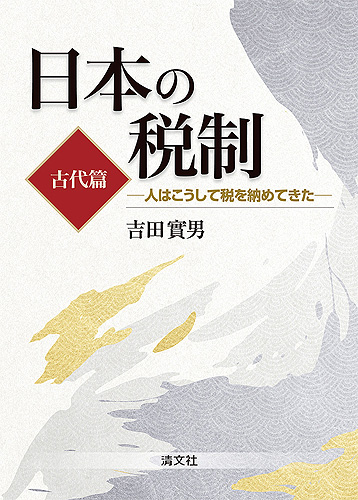税務判例を読むための税法の学び方【40】
〔第5章〕法令用語
(その26)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
14 不確定概念と宥恕規定
(① 宥恕規定の意義と例示)【第37回参照】
(② 「違法」と「不法」「不適法」「非合法」「不当」「不正」「不適当」「不相当」「反正義」「不公正」【前半】)【第38回参照】
(③ 「違法」と「不法」「不適法」「非合法」「不当」「不正」「不適当」「不相当」「反正義」「不公正」【後半】【前回参照】)
④ 基本的な宥恕規定「『正当な理由』、『やむを得ない理由』と『やむを得ない事情』」
第37回では、宥恕規定の例をいくつか示したが、今回は、この宥恕規定の基本的な表現である「正当な理由」、「やむを得ない理由」と「やむを得ない事情」について、それぞれ見ていこう。
(1) 「正当な理由」
「正当な理由」の「正当」とは何であろうか。
「正当」は、正しいこと、道理にかなっていることで、「適法」が法令にかなっていることを表す概念なのに対し、「正当」は、一般的な正しさや、正当性を指すものといえる。
前々回「不当」は、通常形式的には法令に違反しないが、その内容が実質的にみて妥当ではないことを表すときに使われると書いた。すなわち、通常は、違法ではないが正当ではない「不当」という領域が存在することになる(前回「「不当」ではあるが「違法」ではない領域がある」と書いたのはこの意味である)のであるから、これを裏返せば、単に違法ではないのみならず、正当性が問われることになる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。
税務判例を読むための税法の学び方【40】
〔第5章〕法令用語
(その26)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
14 不確定概念と宥恕規定
(① 宥恕規定の意義と例示)【第37回参照】
(② 「違法」と「不法」「不適法」「非合法」「不当」「不正」「不適当」「不相当」「反正義」「不公正」【前半】)【第38回参照】
(③ 「違法」と「不法」「不適法」「非合法」「不当」「不正」「不適当」「不相当」「反正義」「不公正」【後半】【前回参照】)
④ 基本的な宥恕規定「『正当な理由』、『やむを得ない理由』と『やむを得ない事情』」
第37回では、宥恕規定の例をいくつか示したが、今回は、この宥恕規定の基本的な表現である「正当な理由」、「やむを得ない理由」と「やむを得ない事情」について、それぞれ見ていこう。
(1) 「正当な理由」
「正当な理由」の「正当」とは何であろうか。
「正当」は、正しいこと、道理にかなっていることで、「適法」が法令にかなっていることを表す概念なのに対し、「正当」は、一般的な正しさや、正当性を指すものといえる。
前々回「不当」は、通常形式的には法令に違反しないが、その内容が実質的にみて妥当ではないことを表すときに使われると書いた。すなわち、通常は、違法ではないが正当ではない「不当」という領域が存在することになる(前回「「不当」ではあるが「違法」ではない領域がある」と書いたのはこの意味である)のであるから、これを裏返せば、単に違法ではないのみならず、正当性が問われることになる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。