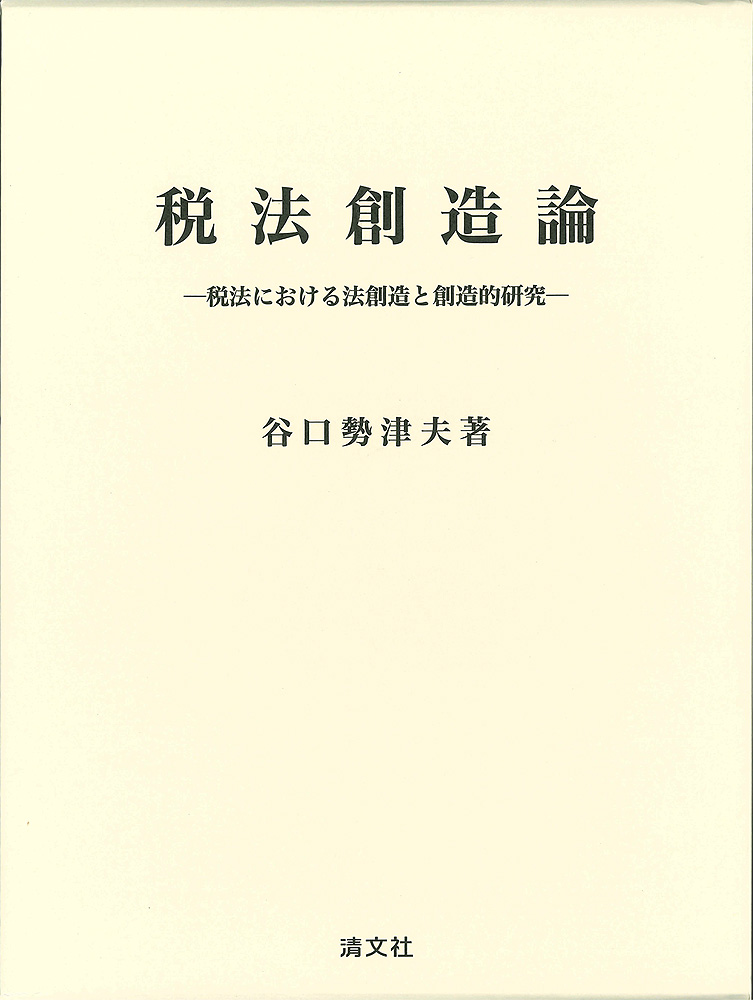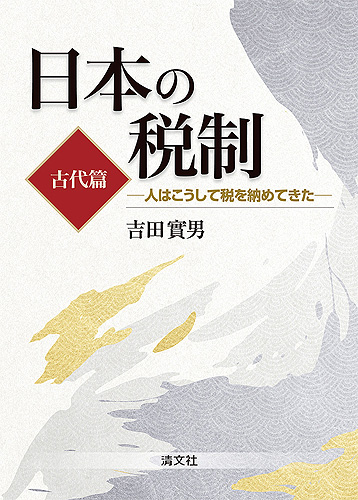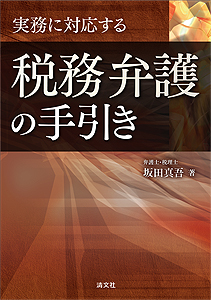税務判例を読むための税法の学び方【11】
〔第4章〕条文を読むためのコツ
(その4)
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
(前回はこちら)
(4 主文の主要素を見極める方法)
④ 併合的接続詞「及び」「並びに」による段階構造の分析
法令文において語句を併合的に結び付ける併合的接続詞には、「及び」と「並びに」が用いられる。すなわち、前回の選択的に結び付ける語は英語の「or」に相当するものであるが、併合的に結び付ける「及び」「並びに」は、英語の「and」に相当するものである。
両者は、文字的意味の上では同じものであり、日常用語としては同じような意味で区別せずに使われている。しかし、法令用語としての「及び」と「並びに」は、明確に使い分けられている。
単純に並列的に並ぶだけのときには、「及び」が使われ、語句が3つ以上であっても、同じ段階で並べるときは、最初の接続は「、」でつなぎ、最後の部分を「及び」で結ぶ。すなわち、「A及びB」や「A、B及びC」「A、B、C及びD」というふうに表現される。
例えば、所得税法第22条第1項は、「居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。」とある。ここでは「総所得金額」「退職所得金額」「山林所得金額」が同じ段階で並べられている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。