所得税還付申告とは?時期や受けるための条件など
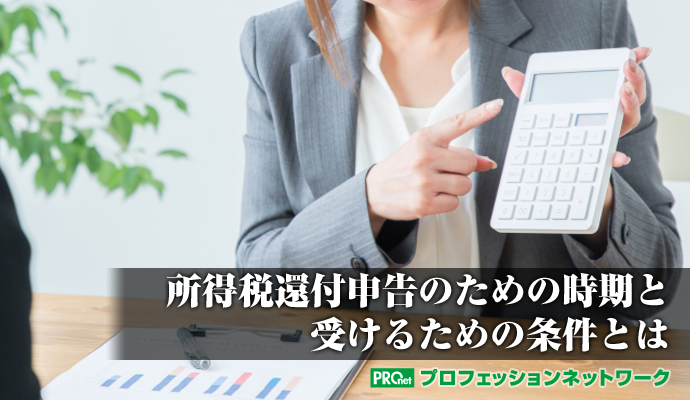
更新日:2024/04/11
源泉徴収税額や予定納税額などが年間の所得税額よりも多い場合には、確定申告を行うことにより納めすぎていた所得税の還付を受けることができます。この場合の確定申告のことを「還付申告」といいます。
税務署は所得税を納めすぎていても連絡してはしてくれません。特に一般の会社員の場合は、勤務先が行う年末調整によって確定申告不要となるケースが多いため、自分の税金の払いすぎについて見逃している可能性もあります。
[ 解説 ]
- 所得税の確定申告と還付申告
- 所得税の還付申告書の申告期限と提出先(申告先)
- 所得税還付金額の計算方法
- 所得税還付手続きをするために必要な書類
- 所得税還付金の種類
- 確定申告を間違えたときの対処
- まずはチェックをしてみましょう!
[ お役立ち ]
所得税の確定申告と還付申告
所得税は「申告納税方式」を採用しているため、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までの間(確定申告期間)に確定申告を行うことが義務付けられていますが、年間の所得金額がゼロの場合(赤字になった場合を含む)や勤務先で年末調整を受けた一般的な会社員の場合は、原則として確定申告が不要となります。
しかし、源泉徴収税額や予定納税額などが年間の所得税額よりも多い場合には、確定申告を行うことにより納めすぎていた所得税の還付を受けることができます。この場合の確定申告のことを「還付申告」といいます。
所得税の還付申告書の申告期限と提出先(申告先)
還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。つまり、税務署が混雑する確定申告期間を避けて、確定申告期間前や確定申告期間後でも行うことができます。
時効は法定申告期限から5年間ですから、過去の分をチェックしてみると良いでしょう。
なお、還付申告書の提出先は、納税者の納税地(住所地など)を管轄する税務署長(税務署)となります。
所得税還付金額の計算方法
所得税の還付金は、あらかじめ納めた源泉徴収税額や予定納税額が、年間の所得税額を超える部分の金額となります。
あくまでも前払いした金額が多すぎた場合です。
年間の所得税額は、10種類に分けた各種所得の収入からそれぞれの所得ごとに定められている必要経費や一定の控除額など控除し、それぞれの金額を合計した金額から医療費控除や扶養控除などの所得控除を控除した金額に税率を乗じて計算します(特殊な計算をする場合もあります)。
なお、一般的な会社員が受ける年末調整では、勤務先から受ける給料を基礎に上記の計算がされ、結果的に適正な年間の所得税額を納税する仕組みとなっています。
ただし、年末調整の際に、所得控除のうち雑損控除、医療費控除、寄附金控除、また、住宅ローン控除(税額控除)は考慮されませんが、確定申告をする際の年間の所得税額の計算では考慮されますので注意しましょう。
また、あらかじめ納めた(源泉徴収された)源泉徴収税額は、一般の会社員の場合は勤務先から交付された「源泉徴収票」に、源泉徴収の対象となる報酬などを受けた個人事業主などの場合は支払先から交付された「支払調書」に記載されています。
所得税還付手続きをするために必要な書類
所得税(厳密には「所得税及び復興特別所得税」)の確定申告書には、「申告書A」と「申告書B」の2種類の様式があります。
「申告書A」は、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない人が対象となりますので、一般的な会社員が所得税の還付を受ける場合はこれを使用します。
「申告書B」は、上記の所得の他、不動産所得や事業所得などがある人が対象となりますが、さらに、譲渡所得、山林所得、退職所得がある人は「申告書B第三表」、所得が赤字の人などは「申告書B第四表」の提出があわせて必要となります。
なお、還付申告を行う場合は、上記の確定申告書の他に、源泉徴収された税額が記載された「源泉徴収票」や「支払調書」の提出が必要となります。
また、還付申告の内容に応じて異なりますが、医療費控除を受ける場合であれば医療費の領収証など、住宅ローン控除の適用を受ける場合であれば住宅ローン控除額の計算明細書や住民票などの「添付書類」の提出も必要です。
所得税還付金の種類
所得税の還付を受けるための条件は、次のようなケースに該当することです。
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっている場合
- 一定の要件のマイホーム新築などを住宅ローンでした場合
- マイホームに特定の改修工事をした場合
- 認定住宅の新築などをした場合
- 災害や盗難などで一定の資産に損害を受けた場合
- 特定支出控除の適用を受ける場合
- 多額の医療費を支出した場合
- 特定の寄附(ふるさと納税など)をした場合
- その他一定の場合
なお、上記に該当する場合であっても、次の所得は源泉分離課税(課税関係が完結)とされているため、それに係る税額は還付を受けることはできません。
- 預貯金の利子
- 抵当証券などの金融類似商品の収益
- 一定の割引債の償還差益
- 一時払養老保険の差益(一定のもの)
確定申告を間違えたときの対処
確定申告をした後に、計算違いなど一定の理由により申告内容に間違えがあり、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合には、「還付申告」はできず、納税地(住所地など)を管轄する税務署長(税務署)に対し、「更正の請求」をすることにより、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。
※納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合は「修正申告」となります。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については1年)で、「更正の請求書」の提出が必要となります。
なお、更正の請求をした場合は、税務署がその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合に限り、減額更正により税金が還付されます。
まずはチェックをしてみましょう!
税金に関する要件や手続きは難しく考えがちですが、具体的な状況を把握し、所得税の還付要件に該当するかどうか(納めすぎの税金があるかどうか)の判断ができれば、手続きはさほど難しいものではありません。
また、一般の会社員の場合は年末調整の適用を受けていますから、還付があることに気づかないケースもありますが、過去の分も含めて5年間分が対象になりますので、意外と多額になることもあります。一度、過去の分をチェックしてみるのも良いかもしれません。
実務において正しい処理ができるようになるために
実務において、正しい処理ができるようになるために、基本的な考え方や計算方法について、実例を交えながら分かりやすく解説した講義を紹介します。
所得税還付申告に関する解説講義のご案内
税法入門 所得税(令和6年版)セミナー研修
『所得税』とは何か?知識ゼロの方へ入門知識を体系的にマスター!
簿記の基礎知識(日商簿記3級程度)のある方で、税法知識の全くない初心者の方を対象とした所得税の入門講座です。
所得税は個人が稼いだ所得に対して税額計算を行います。当講座では、個人の所得を把握した上で、所得控除・税額控除を確認し、所得税の税額が体系的に計算できるように解説していきます。
【実務に使える税務用語解説】一覧
- 所得税関係
- 法人税関係
- 所得税・法人税関係
- 資産税関係
- 消費税関係
- 会計分野
- その他の税法
