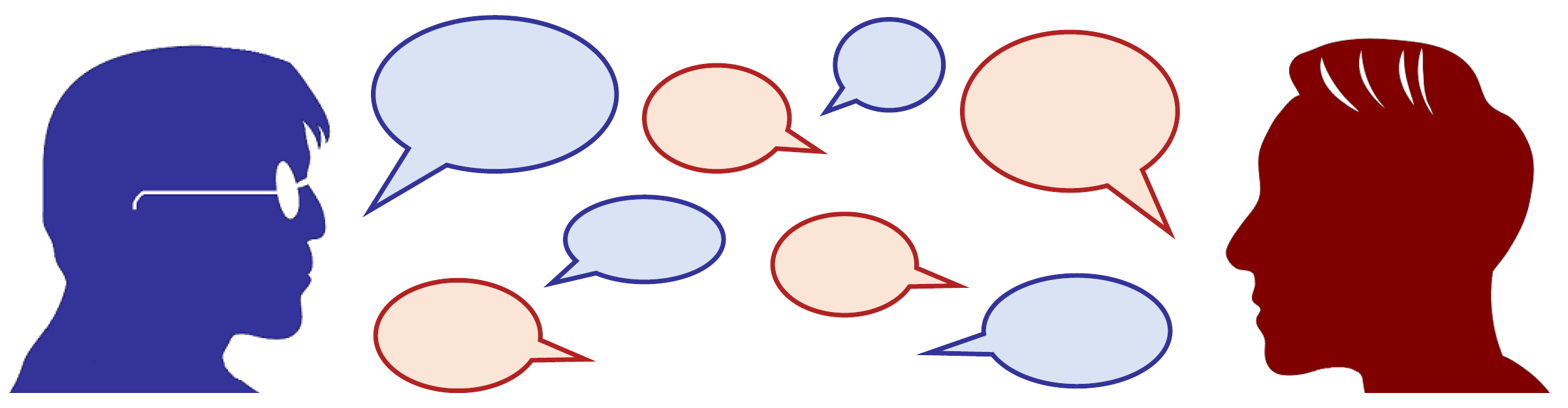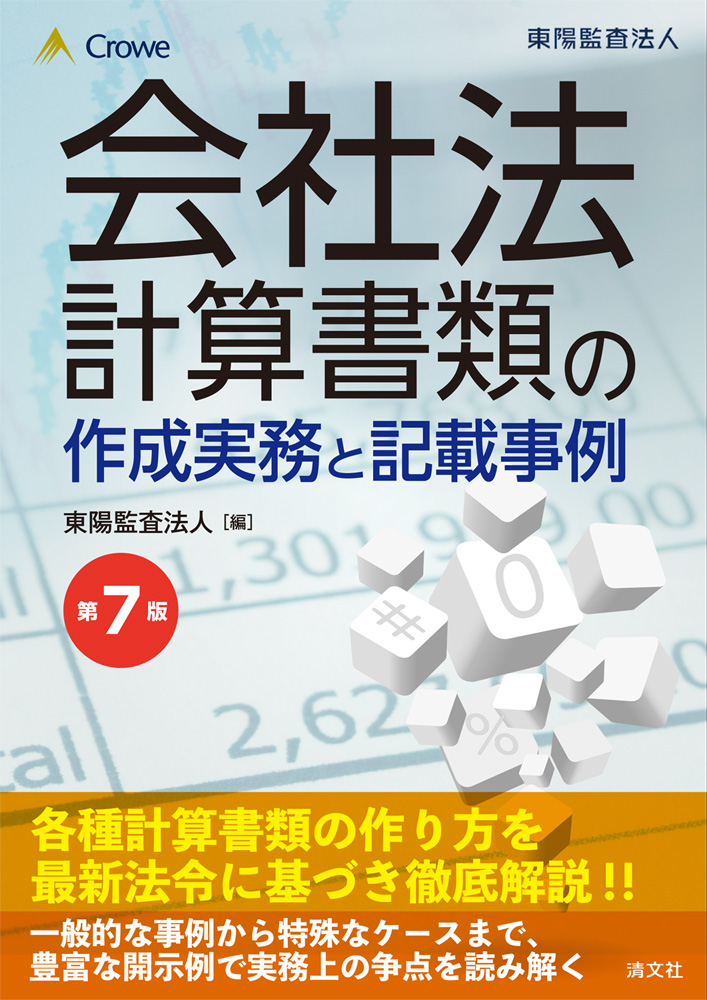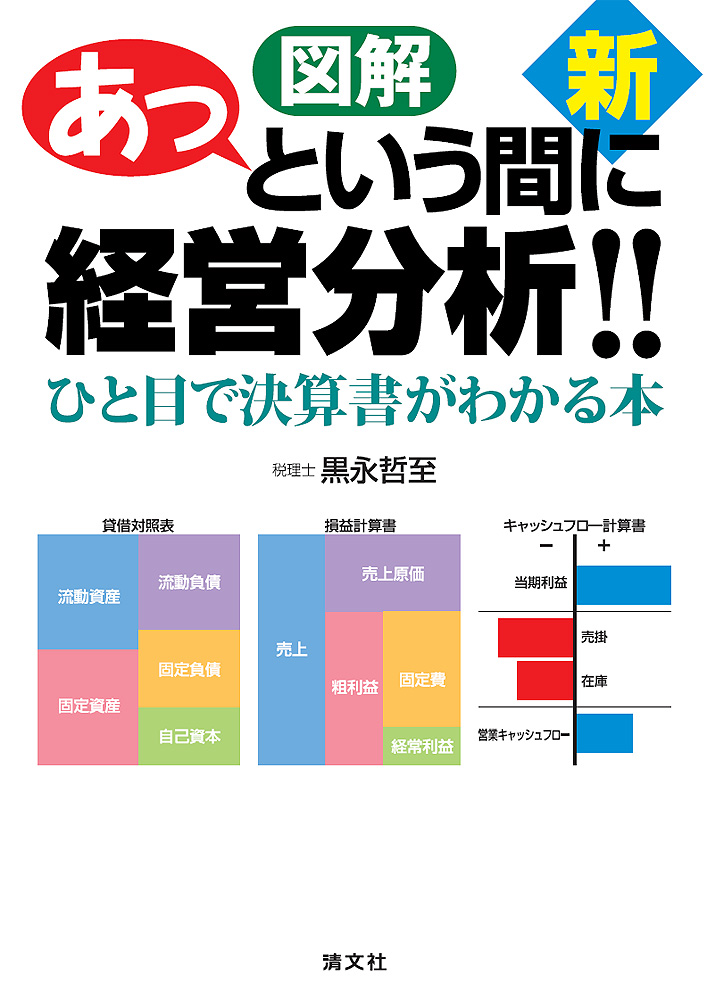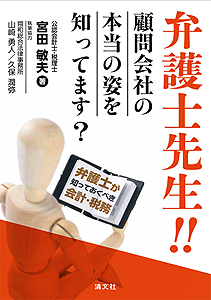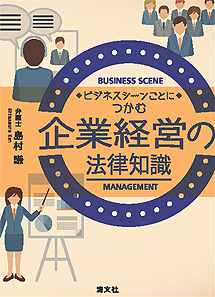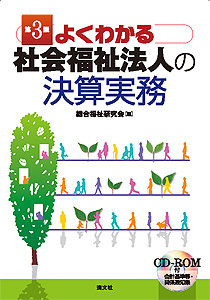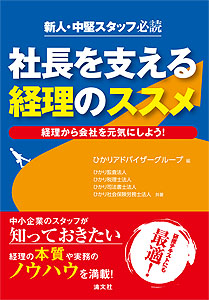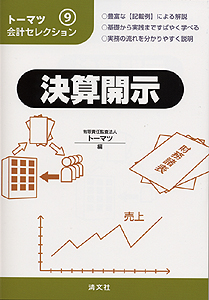会計士が聞く!
決算早期化「現場の回答」
【第1回】
「“ムダな作業”について聞きたい!」
石王丸公認会計士事務所
-はじめに-
決算早期化に秘訣はあるのか?この連載では、それを探っていきます。とある会計士が、実際に決算早期化を成功させた「ベテラン経理のコバヤシさん」のもとを訪れて、「現場の回答」を聞き出していきます。
はたして、・・・決算早期化対策のヒントは見つかったのでしょうか。
* * *
《登場人物紹介》

〈ベテラン経理のコバヤシさん〉
世界シェアトップの某メーカーで30年以上にわたり経理部に勤務。その間に会社は東証一部上場を達成。年々、開示制度の充実強化が図られる中で、5年間で13日の連結決算早期化を実現。
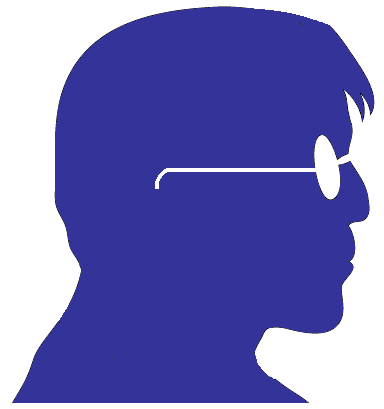
〈会計士〉
決算早期化の秘訣を知りたい公認会計士。といっても、そういうコンサルをしているわけではなく、単なる興味本位。
* * *
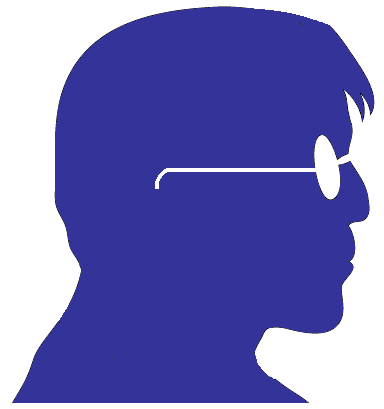 会計士
会計士
決算早期化対策としてすぐにできそうなのは、ムダな作業の削減でしょうか?
ムダな作業なんて、そんなにはないかもしれませんが・・・。
 コバヤシさん
コバヤシさん
それが結構あるんですよ。
本来不要な資料収集・作成などが、過度に行われているケースなんですけどね。
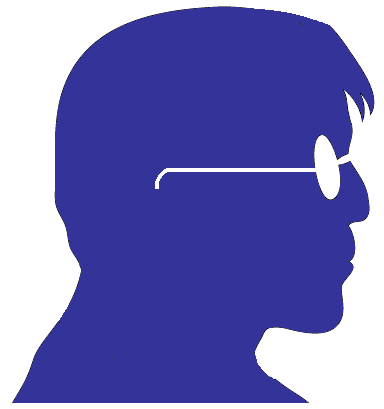 会計士
会計士
それはまた不思議ですね。
不要な資料であれば、次回から作成しないようにすればいいかと思いますが・・・。
 コバヤシさん
コバヤシさん
そう思うでしょう。でも現場はそうじゃないんですよ。これまでやってきた方法が保守的に踏襲され、本来なら不要な作業がいつまでも行われているんです。
決算作業などで提出が求められる資料の作成は、基本的には定型化された作業なのですが、提出資料には提出期限がおおよそ決められているため、従業員は提出期限を厳守しようとします。
そのため、定型業務の見直しを行う必要があっても、それを行うには相応の時間もとられることから、躊躇し、後回しにしてしまう、というわけです。
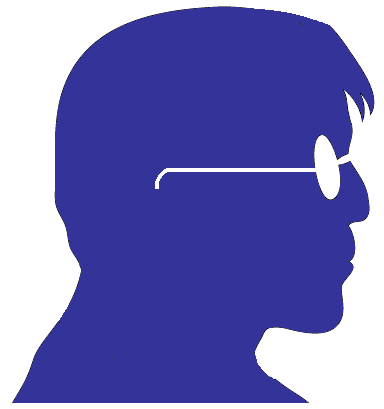 会計士
会計士
経理の仕事というのは、かなり盛りだくさんなのですね。
 コバヤシさん
コバヤシさん
一般的に経理では、年間を通じて残業が多いです。決算時などでは、月次で行っている定例業務のほか、単体・連結・開示などの業務が並行して行われ、期末決算では内部統制監査に対する作業も行われます。
さらに管理会計用や税務会計用、他部門や経営層から要求された資料など、様々な資料が作成されます。繁忙期以外に業務の見直しをやればよいことはわかっているのですが、意外とやっかいな部分もあります。
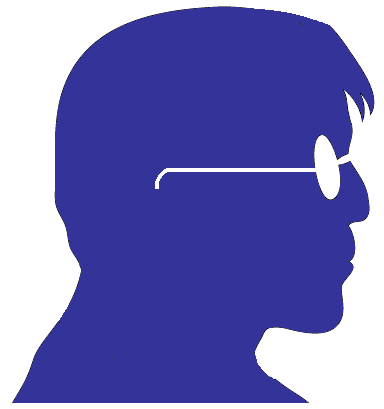 会計士
会計士
「やっかい」と言いますと?
 コバヤシさん
コバヤシさん
担当者の異動などにより業務の引継ぎがあった場合などでは、何の目的で作成しているのか、使用用途がわからないまま作成している資料もあるのです。
さらに、経理部門の部長・課長には報告せずに、経理以外の部門からの依頼により作成しているものもあり、担当者の判断で業務を増やしているケースも見受けられます。
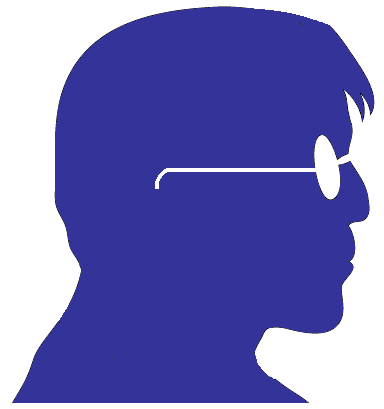 会計士
会計士
確かにやっかいですね。
それだと、「業務の見直しはまた今度にしよう」と先延ばしにしたくなる気持ちもわかります。監査法人は、何かアドバイスしてくれないのですか?
まあ、アドバイスの義務はないんですが。
 コバヤシさん
コバヤシさん
監査法人からは、内部統制に不備がない限りは、それ以上踏み込んだアドバイスはないことが多いようです。
監査法人に対して、内部統制に関する業務フローの簡素化についてアドバイスを要望しても、具体的な要望を示さない限り、基本的には変更しないままでよいということになります。
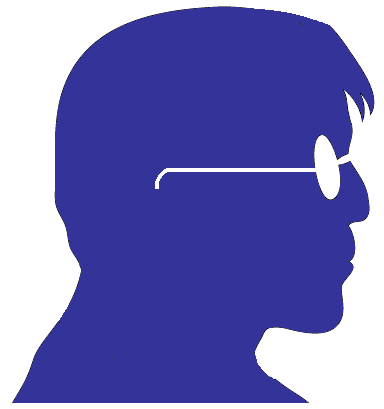 会計士
会計士
いかにもありそうな話ですね。
他にはどんなムダがよくありますか?
 コバヤシさん
コバヤシさん
よくあるのは、複数の担当者が同じような資料を作成しているケースです。管理・監督者がすべての業務を把握し適切に指示していれば、このような問題は発生しませんが、意外とそれができていないんです。
また、担当者の作業には、上司からの指示や他部署・外部からの要請、自己の業務の中で必要となる場合などもありますが、不慣れ(担当外)な業務のため時間がかかっていたり、主旨の認識・理解不足により、まとめ方が意図しない方向になっている場合などもあります。
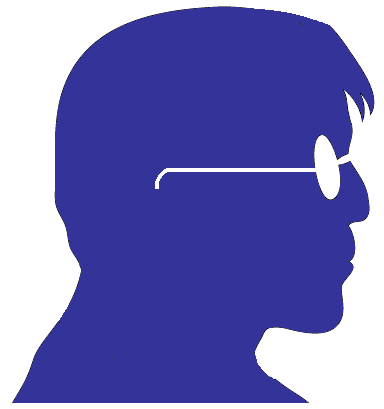 会計士
会計士
こうした“ムダな作業"を洗い出すためには、監査法人ではなくコンサルタントの力が必要になるのでしょうか?
 コバヤシさん
コバヤシさん
そうですね。
本来であれば社内で確認することが必要ですが、時間と労力がかかりますので、外部のコンサルを使い、客観的に判断してもらうほうが、お金はかかりますが進めやすいかもしれません。
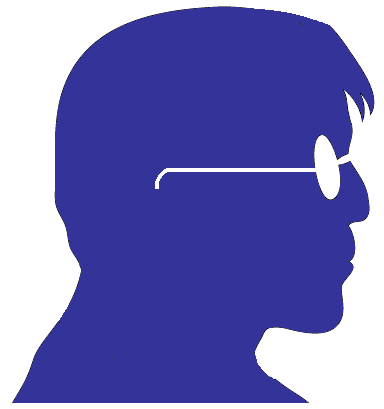 会計士
会計士
お話を伺っていると、ムダな作業を削減しても、しばらく経つとまた、ムダな作業が復活してしまうようにも思えます。そうならないために、日々の業務でできる工夫や対策はあるのでしょうか?
 コバヤシさん
コバヤシさん
私がやっていた方法ですが、決算(四半期)が終わったタイミングで、課員に業務調査表を作成させていました。書くほうからするとイヤな作業かもしれませんが、課員に何が不足しているのか、何に対して努力したのかなど、各人の状況が見えてきます。
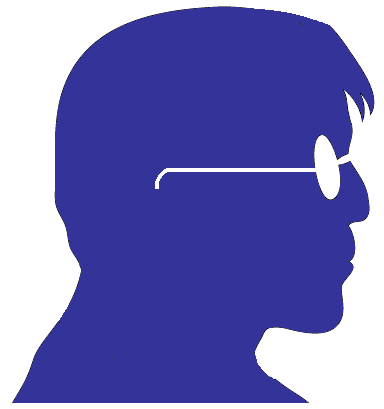 会計士
会計士
その業務調査表にどんなことが書いてあったのか、ちょっと読んでみたいですね。
課員が書いてきたことで、最も印象に残っていることなどあれば、差し支えない範囲で教えていただけますか。
 コバヤシさん
コバヤシさん
では、30代の中堅社員(主任)が数年前に記載した内容を一部ご紹介します。
業務調査表
【質問1】
期末決算時の作業量について確認します。下記の項目で1番近いものに“✓”をつけてください。また、それを選んだ理由について記載してください。
:非常に多い
✓:多い
✓:適量
:少ない
:非常に少ない
(選んだ理由)
何かトラブルが発生した時に、調整して対処することができない状態です。常にトラブルがないことを目指してはいますが、トラブルの際に対処する時間的余裕がなく、他の業務が遅延してしまい、それが決算のスケジュールを押してしまいます。
また、他の課員が作成した資料をチェックする側としては、表面的なチェックで終わってしまわないよう、改善の糸口を早く見つけたいと思います。
【質問2】
上記【質問1】の作業量について、“多い”、“非常に多い”に該当している場合で、業務を軽減するために前期(四半期)と比べて改善した成果があれば記載してください。
また、定期的な進捗の報告で、停滞業務の優先順位や打開策を示唆していただき、個人的な不安は解消されました。
1点毎の提出物について再提出をなくす、また、間違いが発生しにくい資料体系にしていくことで、結果的に全体の作業量を軽減化することが目標です。
難解で読みづらい資料は、ミスの発見が難しいことを実感しているので、資料の作り方も工夫していきたいです。
 コバヤシさん
コバヤシさん
この課員は中途採用の社員で、主に製品原価の振替、たな卸資産や有価証券の評価、開示関連業務を担当業務として行わせていました。入社当初から重要な業務を任せていましたので、決算時の業務量的には多かったかと思います。その中で、作業量を軽減できるよう努力をしていたことがわかりました。
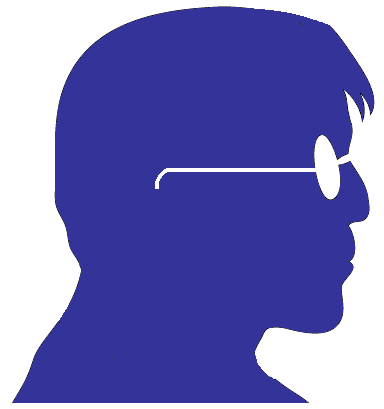 会計士
会計士
トラブル対応の時間的余裕をあらかじめ考えておかなければ、決算早期化の努力も水の泡となってしまうことがわかりましたが、これは示唆に富みますね。
こういう話が決算終了後に課員から聞き出せるということなら、一見、決算早期化とは関係のなさそうな「業務調査表」というものを導入する意義は、大いにあると思いました。
(注) なお、本連載「会計士が聞く! 決算早期化「現場の回答」」の著作権は、石王丸周夫公認会計士及びベテラン経理のコバヤシさんに属するものとします。
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。