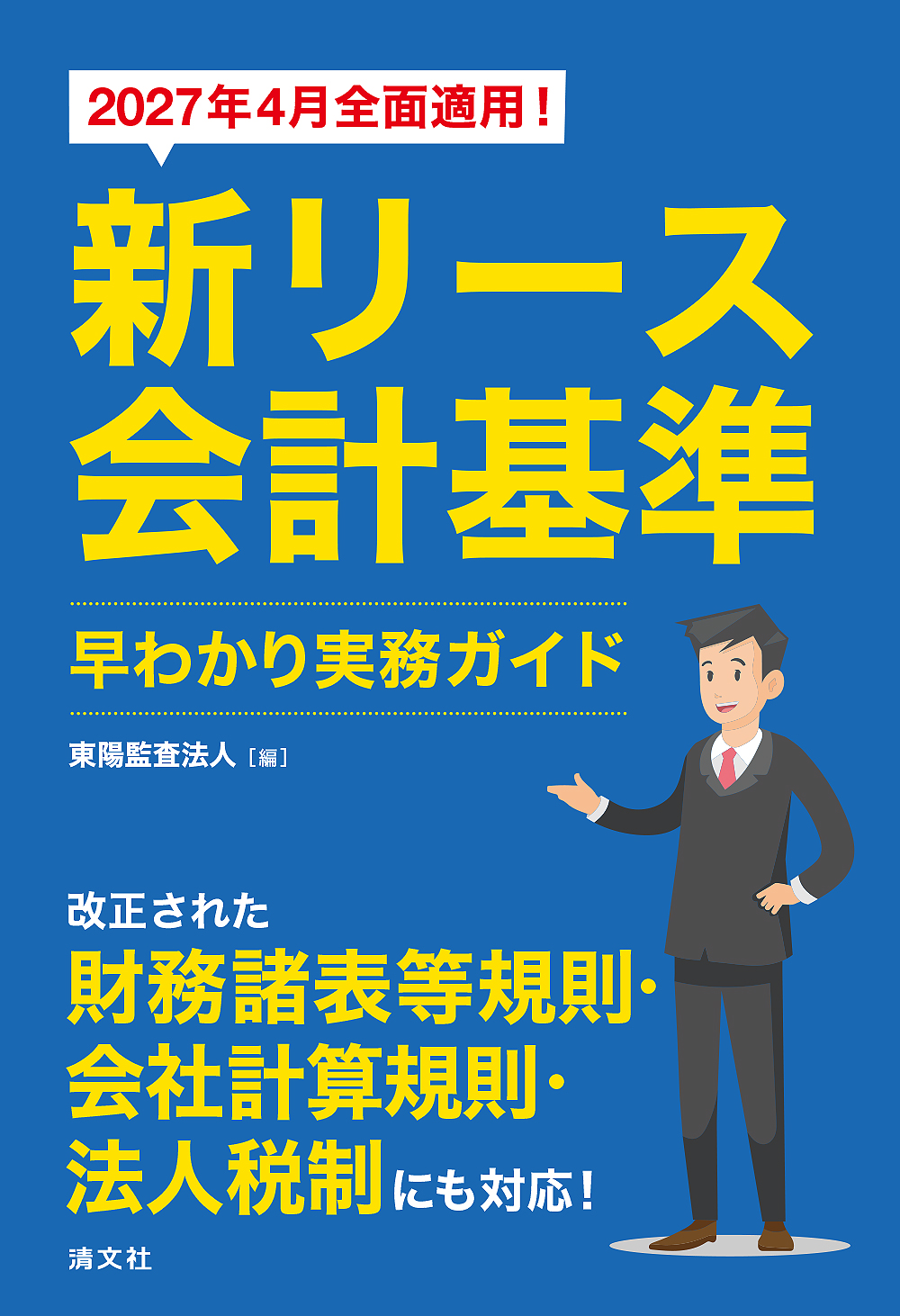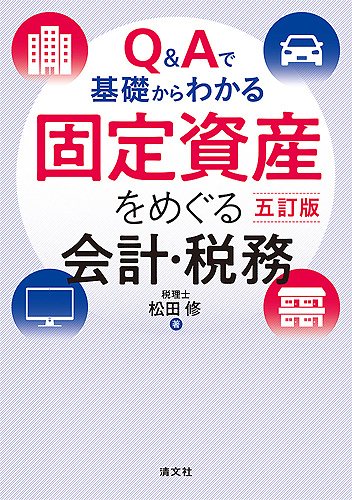〈一から学ぶ〉
リース取引の会計と税務
【第14回】
「リースに関する最新動向」
公認会計士・税理士
喜多 弘美
前回まで、今の日本のリース会計や税務上の取扱いについて、確認してきました。今回は、今後、改正されるリース会計基準について、改正の背景と改正後の会計処理を、ほんの少しになりますが確認していきたいと思います。
1 IFRSと世界の状況
経理の仕事をしていると、「IFRS」という言葉を耳にすることも多いかもしれません。ご存知の方も多いと思いますが、最初にIFRSとは何か、また、なぜ必要なのか確認し、各国の状況を整理します。
(1) IFRSとは
IFRSとは「International Financial Reporting Standards」の略で、国際財務報告基準のことです。国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board:IASB)がIFRSを策定しています。
企業の経済活動は自国だけに留まらず、他国に進出することが増えました。それに伴い、企業の決算書も自国の投資家や株主だけでなく、他国の投資家や株主にも利用されます。多くの投資家や株主は、各企業の決算書を比較し、自分がどの企業に投資するかを判断します。
各国の会計基準が異なると、世界の投資家や株主は各企業の決算書を比較することが困難になります。高校野球のルールが各学校で異なると、全国大会を行うことが困難になるのと同じイメージです。そのため、国際的に統一された会計基準として、IFRSが作成されています。
(2) 各国の状況とリース会計基準の状況
米国や日本では、自国基準を保持しながら、自国基準とIFRSとの差異を縮小することで、IFRSと同じような会計基準を採用する方向で進めてきましたが、IFRSを自国の会計基準として採用する国が急増しています。
リース会計基準についても、2016年にIASBによってIFRS第16号「リース」(以下「IFRS第16号」)が公表され、同年2月に米国の会計基準を設定している米国財務会計基準審議会(Financial Accounting Standards Board:FASB)がTopic842「リース」(以下「Topic842」)を公表しました。IFRS第16号とTopic842ではどちらも、借手の会計処理は、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて、資産と負債を計上する「使用権モデル」を採用することとしています。
今まで見てきた通り、現状、日本では、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「企業会計基準第13号」)にてオペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う(いわゆる賃貸借処理)とされています。
そのため、同じ取引でも、企業会計基準第13号に基づいて決算書を作成した場合と、IFRS第16号やTopic842に基づいて決算書を作成した場合では、決算書への影響が異なるため、決算書を比較することが困難になってしまいます。
そこで、日本の会計基準を設定している企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan:ASBJ)が検討を重ね、2023年5月2日に企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」(以下「本公開草案」)を公表しました。
2 本公開草案の概要
次に本公開草案について、細かい点には言及せず、主に開発にあたっての基本的な方針を確認しようと思います。
(1) リースの定義とリースの識別
本公開草案では、借手に関する用語の定義は、本公開草案に関連があるものについて、IFRS第16号の定義を取り入れ、貸手に関する用語の定義は、現行基準における定義を基本的に踏襲することとしています。
リースの定義は、IFRS第16号と整合させて、「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」(本公開草案第5項)とすることを提案しています。
また、企業会計基準第13号にはなかったリースの識別に関する定めについても、基本的にIFRS第16号と整合させて、借手と貸手の両方に適用することを提案しています。
(2) 借手の会計処理
借手の会計処理について、基本的な方針としては、IFRS第16号のすべてを取り入れるのではなく、主要な内容のみを取り入れ、簡素で利便性が高いなど、実務に配慮した方策が検討されています。
具体的には、本公開草案では、IFRS第16号と同じく、ファイナンス・リースかオペレーティング・リースかに関係なく、すべてのリースについて、貸借対照表ではリース開始日に使用権資産とリース負債を計上し、損益計算書上では使用権資産に係る減価償却費とリース負債に係る利息費用を計上する「単一の会計処理モデル」を採用することを提案しています。
ただし、以下の場合は、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができます。なお、最後の②(ⅱ)(ロ)以外は、現行基準を踏襲しています。
① 短期リース(リース開始日において、借手のリース期間が12ヶ月以内であるリース)
② 少額リース
(ⅰ) 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用される場合で、借手のリース料が当該基準額以下のリース
(ⅱ) 次のいずれかを満たすリース
(イ) 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、リース契約1件当たりの借手のリース料が300万円以下のリース
(ロ) 原資産の価値が新品時におよそ5,000米ドル以下のリース
(3) 貸手の会計処理
貸手の会計処理については、IFRS第16号とTopic842がどちらも抜本的な改正が行われていないため、以下の点を除き、基本的に企業会計基準第13号の内容を維持することとしています。
- 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」との整合性を図る点
- リースの定義及びリースの識別
* * *
なお、本稿執筆時点においては、本公開草案に寄せられたコメントへの対応がASBJで検討されています。検討を踏まえ、改正が確定された際には、本公開草案からの変更箇所もあると思われますので、その点については注意が必要です。
(了)
「〈一から学ぶ〉リース取引の会計と税務」は、毎月第1週に掲載されます。