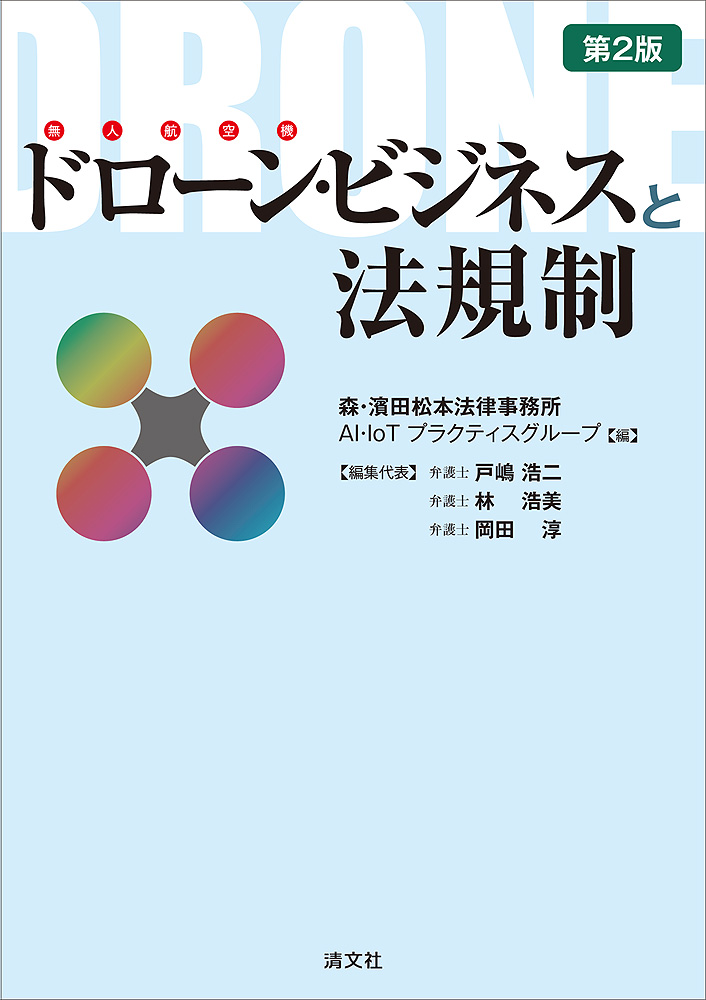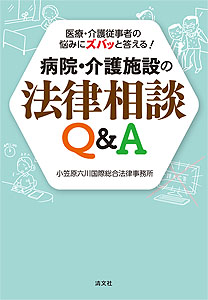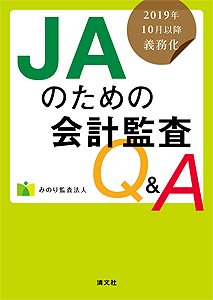企業担当者のための
「不正リスク対応基準」の理解と対策
【第2回】
「企業自ら不正リスク要因を検討することの重要性」
公認会計士 金子 彰良
はじめに
不正な財務報告の事案から、具体的な不正の手法を分析すると内部統制の脆弱性があることが多い。その原因として考えられるのは、不正リスクを認識することができなかったため、内部統制を整備できなかったというものである。
このような不正リスクを想定するためには、不正リスク要因を不正が発生するメカニズムとして、理解する必要がある。
実際の不正な財務報告の事案から、不正リスク要因を検討することができる。そして、不正の理解と適切な対策には、3つの不正リスク要因を考慮しなければならない。そのために、不正リスク対応基準では付録1として、不正な財務報告に関連する不正リスク要因が例示されている。
前回の不正リスク対応基準をめぐる現状把握と不正リスクの想定に続き、【第2回】では、不正リスクを識別するための不正リスク要因の検討の重要性について解説する。
なお、文中の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解である。また、本稿で触れている個別の事案については、これらが一般的にも起こりうることを鑑みて、企業が不正リスクに対応する際の参考になることを目的として記載している。特定の会社の経営管理のしくみを批判・批評することを目的としていないことをお断りしておく。
《不正リスク要因の検討》
不正な財務報告の事案から、具体的な不正の手法を分析すると内部統制の脆弱性があることが多い。
不正が発生した背景には、経営者による内部統制の無視のように、内部統制が無効化された状況がその原因であることもあるが、不正な財務報告の事案における原因や不正の手法を分析すると内部統制の脆弱性があることも多い。この点について、昨年3月に訂正内部統制報告書で開示すべき重要な不備があり内部統制は有効でないとの評価結果を報告した明治機械株式会社の事案の一部「押込販売」「架空販売」の概要をみてみる。
まず、関連する業務プロセスの概要と売上計上基準は次のとおりであった。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。