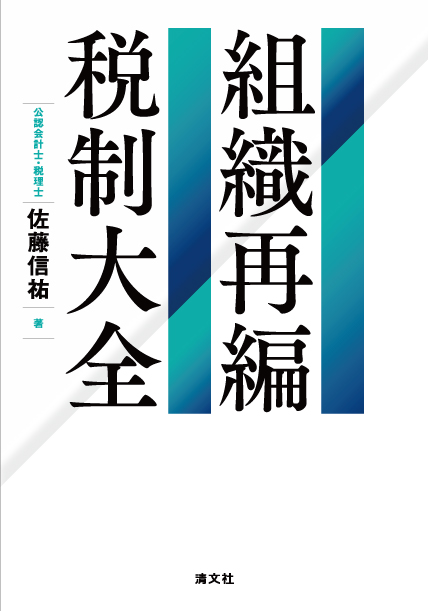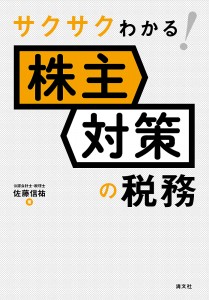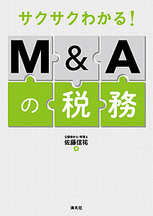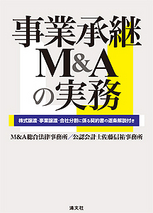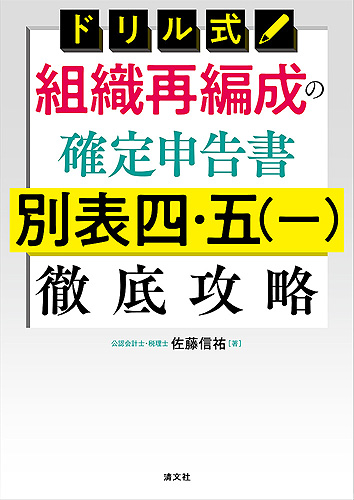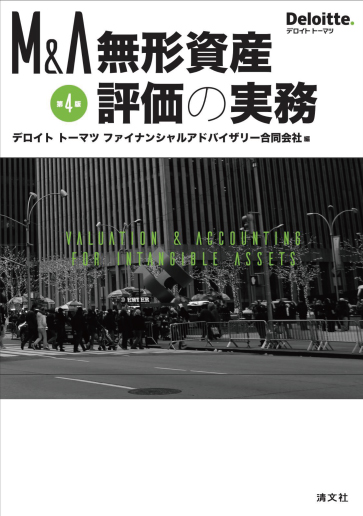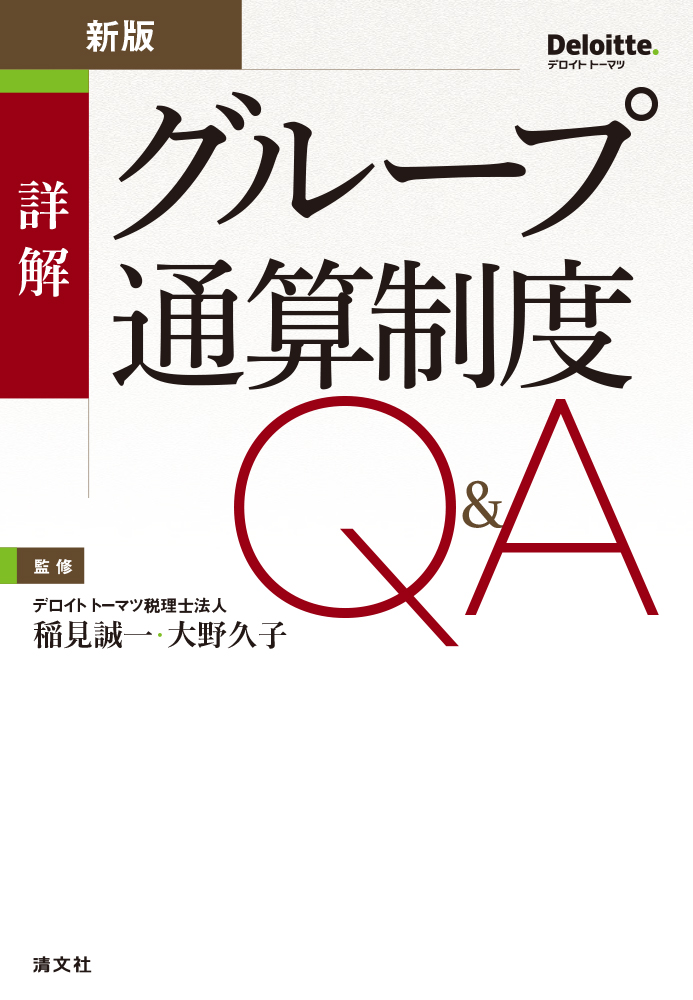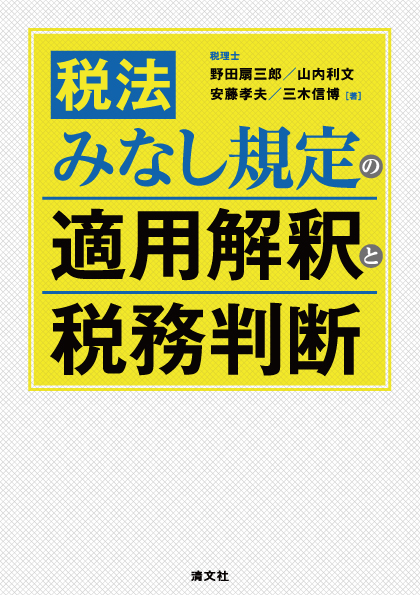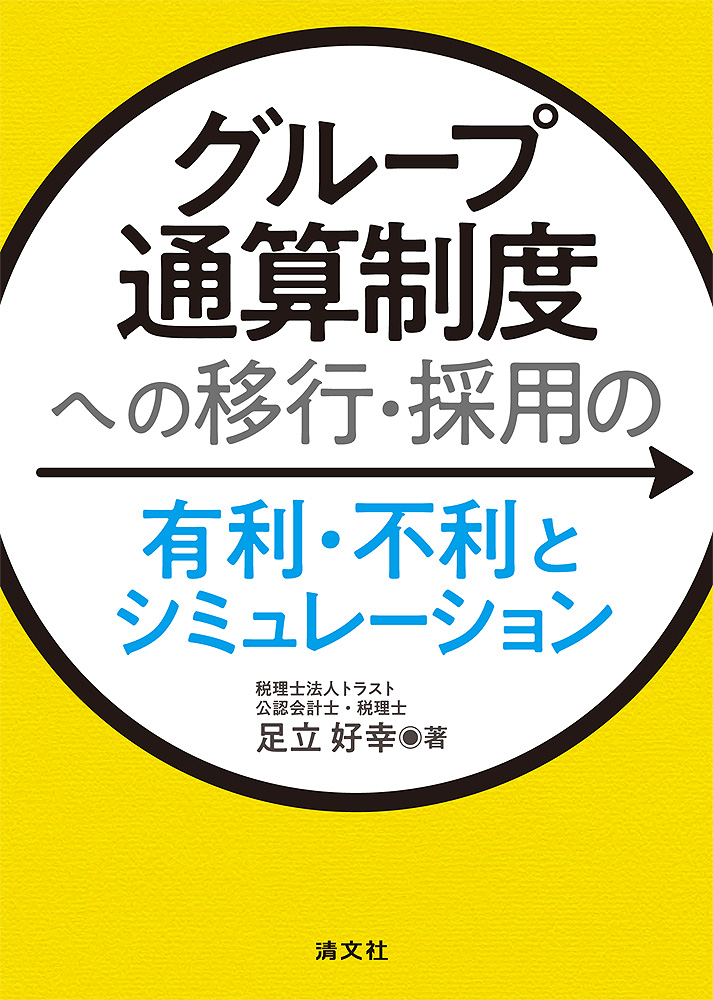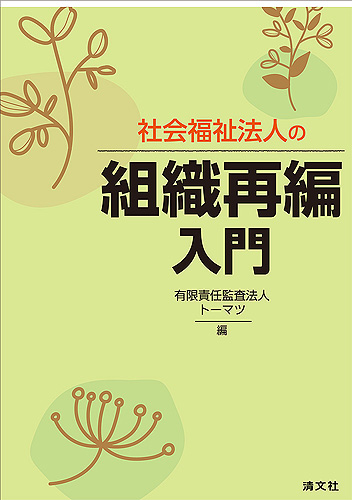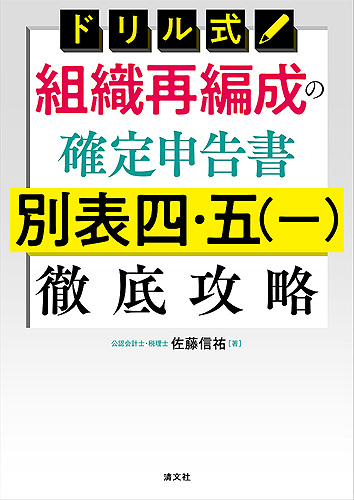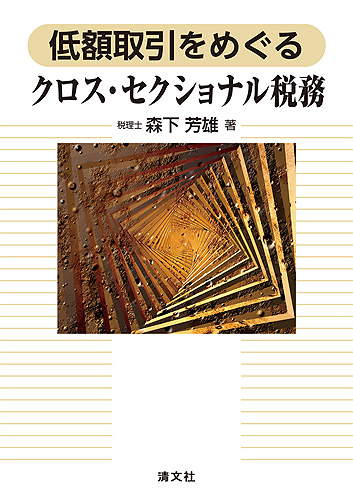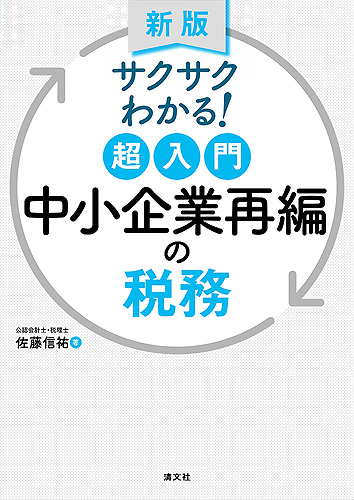組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の
現行法上の問題点と今後の課題
【第1回】
「序論」
公認会計士 佐藤 信祐
《第1章:総論》
1 はじめに
「連結納税制度と組織再編税制の整合性がない」という問題があったことから、令和2年度税制改正による連結納税制度からグループ通算制度への移行においては、組織再編税制との整合性が意識されている(※1)。
(※1) 連結納税制度に関する専門家会合「連結納税制度の見直しについて」9頁(令和元年)。
その結果、グループ内の適格組織再編成を完全支配関係内の適格組織再編成と支配関係内の適格組織再編成に分けて規定したことによる弊害がむしろ明らかになったようにも思える。それだけでなく、それぞれの時代における要請に応える形で改正を重ねていった結果、全体からすると整合性が保たれているとは言い難い。今後、組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度について整合性の保たれた制度にするためには、さらなる改正が必要になると思われる。
結論を先取りすれば、①グループ通算制度のうち相当程度をグループ法人税制に取り込む必要があると考えており、かつ、②グループ内の適格組織再編成を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係のある法人との間で行われる組織再編成」としたうえで、金銭等不交付要件、主要資産等引継要件、従業者従事要件及び事業継続要件を課さないようにすべきであると考えている。本連載において、そのような税制改正の可能性について探っていきたい。
そのほかにも、組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度には、様々な問題点がある。実務家の立場から言い換えると、「抜け穴」と「落し穴」があるということが言える。立法論の立場からすれば税制改正をすべきということになるが、実務家の立場からすると「抜け穴」が使える場合には租税回避に該当しないようにする必要があり、「落し穴」にはまりそうな場合には避けるようにする必要があるということが言える。そのため、こういった立法論による分析も実務家にとって決して無駄なことではない。
さらに、「抜け穴」や「落し穴」があるということは、今後の税制改正の可能性があるということなので、将来的な税制改正に備えるという意味でも重要なことであると思われる。本連載では、現行法上の問題点を探るとともに、今後の税制改正の可能性についても探っていきたい。
2 グループ通算制度の加入に伴う時価評価課税から見える現行法上の問題点
「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点とりまとめ」(平成21年)では、中長期的課題として、以下の3点を掲げていた。
① グループ法人税制の範囲について、100%未満のグループ会社を対象とすること
② 通算子法人(※2)の範囲について、100%未満の子会社も対象とすること
③ 金銭を対価とする組織再編成であっても、適格組織再編成を認めること
(※2) 連結納税制度からグループ通算制度に移行する前に公表されたものであるため、厳密には、「連結子法人」と表記されていたが、分かりやすさの観点から「通算子法人」と表記している。
このうち、③については、平成29年度税制改正により、吸収合併及び株式交換における金銭等不交付要件が緩和され、合併法人又は株式交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合には、金銭等不交付要件が課されないことになった(法法2十二の八・十二の十七)。
これに対し、①②については、未だ先送りの状態となっているが、今後の税制改正の対象になる可能性は否めない。もし、そのような税制改正がなされた場合には、支配関係内の適格組織再編成を廃止し、完全支配関係の定義を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係」に改正すべきであると考えている。この考え方は、筆者独自の理論ではなく、上記①②を受けてのものであり、「3分の2以上」という数値を持ち出したのは、金銭等不交付要件との整合性を意識してのものである。
そもそも金銭等不交付要件の緩和の対象が吸収合併及び株式交換に限定されているのは、新設合併及び株式移転については、組織再編成の対価が株主ごとに異なるのは租税回避防止の観点から問題があるからであり、分割及び現物出資については、グループ法人税制との整合性が取れないからである(※3)。すなわち、完全支配関係の定義を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係」にしてしまえば、グループ法人税制の対象が広がり、グループ内の組織再編成のすべてに対して金銭等不交付要件を緩和することができる。
(※3) 藤田泰弘ほか『平成29年度税制改正の解説』327頁(国立国会図書館HP、平成29年)。
さらに、支配関係内の適格組織再編成に対しては、個別資産の売買取引との違いを設けるために、事業単位の移転であることを要求し、その結果、主要資産等引継要件、従業者引継要件及び事業継続要件がそれぞれ設けられることになった(※4)。これに対し、グループ通算制度では、組織再編税制との整合性から、以下の法人については、グループ通算制度の加入に伴う時価評価課税の対象から除外されている(法法64の12①、法令131の16③~⑤)。
(※4) 「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」参照(朝長英樹『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』39頁(日本租税研究協会、平成13年)掲載)。
イ.適格株式交換等により加入した株式交換等完全子法人
ロ.通算グループ内の新設法人
ハ.適格組織再編成と同様の要件として次の要件(加入の直前に支配関係がある場合には、(イ)から(ハ)までの要件)のすべてに該当する法人
(イ) 通算親法人との間の完全支配関係継続要件
(ロ) 従業者従事要件
(ハ) 事業継続要件
(ニ) 通算グループ内のいずれかの法人との間の事業関連性要件
(ホ) 事業規模要件又は特定役員引継要件
組織再編税制との整合性を考えれば、組織再編成の直前に支配関係があり、組織再編成後に当該支配関係が継続することが見込まれていれば、支配関係内の組織再編成に該当することから、このような制度でもやむを得ないのかもしれないが、そもそも支配関係内の適格組織再編成という制度がなく、完全支配関係内の適格組織再編成と共同事業を行うための適格組織再編成という制度だけであれば、このような問題は生じることはない。
このように、支配関係内の適格組織再編成という制度を認めてしまったが故に、グループ法人税制ともグループ通算制度とも整合性が取れなくなってしまっている。もちろん、現行法のように、完全支配関係の定義が「発行済株式又は出資の全部を保有する関係」となっていれば、支配関係内の適格組織再編成を廃止すべきという議論は、実務のニーズを無視した暴論ということになるが、完全支配関係の定義を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係」としてしまえば、組織再編成を行うためには株主総会の特別決議が必要になることから(会社法309②十二)、現行法上の支配関係内の組織再編成のうち多くのものが完全支配関係内の組織再編成として取り扱うことができるため、それほど暴論というわけでもなくなってくる。
さらに言えば、支配関係の定義が「発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有する関係」となった経緯は、当時の商法を参考にしただけであり、理論的な根拠があるわけではない(※5)。当時の大蔵省主税局から経団連に対して「80%でどうか」という提案があった(※6)ということも考えると、完全支配関係の定義を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係」とすることは、それほど違和感のある話でもないと思われる。
(※5) 阿部泰久「改正の経緯と残された問題」江頭憲治郎ほか編『企業組織と租税法(別冊商事法務252号)』83頁(商事法務、平成14年)参照。
(※6) 阿部前掲(※5)83頁。
* * *
次回では、グループ通算制度及び受贈益の益金不算入の範囲を拡大することの問題点について解説する予定である。
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。