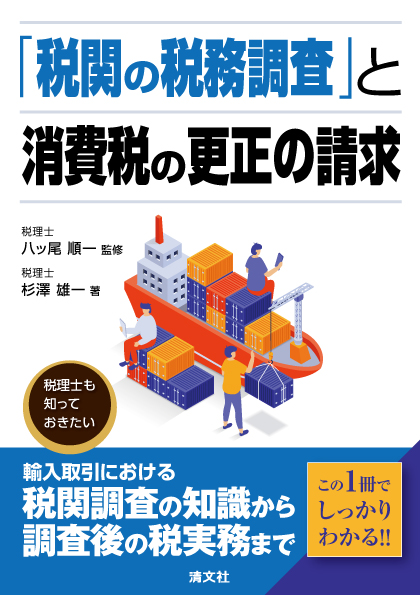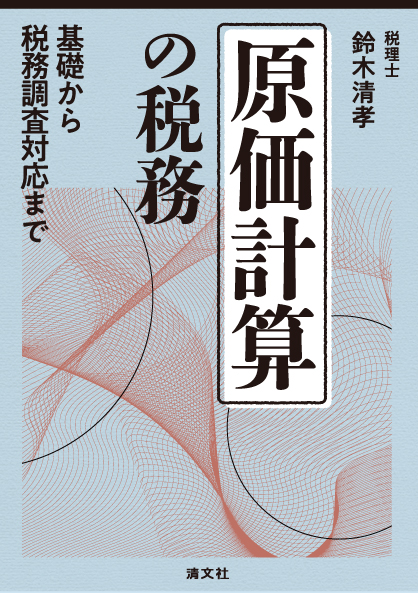〔弁護士目線でみた〕
実務に活かす国税通則法
【第2回】
「改めて『税務調査とは何か』を理解する」
弁護士 下尾 裕
1 はじめに
「国税通則法は何を定める法律であるか」と問われた場合、本誌読者の皆様が最初に頭に浮かぶのは、おそらく税務調査であろう。
税務に絡む実務家の中で、税務調査に一切関わらないという方はごく少数と思われ、それだけ重要性の高い事柄である。
今回は、国税通則法における税務調査の定めについて取り上げてみたい。
2 税務調査(国税通則法における「調査」)を理解する意味
「税務調査」は、国税通則法においては「調査」という文言で表示されており、法的には「質問検査権の行使」と説明される。
この質問検査権は、納税者に受忍義務があり、正当な理由がなく応じなければ罰則等がある(国税通則法第128条)という意味では、実質的な強制力のあるものである。ただし、刑事事件における逮捕や捜索・差押とは異なり、納税者の同意なく調査資料等を取得することはできず、本当の意味での強制力が伴うものではない点に特徴がある。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。