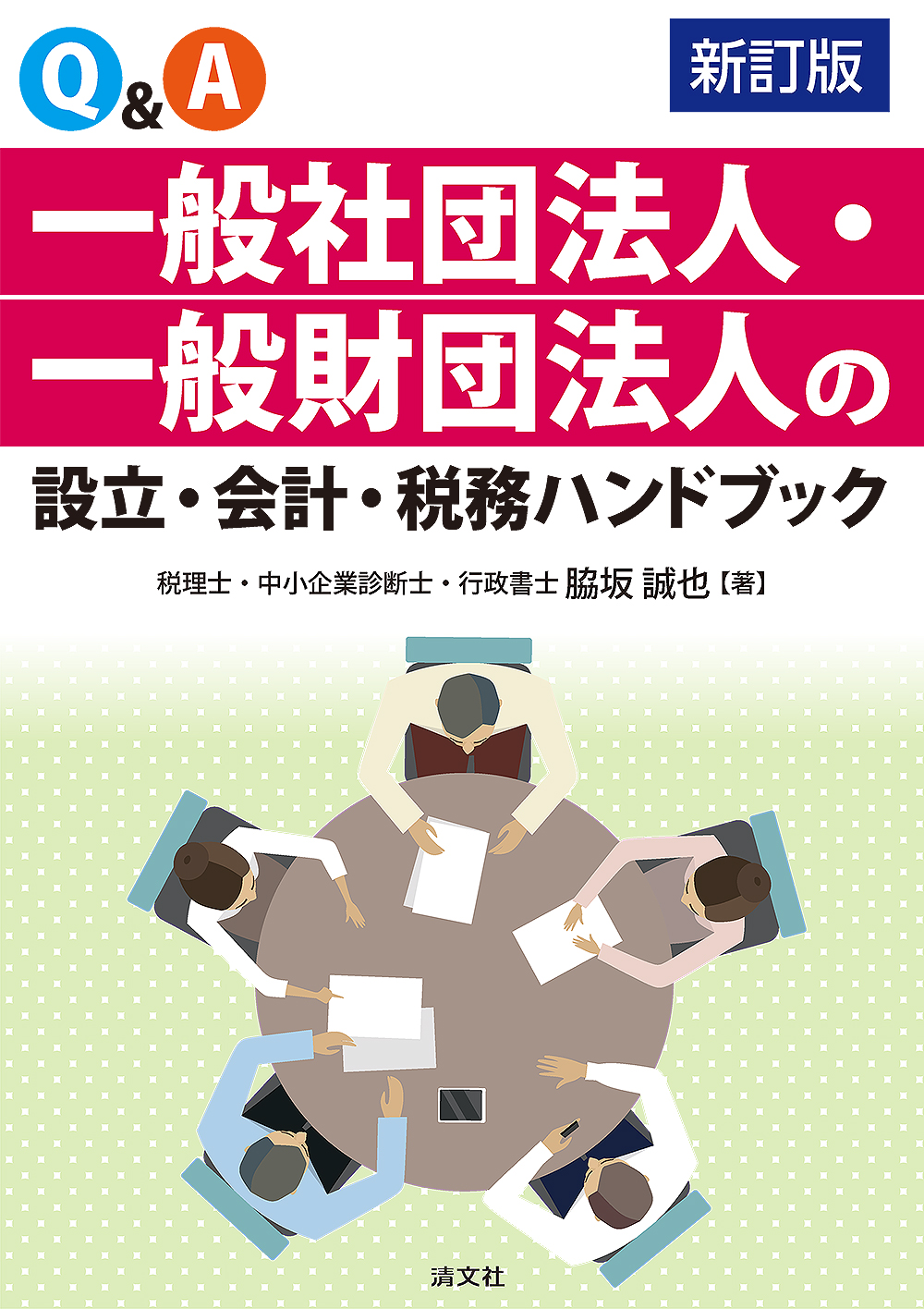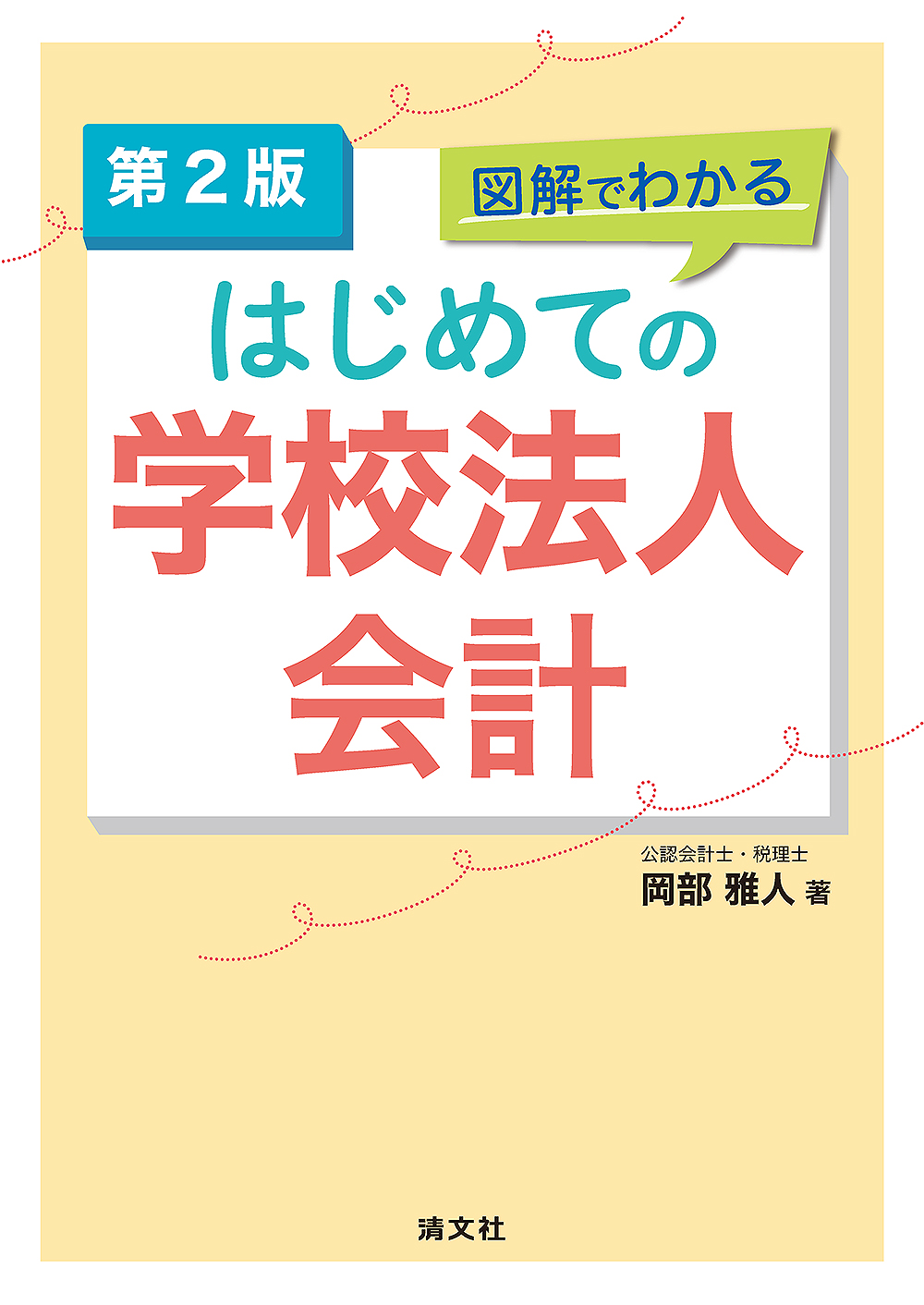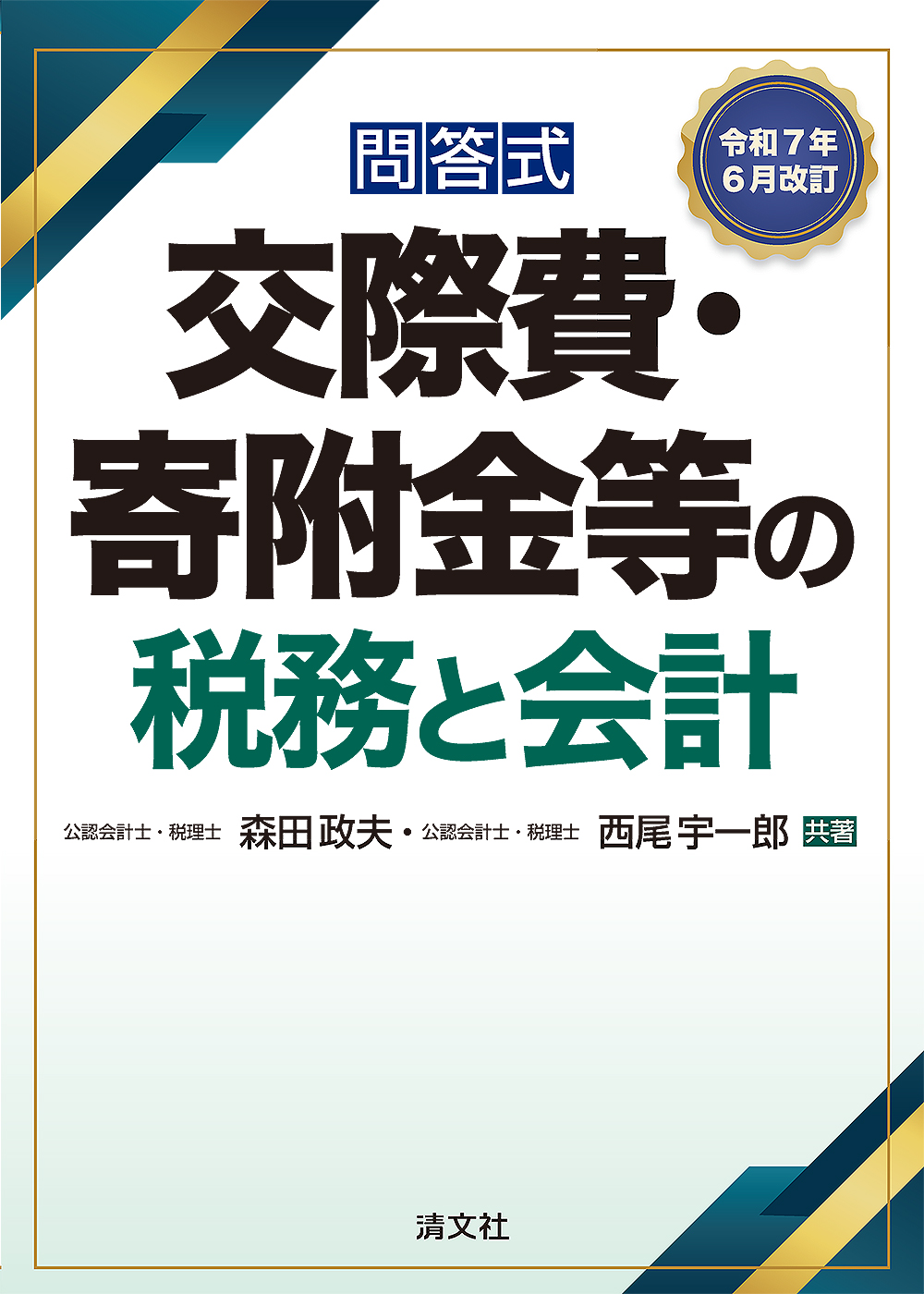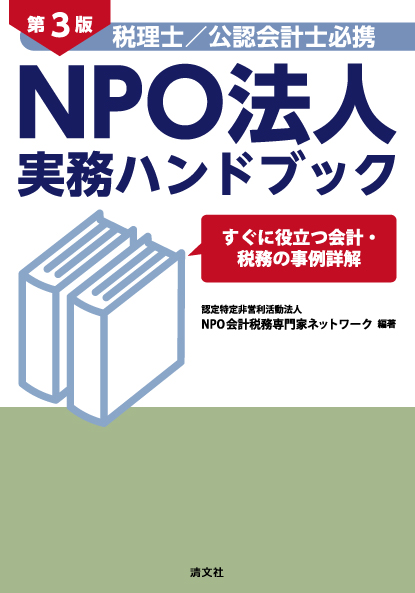遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント
【第1回】
「近年の遺贈寄付の高まりと税理士の役割」
税理士・中小企業診断士・行政書士
脇坂 誠也
1 遺贈寄付が注目される背景
今、遺贈寄付が注目されている。遺贈寄付とは、遺言により学校法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人などの非営利団体や国、地方公共団体(以下「非営利法人等」とする)に財産の全部又は一部を寄付することや、相続人が相続財産の全部又は一部を非営利法人等に寄付することをいう。
遺贈寄付が注目されている要因はいくつかある。
1つ目は人々の社会貢献意欲の高まりである。内閣府が毎年実施している「社会意識に関する世論調査」によれば、「社会への貢献意識」について、1974年の調査開始から、右肩上がりで上昇しており、2020年の調査では、63.4%になっている。また、民間団体による調査によれば、社会の役に立つために、自分の遺産の一部を寄付したいと思う人は4人に1人程度で存在するというアンケート結果もある。
2つ目は、社会構造の変化である。今後は、将来未婚や配偶者を亡くした「おひとりさま」の高齢者が増加することが予想される。相続人がなく、遺言がない場合、遺産は国庫に帰属されるが、その総額は、年間600億円を超え、わずか4年で1.4倍に増加している。
民間団体による調査によれば、配偶者と子供の有無別に「遺贈寄付に前向き」な割合は、直系卑属がいる「ひとり親」では21.0%、「父母子」では21.9%であるのに対し、直系卑属がいない「独身」では50.0%、「ふたり夫婦(子供なし)」では46.8%となっている。相続人がいなかったり、相続人がいても、配偶者や子供がいなければ、自身の遺産は社会の役に立つことに寄付をしたいと考える人が増加することが予想される。
3つ目は、遺贈寄付の受け入れ態勢が充実しつつあることである。特定非営利活動法人「国境なき医師団日本」が行っている「遺贈寄付意識調査」によると、遺贈寄付の障害になることとして、「遺贈の方法(どんな手続きが必要か不安、など)」が36.2%で最も高く、「寄付する団体選び(詐欺にあわないか不安、など)」が33.0%と続いている。
現在、全国のコミュニティ財団を中心に遺贈寄付の相談窓口の設置が進んでおり、民間の事業者も、遺贈寄付希望者の希望に合わせた寄付先や方法を紹介するサービスが始まっている。また、遺贈寄付を受ける非営利法人等も、遺贈寄付に積極的に取り組む法人が増加している。
2 遺贈寄付の現状
それでは、実際に遺贈寄付をする方はどれくらいいるのであろうか。
わが国における遺贈寄付の正確な統計はないが、相続税の申告をした人については、国税庁から公表されている。平成30年の数字の集計(認定NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会が国税局に開示請求して集計)では、遺言による寄付は99件で約56億円、相続人による相続財産の寄付は579件で約410億円となっている。
相続税の申告に係る被相続人が116,341人、相続人が258,498人(国税庁『平成30年分 相続税の申告事績の概要』より)であるから、遺言による寄付は0.1%以下、相続人による相続財産の寄付が0.2%程度であり、非常に少ない。まだ、大部分の人が、遺贈寄付について考えたとしても、実行をしている人はほとんどいないことがうかがい知れる。
ただし、件数や金額は、ここ数年、徐々に増えてきている。また、雑誌や新聞の広告等で遺贈寄付が取り上げられることが増えており、一部の公益法人等では遺贈寄付について大幅に増加していることも報告されている。
3 遺贈寄付における税理士の役割
遺贈寄付をしたいと思っている人は増えているが、実際に実行するためにはハードルは高い。その原因は何であろうか。
『遺贈寄付に関する実態調査』(2020年、一般社団法人日本承継協会)によれば、「遺贈寄付に興味がある」と回答した方の半数以上が寄付の手続きや方法を相談したいと思っているが、どこに相談していいのかわからないと答えている。遺贈寄付を実行するためには、それをサポートする人が必要なのである。そのサポート役として税理士は相応しいのではないだろうか。遺贈寄付には、税務の問題は切り離せない。また、日頃から中小企業のオーナーや資産家、あるいは確定申告などに関わっている税理士は、これらの方たちの身近で信頼できる相談相手として、最適である。海外の調査によれば、専門家などが資産承継の1つの手段として遺贈寄付という方法もあるということを触れることで、遺言で遺贈寄付をする人の割合が大幅に上昇するという調査も報告されている。
一方で、税理士がクライアント等に遺贈寄付について相談を受けたり、アドバイスをするためには、遺贈寄付の課税関係について正確に理解をする必要がある。
次回から、遺贈寄付をいくつかの種類に分けたうえで、税務上どのような取扱いになるのか、どのような点に注意をすべきかについて見ていくことにする。
(了)
「遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント」は、毎月第1週に掲載します。