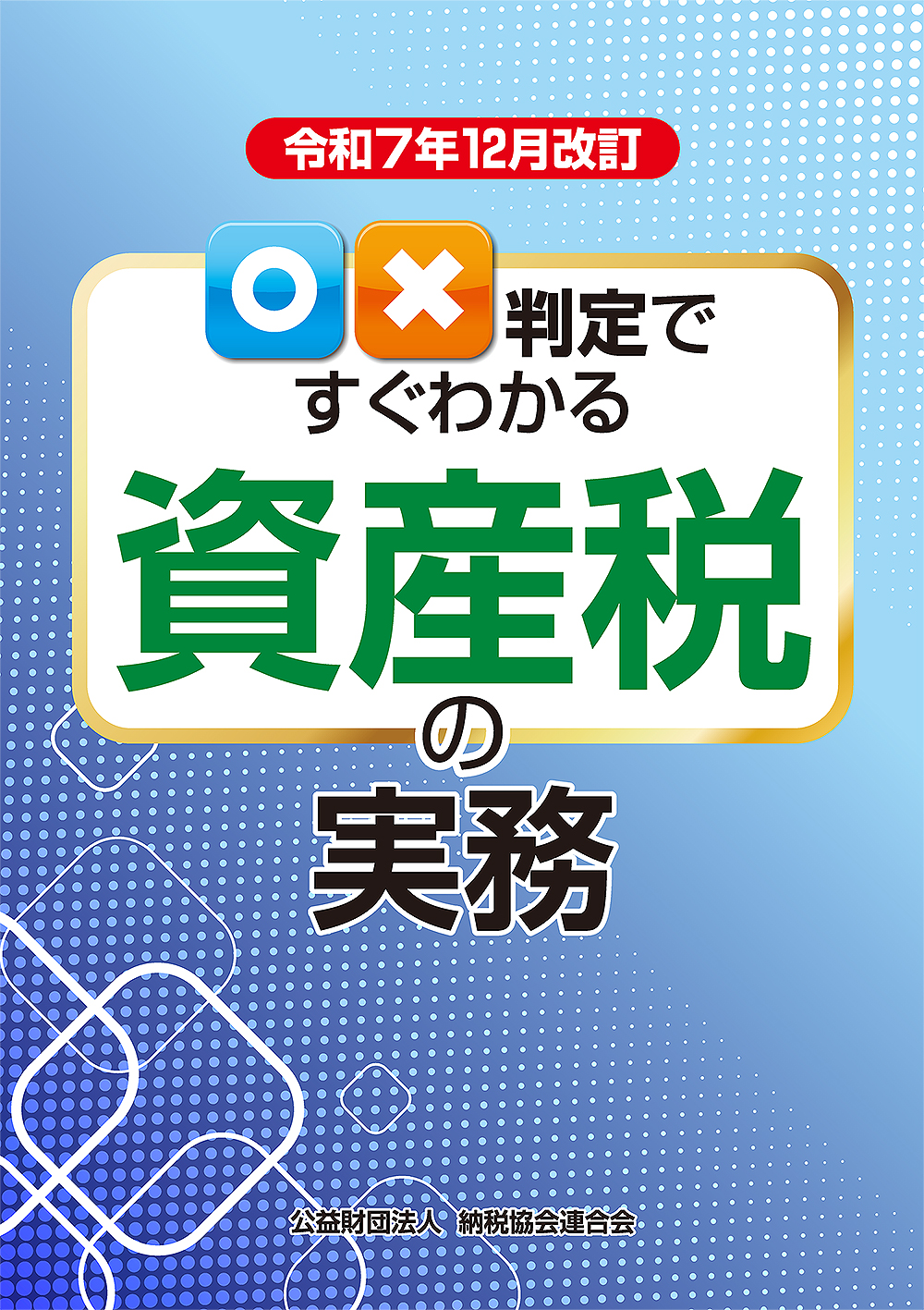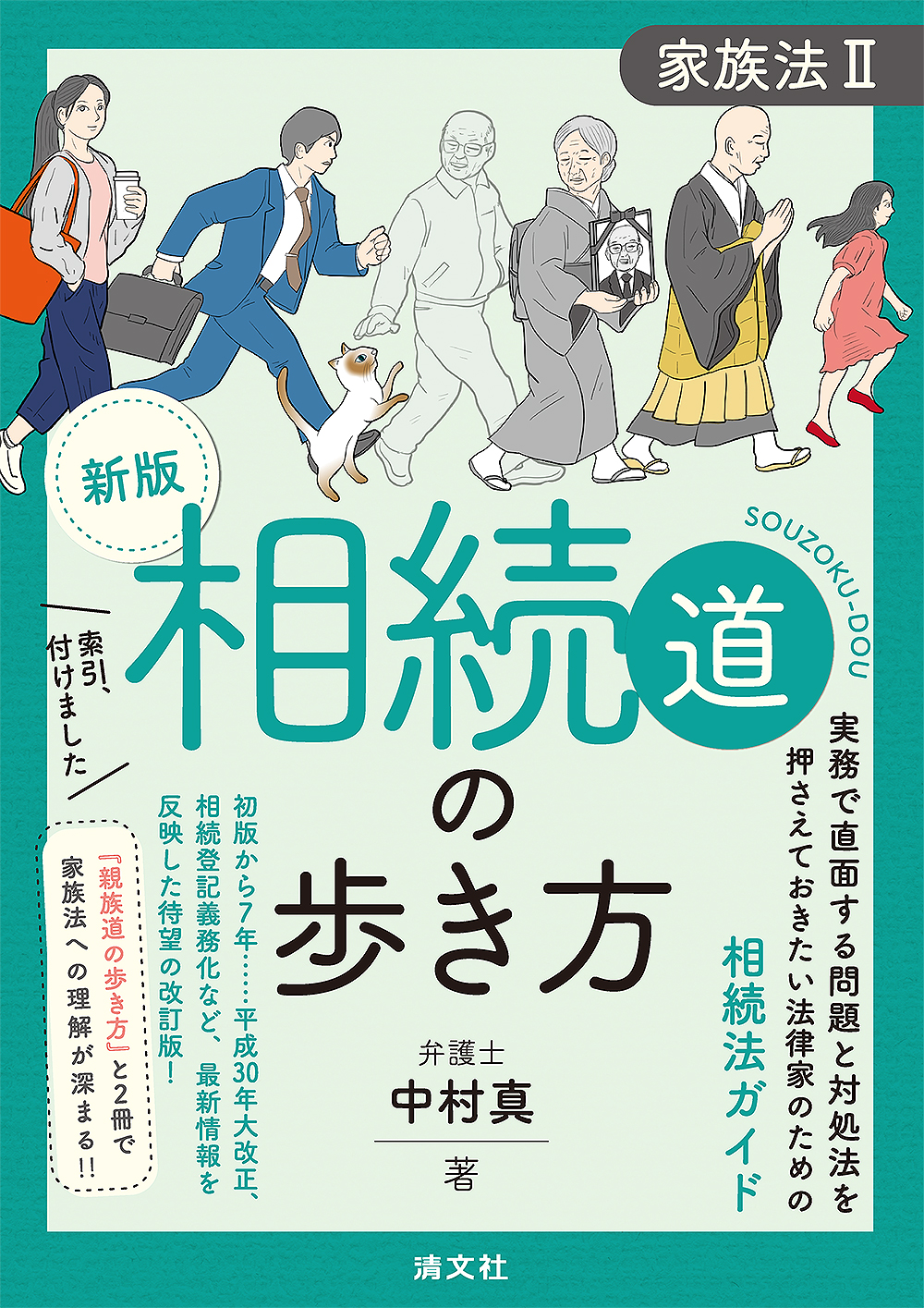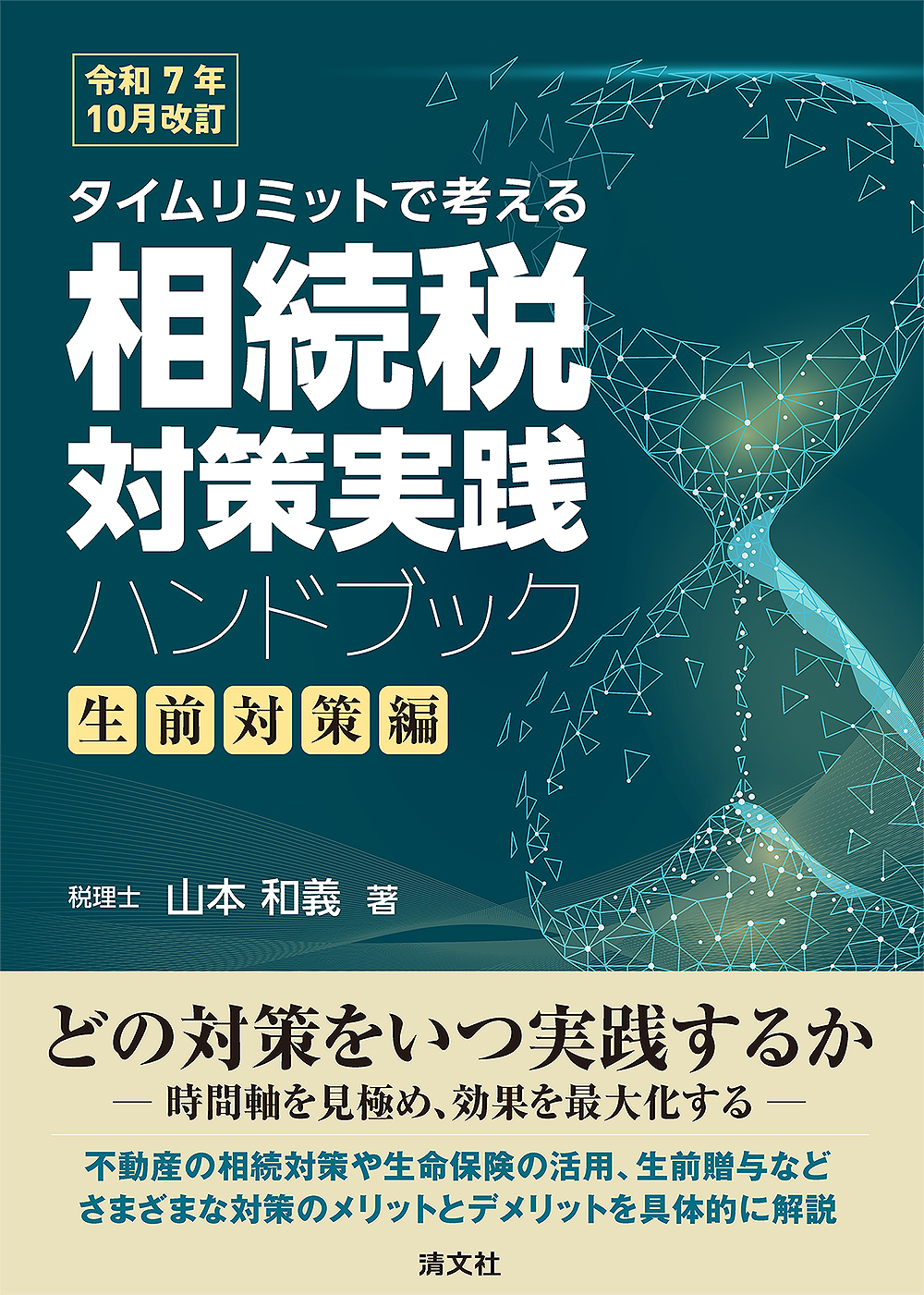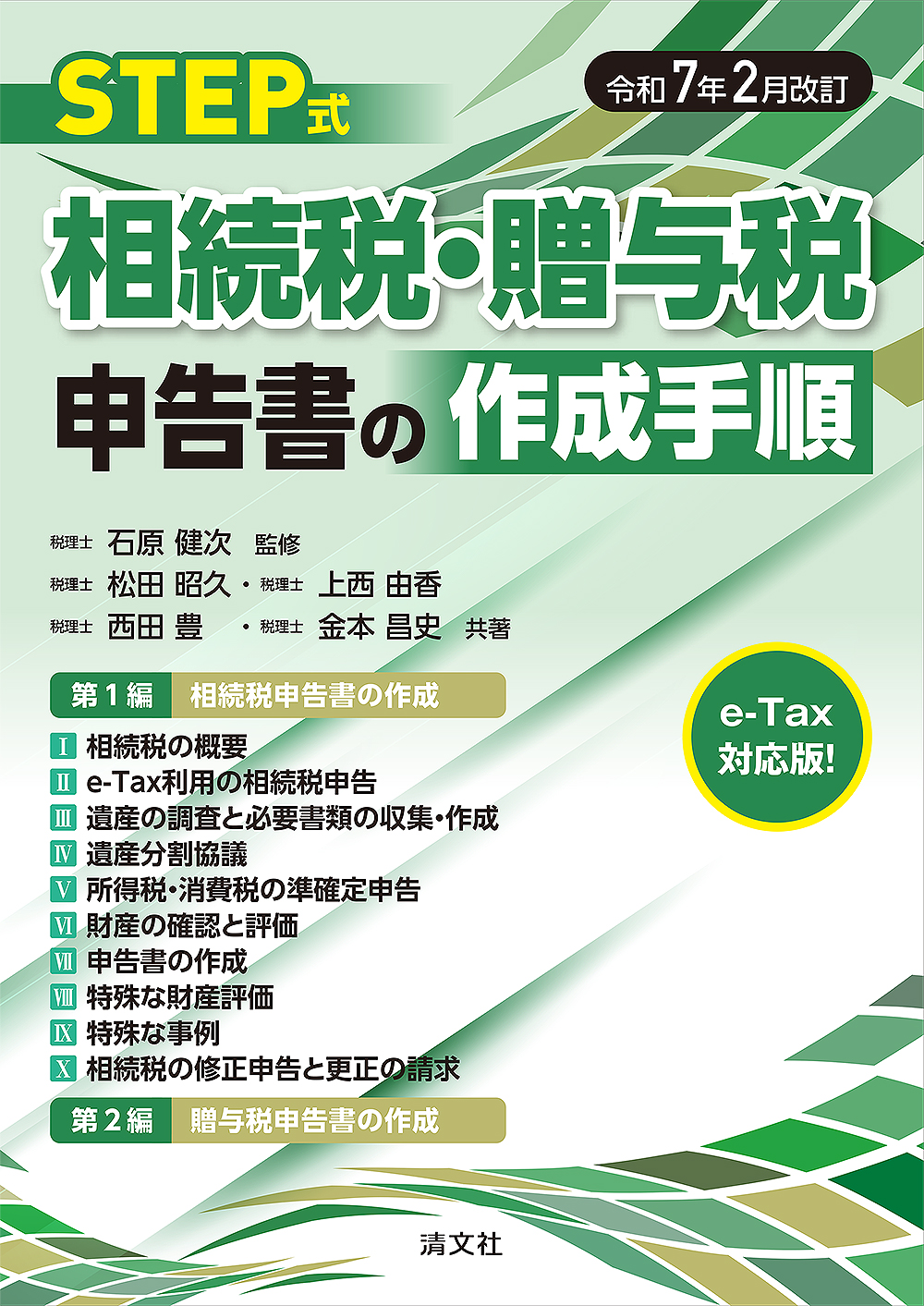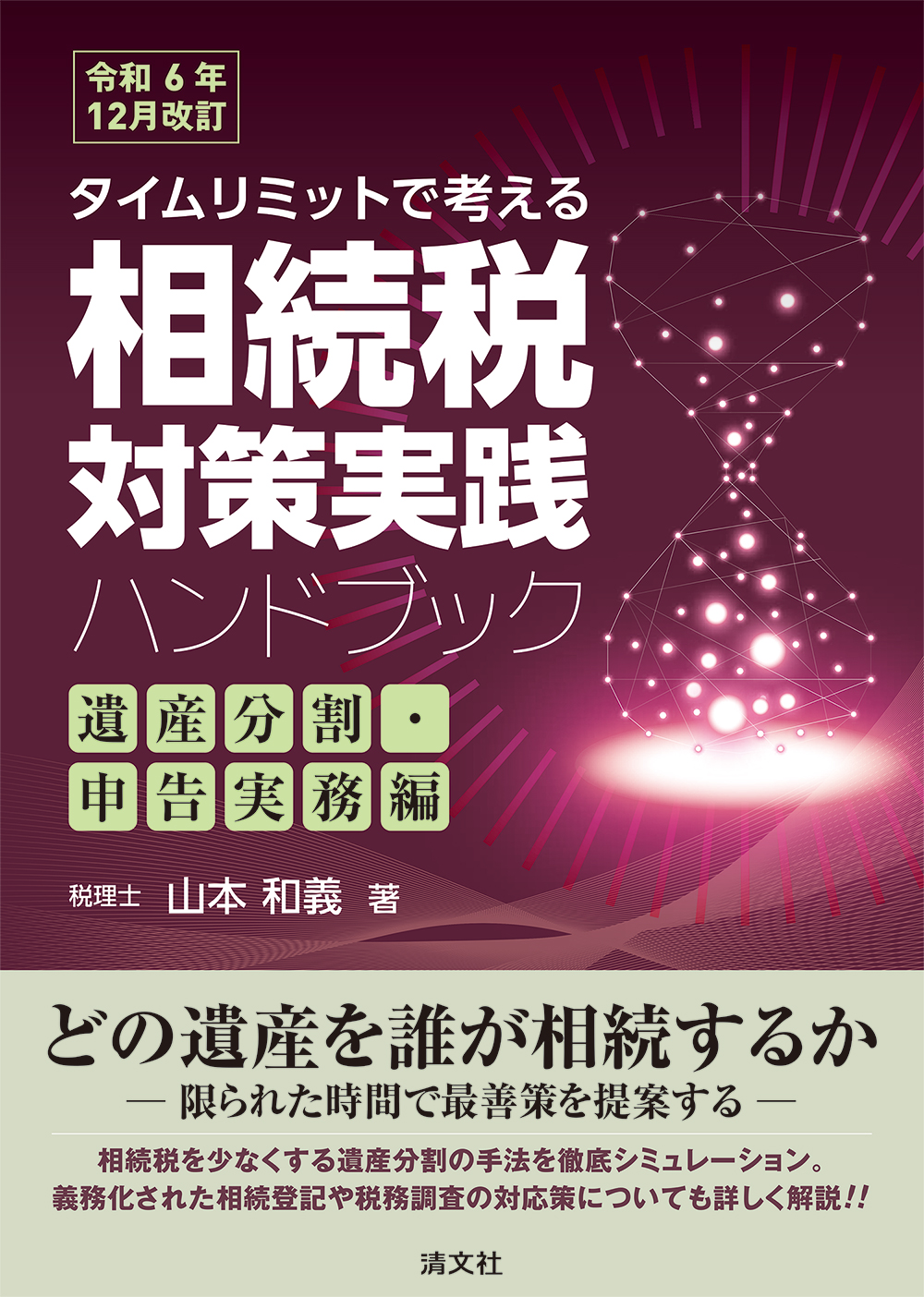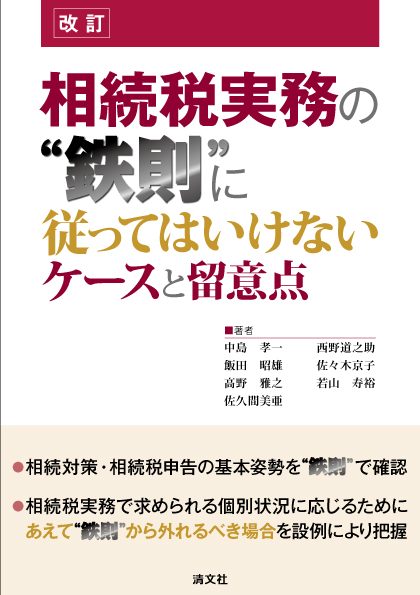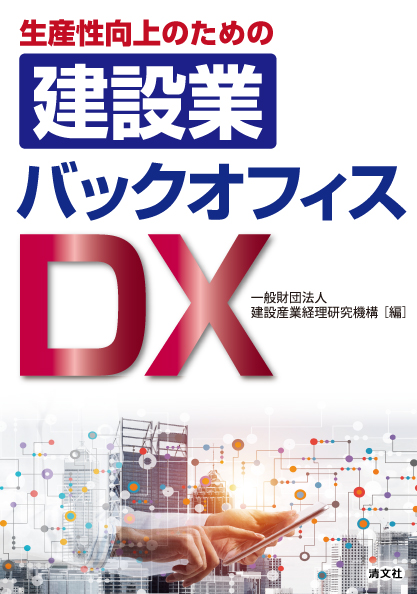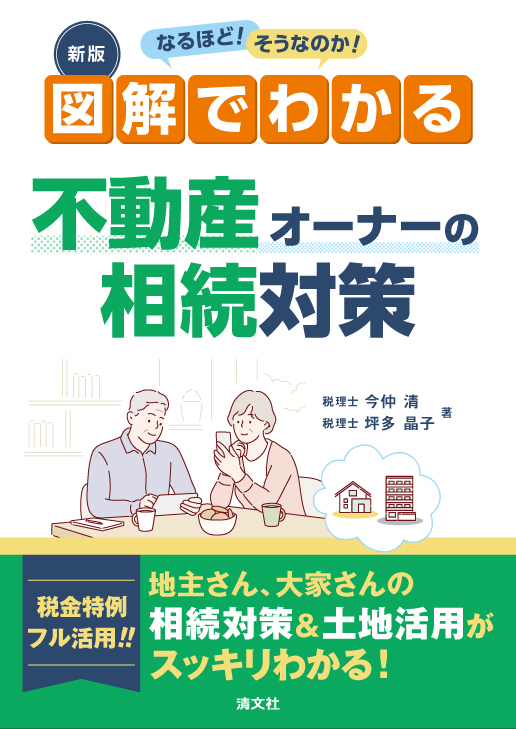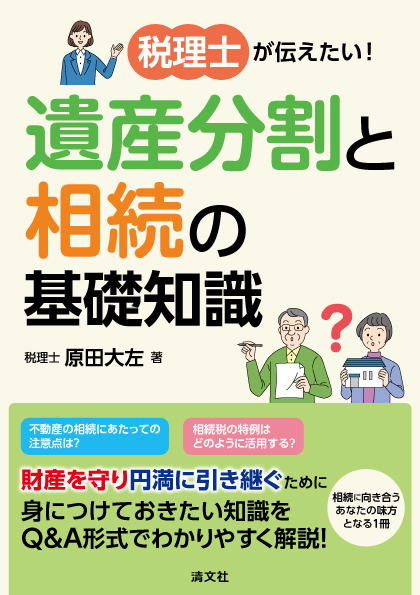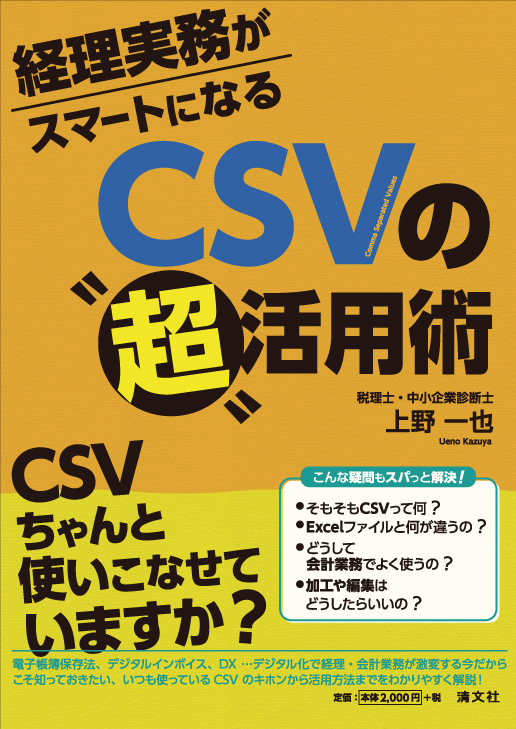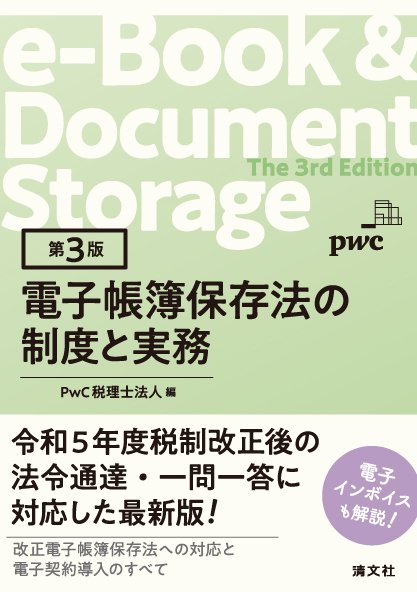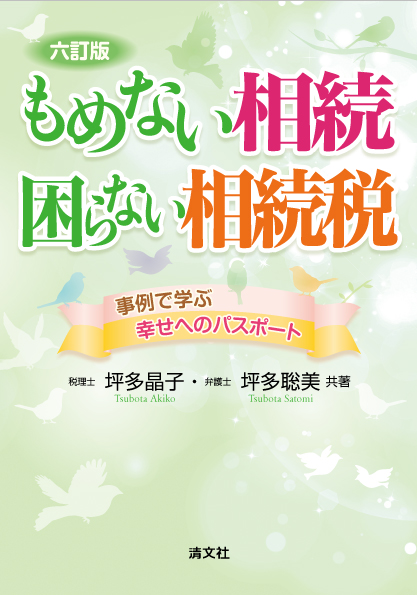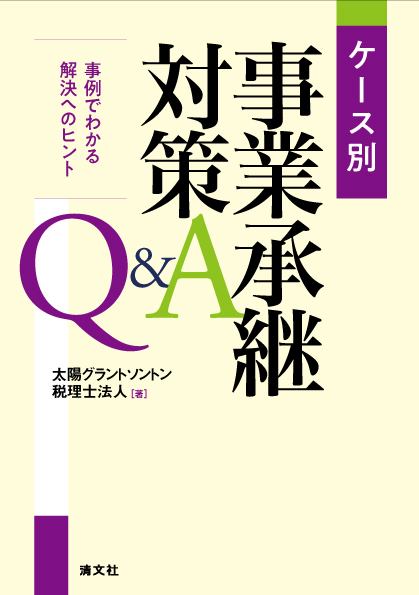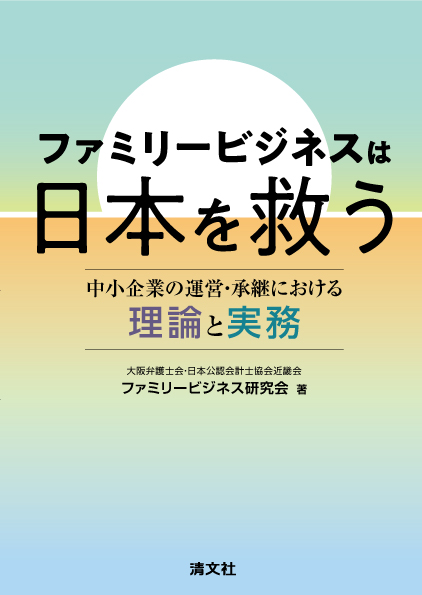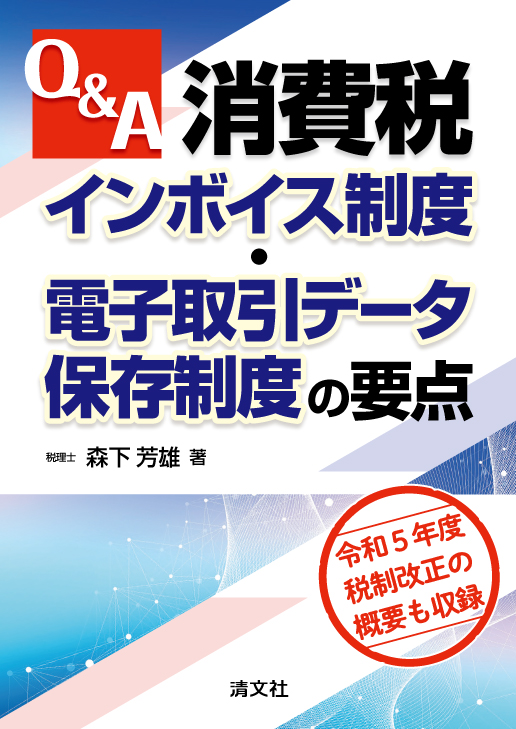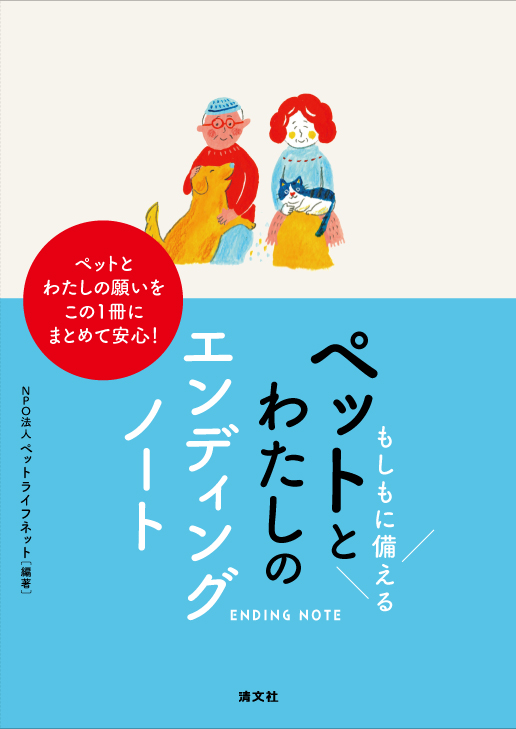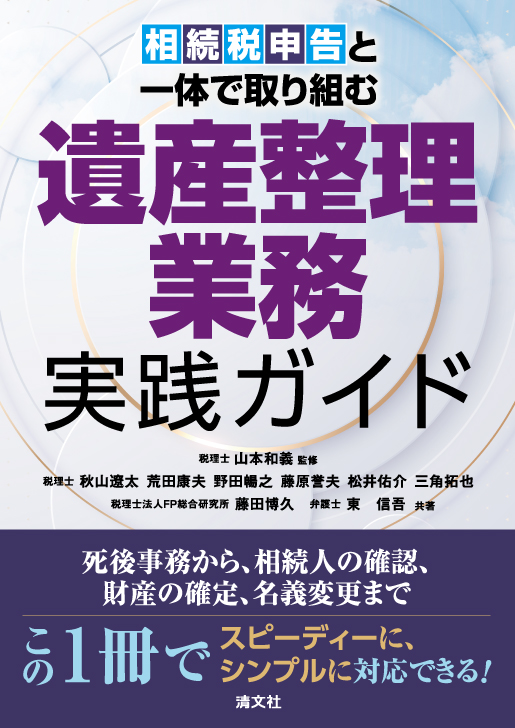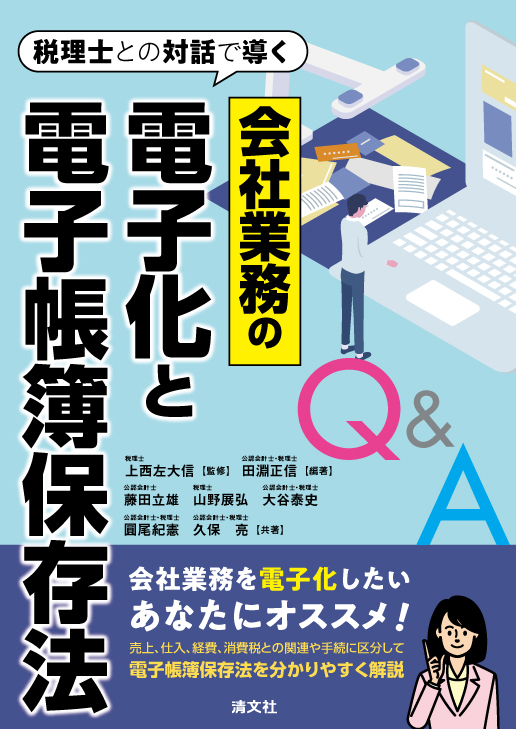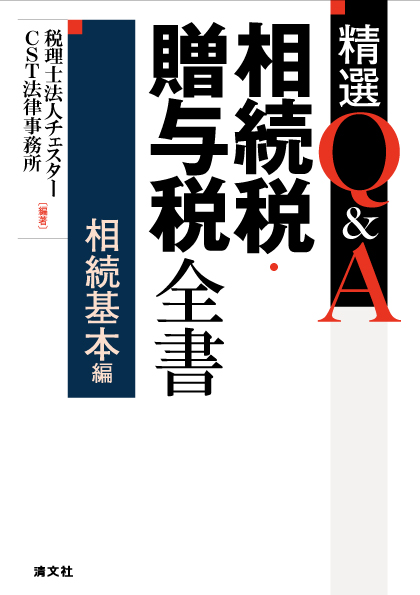対面が難しい時代の相続実務
【第1回】
「コロナショックがもたらした激変」
-コロナ“以前”と“以後”の現場の状況-
クレド法律事務所
弁護士 栗田 祐太郎
1 2020年コロナショックによる激震
令和の時代は、期せずして「コロナ」という3文字とともに歩みを始めた。
2020年1月のダイヤモンド・プリンセス号の一件から始まった“コロナショック”によって、文字どおり、日本を含めて世界中の、さまざまな場面での日常生活は激変した。
本連載は、現在もまだコロナウイルスの感染拡大が終息しない状況のもとで、①コロナがもたらした「人との接触・対面をできるだけ避けるべき(非対面・非接触)という社会的要請」と、従前からの社会の動きである「IT化・オンライン化」という波が相続実務にどのような影響を与えているか、そして、②このような状況下で、われわれ実務家はどのような工夫ができるかを考えてみたい。
なお、税理士や弁護士といった士業の日常業務で非対面化・非接触化が問題とされる場合、大きく分ければ、
(1) 事務所の「外」との関係(顧客や相手方当事者への対応など)
(2) 事務所の「内」での関係(所内での業務フローやテレワークの推進など)
の2つの側面に大別されよう。
本連載では、このうち「(1)事務所の「外」との関係」を取り上げることにしたい。
2 筆者の日常業務において実際に起こった変化
検討の出発点として、第1回では、コロナ下で推移した2020年3月以降において、筆者自身の日常業務に起こった変化を具体的に紹介したい。
相続実務に関係するものとして、次のような場面での変化が挙げられる。
場面①-法律相談・依頼者との打合せ
コロナ前
従来は、ほぼ全件で相談者・依頼者に事務所まで来所してもらい、会議室にて直接面談する形で法律相談・打合せを実施してきた。
コロナ後
新規相談も含めて約9割以上の相談・打合せが、電話・メール又はZoom等を利用しての非対面形式に切り替わった。
コロナによってまずもって大きく変化した点は、この場面である。
従来も、依頼者が遠方に居住していたり、深夜の時間しか空きがないような場合には電話やメールでの打合せを行ってきたが、大部分は事務所に来所してもらい、直接顔をあわせて打合せを行ってきた。
コロナ前は、Zoom等を利用してオンライン上でお互いの顔が見える形で打ち合わせることは、筆者の事務所では実施した例はなかった(依頼者の側からも特にそのような要望はなかった)。
しかし、コロナ後は、上記のあり方が180度転換した。
相談・打合せは原則として電話やメール、Zoomを利用した非対面方式で実施するようになった。これは、既存の顧客でも新規顧客でも変わりはない。
打合せの内容や依頼者の希望によっては、現在でも面談で打合せを行うこともあるが、会議室のイスの配置や打合せ中・打合せ後の室内の換気やテーブルの消毒等、感染防止に配慮しようとするといろいろな手間がかかるのが実情である。
それもあって、筆者の場合は、極力、来所・面談での打合せは遠慮していただくようお願いをしている。
場面②-相手方弁護士との示談交渉
コロナ前
相手方本人や相手方代理人との示談交渉を行う場合、これまでは事務所や弁護士会の打合せ室を利用し、面談にて行っていた。
コロナ後
電話やFAX、Zoom等を利用した交渉方法が中心となった。
従来は、たとえば遺産相続に関連して相手方となる本人や代理人弁護士と交渉を行う場合、相手方が遠方のときは別として、事務所や弁護士会館の打合室にて面談し、リアルの場で示談交渉を行うのが常であった。
しかし、コロナ後は、このような示談交渉の場面でも電話やZoom等を利用することで、なるべく対面・面談を避ける形で交渉を行っている。
お互いに東京在住で、会おうと思えば会える距離の弁護士同士がZoom等を使って示談交渉を行うという方式は、コロナ前にはまったく考えつかなかった発想であった。
場面③-民事裁判手続
コロナ前
従来も、裁判所が、裁判手続(弁論準備期日や和解期日)にて電話会議システムを使用することを許可すれば、裁判所に直接出頭しなくとも電話で出席することで足りるとの運用がなされてきた。
しかし、近隣の裁判所だけでなく、電車で2時間以上かかるような遠方の裁判所などでも、電話会議システムの使用が原則認められず、裁判所への出頭を毎回求められるケースも多々あった。
コロナ後
電話会議システムの使用のみならず、新たに導入されたウェブ会議システムを使用することで、近隣の裁判所の事件であっても、裁判所に出頭せずに手続を進められる事件が大幅に増加した。
通常の民事訴訟の場合、大半の事件では1回の裁判期日はおよそ5~20分前後である。このような短時間のやり取りのためだけに、わざわざ電車を乗り継ぎ、遠方であれば移動時間だけでも半日近くを費やすような状況が、長年にわたり当たり前の状態にあった。
しかし、コロナ後は、以前は電話会議システムの利用が許可されなかった近隣の裁判所(筆者の場合であれば、最寄りの東京地裁など)の事件でも、裁判所のほうから積極的に、電話会議や新たに導入されたウェブ会議システムを利用した形での手続進行を打診されるケースが非常に多くなった。
ただし、家事調停事件や高裁の事件は、東京での取扱いを見る限り、2021年5月現在では電話会議やウェブ会議システムへの切替えはまだそれほど進んでいないようである。
場面④-研修・研究会等
コロナ前
弁護士会や出版社等が主催する研修会やセミナー、各種大会、学会などについては、会場でのリアル開催が基本であった。
コロナ後
上記はほぼ全てZoom等を利用してオンラインで開催されることが標準となった。
筆者が個人的にありがたいと思っていることの1つが、上記の場面である。
コロナ以後は、研修会やセミナー、学会等はほぼ全てがオンラインに切り替わった。従来であれば、開催地が遠方であったりスケジュールが合わない場合には研修等への参加が難しかったが、オンラインで開催・配信されることにより、開催地や移動時間が障害とならずに、自宅で気軽に参加できるようになった。
特に、海外で開催される学会やシンポジウム、海外のスピーカー(演説者)が主催するセミナーについては、従来は長期の休みを取り、飛行機に乗って海外のセミナー会場に出向いて参加するしか方法がなかった。これらがコロナ後はこぞってオンライン開催されることにより、渡航費や宿泊費、移動時間も要せずに自宅にいながらにして参加できる機会が増えたことは非常にありがたい。
コロナが沈静化した後も、ぜひこのような取扱いを続けてほしいと思っている。
3 相続実務の現場に押し寄せる“非対面化の波”
冒頭でも触れたように、もともと社会のIT化の流れによって進んでいた“オンライン化”の波に、コロナによる“非対面・非接触”の社会的要請とが合わさることにより、今後もより一層、相続実務のあらゆる場面で“非対面”方式の導入が進んでいくことは疑いがないものと思われる。
そこで、本連載では、相続実務で頻出するような具体的場面を取り上げ、コロナ後に筆者がどのような取組みや工夫をしているか、また筆者が見聞きした範囲でどのような取組みがなされているかを紹介していきたい。
なお、弁護士と公認会計士・税理士の先生方との業務内容や関心の違いというものが少なからずあると思われるため、連載を読まれての疑問や質問、テーマのご要望等がもしおありであれば、ぜひお寄せいただきたいと思う。
(了)
「対面が難しい時代の相続実務」は、毎月第1週に掲載します。