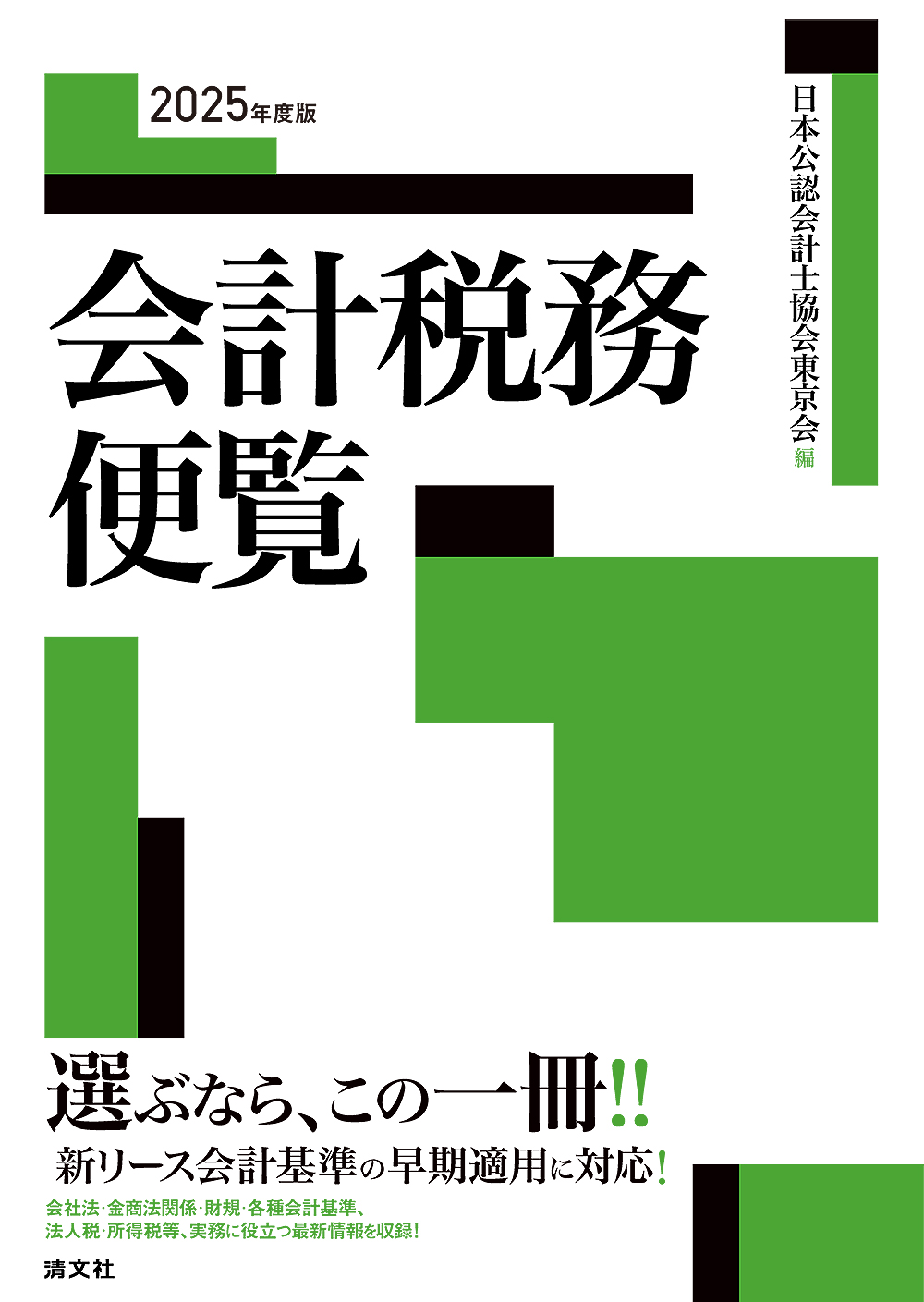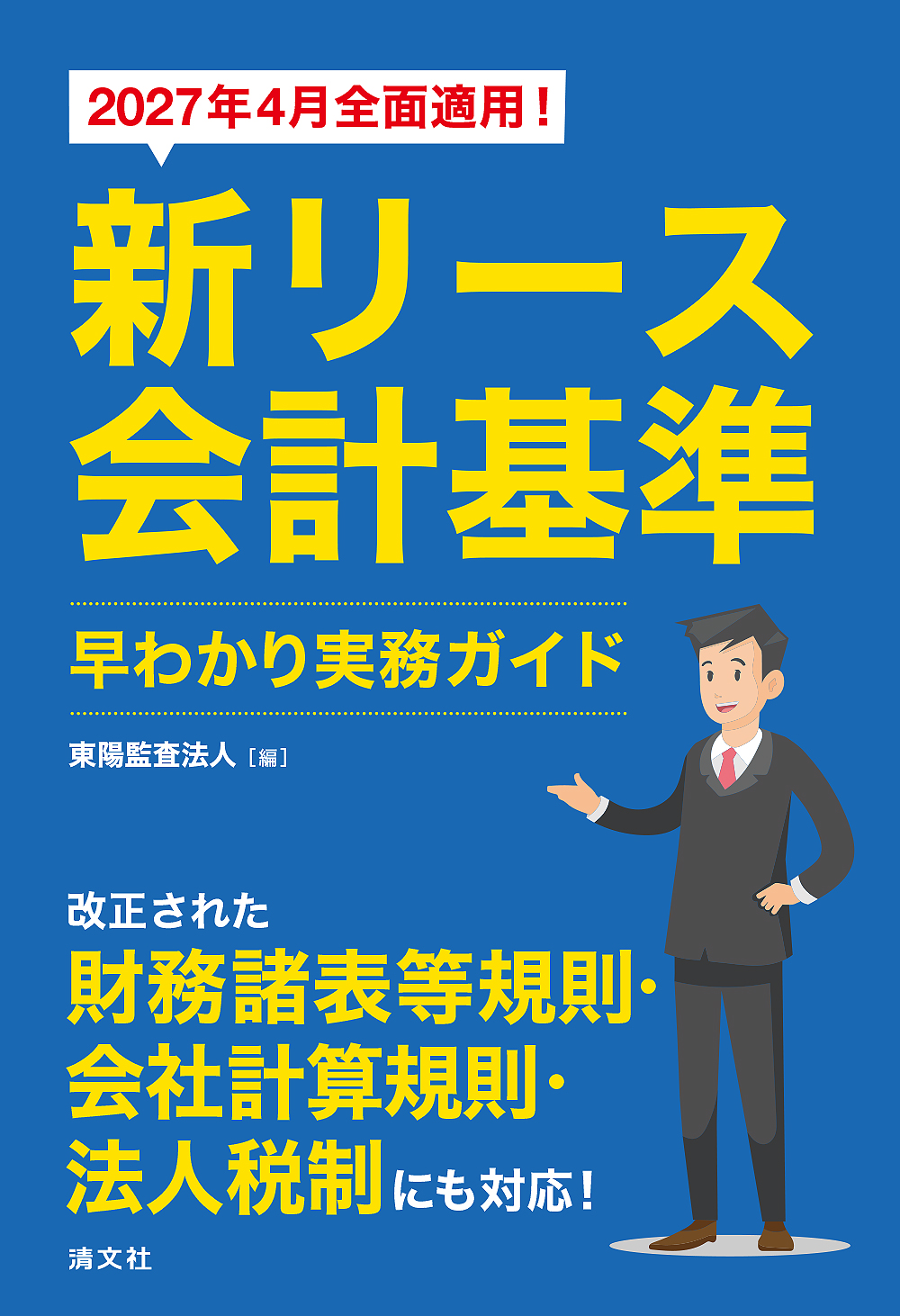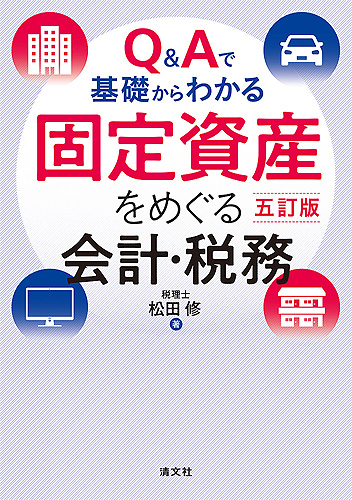〈一から学ぶ〉
リース取引の会計と税務
【第4回】
「ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引」
公認会計士・税理士
喜多 弘美
【第3回】では、リース取引の流れについて整理しました。リース契約を締結すると、今後、リース会社と取引が発生し会計処理を行います。どのような会計処理を行うか、その判断に必要になってくるのが、リース取引の判定です。
1 リース取引の全体像
まずは、リース取引の全体像をみていきましょう。リース取引には、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引があり、オペレーティング・リース取引はファイナンス・リース取引以外の取引と定義されています。また、ファイナンス・リース取引には、所有権移転ファイナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引があります。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。