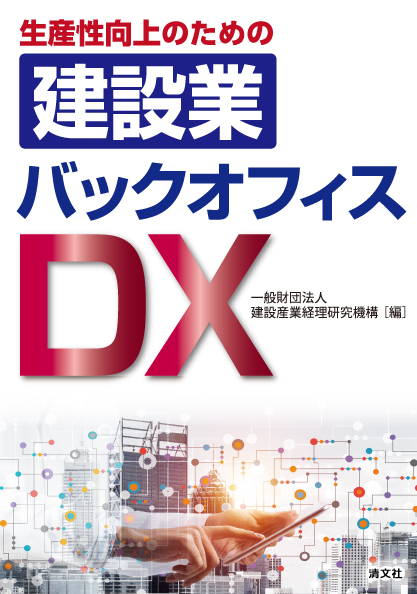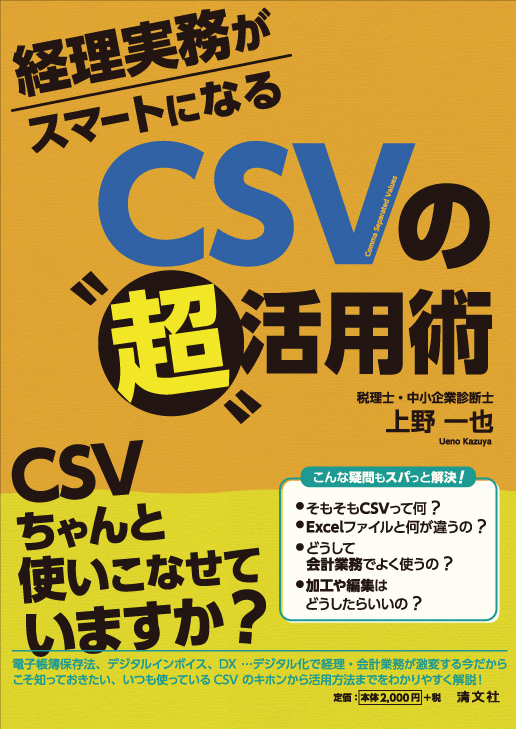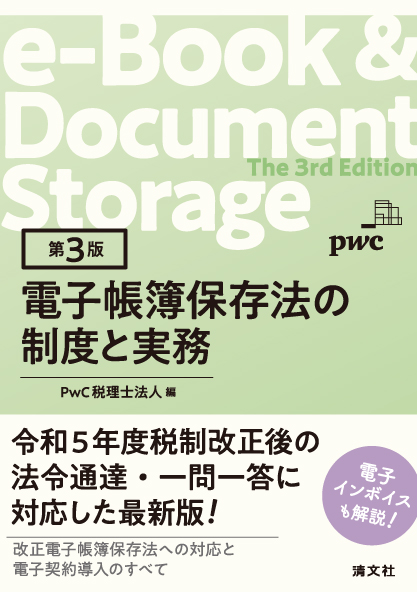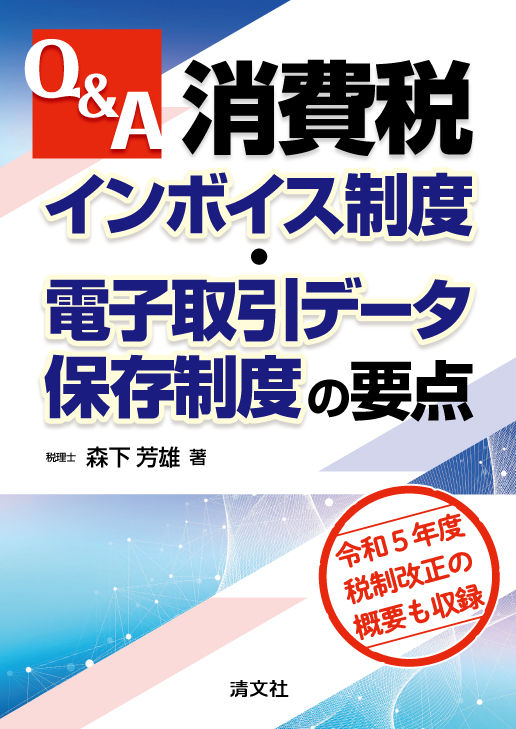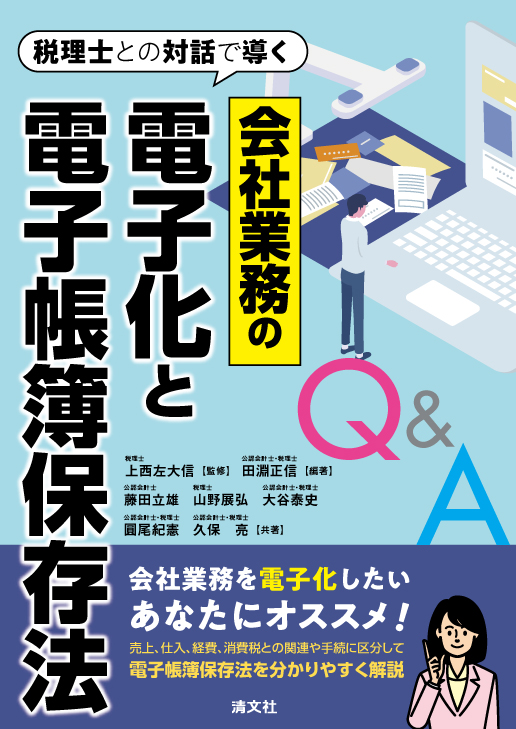企業の不正を明らかにする
『デジタルフォレンジックス』
【第4回】
「デジタルフォレンジックスの現場」
~証拠収集編①~
プライスウォーターハウスクーパース株式会社
シニアマネージャー
池田 雄一
1 はじめに
デジタルフォレンジックス調査を依頼した経験のある方は、専門家が現場でコンピュータなどの電子媒体を収集する様子を見たことがあるかもしれない。今回から2回にわたって、電子証拠の収集に使われる「七つ道具」の概要から、証拠収集の流れ、保全したデータ、実際の現場での様子などについて解説する。
本題に入る前に、証拠の「保全」と「収集」の言葉の使い分けについて解説しておきたい。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。