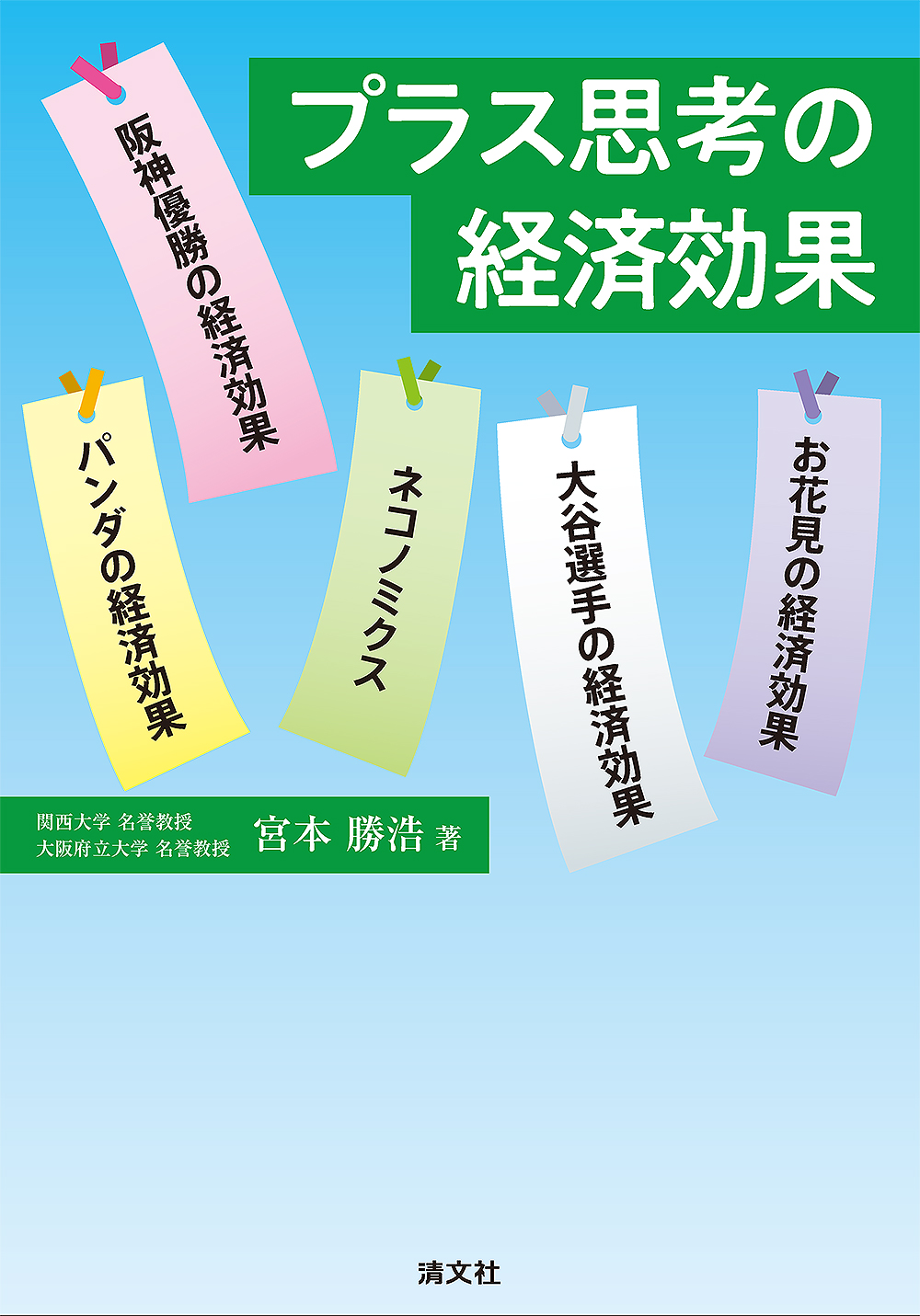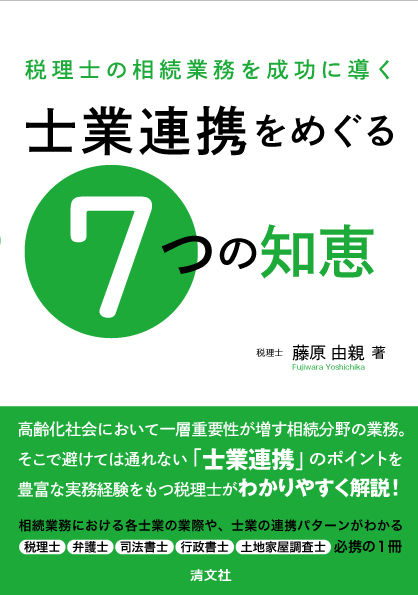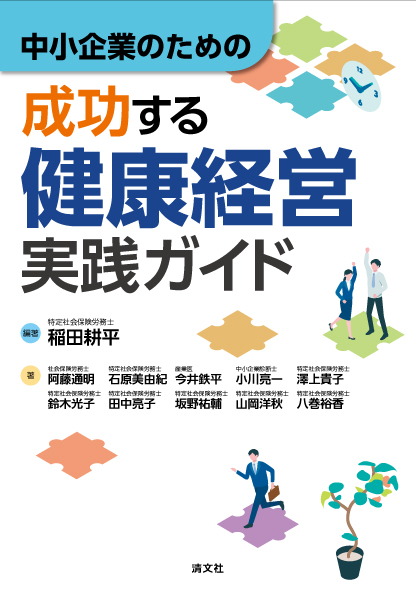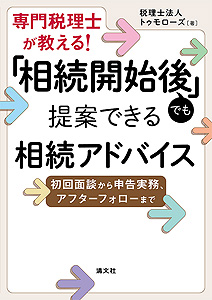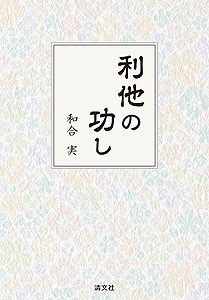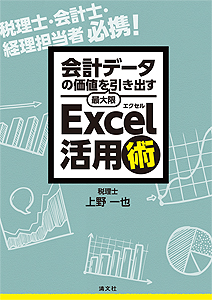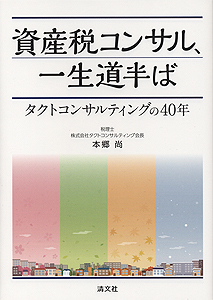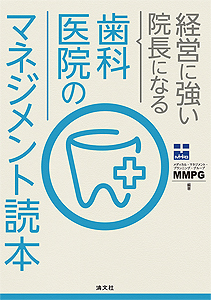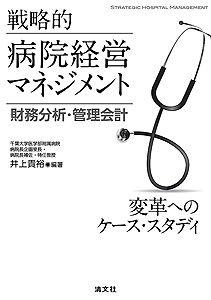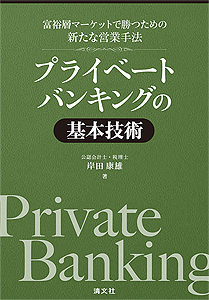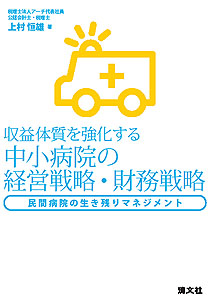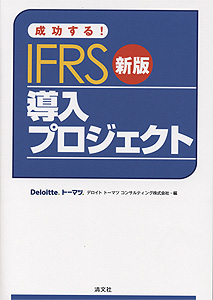プラス思考の経済効果
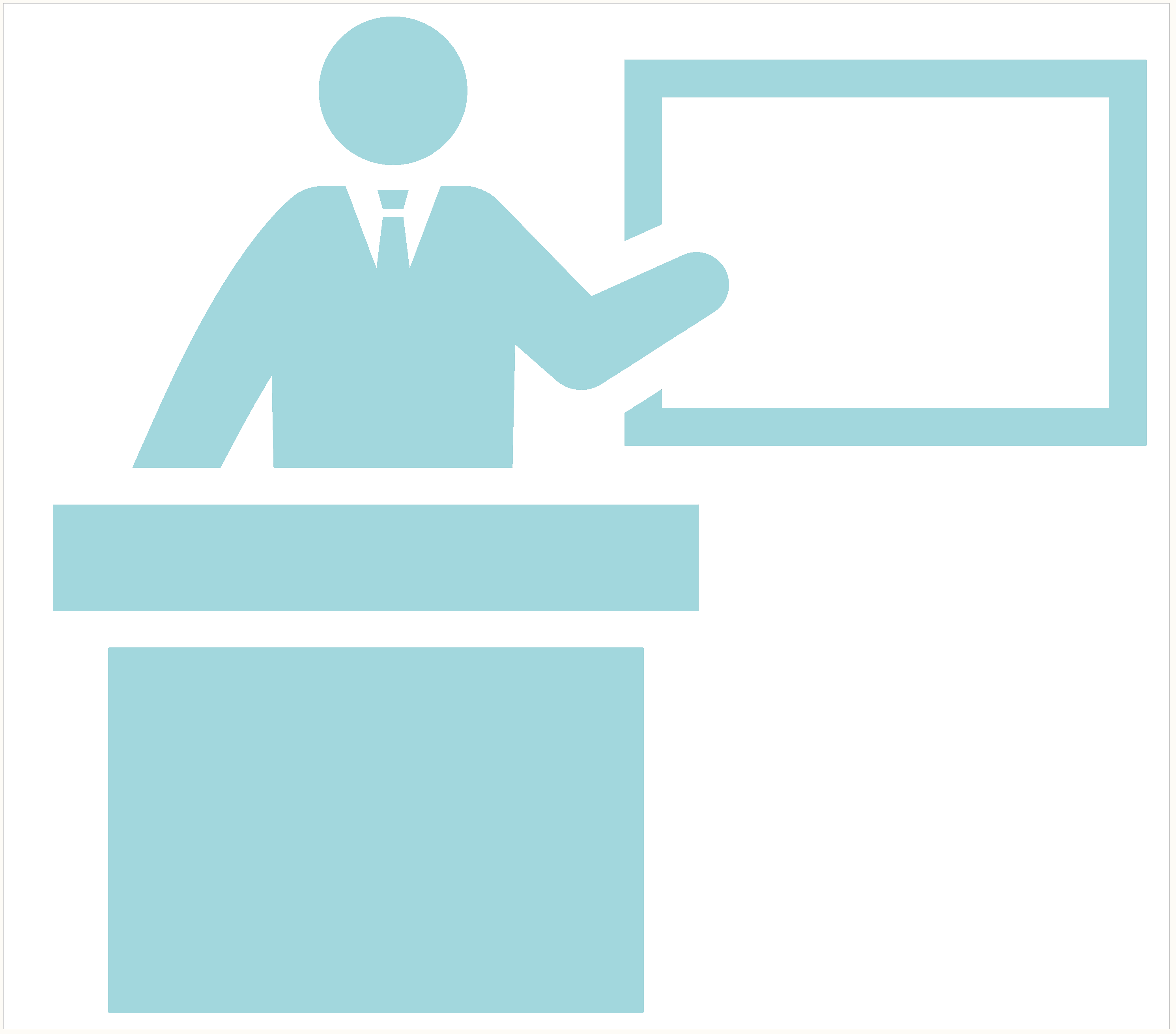
【第24回】
「2024年の恵方巻き等の経済効果と食品ロス」
関西大学名誉教授・大阪府立大学名誉教授
宮本 勝浩
1 はじめに
今年は、新型コロナが5類に移行してからはじめての「節分」でした。多くの人たちが恵方巻きを食べたのではないでしょうか。今年の立春は2月4日(日)で、立春の前日が節分ですから、今年の節分は2月3日(土)でした。
「恵方巻き」は、節分に恵方(その年の吉方、縁起の良い方角のことで、今年の恵方は「東北東やや東」)を向いて願い事をしながら無言で巻き寿司を食する風習のことで、この方法で恵方巻きを食するとその年の縁起が良いと言われています。
起源は大阪の花柳界、花街、船場などで、昔から行われていた風習と言われていますが、近年はマスコミが大々的に取り上げて、寿司業界、海苔業界、コンビニやスーパーの食品小売業界、百貨店などが積極的に宣伝・販売活動を行うことにより、売上高を拡大してきています。しかし、日持ちのしにくい寿司であるため、売れ残りが廃棄処分される食品ロスが問題になってきています。
今回は、2024年の恵方巻きをはじめとする「節分の寿司」の売上高と経済効果を予測し、さらに廃棄処分される食品ロスの金額を推計しました。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。