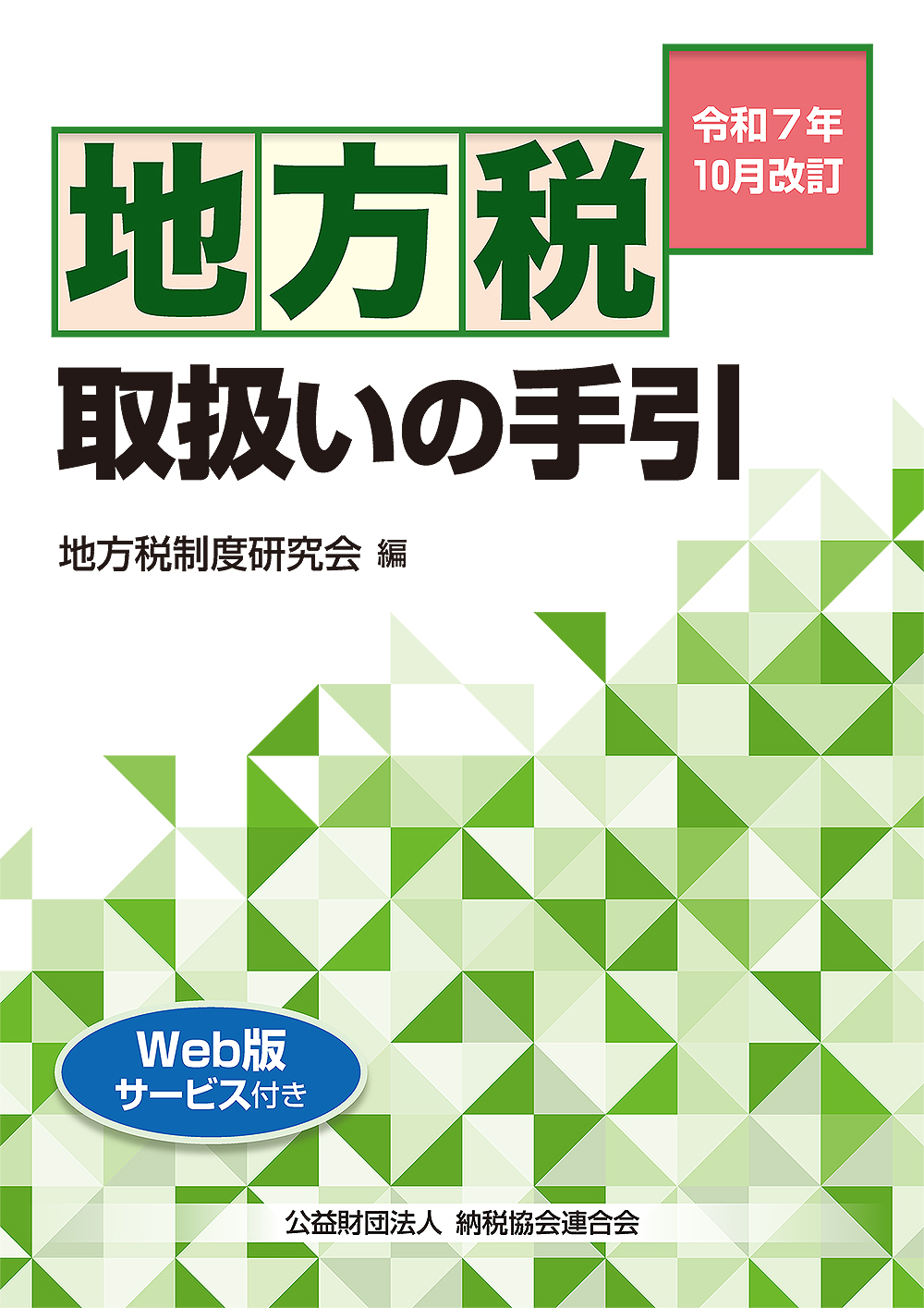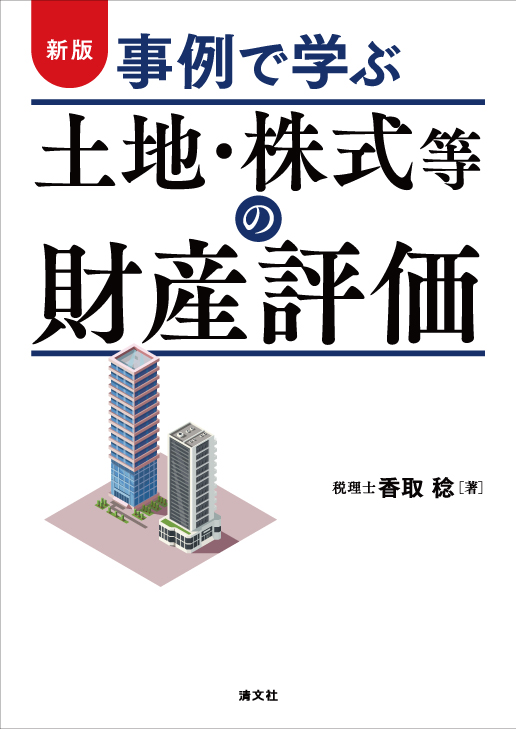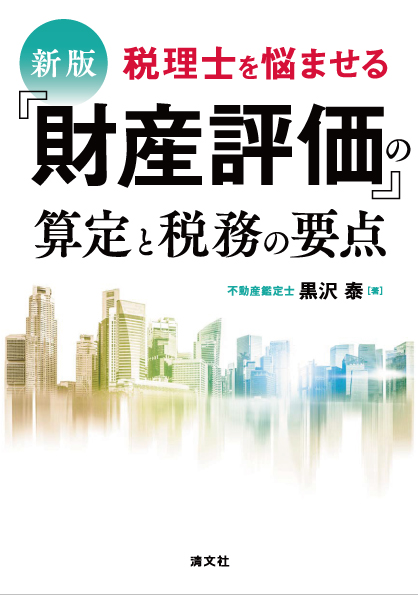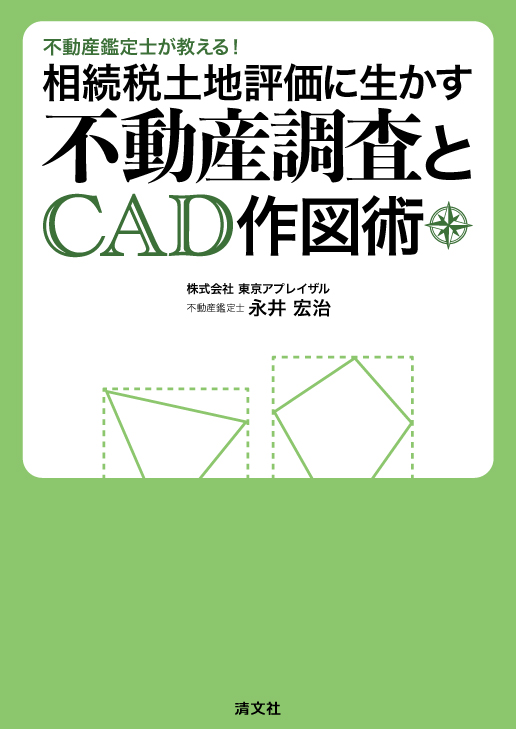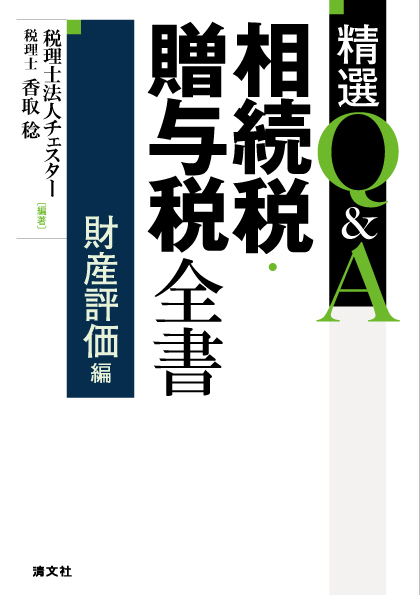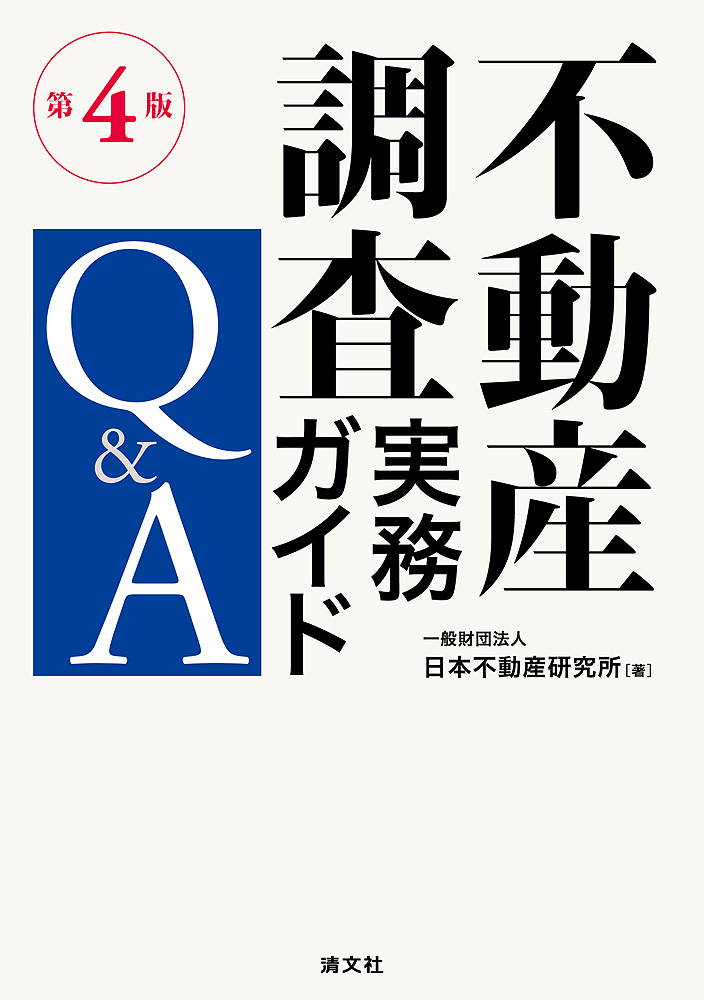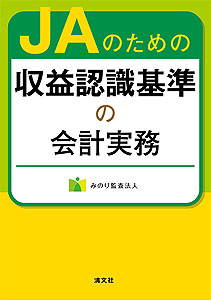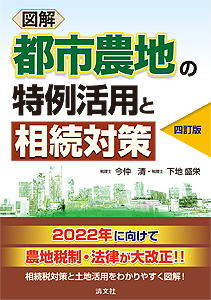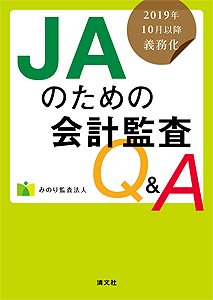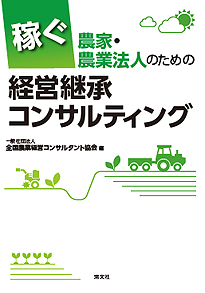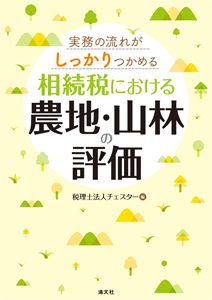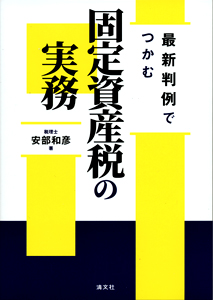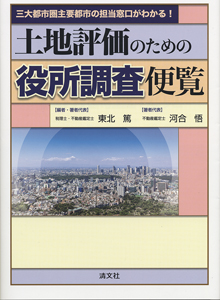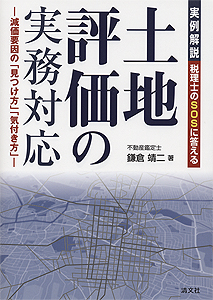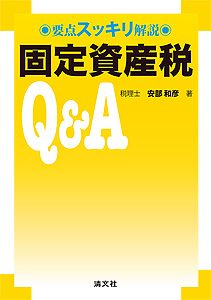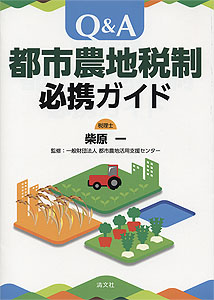税理士業務に必要な
『農地』の知識
【第10回】
「農地の固定資産税」
税理士 島田 晃一
今回は農地の固定資産税の計算について解説を行う。固定資産税は、納税者が申告するのではなく市町村から賦課される税金であるため、その計算方法について意外と理解されていない部分がある。そのため、改めて基本的な計算方法について確認をしておきたい。
1 一般農地の固定資産税の計算
固定資産税額は「課税標準額×税率(1.4%)」により計算される。課税標準額は固定資産税評価額を基準として計算する。固定資産税評価額は3年ごとに評価替えが行われており、次回は平成30年度になる。
固定資産税評価額の算定上、農地は「一般農地」と「市街化区域農地」に区分され、それぞれ評価額及び課税標準額の計算が異なる。一般農地は、その農地の売買価格や収益力を基準に評価額が決められているが、その評価額は宅地と比較して非常に低くなっている。
具体的には、各市町村内において田畑の別に状況類似地区を定め、その地区内の農地から標準田又は標準畑を選定する。当該地区内の農地の評価額は標準田又は標準畑の価額に比準して計算される。標準田又は標準畑の価額は「正常売買価格」といい、当該地区内の農地の売買実例等に基づいて定められるが、農地ごとの収益力の差を考慮し、正常売買価格に0.55の割合を乗じて評定されることになっている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。