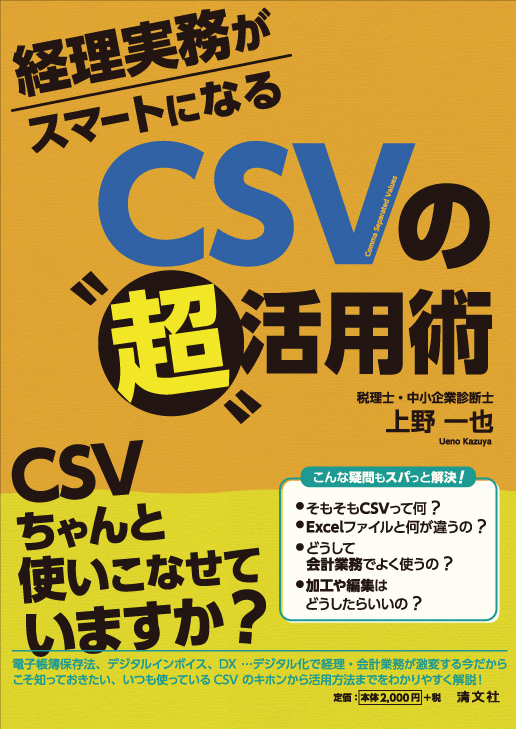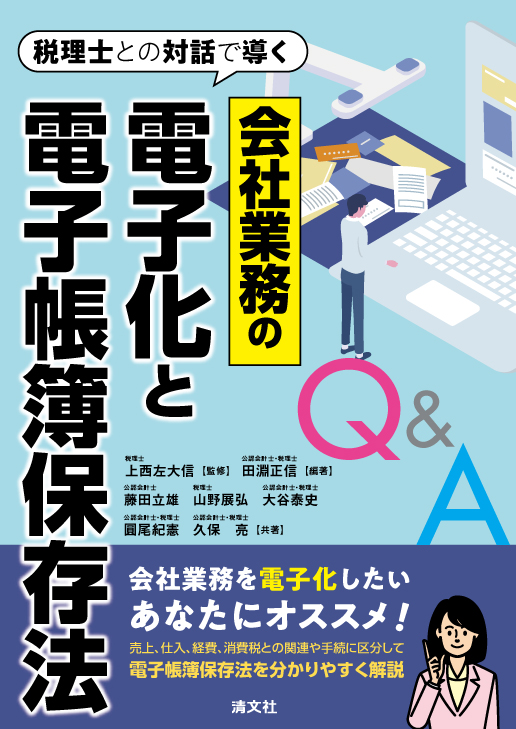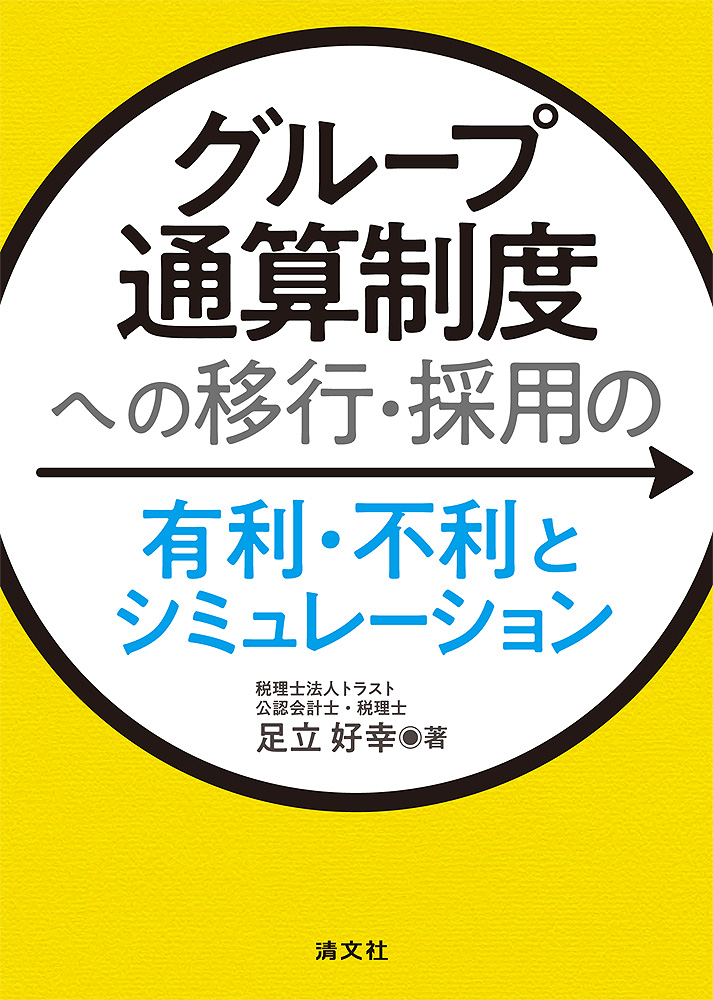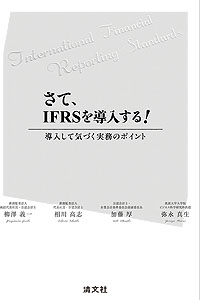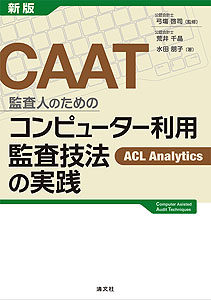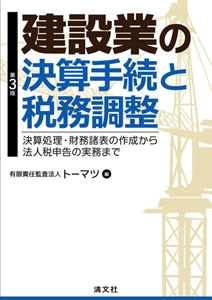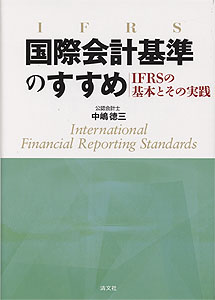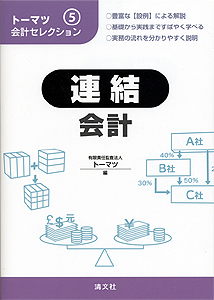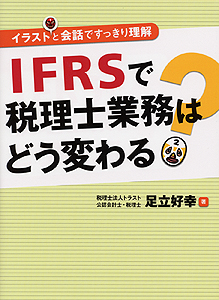(前ページへ)
――IFRSを使いこなす企業とは
次に、我々の事業とも関係の深いIFRSについてお話したいと思います。
民主党政権時代の自見金融担当大臣の発言で、国内のIFRSについての議論が大きくトーンダウンしたのはご存知の通りです。事実、「適用することが義務化されるから」というだけの理由でIFRSの検討を行っていた企業は、その時点で完全に動きが止まってしまったのですが、一方で先ほどの「レポーティングからインテリジェンスへ」という流れの中で、IFRSを適用することによって、ガバナンスも含めて連結グループ全体の会計処理を制管一致させ整えていこうと検討している企業は、動きを止めることなく粛々と検討を続けていました。つまり、IFRSを適用するということを御旗にして、制管だけでなく、グループ内会計基準も統一していこうというわけです。
IFRSはあくまで開示のための会計基準です。ただし、経営者が判断に使用している情報と同等のものを投資家にも開示することを求めているものなので、形式よりも実態を重視している点が特徴と理解しています。そういった中で、任意適用が認められているということ自体は変わらなかったわけですから、トーンダウンさせる理由がないのです。
また、10月28日付けで内閣府令の改正が公表され、IFRSの任意適用可能対象企業の範囲が広がることになりましたが、これにより適用可能となるベンチャー企業は加速度的にIFRS適用へシフトしていくのではないかと考えています。
その理由は、コストの問題ではなくリスクをとる経営にとって、とったリスク(B/S)とオペレーションの健全性(P/L)を明確にすることができることから、成長よりも利益を重視されがちな日本市場においてもリスクをとりやすくなるためです。具体的には、のれんの償却や研究開発費の資産計上といった部分がこれに該当します。
例えば仮にM&Aをしてのれんの償却がある場合などは、のれんの償却後の利益を見ても、実態を表しているとはいえないわけです。売上に対する利益があって、それに対する労働分配率を見たときに、のれん償却後の最終利益だけで見てしまうと、日本基準ですと利益が出ていないような数字が出てきて、社員への適切な還元ができなくなってしまいます。つまり、のれんとは別に、本来きちんと活動している成果としての利益から逆算したときに、これぐらいしっかりと還元すべきだという判断にズレが生じてしまうのです。
のれんというのは、あくまでも投資をした側がしっかりとリスクを持って、通常のオペレーションとは別のところで見ていかなければならないのが今の日本基準ですから、そのあたりで使いづらいところがある。
そういった観点では、M&Aをする機会がある会社にとってみれば、IFRSというのは1つの力になると思います。
また、研究開発費についても、特にIT企業の場合はなかなか資産計上できませんし、資産計上したもの自体が改めて売却可能性があるかというとほとんどありませんから、基本的には資産計上せずに可能な限り経費で落とすようにしてきていますが、それをし過ぎると赤字が膨らみ利益率が下がりやすい。そういった観点で、投資を促せないというリスクがあります。
もちろん、事業規模が小さい時は、事業の継続性の観点からその方が良いのですが、ある程度体力がついてくると、1年以上の単位で投資をして回収するというモデルをリスクをとってやっていかない限り、サービスカンパニーではなくプロダクトベンダーとしてやっていく以上、成功は難しいと思います。ここも今までの日本基準だとなかなか使えなかったところですが、IFRSを適用することで一定のリスクと引き替えに資産計上することが可能になります。
そうすることで、経営者としては今まで以上に、投資に対する「リスクへの感度」を高めなければならなくなります。しかし、それを高めることによってリスクのある選択肢を選ぶことができるようになり、B/Sを使った経営がやりやすくなる。
ですから、ベンチャー的な志向がある企業というのは、こういった面でIFRSの使い勝手はすごく良いのではないかと思っています。
――連結経営者になって見えてきたもの
次に、我々アバント自身のグループ経営について、どういったテーマを持って臨んでいるかをお話します。
我々のグループ経営においても、冒頭で述べた「アカウンタビリティ経営の実践」を重要視しています。
もちろん、プライベートカンパニー、非上場会社であればそのような必要はないのかもしれませんが、やはり公開企業、パブリックな存在としての上場企業である以上、アカウンタビリティを担保することは絶対に必要なことだと考えています。
その際、すべてを闇雲にディスクローズすればいいと考えているわけではありませんが、いざ開示を求められた時にはすぐに出せる、そういった心づもりをして企業経営に臨む必要があると考えています。
事実、私自身、経費の細部に至るまで、説明がつけられる範囲のものしか使わないよう、万が一誰かに見られても恥ずかしくないようにするというのは、創業の時から心がけてきました。
しかし、このアカウンタビリティを、経営者である私だけに留まらず、いかに現場に落とし込むかということは大きな課題でした。
現場を事業部単位で分割し、P/Lも事業部単位に分解して、個々にマネジメントするようなモデルを試したりもしてみたのですが、なかなかうまくいきませんでした。結局のところ、事業部を細分化した場合には、個々の事業部にP/Lとして管理させるのは、いくら近年会計リテラシーが上がったといっても無理があったのです。
ただ一方で、例えば家計簿程度のレベルまで落としてしまうと、それをマネージするだけでは、現場レベルにアカウンタビリティを持たせるというテーマは達成できません。やはり分割されていても、P/Lという単位を管理できる組織単位は作る必要がありました。
これについては試行錯誤した結果、1単位として数千万程度の事業単位では難しいのですが、数億程度の事業部単位であればP/Lとしての管理が可能になる、という結論に最近至っています。
今は、この単位での管理・運営ができる体制を作り込んでいるところです。
――ホールディングカンパニーは、事業のセコンド役
こうして事業部単位でP/Lを管理するようにしていくことで1点問題になってきたのは、「事業そのものの継続可否については、誰が判断するのか?」ということでした。
個々の事業部ごとにP/Lに落とし込んで、それをマネージしてくと、当然自分たちの事業部のP/Lをいかに最大化させていくか、どうやって一番良いパフォーマンスをしていくかということが最大目標になっていきます。
これはこれで良いことなのですが、時と場合によっては、「その事業は継続せず、たたむべきではないか」という経営判断をしなくてはならない時も出てきます。しかし、その事業のP/L単位で管理を任されている現場からすると、なかなか事業そのものの打切りを自分たちで判断することは難しい。
このようにP/Lの細分化は、権限を委譲して現場の人間のモチベーションを上げるという意味では非常に有用なのですが、どうしてもタコツボ化してしまう傾向にあります。
ですから、経営的にはやはり「セコンドのような立場の人間」、タオルを投げる役割がどうしても必要になりますし、これは現場とは別に設ける必要があります。
そういった判断をする際に、最も参考になるのがB/Sです。
B/Sを管理することで、企業全体の事業資産を把握して、各事業部に予算を設定し、事業部毎のROEなどのパフォーマンスを管理することで、事業継続の可否を、つまりタオルを投げるべきかどうかを判断する役割として機能します。
そして、その役割を持たせるために、今回、ホールディングカンパニーを設立することになりました(2013年10月、株式会社ディーバから株式会社アバントへ商号を変更し持株会社制へ移行)。
このホールディングカンパニーが司令塔として、各事業部が結果を出せるように徹底的にサポートして現場との信頼関係をつくることで、各事業のP/Lを管理する現場は自分たちの事業に集中できますし、事業継続の可否についてはホールディングカンパニー側で適切な判断が可能になります。
つまり、財務諸表的な観点から、P/Lドライブの人とB/Sドライブの人の役割を明確に分けて、B/Sプライムの組織としてホールディングカンパニーを設立した、というのが、会計的な視点から見た今回のホールディングに至った経緯、ということになります。
マネジメントの人材はホールディングに籍を置かせて、基本的にマネジメントのプロとして事業体に出向させていく。さらには人の一部とお金と情報に関してはすべてホールディングの所有にして各事業へ再配分していくことで、タコツボ化が起きにくく、全体的な視野を持った組織にしていく。
そうすることで、事業部制のメリットとデメリットをそれぞれクリアにし、新しい成果を出せるタイプの事業部制をつくっていきたいというのが、現在の我々のチャレンジです。
――公器としての企業であり続けるために
これらの事業のノウハウは、もちろんこれまで多くの顧客から話を伺ってきたことが大きな財産として活かされています。
ですが、すべてがどこかのモデルをそのままコピーしたものかというと、そうではありません。やはり自分たち自身が連結経営のあり方そのものに関わっている以上、自分たちなりに考え、かつ、自分たちの事業モデルとして一番有効であろうというモデルを導入し、なおかつプラスアルファで独自性を出していく必要があると考えています。
少なくとも全体の1割程度はオリジナリティを投入した経営モデルを作っていきたいという意識を持っています。
例えば最近ですと、わりと近い業種でMBOをしている企業がいくつかあるのですが、我々としてはこれに追従することなく、パブリックな存在、公器としての企業という存在として独自色を出し、これからも経営を続けていくつもりです。
MBOもファイナンス的には決してネガティブな選択肢ではないのですが、上場企業として、絶対的にアカウンタビリティを求められる企業体として、それでも投資家からの要望に応えつつ、説得しきって経営を続けていく。これが当初から目標としているアカウンタビリティ経営の真骨頂だと思っていますし、我々の経営におけるこだわりでもあります。
もちろん、容易なことではありませんが、それでもアカウンタビリティに資するものとして連結システムの提供を行っている以上、絶対にやりきるべきものだと考えています。
ですから、私は創業者ではあるのですが、「オーナーシップでは経営しない」「リーダーシップで経営していく」と言い続けていて、今後は一層多様なステークホルダーの集まりにしていきたいという志向があります。
これも公器としての企業という立ち位置を、アカウンタビリティを徹底的追求することにつながると思っていますし、そうすることで中長期的に、さらに超長期的に考えるとフリーキャッシュフローを最大化することができるというコンセプトを持って経営に臨んでいます。
もちろん簡単にはいかないでしょうし、30年程度では結果が出ないかもしれませんが、50年後にはこの選択が結果的には正しかった、ということを実証できればいい、と思っています。
《次号のランナー紹介》
次回は、GCAサヴィアン株式会社代表取締役の渡辺章博氏(米国・日本公認会計士)へバトンタッチ。
渡辺氏と初めてお会いしたのはおおよそ10年前のとあるゴルフ場、まだGCA社を設立されたばかりのこと。以来、当時コンサルティングファームなどの一業務であったM&Aアドバイザリーサービスを事業として確立し、短期間で東証上場企業まで育て上げ、さらなる躍進を目指される姿にいつもインスピレーションをいただいている。
渡辺氏から教えていただいた「Substance over form」は、様々なレギュレーションや社会的責任を果たす企業であっても現実、実態を重視することの重要性を常に意識するため、心に刻んでいる。私はゴルフをやめ山走り専門となったが、渡辺氏は今年ホールインワンを達成。公私共にますます充実のご様子である。
(了)
「会計リレーエッセイ」は執筆者をリレーしつつ、毎月第2週に掲載します。