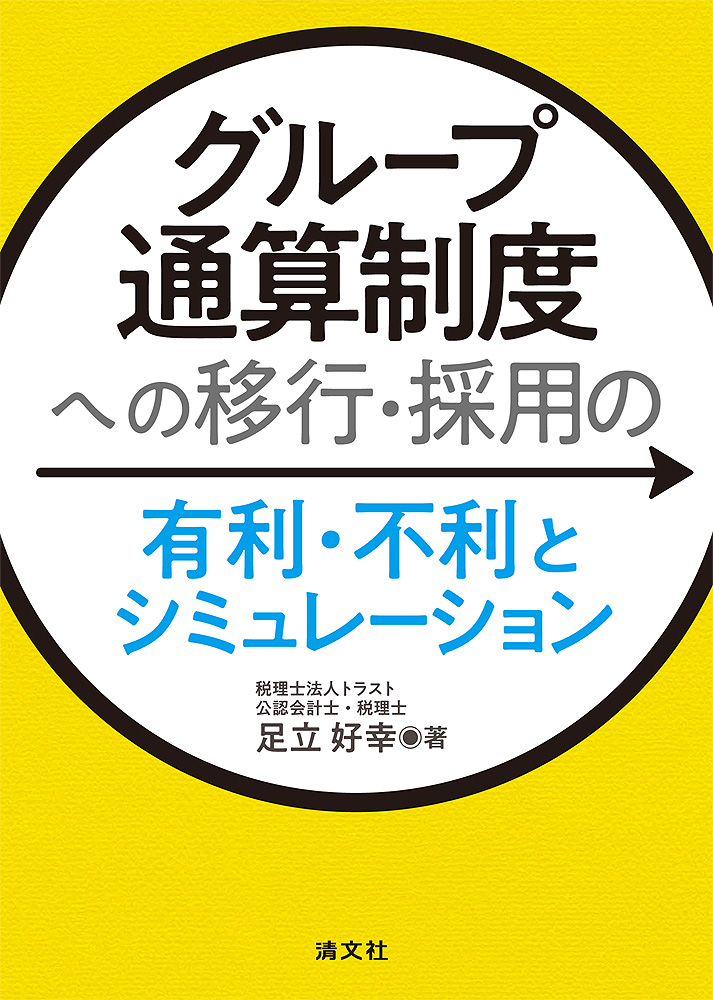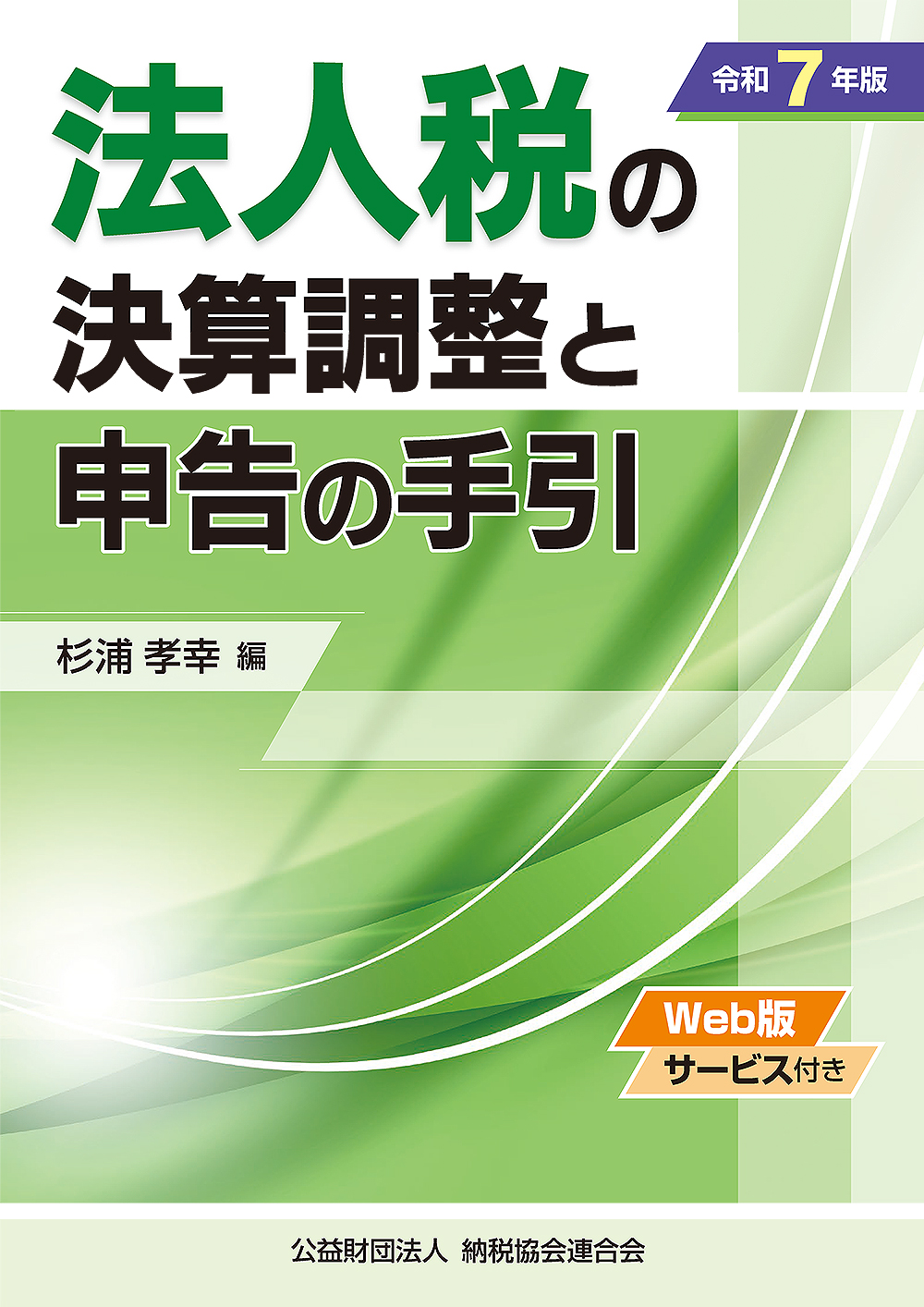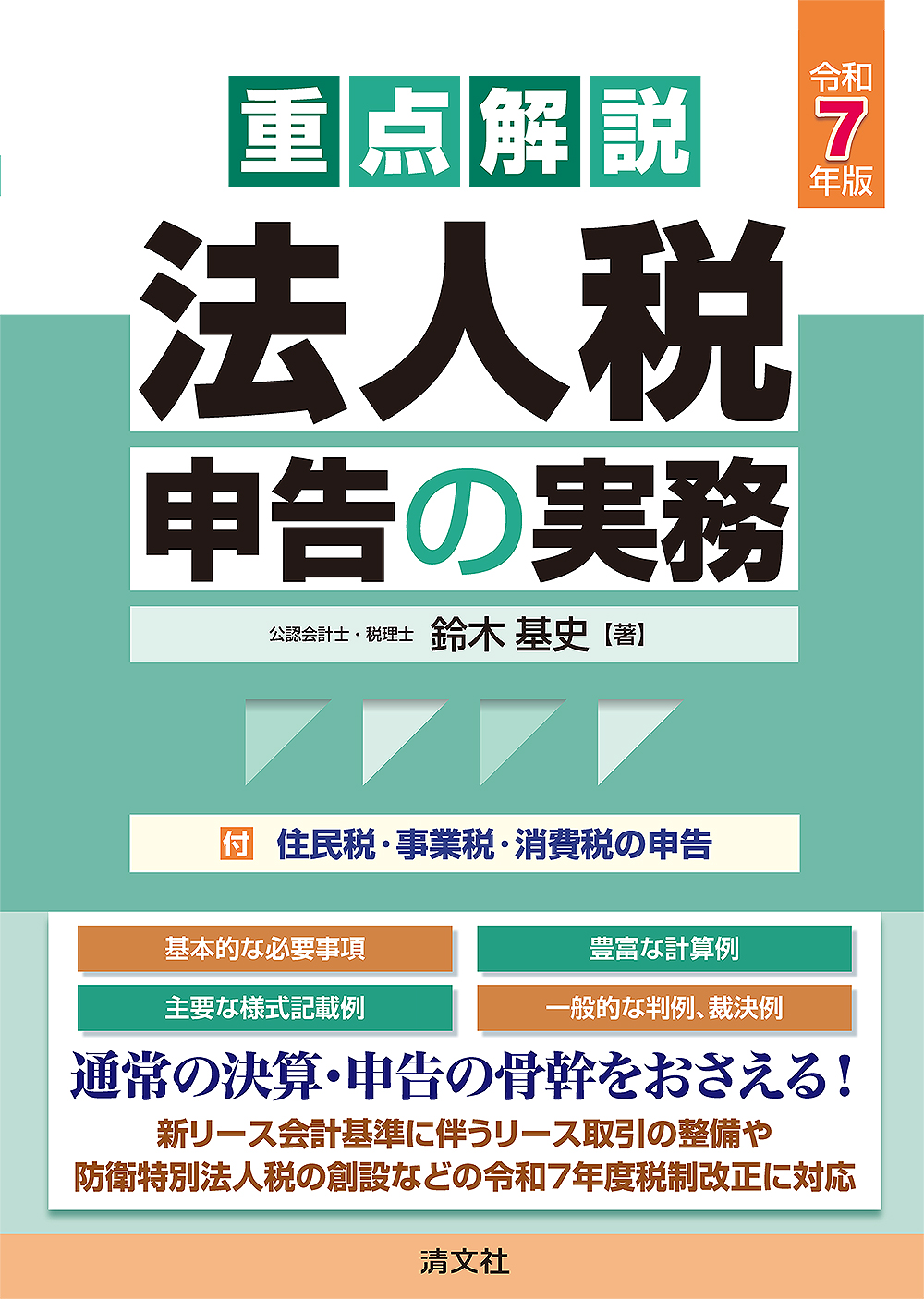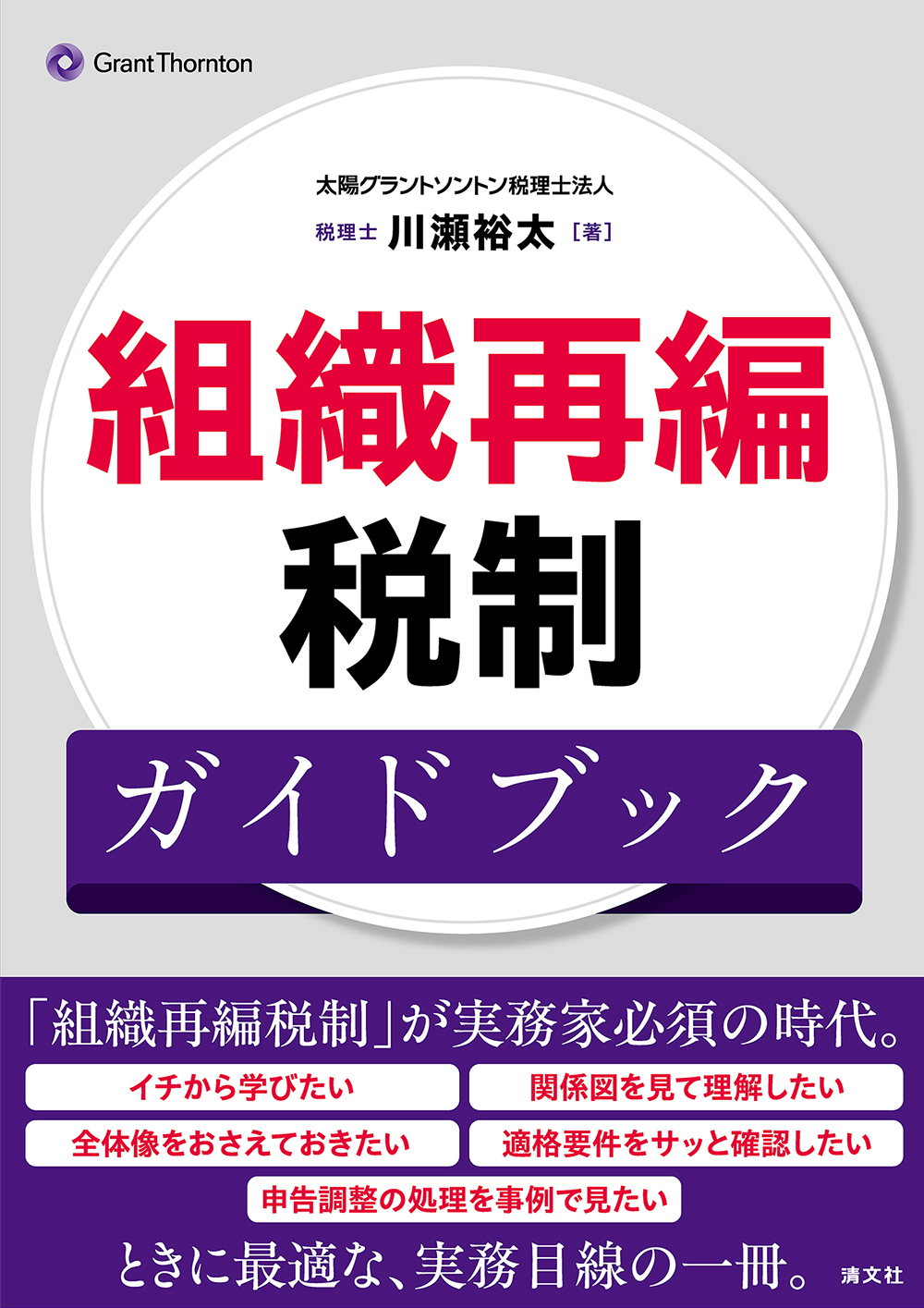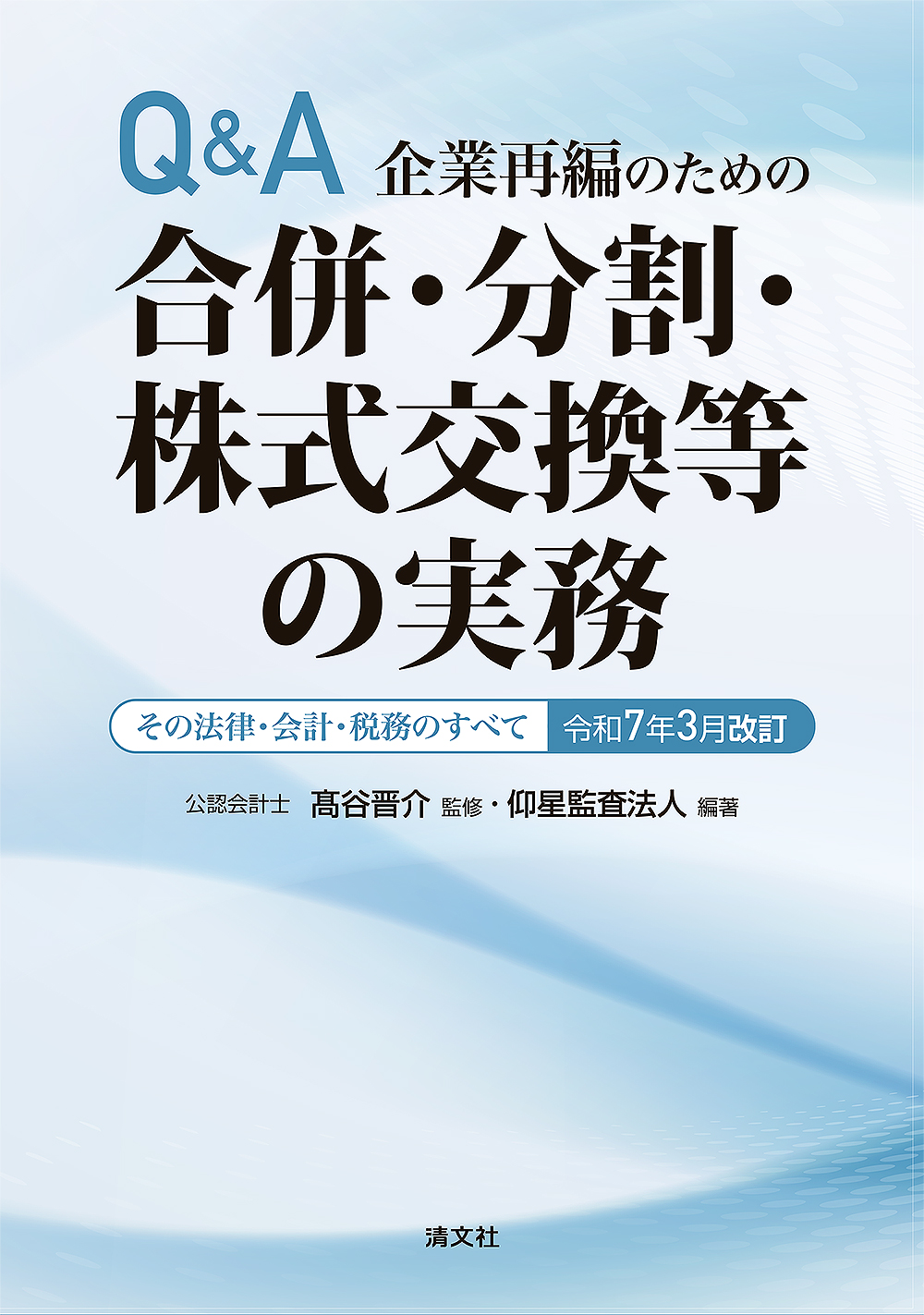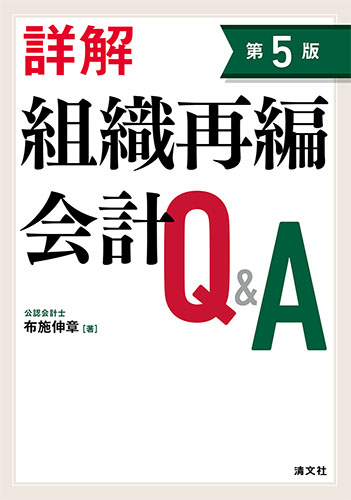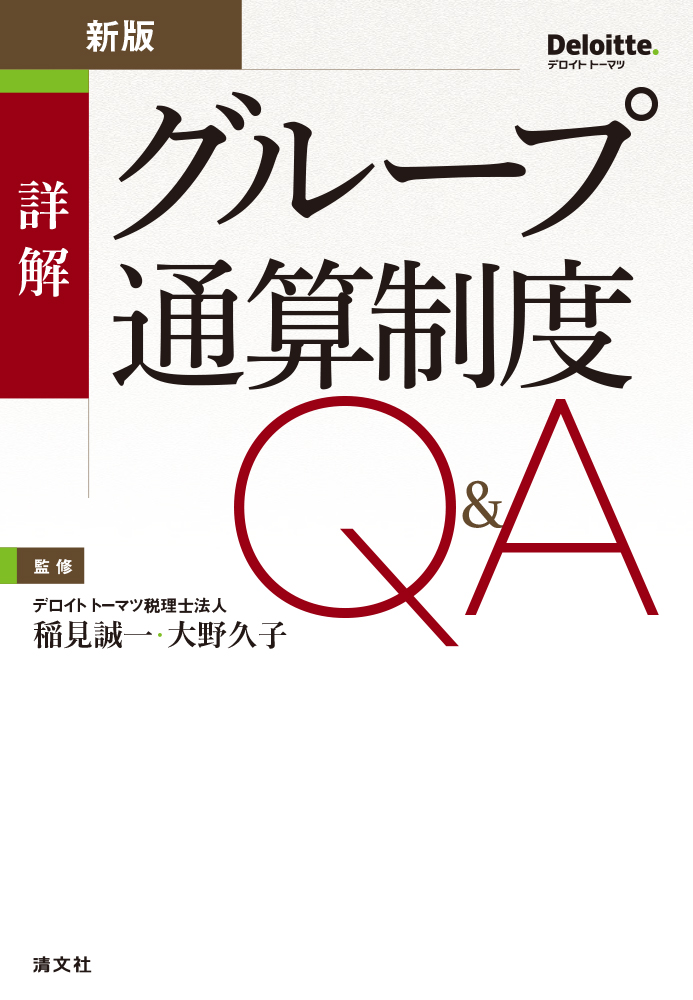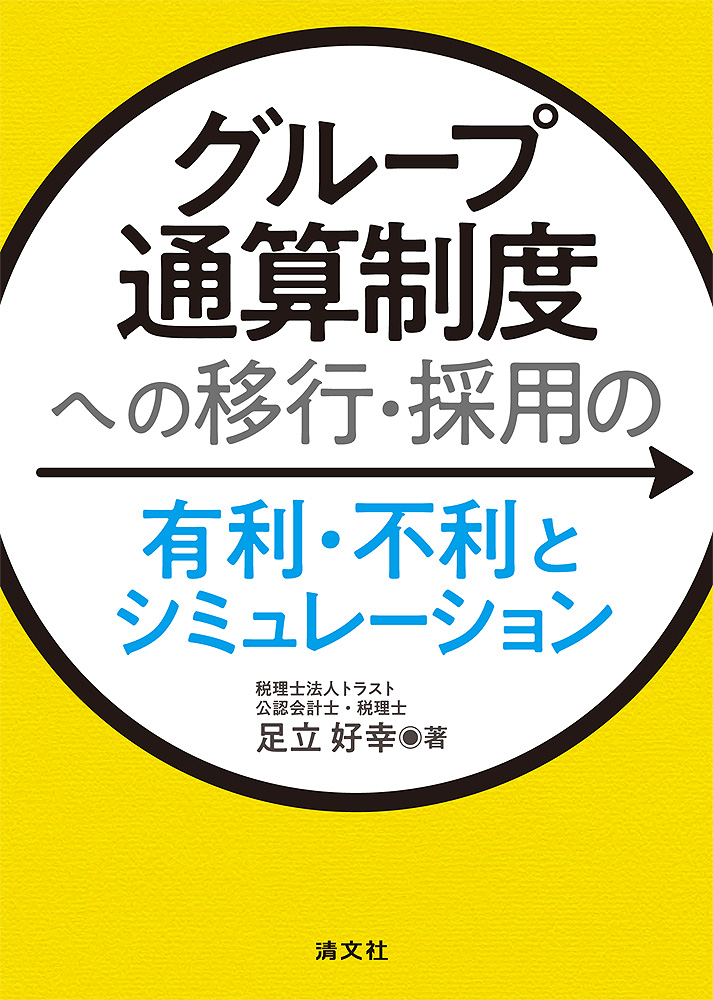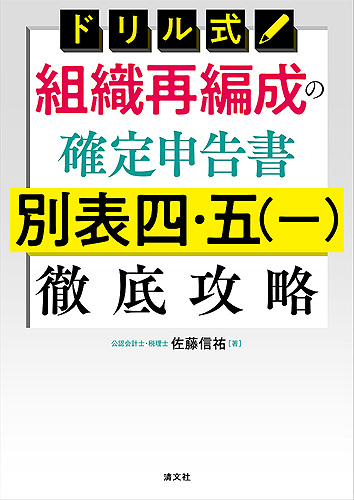3 連結納税の実務への影響
~上記2のポイント踏まえて~
上記2において、見直しの方向性と実務上のポイントを記載したが、それらを踏まえた上で、既に連結納税を採用している会社とまだ連結納税を採用していない会社、それぞれについて、連結納税の実務への影響をイメージしてみたい。
(1) 既に連結納税を採用している会社への影響
① 事務負担はどれくらい軽減されるのか?
今回の見直しは、個別申告方式への変更によって、納税者及び課税庁の事務負担の軽減を図ることが最大の目的といえるが、既に連結納税を適用している会社について、実際に、事務負担がどれくらい軽減するかについては、以下のように考えられる。
(ア) 税務調査の事務負担(修更正の手続を含む)が大きく減少することは確実だろう。
(イ) 受取配当金の負債利子控除や研究開発税制など、グループ調整計算がなくなることで、各社の事務作業と連結親法人による子法人チェックの作業時間が減ることが確実であるため、その点で事務負担が大きく減ることになろう。
(ウ) ただし、損益通算が全体計算であるため、上場会社グループの決算作業における税額計算の流れは、現行制度と大きく変わらない可能性が高い。具体的には、連結グループの税額計算のスケジュールが全社で組まれる点と税額計算の完了のタイミング(決算時の税務仕訳)が全社同時になる点は変わらないだろう。この点では、決算時の事務負担は軽減されないだろう。
(エ) また、下記②のとおり、連結納税の税効果会計の実務は変わらないことが予想されるため、その点では、決算時の事務負担の軽減にはつながらないだろう。
② 税効果会計はどうなるのか?
新制度においても法人税では損益通算ができるため、繰延税金資産の回収可能性の検討について、現行制度と同様に、連結グループを一体として行うことになる。つまり、連結グループを一体として企業分類を設定し、全社参加でスケジューリングによる回収可能額の計算を行う実務については、変更がないだろう。
また、新制度でも地方税は単体納税が適用される場合、現行制度と同様に、法人税、住民税、事業税の別に回収可能額の計算を行うことになる。
いずれにせよ、損益通算があることから、連結納税の税効果会計の実務には、大きな影響はないことが予想される。
③ 連結納税システムはどう変わるのか?
連結納税の実務において、連結納税システムには「申告書作成システム」と「税効果会計システム」の2つがある。
まず、現行制度の連結納税の申告書作成システムは、「1つのシステムを全社で使用するもので、各社が個社入力をした後に、ボタン1つで全体計算を行い、連結納税申告書と各社の地方税申告書を完成させる」、全社参加型システムが一般的である。
この点、個別申告方式になった場合、連結納税申告書システムは、次の2つのタイプに分かれると予想される。
(ⅰ) 全社参加型システム
現行の連結納税システムを継承するタイプ。
新制度において、損益通算及び繰越欠損金の控除等のプロラタ計算(全体計算)が行われる場合、結局、全社の所得計算が完了しない限り、各社の申告書の作成が完了しないことから、現行と同様のタイプになる。
具体的には、「1つのシステムを全社で使用するタイプで、各社が個社入力をした後に、損益通算及び繰越欠損金の控除等のプロラタ計算(全体計算)をボタン1つで行い、各社の法人税申告書と地方税申告書を完成させる」システム。
(ⅱ) 個社単独型システム
単体申告システムをそのまま利用するタイプ。
単体申告の別表に、損益通算及び繰越欠損金の控除等のプロラタ計算(全体計算)を行う連結特有の別表を追加するタイプになる。
具体的には、「各社で単体申告と全く同じ画面と手順で入力を行い、損益通算及び繰越欠損金の控除等のプロラタ計算(全体計算)も他社から数字を入手し、各社で入力を行い、各社単独で法人税申告書と地方税申告書を完成させる」システム。
また、連結納税の税効果会計は、現行制度と同様に、連結グループを一体として企業分類を設定し、全社参加でスケジューリングによる回収可能額の計算を行うため、連結納税の税効果会計システムは、既存のシステムの仕様をほとんどそのまま承継した全社参加型のシステムが主流になるだろう。
④ 連結納税から単体納税に移行する連結グループはどれくらいありそうか?
新制度への移行に伴い、既に連結納税を採用している連結グループのうち、単体納税に移行する企業はどれくらいあるだろうか。
この点、筆者が日常業務の中で感じることだが、潜在的に単体納税に戻りたいと思っている会社は多い(今は戻りたいけど戻れないため思っているだけであるが)。
- まず、個別申告方式への移行により、連結納税の事務負担が減るとはいえ、単体納税よりは事務負担が重いことは明らかである。そのため、新制度による税負担の増加(連結納税の税務メリットの減少)が大きい場合、単体納税に戻すこともあるだろう。特に、連結親法人の繰越欠損金の活用メリットがなくなり、単体納税と同程度の税負担になる場合、単体納税に戻すことも考えられる。
- また、連結納税採用の動機となっていた連結親法人の繰越欠損金の活用について、既に全額使用されており、現在は損益通算効果が小さく、渋々、連結納税を継続している連結グループもある。このような会社は、特に、連結法人数が5社未満の連結グループに多い印象であるが、既に連結納税のメリットが失われている会社にとっては、連結納税の事務負担だけが残っているため、これを機に連結納税を取りやめたい、と考えるかもしれない。
- 一方、連結法人数が10社を超える連結グループでは、純粋に損益通算を目的に連結納税を採用していることも多く、この場合、連結納税を継続することになるだろう。
- 事務負担の軽減から単体納税に戻りたいと経理担当者が思っても、連結納税から単体納税に戻すに当たって、大きな障害になると思われるのが、税効果会計である。現在、連結納税を採用している会社では、連結グループを一体として回収可能額を計算するため、繰延税金資産の計上について、連結納税の恩恵を受けている。しかし、単体納税に戻る場合、企業分類又はスケジューリングが悪化することが多く、繰延税金資産の取崩しが発生する可能性が高い。そのため、連結納税の取りやめが業績悪化につながる可能性がある点で、少なくとも上場会社が連結納税を取りやめることは難しいかもしれない。
- さらに、連結納税の事務負担を回避したいからといって、単体納税に戻し、損益通算を放棄した場合、将来、リーマンショックのような経済環境の悪化により、グループ法人に巨額の損失が発生しても、欠損金額の有効活用ができず、連結グループの税負担率が上昇し、更なる業績悪化につながれば、税務戦略について株主からの追及も厳しくなるだろう。その点でも、上場会社が連結納税を取りやめるためには、ある程度の覚悟が必要になるだろう。
- なお、連結納税を取りやめた後に、連結納税に再び戻すのに、制限期間が何年あるかも考慮する点になるだろう。
(2) まだ連結納税を採用していない企業への影響
① 新制度適用後は、連結納税を採用する企業は増えそうか?
個別申告方式への移行により、現行制度より連結納税の事務負担が減るため、連結納税を採用しやすい環境になることは間違いない。
ただ、個別申告方式への移行により、連結納税の事務負担が減るとはいえ、単体納税よりは事務負担が重いことは明らかである。そのため、個別申告方式への移行が連結納税の採用を全面的に後押しするとは思えない。
また、連結親法人にSRLYルールが導入されることで、連結親法人の開始前の繰越欠損金を他の連結子法人の所得と相殺して一瞬で巨額の税負担を減少させるという連結納税の最大の採用動機が失われることから、この点は連結納税の採用には大きなマイナスとなるだろう。
ただし、連結法人(連結親法人を含む)の開始前・加入前の繰越欠損金は、単体納税では自社の所得金額の50%を限度としてしか相殺できないが、連結納税では自社の所得金額の100%と相殺することができるため、連結法人の繰越欠損金の活用が見込まれる場合、連結納税を採用する企業も増えるだろう。
② 連結納税を開始、加入、離脱するなら改正前か? 改正後か?
この点、現行制度と新制度のいずれで開始、加入、離脱すると有利かどうかを慎重に検討する必要がある。例えば、現行制度では、特定連結子法人に該当せず、時価評価が必要となり、繰越欠損金が切り捨てられるが、新制度では、時価評価も繰越欠損金の切捨ても行われない場合、新制度の適用開始まで待つことも一案である。
一方、新制度の場合、開始、加入時に時価評価が行われない場合であっても、その後、含み損益の利用制限が課されることがある。また、離脱時には一定の場合、離脱法人が時価評価する必要も生じる。このような場合、現行制度で開始、加入、離脱をしてしまった方が、その後の税負担も減少し、事務手続も簡便になるだろう。
③ 準備期間に連結納税を開始して、その後、取りやめるのもよいのか?
連結親法人や連結子法人の繰越欠損金の期限切れが迫っており、連結納税を採用した方が税負担が減少するのは明らかであるが、連結納税の事務負担の重さに躊躇して採用できていない場合でも、準備期間において連結納税の開始を行い、その後、取りやめを行うことができれば、それも一案になるだろう。
4 おわりに
以上、仮に、専門家会合で示された取扱いがそのまま実現した場合に想定される実務への影響について解説した。
しかし、専門家会合で議論された内容については、今年の9月末までに開催される政府税制調査会の総会でも報告に留まる見通しであり、本稿執筆時点で、何も確定したものではない。また、現状、個別論点(特に、税負担が増える見直し)については反対意見もあると言われている。
そのため、実際の改正の内容は今後の議論によることから、今後も、その行方に注目していきたい。
(連載了)