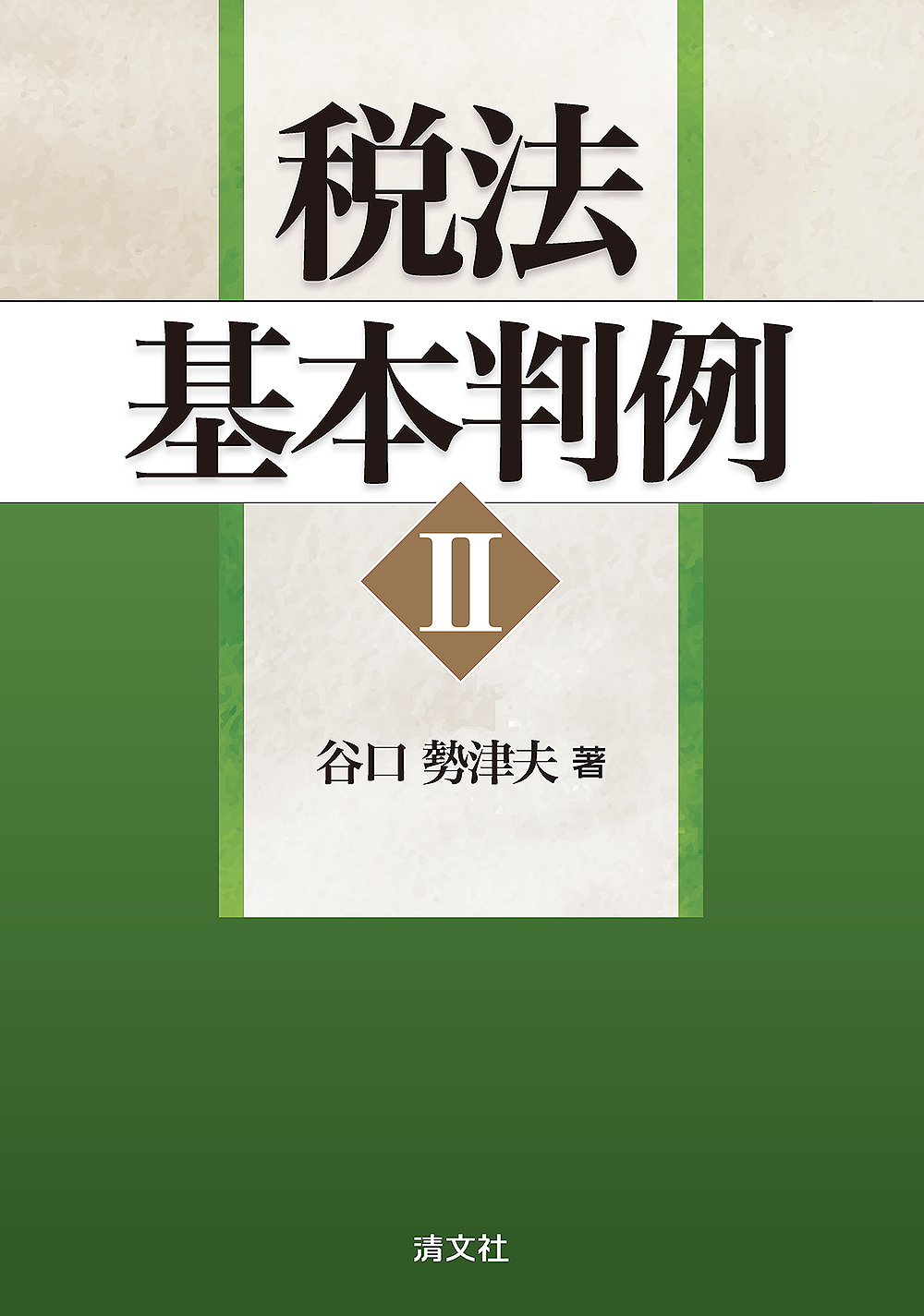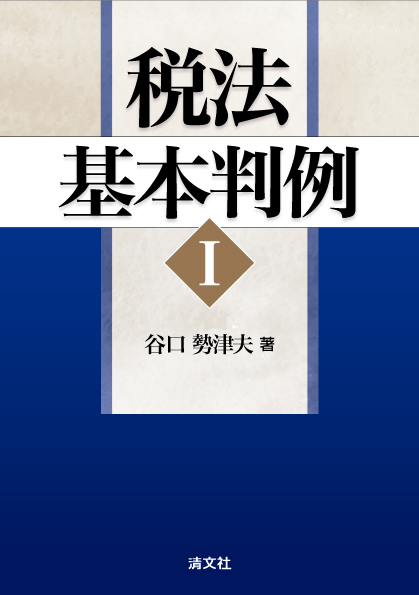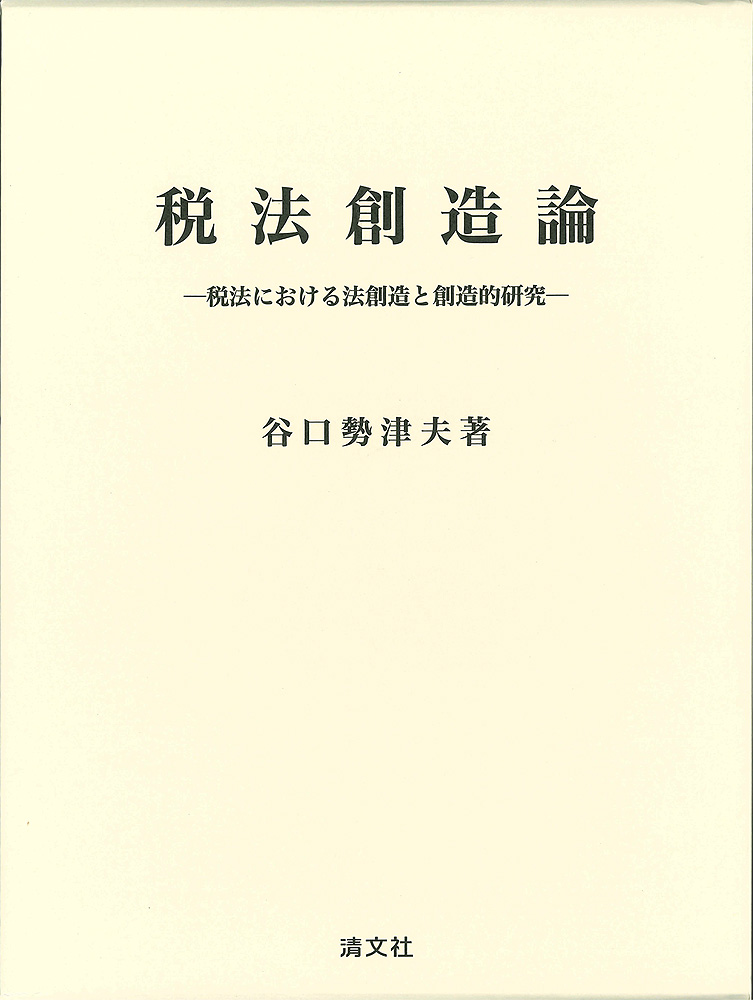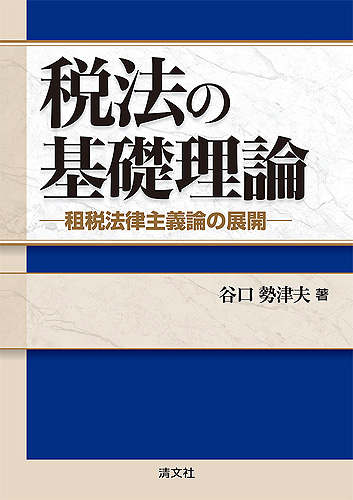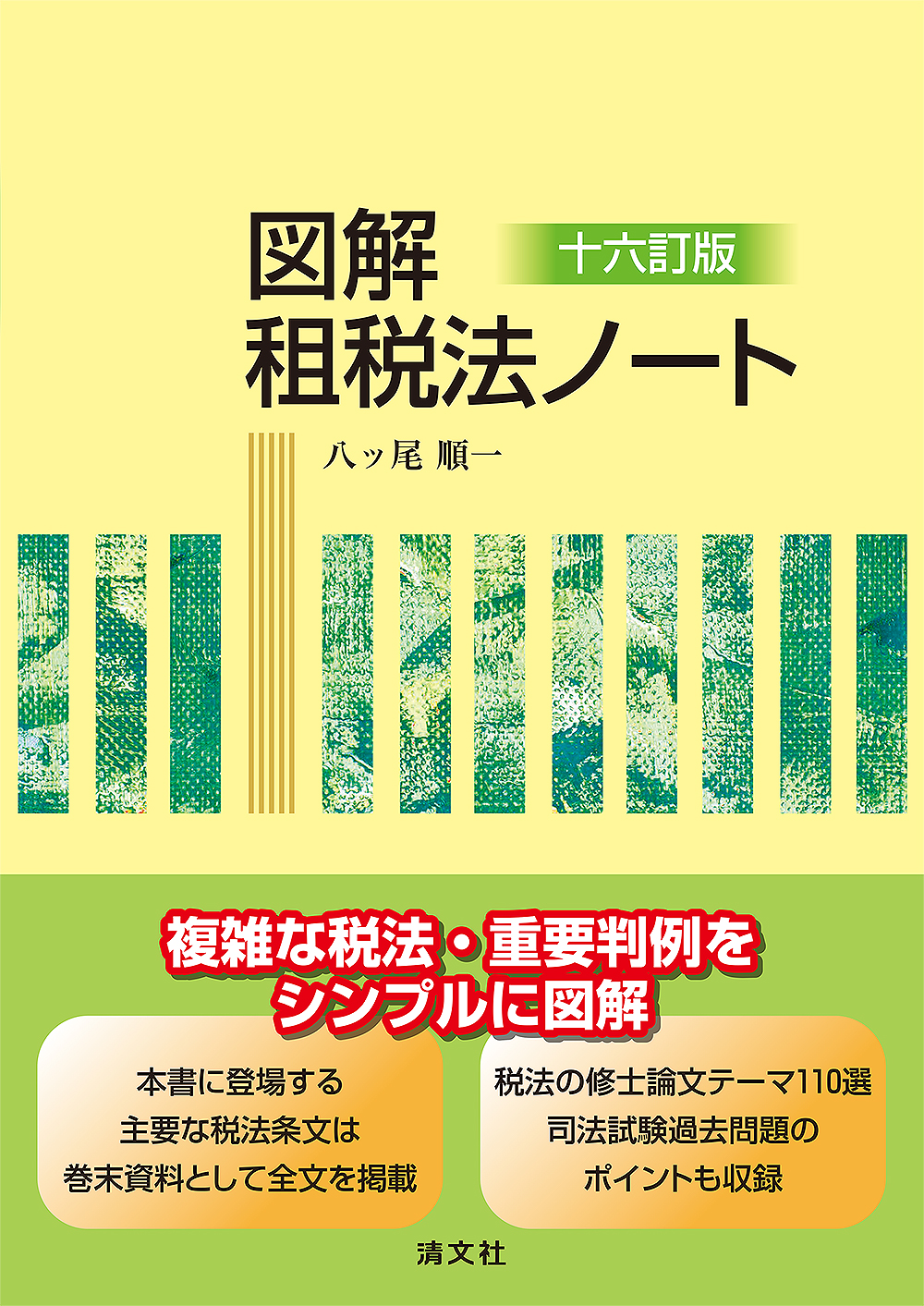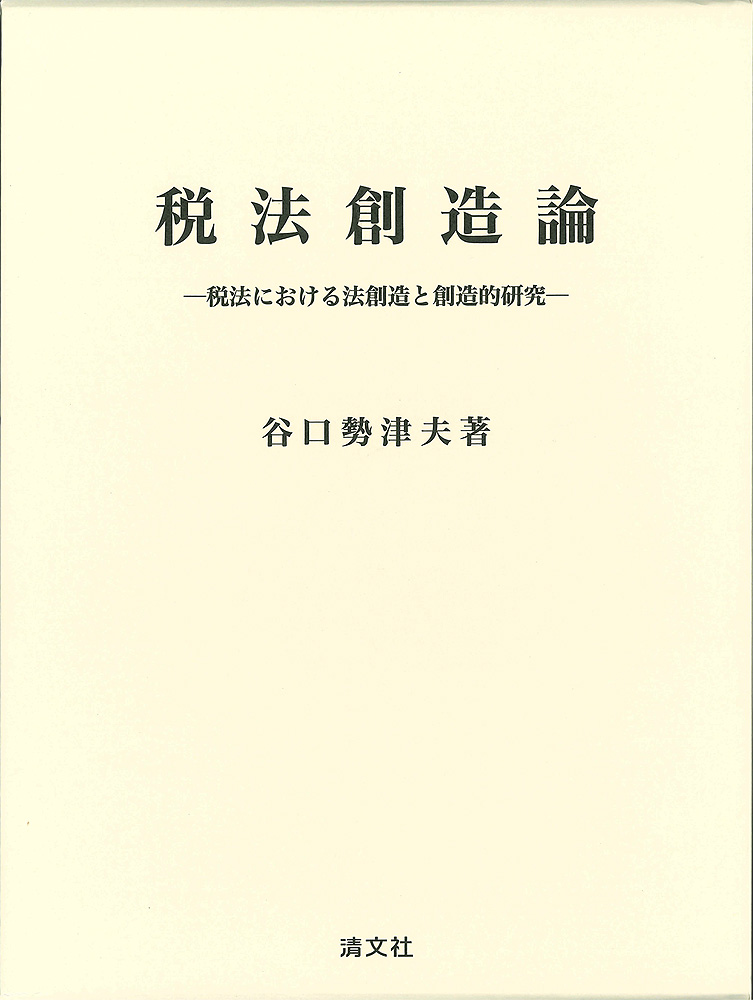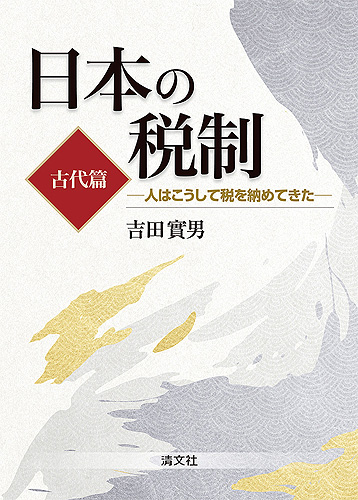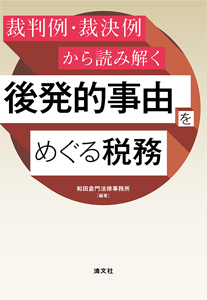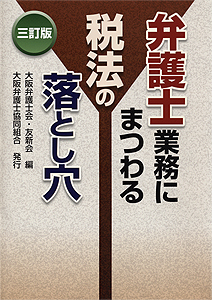谷口教授と学ぶ
国税通則法の構造と手続
【第1回】
「国税通則法のコンメンタール的「読み物」の連載を始めるに当たって」
-国税通則法制定の趣旨と国税通則法の「構造」の意義-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
1 はじめに
一昨年(2020年)12月に連載「谷口教授と学ぶ『税法の基礎理論』」を終えるに際し(同第50回Ⅳ)、「谷口教授と学ぶ」をシリーズ化して、「国税通則法の構造と手続」及び「税法基本判例」の連載を昨年4月から始めさせていただく旨を述べたが、「税法基本判例」の連載は予定どおり始めたのに対して、「国税通則法の構造と手続」の方は、筆者の個人的な事情により、連載を1年間延期させていただいた。記してお詫び申し上げる次第である。
本連載は、国税通則法について基本的には逐条的に、場合によっては「節」あるいは「款」を単位にして、筆者の問題関心に基づき論点を選んで検討を加えようとするものである。その意味で、本連載は、形式の点ではコンメンタール的なものではあるが、内容の点では、条文の意味内容の正確な理解のために条文を逐条的に解説するコンメンタールではなく、他の「谷口教授と学ぶ」シリーズと同じく(「税法の基礎理論」(全50回完結)第1回Ⅰ、「税法基本判例」(昨年4月から連載中)第1回Ⅰ参照)、原則1回読み切りの「読み物」(コンメンタール的「読み物」)とすることを基本コンセプトとするものである。
なお、以下の叙述を読まれてお気づきになることと思われるが、本連載では、文献資料等の原典をできるだけそのまま引用するように心がけることにする。それは、「谷口教授と学ぶ」シリーズでは、そうすることによって、文献資料等について筆者の理解したところを、読者には、原典に当たって検討しながら読んでもらいたいと考えているからである(谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」第50回Ⅳ参照)。
2 国税通則法制定の趣旨
本連載において検討する論点は条文等ごとに筆者の問題関心に基づいて選ぶものであるが、その選定に当たっては、税制調査会「国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)」(昭和36年7月。以下「国税通則法答申」という)1頁にいう「国税通則法制定の趣旨」を重視することにする(ただし、その「趣旨」に対する見方には注意を要するが、この点については3で国税通則法の「構造」に関して述べる)。同答申1-2頁は「国税通則法制定の趣旨」について次のとおり述べている(下線筆者)。少し長くなるがそのまま引用しておこう。
現行の国税に関する法律は、法体系としてみると、所得税法、法人税法、酒税法、物品税法等のいわゆる各税法と国税徴収法とからなつている。各税法は、各税ごとに課税物件、納税義務者、税率等の課税実体が異なつているところから、それぞれ独立の税法として制定され、課税実体に関する規定とこれに関する手続規定を中心として構成されている。また、国税の滞納処分を中心とした徴収手続は、各税に共通して統一的にされるものであるから、まとめて国税徴収法に規定されている。
各税に関するこれらの法律は、各税ごとにそれぞれの実体上の必要から、いわば自然発生的に個別的に制定され、成長してきたものであつて、およそ租税法の基礎にあるべき基本的な法律関係、すなわち政府と納税者との間における権利・義務の態様や限界に関する制度上の仕組みを明らかにし、その上に立つて各税法を組み立てたというのではなく、これまでの税法改正もまた、その時時における各税法ごとの必要に応じて、各税法につき部分的に手当が加えられてきたにとどまつている。
したがつて、現行のこれらの法律の規定を総合的にみると、そこには、租税に関する基本的な法律構成に関する規定が欠けているし、また、各税に共通する事柄でありながら、規定の不備不統一ないしは重複等がかなりみられるのであつて、そのため、税法についての統一的な理解を困難にしたり、あるいは解釈上の疑義を生じる結果となつているものが相当みられることは否定できないと思われる。
たとえば、その主な例として次のようなものがあげられよう。
(1) 税法と私法との関係その他税法の解釈・適用に関する基本的なあり方について規定が不十分なため、解釈上疑義を生じているものがあること。
(2) 租税債権の成立及び確定のような租税法律関係の基本的な事柄について実定法に規定がないこと。
(3) 政府が課税標準や税額の更正決定をするについて、これをすることができる期間が直接税と間接税とで異なつていること及び更正決定と納税者の申告又は前にされた更正決定との間の法律効果の関係について規定がないため、判例等でも種種の解釈を生じていること。また、このような租税の賦課権と徴収権とについて、その区分が明らかにされていないため、これらの行使に関する期間制限について解釈に疑義を生じていること。
(4) 利子税や各種加算税の制限について、直接税と間接税との間に、更には各税の間に不統一があつて、負担の公平上問題があること。
(5) 課税処分に関する不服申立ての制度について、直接税と間接税との間において規定の仕方が不統一であること。
(6) 人格のない社団又は財団の納税義務に関する規定が統一的に定められていないため、税法上の法律関係の解釈につき問題を生じていること。
したがつて、このような租税制度の基本的な仕組みないし各税に共通する事項、すなわち租税に関する通則事項と称すべきものについては、この際、これを統一的に整備規定することが必要であると考えられる。
もつとも、現在、国税徴収法は、単に滞納処分等の徴収手続のみを定めたものにとどまらず、その外に各税に共通する事項について部分的に規定を設けており、この意味で同法は、中間的な通則法としての性格を有しているといえよう。しかし、国税徴収法として制定される限り、通則法としての性格をもたせるには限界があり、かえつて現行の制度はこの意味で国税徴収法の性格をあいまいにしているといわなければならないであろう。また、このような事項を各税法においてそれぞれ規定することは、いたずらな規定の重複と複雑化をもたらすだけでなく、法律形態としても適当でないと考えられるのであつて、結局、これを統一的に整備して規定した法律を制定することが最も適当かつ必要であると求められ、このような法律として、国税通則法の制定が望ましいと考えられる。
上記のようにして国税通則法を制定するに際しては、単に現行の不備不統一を是正したり、解釈上疑義のある点を明らかにするにとどまらず、従来から内容について問題のあつた諸点について、これまで毎年のように行なわれてきた税制改正が各税の課税実体に関する部分に重点がおかれたため、共通的な事項でしかも負担に関係するものでありながらその検討や改正が見送られてきたと事思われる情[→思われる事情]を考慮して、この際充分検討を加えて、所要の改正を行なうことが適当であると考える。
ここで「課税実体」・「課税実体に関する規定」という概念は、今日の税法学説・実務で一般に使用される「課税要件」・「課税要件規定」という概念に相当するものと解されるが、国税通則法答申が当時の税法に欠如しているとし、したがって、国税通則法で定めようとした「およそ租税法の基礎にあるべき基本的な法律関係、すなわち政府と納税者との間における権利・義務の態様や限界に関する制度上の仕組み」ないし「租税に関する基本的な法律構成」に関する規定は、課税要件規定及びこれに関する手続規定(租税手続規定)の両方を含むものと解される。
ちなみに、課税要件という概念は、杉村章三郞教授がアルベルト・ヘンゼルの著書(Albert Hensel, Steuerrecht, 2. Aufl., 1927)を翻訳した『獨逸租税法論』(有斐閣・1931年)の中で用いたのがわが国においておそらく初めてであろうと思われるが、同88頁では次のとおり定義されていた(旧漢字は改めた)。
租税債務は「租税法」(・・・・・・)によれば課税要件の実現により成立する(81条1項第1段)。従つて租税債務法を系統的に叙述せんとすれば第一に課税要件の何たるかを知らなければならない。課税要件とは実体的課税法規に規定せらるゝ抽象的条件であつてその実体的存在(課税要件の実現)によつて一定の法律上の効果を生ずとせらるゝものを云ふ。従つて課税要件とは具体的租税債務関係の抽象的映像と云ふことが出来る。法律又は経済生活の具体的事実又は行動が決定しうべき状態に在り而して課税要件の法規に於てその総括が可能な場合にのみ租税債務は存在し国家の租税債権は成立するのである。
しかし、国税通則法答申当時の学説・実務の状況を知る上で有益な文献である租税法研究会編『租税法総論』(有斐閣・1958年)では課税要件という言葉自体ほとんど使用されていなかった(数少ない使用例として30頁[田中二郎発言]参照)ことからすると、同答申が課税要件ではなく「課税実体」という言葉を使用したことについて特に違和感はなかったのであろう(日本税法学会「国税通則法制定に関する意見書」税法学131号(1961年)1頁でもこのことに関する言及はない)。
さて、話を元に戻すと、前記のような理解に基づき国税通則法答申を更に読み進めると、国税通則法は、①課税要件規定については「各税に共通する事柄・事項」を、②租税手続規定については「各税に共通する事柄・事項」及び「中間的な通則法」としての国税徴収法が定める「国税の滞納処分を中心とした徴収手続」以外の手続事項をそれぞれ定めることを、その「制定の趣旨」とする法律であるといってよかろう(この点については次回「国税通則法の目的」との関係で更に検討することにする)。
もっとも、国税通則法制定の経緯をみると、そもそもは、昭和30年12月16日閣議決定により大蔵省に設置された租税徴収制度調査会が、「租税徴収制度調査会答申」(昭和33年12月)3-4頁において次のとおり述べた(下線筆者)ことから、国税通則法制定の必要性が認識されるようになったものである。
[国税徴収法]改正の法形式については、納税者の税法に対する理解を容易にするという観点からは、各税法に分散する租税の共通規定を整理統合し、かつ、租税債権の発生、消滅、時効等の総則的規定を整備した租税通則法を制定することが最も望ましいといわなければならない。しかし、現行の租税の賦課形態についても根本的に検討すべきものが含まれているから、将来できるだけ早い機会において租税通則法を制定することとし、今回は、租税の優先権、滞納処分手続等すみやかに改正を要する点を中心として、現在の国税徴収法と同様の法形式により改正し、改正法にいわば中間的な租税通則法としての性格をもたせることが適当であると考えたのである。
その後、昭和34年5月19日付で内閣総理大臣から「国税及び地方税を通じ、わが国の社会経済事情に即応して税制を体系的に改善整備するための方策」について諮問を受けた税制調査会は、「租税徴収制度調査会答申」の前記の指摘を踏まえ、「税法整備に関し、国税の基本的な法律関係及び手続等についての規定を整備統合して国税通則法を制定する問題」(国税通則法答申まえがき)について審議検討を行い、国税通則法答申を行ったのである。
このような経緯に照らしてみると、国税徴収法は「租税徴収制度調査会答申」から国税通則法答申に至るまで一貫して「いわば中間的な租税通則法」ないし「中間的な通則法」として性格づけられてきたことから、国税通則法は国税徴収法の延長線上で制定されたとみるべきものであり、両法は「実は[手続の]実体的には一本のやつを、便宜主義的に二本に分かれている」(研究会「国税通則法をめぐって」ジュリスト251号(1962年)10頁、14頁[志場喜徳郎発言])というようにみることができるように思われる。
そうすると、国税通則法答申が「国税通則法制定の趣旨」として「およそ租税法の基礎にあるべき基本的な法律関係、すなわち政府と納税者との間における権利・義務の態様や限界に関する制度上の仕組み」を明らかにして「租税に関する基本的な法律構成に関する規定」を整備する旨を述べているのは、これをⓐ国税徴収法の側からみてそう述べているのであって、「課税実体」に関する法すなわちⓑ課税要件法の側からみてそう述べているのではない、ということになるように思われる。
3 国税通則法の「実定的構造」と「体系的構造」
このことを税法学の体系の観点からみると、国税通則法の「構造」が浮かび上がってくるように思われる。「租税法の諸分野のうち中心をなすと考えられる租税債務法と租税手続法」(金子宏「租税法学の体系」同『租税法理論の形成と解明 上巻』(有斐閣・2010年)第8章所収[初出・1972年]、191頁)の関係については、「租税債務法と租税手続法との関係は丁度実体法と手続法との関係に当るから、ヘーンゼルの言葉を借りるならば、後者は前者に対して目的従属的(zweckgebunden untergeordnet)な関係に立っているといえよう。」(同190-191頁。金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂・2021年)29頁も同旨)といわれるが、税法学の体系は、今日では、租税債務法すなわち租税実体法の中心をなす課税要件法を基礎として構築され確立されていること(その到達点は金子・前掲『租税法』であり、同書は初版(1976年)からその体系を維持している)からすると、国税通則法答申のいう「国税通則法制定の趣旨」は、税法学の体系の観点からは、以下に述べるような意味で「逆転」した「構造」を国税通則法にビルトイン(built-in)することにあるとみてよいように思われる。
すなわち、租税実体法と租税手続法との目的従属的関係からすると、租税手続法に属する国税通則法は、租税実体法とりわけ課税要件法を実現すること、すなわち、課税要件の充足により成立した納税義務の内容を正しく確認し当該納税義務の履行を確保することを目的とすべきであるから、国税通則法は、前述のようにして「租税に関する基本的な法律構成に関する規定」を整備するに当たっては、これを前記ⓑ課税要件法の側からみてその整備を行うべきであったところ、実際には、前記ⓐ国税徴収法の側からみてその整備を行ったものと解される。この点について、次の指摘(中川一郎・清永敬次編『コンメンタール国税通則法』(加除式[1989年追録第5号加除済]・税法研究所)B27-28頁[須貝脩一執筆]、B31頁[同]。下線筆者)は正鵠を射たものである。
【B27-28頁】
国税徴収法は、徴収手続を中心として構成せられたから、徴収手続に必要となる限りの前提的基本規定が同法中に規定せられておつたのであるが、しかし基本的事項を規定することそのことは同法の趣旨とするところではなかつた。従つて、国税徴収法上の基本規定は徴収手続に向けられたものとして規定されていたので、それ以外の目的をもつものではなかつた。国税徴収法における基本規定の取り扱いは、手続法としての構成上やむをえないところであつたのであり、ヘーゲル流にいうて、合理的であつたのである。国税通則法は、なんとかの一つ覚えで、その構成の点についても、国税徴収法のゆきかたをそのまま踏襲した。国税通則法は、構成上は、従来の税法のそのままの延長であるとされるゆえんである。
【B31頁】
租税基本法的な事項は、本来、納税義務の基本的関係、租税債権債務の法律関係の基本的明確化に主として関するものであるから、租税債権債務の確定および実現などに関すべき共通手続法的な事項との間には、目的と手段との関係があるといわないまでも、主と従との関係が存するといわなければならない。そして、国税通則法の現実の構成上は、このような両者の関係が明確化されていないのであるから、精解[=志場喜徳郎・荒井勇・山下元利・茂串俊共編「国税通則法精解」大蔵財務協会刊]の説明にいうところの基本的租税法律関係の明確化に関する第二の趣旨はついに実現されることなくしておわつたというのである。
国税通則法のこのような(税法学の体系の観点からみると)「逆転」した「構造」は、とりわけ国税通則法答申が導入しようとした実質課税の原則に対して、「当時のナチスは今後のいろんな財政需要に備えて、徴税を強化するためにそういう実質課税の原則を入れたのだが、それを模倣しているのじゃないか」(前掲研究会「国税通則法をめぐって」15頁)、「租税法がいかに精緻な実体規定をもっても、[ナチスの]そういう世界観によって解釈されるということで、現実の執行は租税法における実定法の規定を破るような執行が行なわれてきた」(同)というような非難を惹起し、同原則の立法を見送る原因(の少なくとも1つ)となったのかもしれない。
国税通則法の制定については「おそらく国庫主義・権力主義思想で統一しようという意図が当初から潜在していたのであろう。」(中川・清永編・前掲コンメンタールA17頁[中川一郎執筆])という見方もあったが、同法を前記ⓐ国税徴収法の側からみると、そのような見方も強ち「偏見」、「勘ぐり過ぎ」等の一言では片付けられず、したがって、上記の非難も一概に不当とはいえないように思われる。いずれにせよ、このような批判的視点は、国税通則法の「構造」に着目することによって得られるものである。
以上を要するに、国税通則法という実定法の現実の「構造」(本連載では「実定的構造」という)と、租税実体法と租税手続法との目的従属的関係を内包する税法学の体系に基づく「構造」(本連載では「体系的構造」という)のうちいずれから国税通則法の検討にアプローチするかは、同法の規定なり手続をその基礎に立ち返って理解しようとする場合、重要な意味をもつと考えるものであるが、このように考えて、本連載のタイトルを「国税通則法の構造と手続」としたところである。
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。