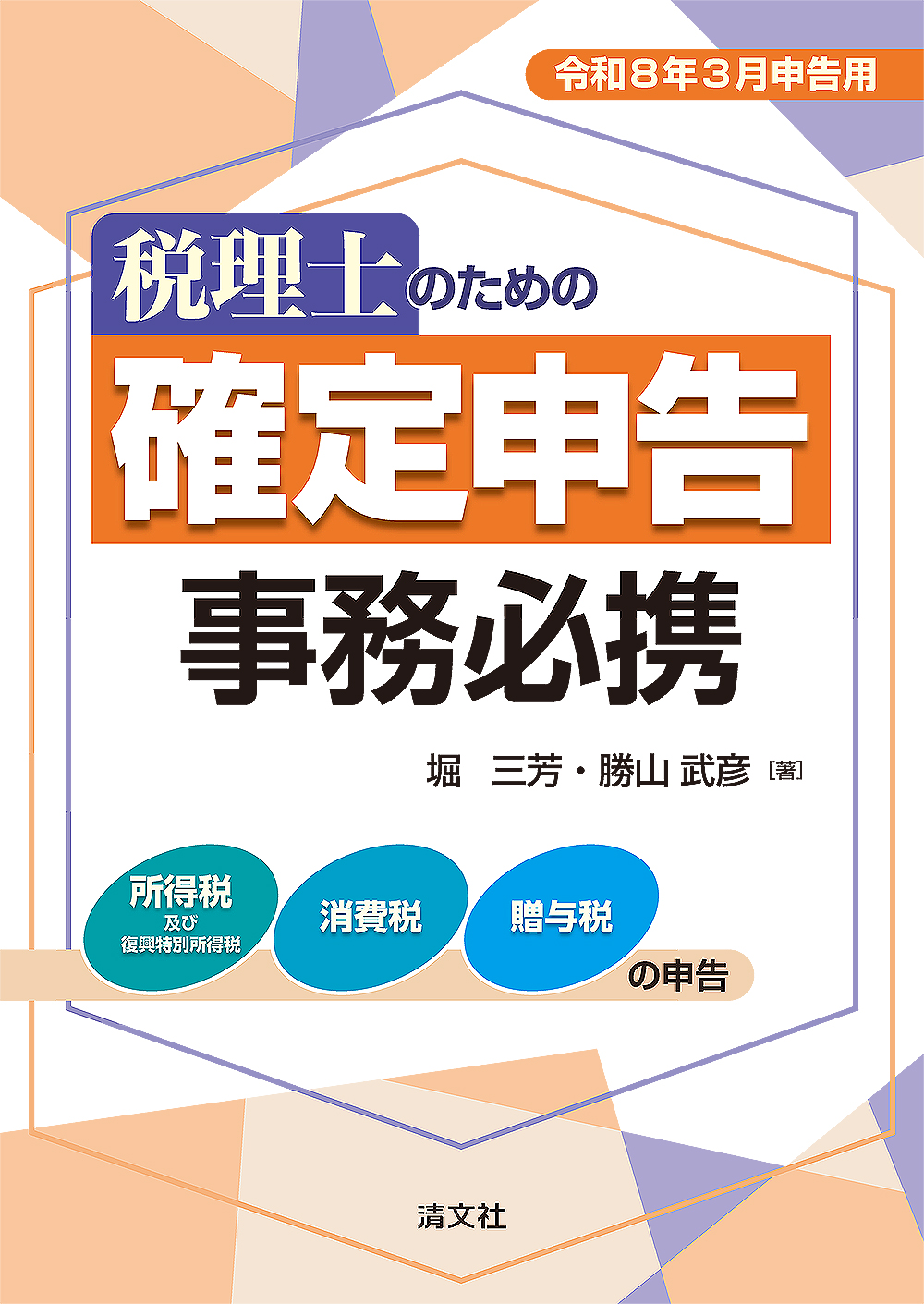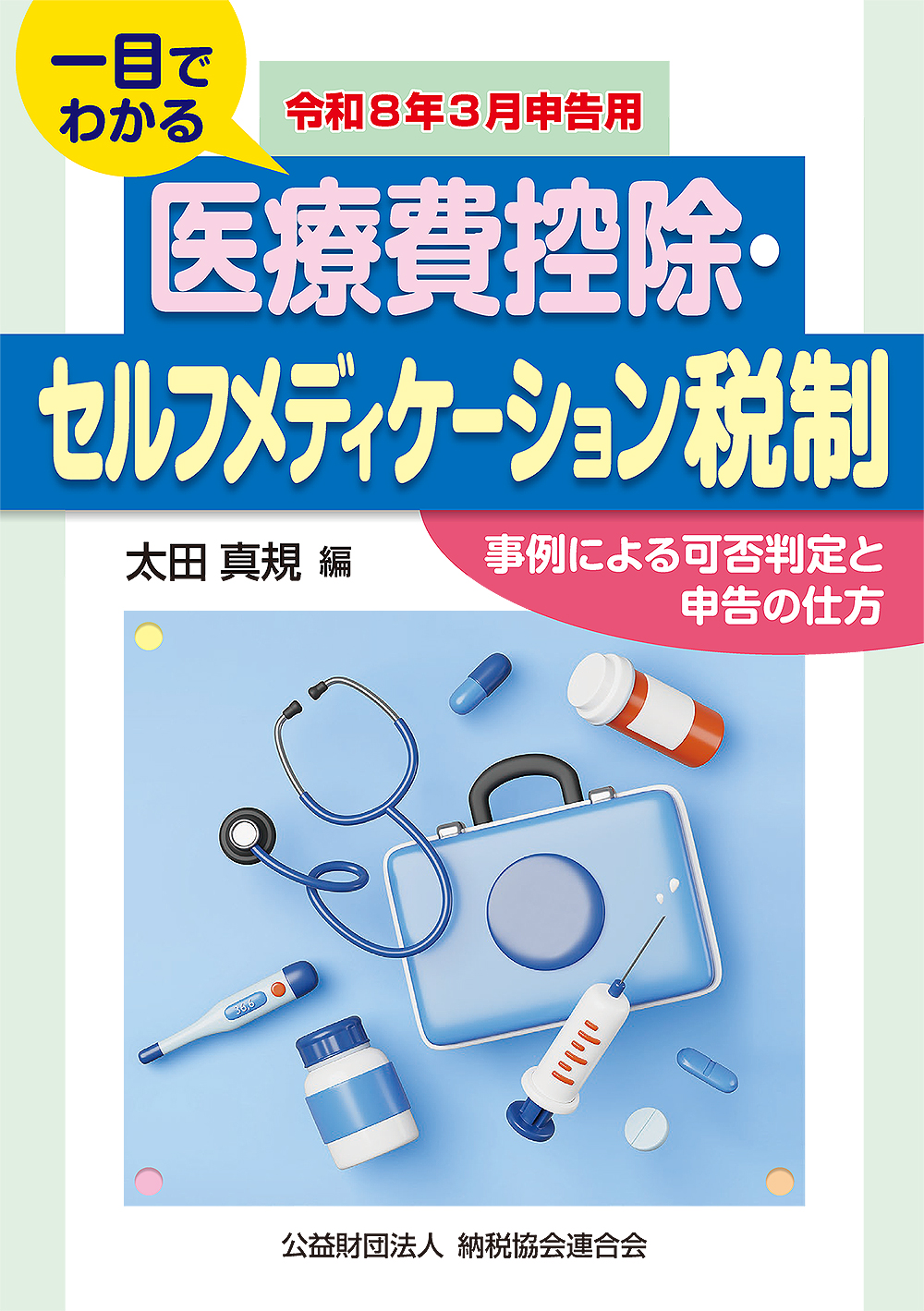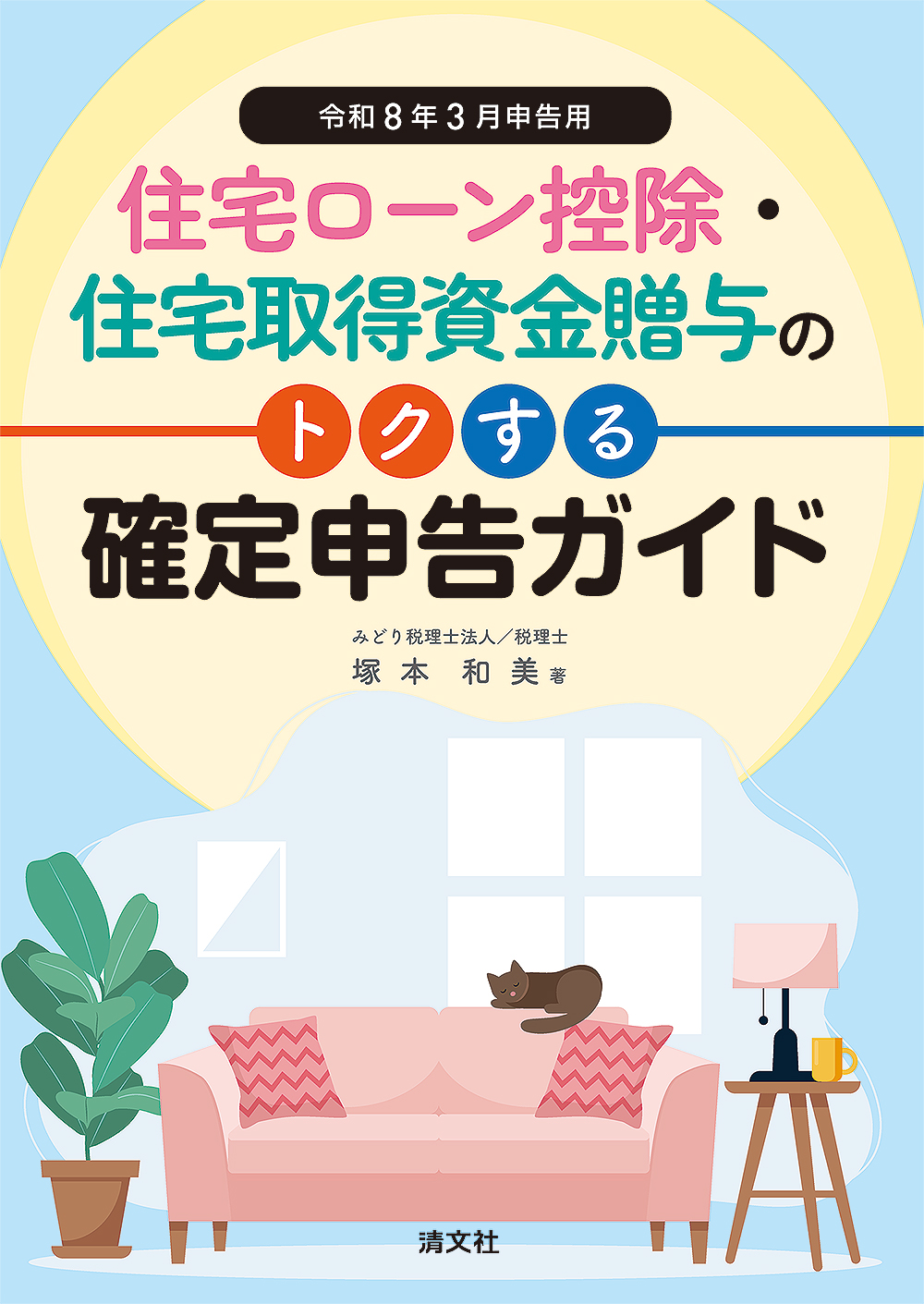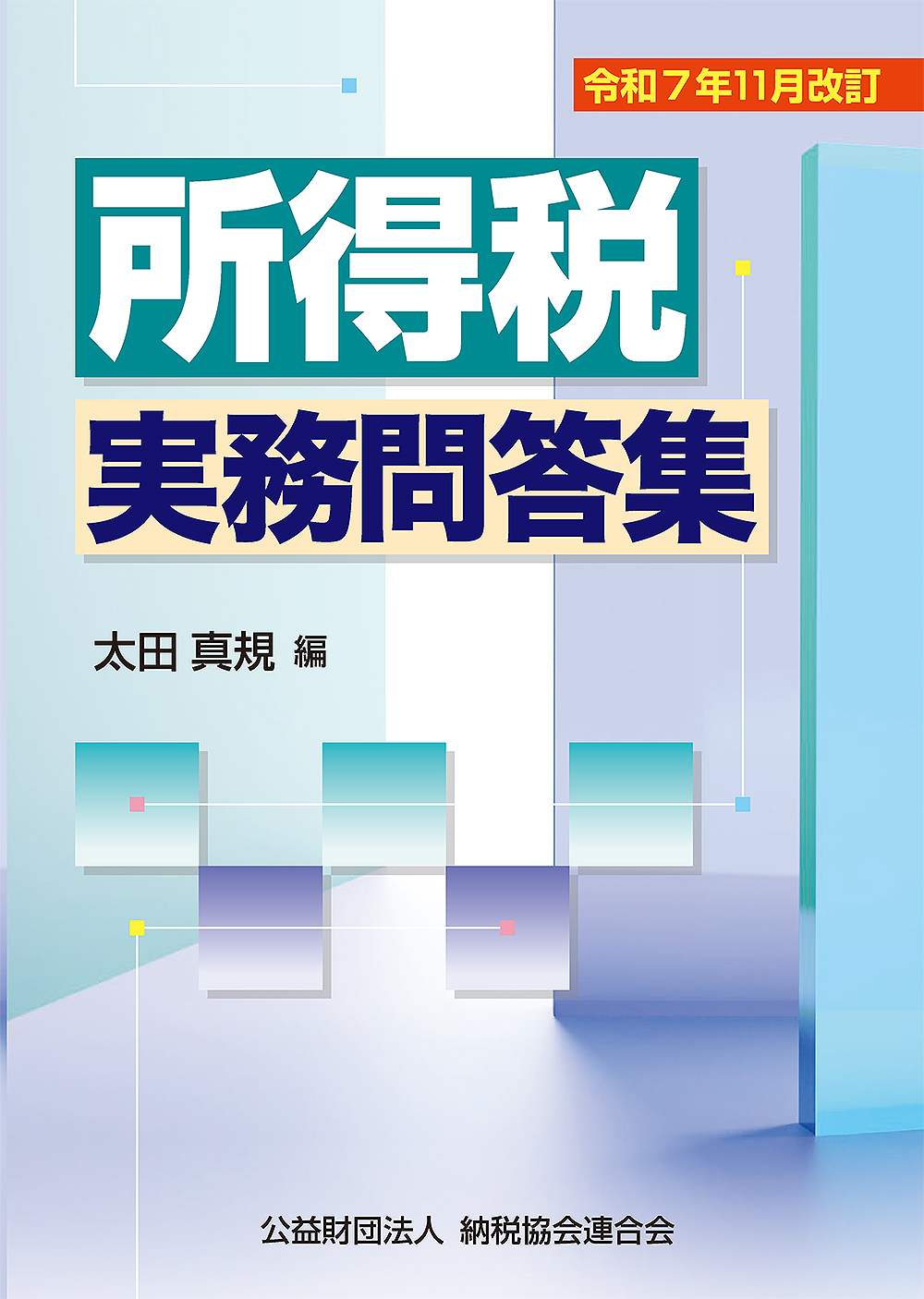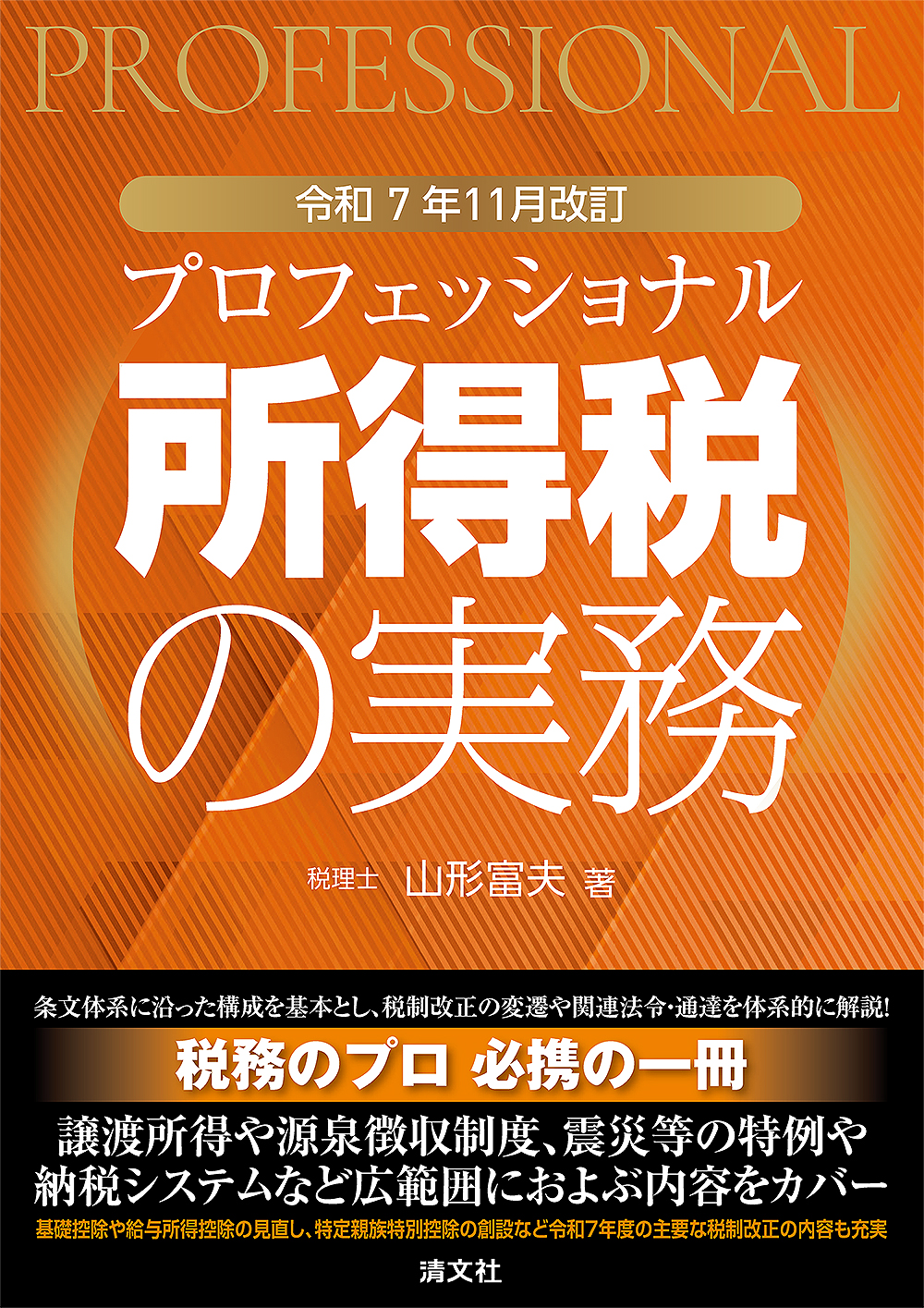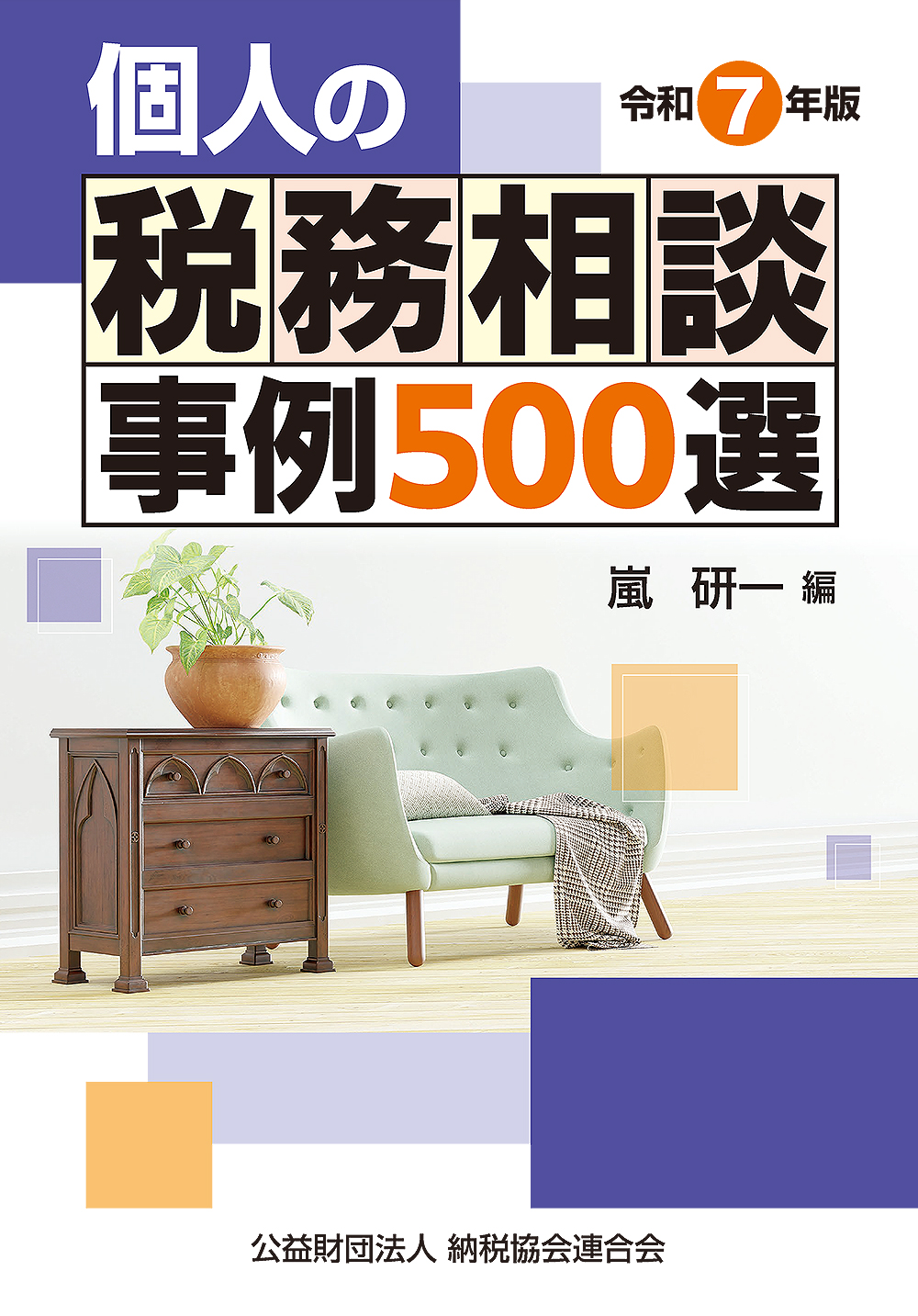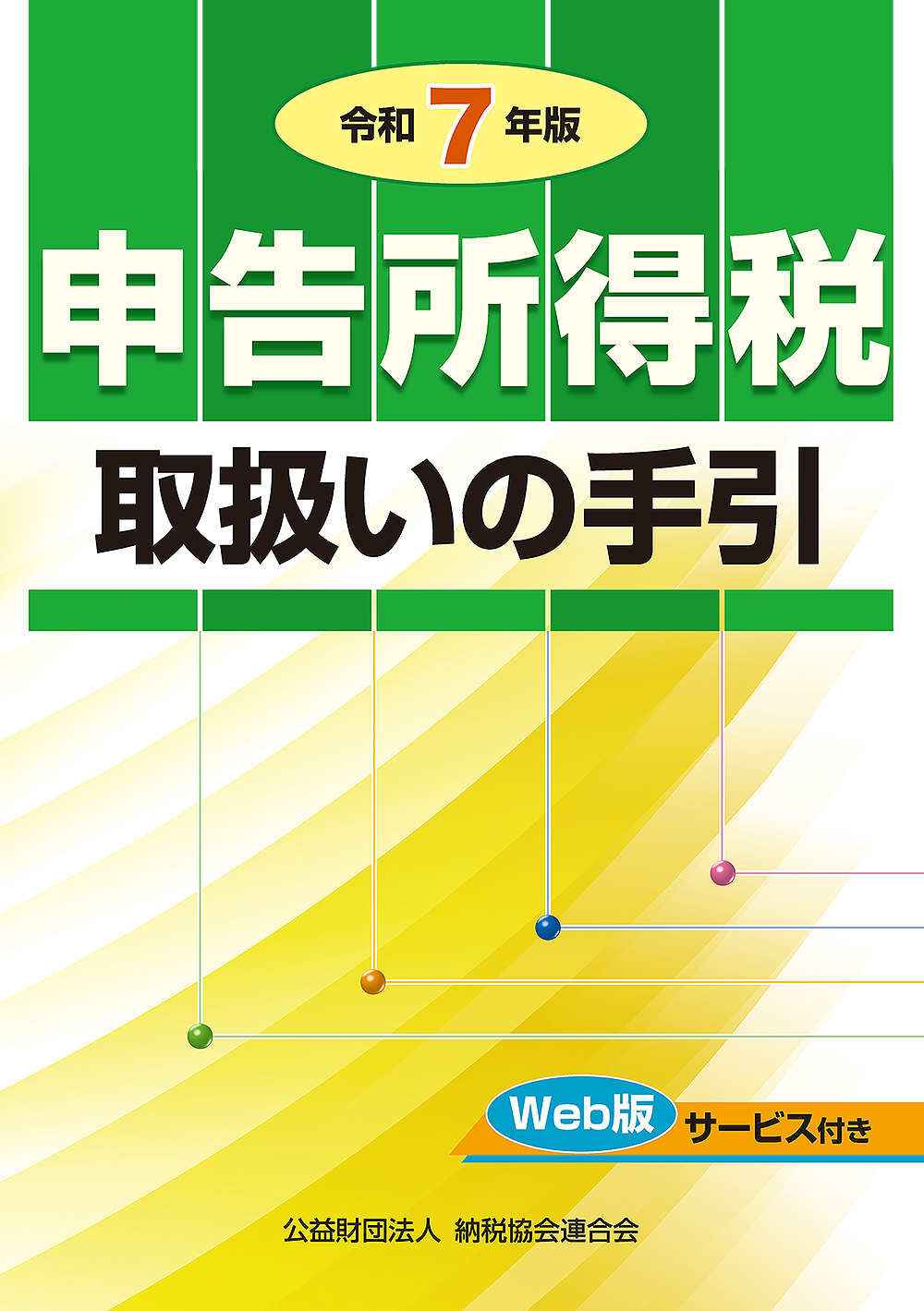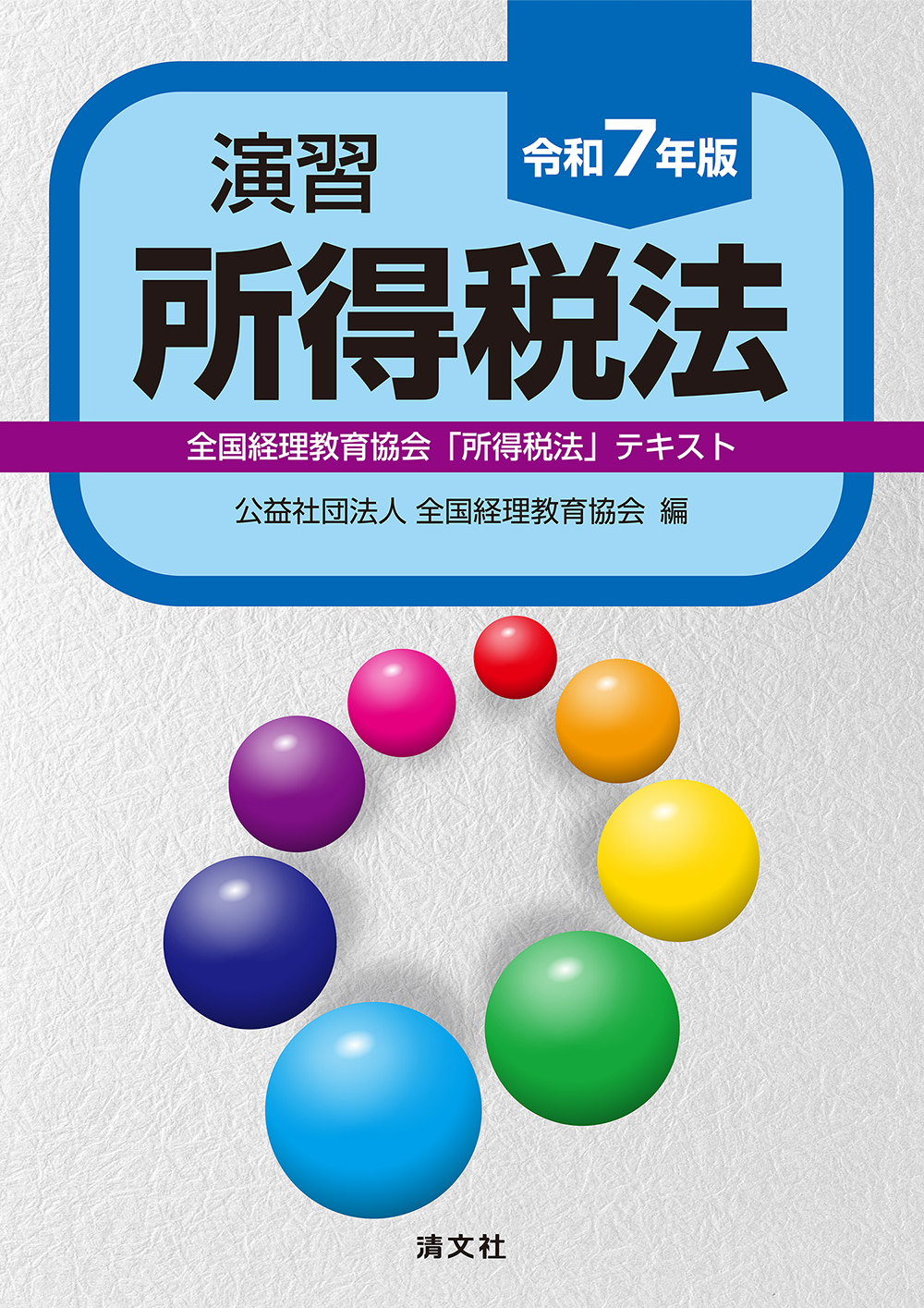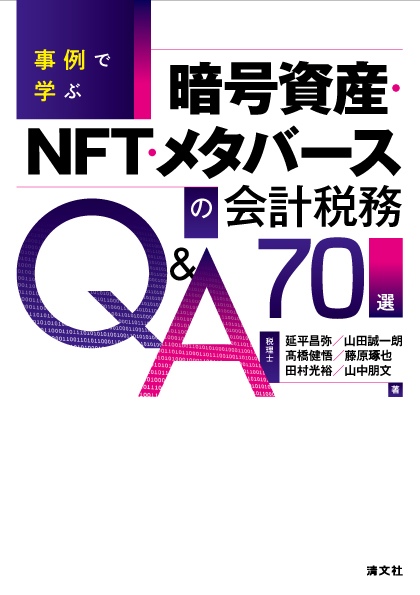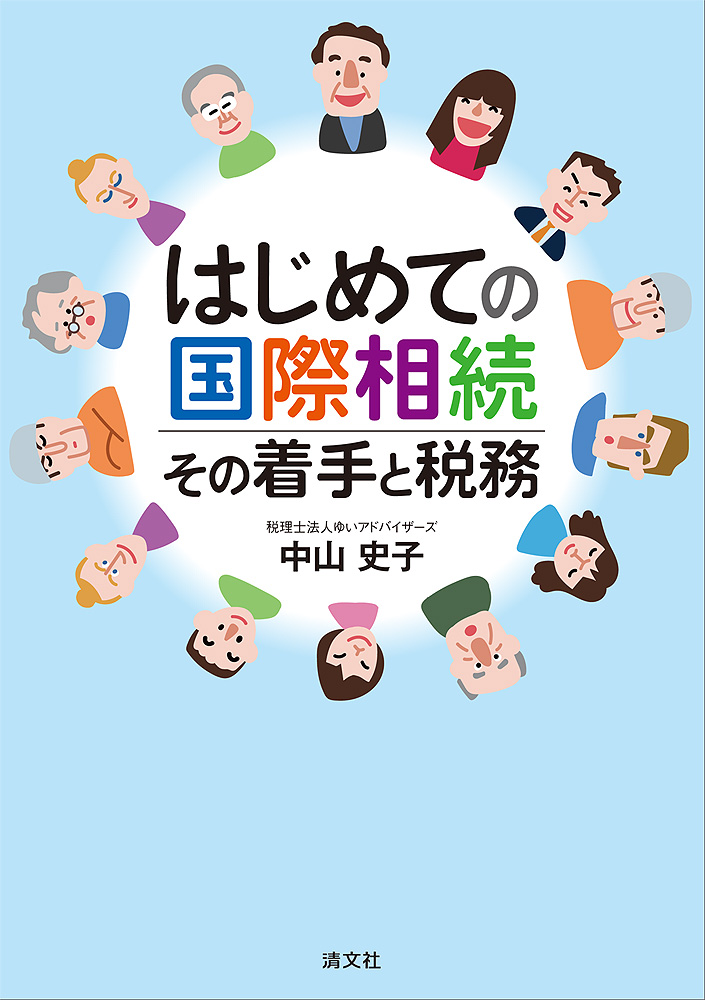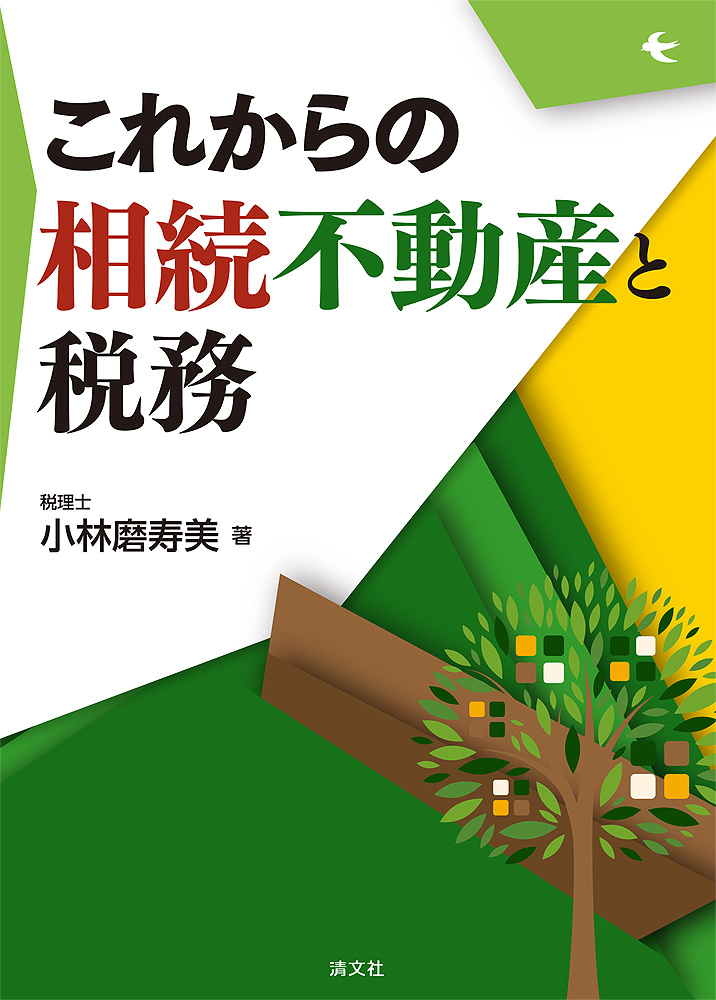財産債務調書の実務における留意点
【第1回】
「財産債務調書提出制度の概要」
デロイト トーマツ税理士法人 ディレクター
税理士 飯塚 信吾
これまで、個人が保有する財産等に関する申告制度としては、所得税法に「財産及び債務の明細書」の提出制度が規定されていたが、この明細書は申告書の添付書類として規定されており、支払調書などとは異なり、未提出などに対する罰則がなかったことなどから、必ずしも適正に提出・活用されていないのではないかと言われていた。
そこで、平成27年度の税制改正において、この制度が見直され、新たに「財産債務調書」の提出制度として、国外財産調書などと併せて「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(以下「国外送金等調書法」)に規定された。
財産債務調書は、従来の財産及び債務の明細書と比較して、提出義務者の要件に保有する財産の額の要件が加わりその範囲が狭められるとともに、財産債務調書の提出を促す観点から、国外財産調書と同様に調書を提出した場合における過少申告加算税等の減額措置及び不提出の場合における加重措置が規定されている。
また、この制度では平成27年7月1日から施行されている国外転出時課税制度の対象となる可能性がある財産について申告を行う必要があり、国外転出時課税制度の適正な執行を担保することを意図したものとなっている。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「取扱通達」)もこれに併せ改正が行われ、詳細な取扱いが明らかにされているので、以下のとおり財産債務調書の実務における具体的な留意点について解説する。
1 提出義務者
財産債務調書を提出しなければならない者は、所得税の確定申告書の提出義務のある者で、次のいずれの要件も満たす者である。
① その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超える者
② その年の年末における価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出時課税制度の対象である有価証券等(以下「国外転出特例対象財産」)を有する者
上記①の「その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額」とは、申告分離課税の所得がある場合には、それぞれの特別控除後の所得金額を加算した後の金額であり、純損失・雑損失の繰越控除、居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの繰越控除適用後の金額となる(国外送金等調書令12の2 ⑤)。
したがって、実務的には、申告書第一表の総所得金額に申告書第三表の退職所得を除く分離課税の所得金額を加算した金額が2,000万円を超える場合に提出義務があることになり、この点は、従来の財産債務の明細書の提出義務と同じである。
財産債務調書では、従来の財産及び債務の明細書の提出要件に加えて、上記②の要件が追加され、年末において保有する財産の価額の合計額が3億円以上であるか、又は、年末において保有する「国外転出特例対象財産」の価額の合計額が1億円以上である場合に提出義務があることとされ、保有財産の額の要件により提出対象者の範囲が狭められている。
国外転出特例対象財産とは、平成27年7月1日から施行されている所得税法60条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》に規定されている有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引である。
平成27年7月1日以降、居住者が国外へ転出する際に国外転出特例対象財産を1億円以上保有しており、国外転出時前10年内に5年以上国内に住所又は居所を有している場合には、国外転出時課税の対象となり、その国外転出特例対象財産を国外転出時に譲渡等を行ったものとしてその含み益に対し譲渡所得の課税が行われることになった。
年末において、この国外転出時課税制度の対象となる財産を保有している者で、その年の確定申告書の提出義務があり所得金額の要件を満たす場合には、財産債務調書を提出する必要がある。このため、財産債務調書は国税当局が将来国外転出時課税制度の対象となる可能性のある者を予め捕捉しておく効果もあると考えられる。
なお、国外財産調書は、その年末において居住者(永住者)であることが提出の要件になっている(国外送金等調書法5①、取扱通達5-1)が、財産債務調書は、年末において非居住者であっても、その年分について確定申告書(年の中途で出国する場合の確定申告書を含む)の提出義務があり、かつ総所得金額及び山林所得金額の合計金額が2,000万円を超えるなどの要件及び保有財産の要件を満たす場合には提出しなければならない(国外送金等調書法6の2 ①)。
2 記載事項
財産債務調書は、国外財産調書と類似した様式で、提出者の住所、氏名のほか、財産の種類、数量、価額、所在などを「種類別」、「用途別」(一般用、事業用の別)、「所在別」に記載することとされているが、国外財産調書と異なり、債務の金額等も記載する必要がある。
また、国外財産を5,000万円以上有するため国外財産調書を提出する者が、財産債務調書も提出しなければならない場合があるが、この場合には、財産債務調書に国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額のみを記載することとされている。なお、国外に存する債務については、財産債務調書に記載する必要がある。
3 財産の「所在」
財産債務調書に記載する財産の所在は、原則的には相続税法10条が規定する財産の所在の判定によることになるが、有価証券等が金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿に記載されているものである場合には、相続税法10条の規定によらず、財産の所在地はその営業所等の所在地とされており、この取扱いは国外財産調書の規定が準用されている。
なお、有価証券等とは次のものをいう。
① 貸付金債権に係る有価証券
② 社債若しくは株式、法人に対する出資又は外国預託証券
③ 集団投資信託又は法人課税信託に関する権利に関する有価証券
④ 国債又は地方債
⑤ 外国等の発行する公債
⑥ 抵当証券又はオプションを表示する証券若しくは証書
⑦ 組合契約等に基づく出資に係る有価証券
⑧ 信託に関する権利に係る有価証券
4 提出期限
提出期限は国外財産調書と同じであり、その年の年末に保有する財産及び債務について、翌年の3月15日(所得税の確定申告期限)までに申告することになる。
* * *
(文中、意見にわたる部分は筆者の見解であり、所属する組織の見解ではないので、ご留意いただきたい。)
〔凡例〕
- 国外送金等調書法・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
- 国外送金等調書法令・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
- 国外送金等調書法規則・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
- 取扱通達・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)
(例) 国外送金等調書法6の2①・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条の2第1項
(了)