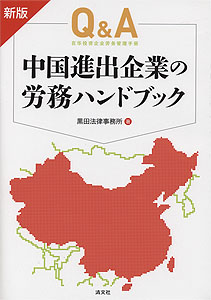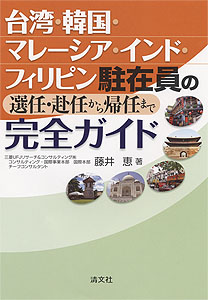外国人労働者に関する
労務管理の疑問点
【第3回】
「外国人留学生(大学生)を社員として雇うとき
(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更)①」
~手続き・制度の概要~
社会保険労務士・行政書士 永井 弘行
はじめに
リクルートスーツを着て街中を歩く大学生を多く見かける時期になりました。
今回から2回にわたって、外国人留学生(大学生)を社員として雇うときの手続きについて解説していきます。
まず今回は「制度の概要」について説明し、次回は具体的な事例などについて説明する予定です。
1 「在留資格の変更許可申請」の手続きとは
これまで外国人を社員として雇ったことのない会社の人事担当者や経営者にとって、「就労ビザの仕組み・制度は、よくわからない」ということが少なくありません。
- 製造業(メーカー)で、海外営業担当者として外国人を採用したい。
- 小売業で、通訳・翻訳担当者として外国人を採用したい。
- 国籍を問わず、ITエンジニアを採用したい。
このようなケースで、会社と本人(外国人留学生)が必要な手続きについて見ていきます。なお、留学生の就職先や従事業務によっては、「研究」や「教育」などの在留資格に変更する場合がありますが、以下では最もケースが多い「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について説明します。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。