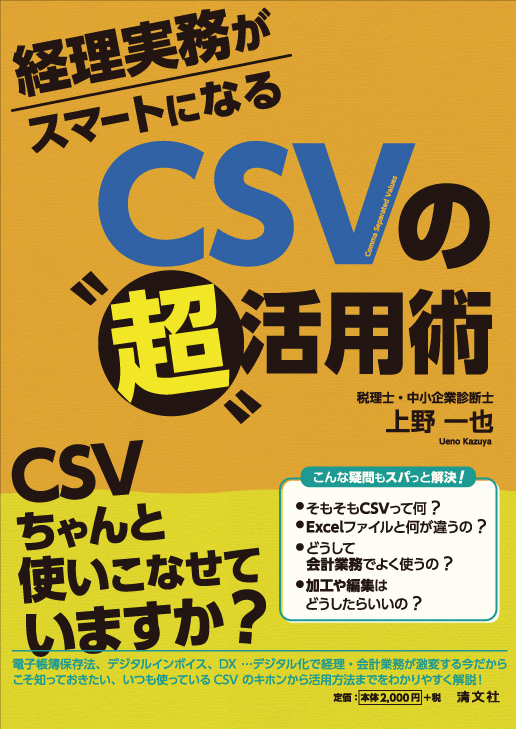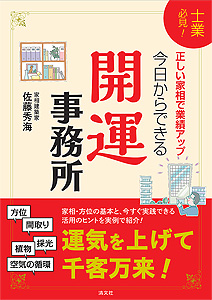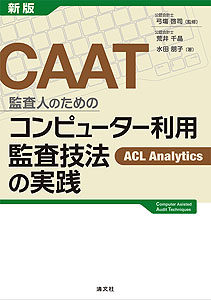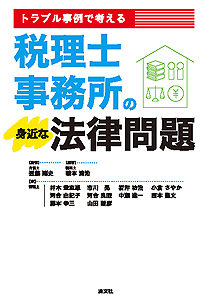〔税理士・会計士が知っておくべき〕
情報システムと情報セキュリティ
【第1回】
「最近の会計システム事情」
公認会計士・税理士 小田 恭彦
会計システムとは
『最近の会計システム事情』というテーマであるが、そもそも「会計システム」とは何であろうか。
人によって思い浮かべるものは違うと思う。会計事務所のスタッフの方々は顧客の記帳代行に使用しているソフト、大企業の経理担当者の方々は自社で利用しているソフト、ソフトウエアベンダーのSEの方々は自社で販売しているソフトなど、それぞれの「会計システム」を思い浮かべるだろう。
狭義の会計システム
まず簡単に「会計システム」を定義しておきたい。
「会計システム」という言葉に明確な定義はなく、機能範囲や規模の異なるさまざまなシステムを「会計システム」と呼んでいる。
ただ、共通しているのは、「仕訳を入力して、総勘定元帳、試算表、決算書を作成するためのシステム」という機能は必ず含んでいる点である。これが狭い意味での会計システムといえるだろう。
この機能だけであれば、わざわざ高価なシステムを購入する必要はなく、表計算ソフト程度でも実現できるかもしれない。ご存知のとおり、会計システムにはそれ以外にもさまざまな機能が用意されている。
以下、いくつかの切り口で分類してみる。
機能充実度による違い
会計システム(ここでは、上記のいわゆる「総勘定元帳作成機能」をイメージしていただきたい)には、街の家電量販店にて数万円ほどで販売している「○○会計」のようなシステムから、数千万円~数億円もするような会計システムまである。この違いは何だろうか。
これらの大きな違いとしては、以下のような機能の充実度による違いがある。
●高速処理機能・・・仕訳の数が何万件も何十万件もある場合に、総勘定元帳や試算表などの帳票をすぐに出力できるための機能
●分散入力機能・・・複数の人が同時にシステムにアクセスして入力や集計をする際に、不整合が起きないようにする機能
●権限管理機能・・・人によって参照できる勘定科目や帳票、ないしは実行できるメニューなどに制御をかける機能
●データ連携機能・・・販売、購買、人事給与などの上流システムから仕訳データを一括して受け取る機能
●グローバル対応(多通貨、多言語機能など)・・・円以外の通貨で帳簿作成が可能であったり、日本語以外の言語でログインして使用することができる機能
対象業務範囲による機能の違い
会計システムと呼ばれているシステムには、総勘定元帳機能以外にもさまざまな機能が実装されている場合がある。
製品毎に機能範囲は異なるが、一般的には以下のような機能が付いている。
・管理会計
・債権管理(得意先元帳)
・債務管理(仕入先元帳)
・固定資産管理(減価償却)
・資金管理
実務的には、上記の機能までを「会計システム」を呼んでいる感覚がある。
管理会計とは、仕訳の中に勘定科目以外の情報、例えば、部門コード、事業セグメント、プロジェクトコードなど入力して、財務会計(制度会計)以外の管理帳票が出せるようにする仕組みや、予算情報との比較や配賦機能などを指す。
債権管理(得意先元帳)は得意先別の売掛金の計上から入金消込み及び滞留売掛金を管理する機能である。
債務管理(仕入先元帳)は仕入先別の買掛金の計上から支払いまでを管理する。
そして、資金管理は、債権管理、債務管理が持っている入金予定情報や支払予定情報から、将来の資金増減を計画したり、借入金の残高や利息を管理する機能などのことである。
なお、法人税等の確定申告書作成システムについては、会計システムの中に機能として準備されているというよりは別製品という感覚であり(個人の確定申告書作成機能が付いた会計ソフトもあるが)、製品原価計算、プロジェクト管理、在庫、生産管理などの機能まで統合されたシステムは会計システムとは呼ばず、ERP(イーアールピー)システムや統合型パッケージと呼ぶ(会計システムの部分だけでも、統合型、ERPなどと呼ぶ製品もある)。
このように、会計システムには機能範囲や機能充実度による違いあり、それぞれ自社のニーズに合ったシステムを使っている。
最近の会計システムの動向
さて、今回のテーマである『最近の会計システム事情』として、ここ数年で大きく変化したのは、まず、監査等の現場における、生データの利用である。
以前は、総勘定元帳や試算表などを紙で入手していたが、最近では監査人などが会計システムを直接操作して、会計システムに保管されている仕訳データを直接参照したり、会計システムから仕訳データなどを一括抽出して分析ツールなどで分析する手法が採用されている。後者を一般的にCAATという。
また、内部統制制度(いわゆるJ-SOX)の施行を機に、会計伝票の変更履歴管理、ユーザ権限管理などいわゆるIT全般統制に対応する機能の充実が図られた。
これは比較的大規模な会計システムには以前から具備されていた機能であるが、これを機に、それまで比較的緩かった中小企業向けの会計ソフトにも付けられるようになった。
最後にクラウド化である。
クラウドとは簡単に言うと、自分ではデータを保持せず、パッケージベンダやサーバベンダーが用意するサーバーにデータを保管する方式をいう。これにより、自分のパソコンや自社のサーバーに破損等が起きた場合でも、データを保全することができる。また、このクラウド化に伴い、会計ソフトを購入するのではなく、会計システムの利用料を払って使用するというSAASという形式も増えた(ASPという呼び方をするものもある)。
このように、ITインフラの進化や税務や会計に関する諸制度の変更などを受けて、会計システムとそれを利用する環境は常に変化している。
(了)
「〔税理士・会計士が知っておくべき〕情報システムと情報セキュリティ」は、各回ごとの担当筆者により、毎月第3週に掲載します。