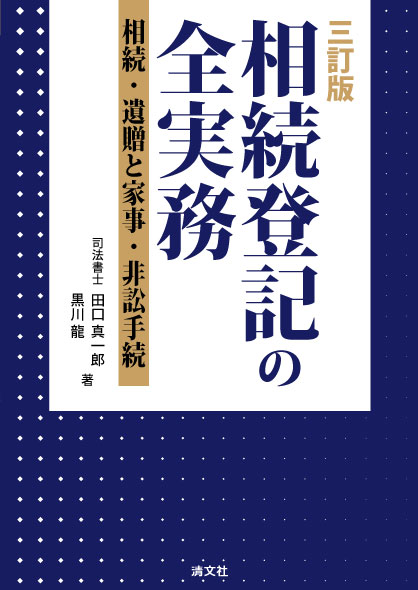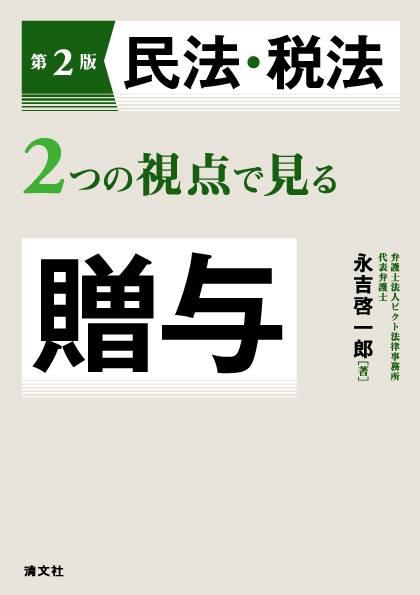老コンサルタントが出会った
『問題の多い相続』のお話
【第1回】
「二次相続対策が進まない・・・」
~自宅が小規模宅地特例不適用の危機に~
財務コンサルタント
木山 順三
〔はじめに~皆さまへのごあいさつ~〕
皆さま、ご無沙汰しています。今から5年ほど前、相続税が増税される直前まで、『私が出会った[相続]のお話』というタイトルで1年間、このWeb情報誌に連載させていただいた、財務コンサルタントの木山順三と申します。
私も今年で「後期高齢者」となり、上記の連載終了後の相続税の改正等について、なかなか的確な対応ができていない状態ですが、クライアント自身も新しい相続制度に対しどのように対処すべきか迷っている模様です。
そこで新たな連載として、私が見聞きした「問題ある相続の事例」をご紹介していきますので、税理士等の相続実務に携わる皆さまにとって少しでも参考になれば幸いです。不定期の掲載ではありますが、これからしばらく、“老コンサルタントのつぶやき”におつき合いください。
◆ ◆ ◆
まず一般的には、平成27年1月1日より開始した相続等からの「遺産に係る基礎控除額の減額」が、相続問題に大きなインパクトを与えたことは言うまでもありません。すなわち、「生前贈与」の積極的対応や相続開始時の「遺産分割」に際し、「配偶者に対する相続税額の軽減制度」を活用すべきか、二次相続を見こして一次相続で課税覚悟での相続人間の分割を優先するかどうかという問題を提起しました。
当然のこととしてそれぞれの「家庭内事情」もあり、一概に節税策のみを講じることはできません。我々コンサルタントとしては、当家の将来の「争族」につながることだけは避けるようアドバイスしなければなりません。場合によっては、「後々の大きな争い」を今のうちに「小さなケンカ」程度に収める対応が賢明なのかもしれません。
今回は、少し前に相続が発生し、「遺産分割」も終わり一次相続としては無事(?)完了しているのですが、私としては必ず次の相続の際に揉めるであろうと懸念している事例をご紹介します。
〔話の背景〕
本件は、私の知人を通じて本人(被相続人)がまだ健在な折に、相続についてのコンサルの依頼を受けたものでした。本人は一部上場会社の元社長経験者で、当時は特別相談役の立場でした。
阪神間の高級住宅地のマンション生活で、自社株を含め金融資産もかなり保有していました。また推定相続人も、妻、長男、次男の平均的家族構成でした。本人の遺産分与の希望は、あくまで妻の生活費確保が第一義で、その後は長男、次男の順に遺産分けしたいという意向でした。
一方、妻は、日頃から夫が長男を金銭面等で甘やかしていることを懸念しており、次男の方を頼りにしていました(当時、長男は離婚し、一人息子を引き取っていました)。私としては、兄弟仲の悪さを考慮し、当家としては「配偶者に対する相続税額の軽減制度」を活用するよりも、むしろ二次相続の際に揉めないよう、一次相続の際に各々の相続人への遺産分割をするような遺言書作成を勧めていました。
そのような中、本人が体調を崩して入院し、退院後の連絡待ちのところ、退院後しばらくして急逝された旨の知らせが入りました。社葬等のあわただしい時間が過ぎ、やっと落ち着いたところで相続人からお呼びがかかりました。
話を聞きますと、急な病気で正式な遺言書を書く間がなく、本人の意向がメモ程度に残されていました。
結論として、そのメモに書かれた意向を主体に「遺産分割協議」を行いました。
案の定、「母親・次男」対「長男」の主張が食い違い苦労しましたが、何とか話し合いが成立しました。
(次の相続が大変だなぁ~という予感を残して・・・)
〔相続税申告の際に想定外の事態が!〕
いよいよ担当税理士とともに、具体的な申告手続きと遺産処理手続きに入りました。ところがその折、居宅マンションが「小規模宅地等の相続税の課税価格の特例」を受けられないことが判明しました。
実は、別途、夫人所有の「医療設備付マンション」(老人ホームではない)があり、本人は退院後、自宅マンションに帰らず、直接夫人所有のマンションへ行ったのです。そして、そのままマンションで逝去されたのです。
(まさか自宅に帰られず夫人所有のマンションへ行かれるとは・・・。そこまで念押ししていませんでした。)
銀行通帳により確認するも、生活費用、公共料金等の引き落としがあり、同マンションの生活実態として把握されました。これにより居宅地に係る「小規模宅地等の相続税の課税価格の特例」の適用は不可となりましたが、救いは別途貸家があり、「貸付事業用宅地」での適用で助かった次第です。
〔やはり進まぬ二次相続対策・・・〕
このように、父親の相続については紆余曲折あったものの、なんとか無事手続きが完了しました。しかし、問題なのは母親の相続です。何しろ長男の母親に対する日頃の不信感が相続開始時に爆発する恐れがあります。すなわち「ひょっとして自分に内緒で多額の生前贈与を次男及び孫にしているのでは?」ということです(自分のことは棚に上げて・・・)。さらに言えば、互いに遡って「特別受益」に関する争いが生ずることになるのではと懸念しています。
母親としては遺留分を配慮したうえで、少しでも次男に分与したい意向でしょうが、あえて母親には、法定相続割合で取得させる旨の「遺言書」作成をアドバイスしています。
本来、法定相続割合による分割であれば「遺言書」作成は不要なのですが、当家の場合は揉めることを想定し、法定相続割合であっても遺言を作成することが、スムーズに手続きできる方法と思っています。
(民法の改正によって、これからは自筆証書遺言書も、「形式」「保管方法」等比較的手軽にできるようになります。)
しかしながら、未だ夫人からは、「遺言書」を作成する旨の連絡がありません(またご主人と同じようにならなければよいのですが・・・)。
このように相続処理の難しさは、たとえ我が子、肉親でも、感情面で複雑になり、なかなか前に進まないことです。
(了)
この連載は不定期の掲載となります。