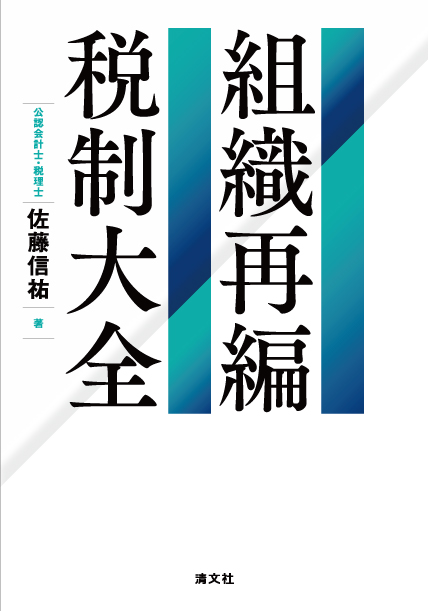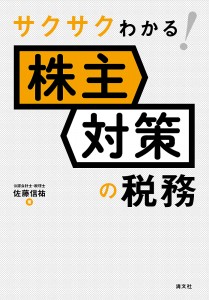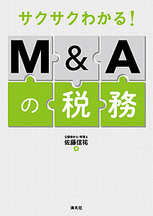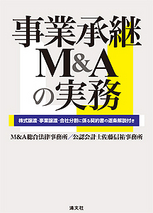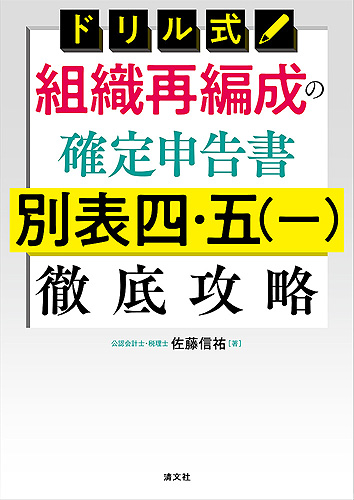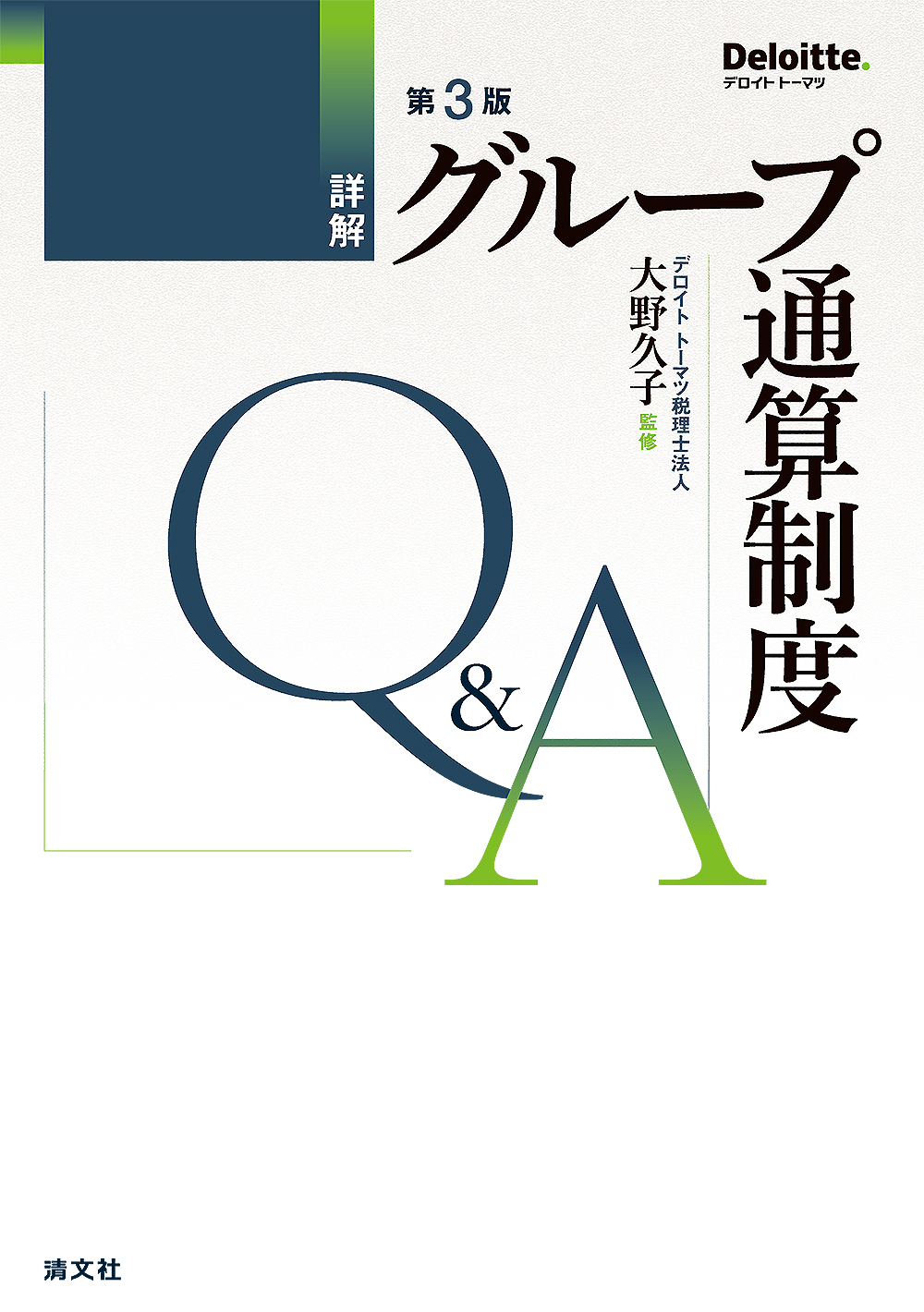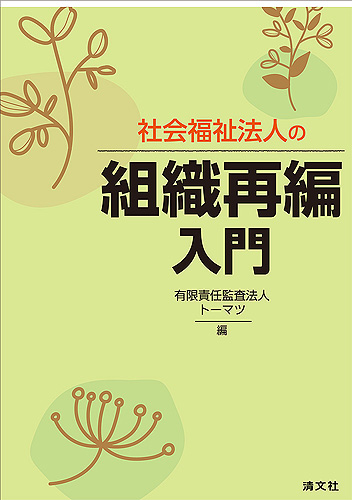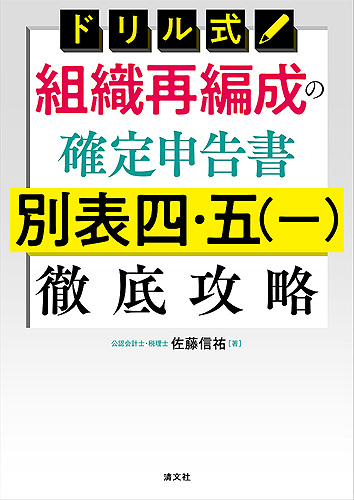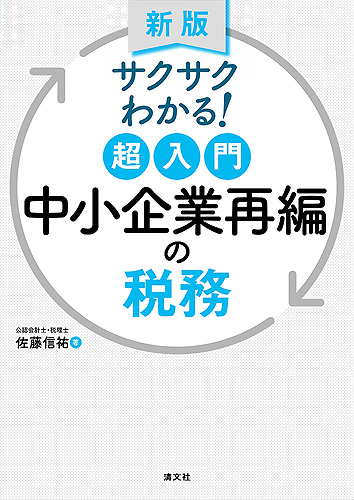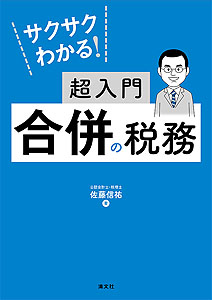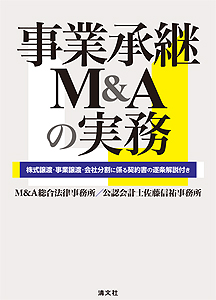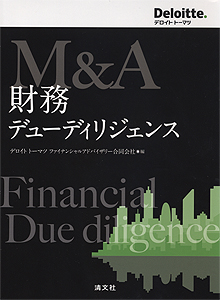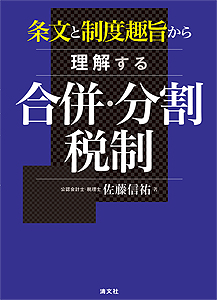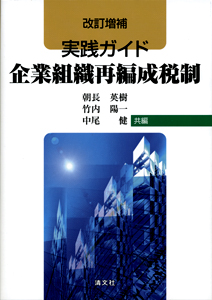組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第1回】
公認会計士 佐藤 信祐
《序 章》
1 はじめに
平成13年度に組織再編税制が導入され、その後も数々の改正が行われた。特に大きな改正は、平成18年度の会社法対応のための改正、平成22年度のグループ法人税制、平成29年度のスピンオフ税制であったと考えられる。平成29年度のスピンオフ税制は、それ自体は大きな改正ではなかったが、組織再編税制の大幅な見直しもなされていることから、今まで指摘されてきた問題点(※1)の多くが改正されており、組織再編税制も一通り完成したということも言える。
(※1) この点については、本連載を通じて解説していきたい。
税務専門家が法律の専門家であると言われるようになったのは、かなり最近のことであり、かつては、著名な国税OBの意見を参考にしながら実務を行うという慣習があった。これに対し、平成10年度以降の法人税法の改正は、なるべく条文に明確に記載しようとする財務省主税局の意図が感じられ、条文にかなり細かく書かれるようになった。そのため、条文の形式的な解釈が一時的に強調された事実があったように思われ、組織再編税制はその顕著な例として挙げられる。そして、租税法律主義が強く意識されるようになった時期とも重なるため、どのような著名な先生の意見であったとしても、国税局や裁判所が同様の意見を採用するとは言えないようになった時期とも重なっている。
その一方で、ヤフー・IDCF事件(平成28年2月29日最高裁判決TAINSコードZ888-1983、1984)では、制度の濫用論が唱えられ、組織再編税制の制度趣旨を理解しておく必要性が言われるようになった。しかしながら、前述のように、どのような著名な先生の意見であったとしても、国税局や裁判所が同様の意見を採用するとは言えない時代になっているため、どのように制度趣旨を理解するのかが問題となる。その顕著な例として、ヤフー・IDCF事件に対する最高裁判所調査官解説が挙げられる(※2)。なぜなら、その内容が、組織再編税制の立案担当者であり、国税局側で鑑定意見書を書かれた朝長英樹税理士の解説(※3)と異なっていることから、今後、立案担当者の意見ですら、制度趣旨として認められないことがあり得るからである。
(※2) 徳地淳・林史高「判解」ジュリスト1497号80-98頁(平成28年)。
(※3) 朝長英樹「検証・ヤフー・IDCF事件は「租税回避」の捉え方をどう変えたか」T&Amaster634号4-13頁(平成28年)など。
これは、学問の世界では、決して衝撃的なことではない。制度趣旨を語るうえで、必ず一次文献を確認するというのは基本中の基本である。なぜなら、立案担当者であったとしても、国税庁での情報に精通していた者であったとしても、記憶違いが生じることがあり得るからである。ましてや、個別の案件ともなれば、個人的な意見になってしまう余地もあるため、退官後に語られた意見は、組織の意見と異なる可能性があることは言うまでもない。さらに、財務省主税局が立案時には想定していなかったことが、その後の運用で、国税庁が明確な解釈を打ち出すということも珍しいことではない。これは、租税法の世界に限らず、あらゆる法律の分野においてあり得ることである。
そして、制度趣旨を語るうえで留意すべきこととして、①著名な先生であっても、その意見を鵜吞みにしない、②税務専門家同士のディスカッションに頼らない、という点が挙げられる。このうち、①については前述の通りであり、必ず一次文献を確認する必要がある。次に、②税務専門家同士のディスカッションは、租税法の理解を深めるうえで貴重ではあるが、「それなりの答え」が出てしまう危険性があるという問題点が挙げられる。「それなりの答え」が出てしまうことから、仮に間違っていたとしても、それが正しいものと勘違いしてしまうからである。
例えば、100人の税理士のうち100人がその通りと思えるようなものであればともかくとして、「制度趣旨を考えると」と書かれていながら、明らかに間違った見解が示されているものも少なくない。このようなことを避けるためにも、税務専門家同士のディスカッションで「それなりの答え」が出たとしても、必ず一次文献を確認し、本当に正しかったのかどうかを検証する必要がある。
本連載では、このような理由から、なるべく該当する条文ができた頃の財務省主税局又は国税庁から公表された資料に基づいて解説をしていくことを心掛けたい。また、賢明な読者は、本連載を鵜吞みにせず、常に一次文献を確認する必要性にも気づかれたと思う。注釈に入れた文献を確認することで、組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨に対する理解を深めることができると思われる。
2 組織再編税制の読み方
組織再編税制を理解するためには、まずは会社法を理解する必要がある。
例えば、2社以上の法人を被合併法人とする吸収合併における税制適格要件の判定に対して、文書回答事例「三社合併における適格判定について(照会)」が公表されているが、会社法上、2社以上の法人を被合併法人とする吸収合併は、複数の合併が同時に行われたと考えることがその根拠となっている。さらに、会計と税務が分かれつつあるとは言え、企業結合会計、事業分離等会計が組織再編税制に全く影響を与えていないとは言い切れない。
そのため、組織再編税制を深く理解するためには、企業会計と会社法も同時に深く理解する必要がある。
そして、組織再編税制は、条文が極めて精緻に作られているという特徴がある。したがって、まずは条文の形式的な解釈を理解する必要がある。その一方で、「おおむね」「見込まれる」といった不確定概念が多いのも組織再編税制の特徴のひとつである。
このような不確定概念については、組織再編税制が制定された当時の資料を確認することで、その解釈や制度趣旨を理解するだけでなく、その後の実務の状況について、公表されている国税局や税務専門家の見解を確認する必要がある。
このように、制度趣旨を理解することが重要であることは言うまでもないが、制度趣旨への理解を強調し過ぎるあまり、条文の形式的な解釈を軽視することも問題である。なぜなら、「こういうつもりで作った」と財務省主税局が強く主張したとしても、実際の条文がそうなっていないのであれば、それを実務で受け入れることはできないからである。
すなわち、条文の形式的な解釈を理解することと、制度趣旨を理解することは、いずれも重要であり、片方だけが極端に強調されるべきではない。本連載では、そのような立場から、一次文献を確認することで制度趣旨を研究しながらも、必ず条文を確認するという姿勢で臨みたい。
* * *
次回以降では、組織再編税制が制定される前に財務省から公表された資料に基づいて、組織再編税制制定の背景を探っていく予定である。
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。