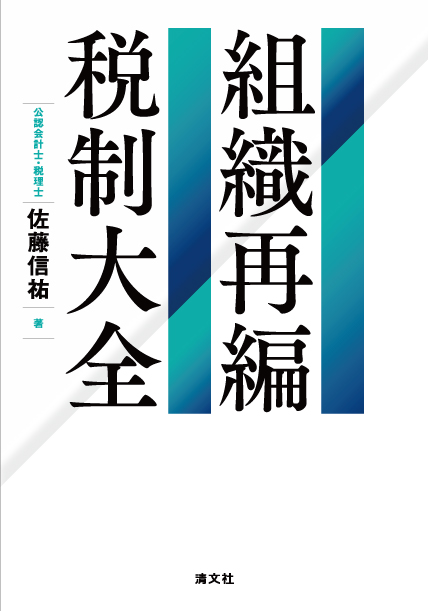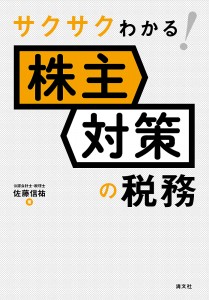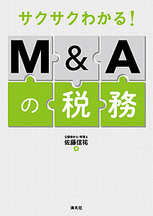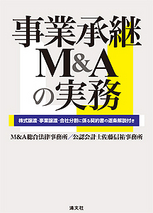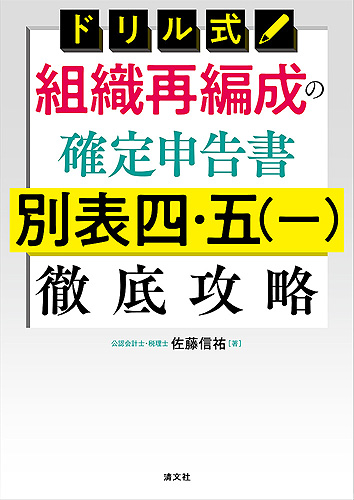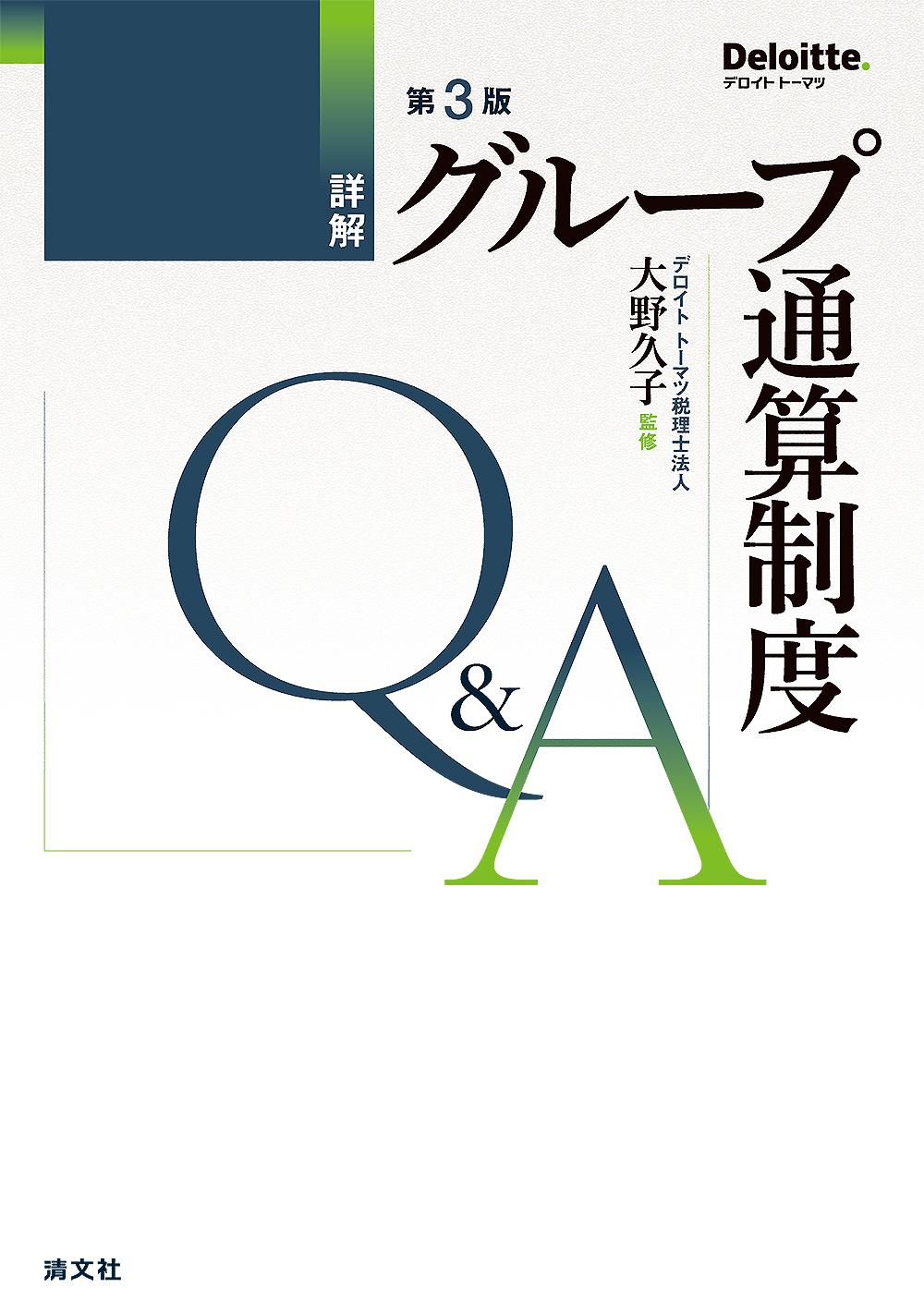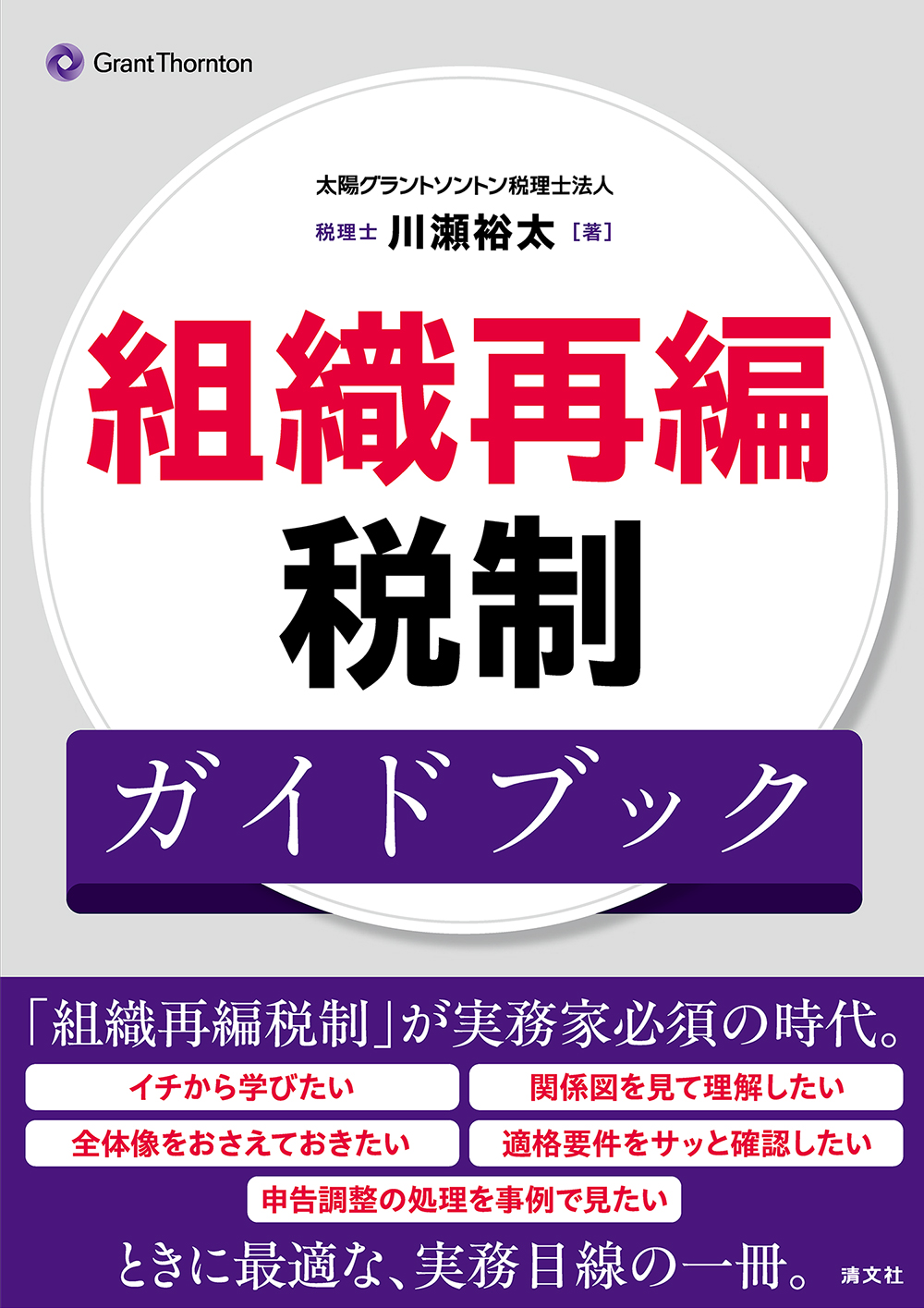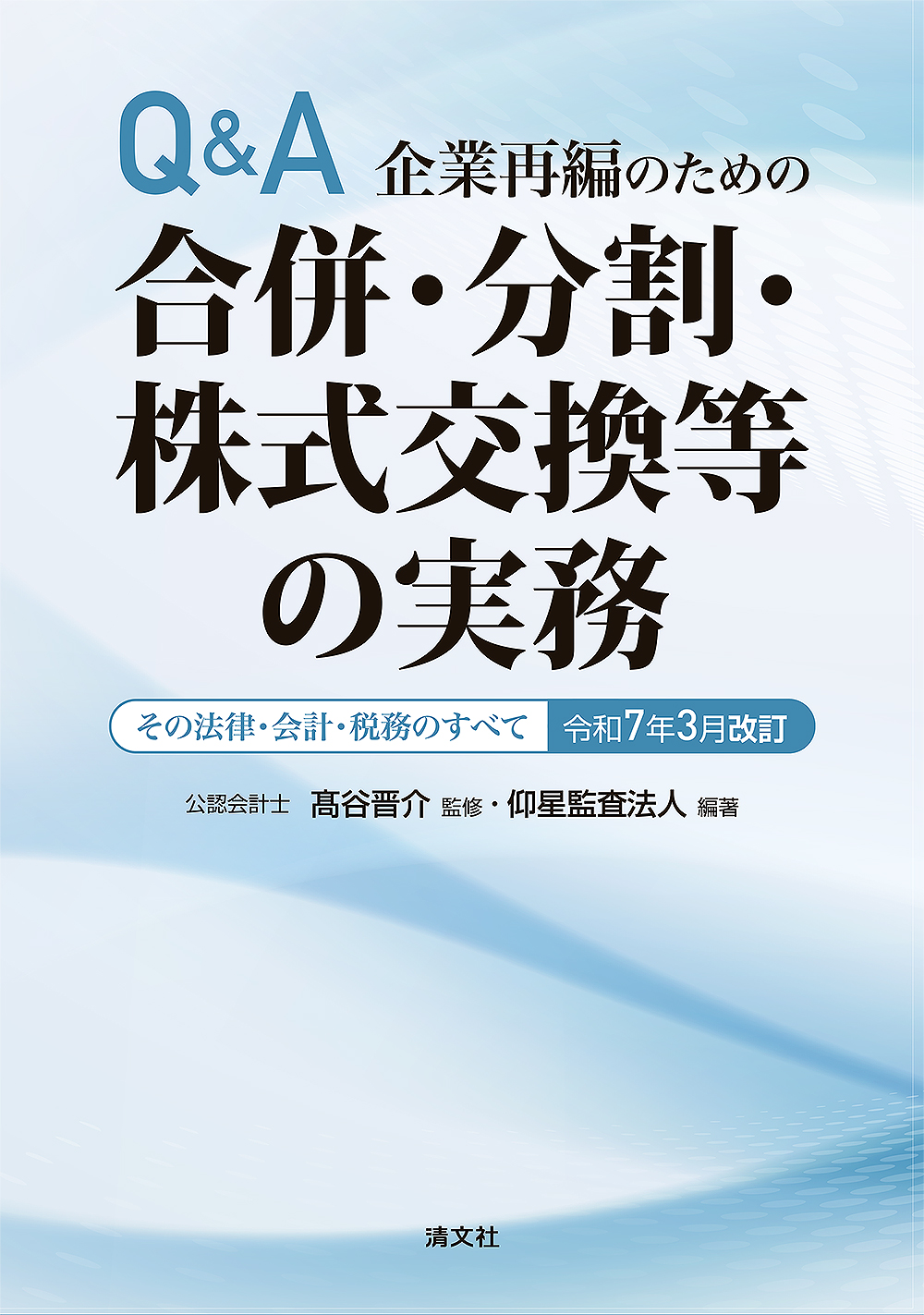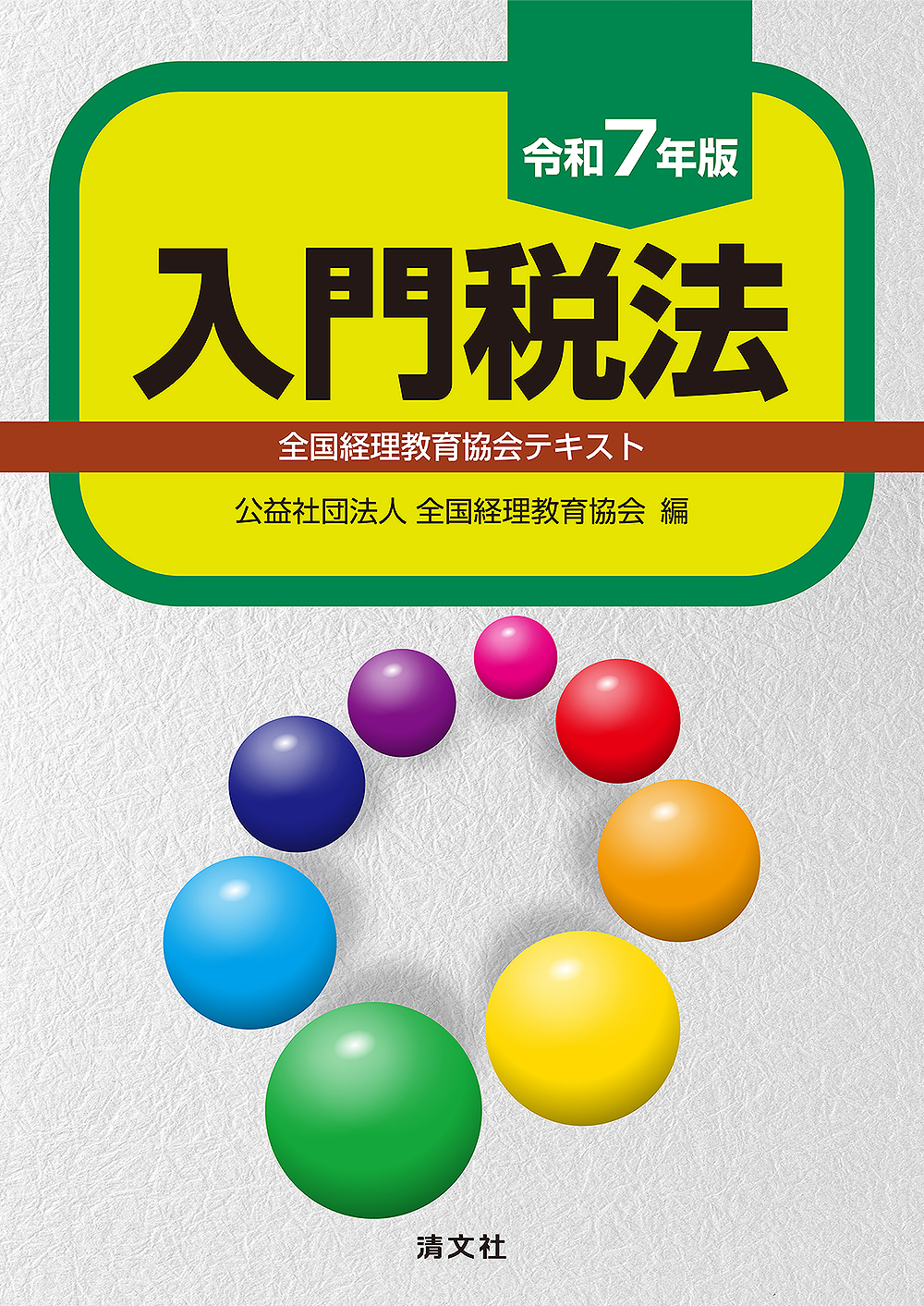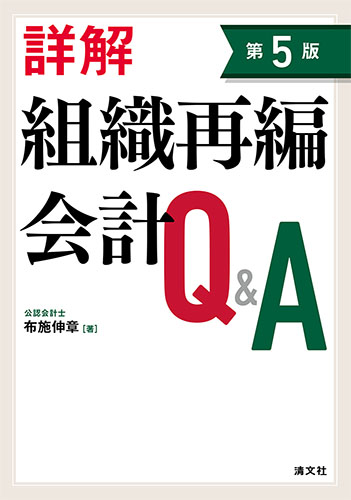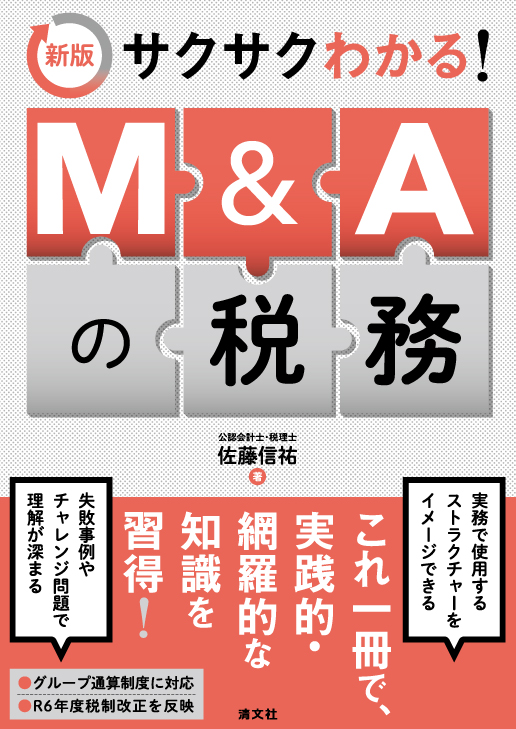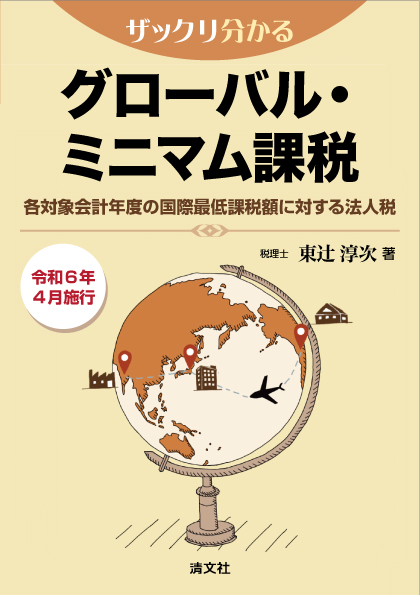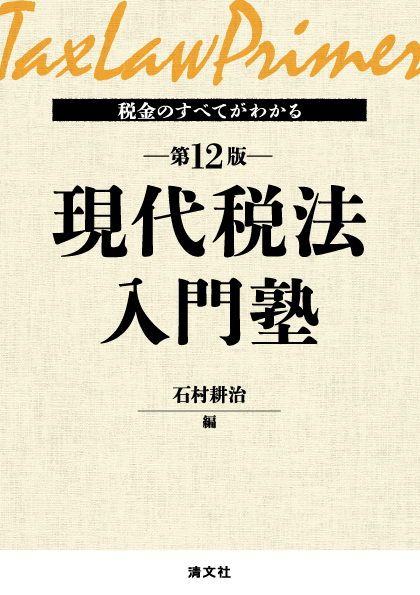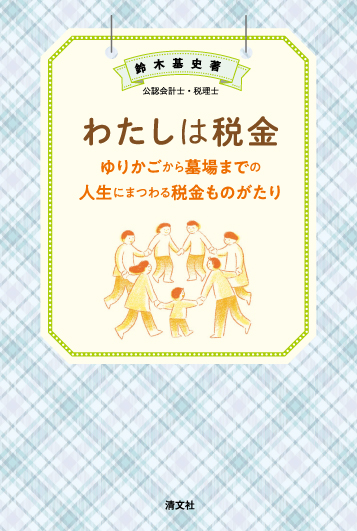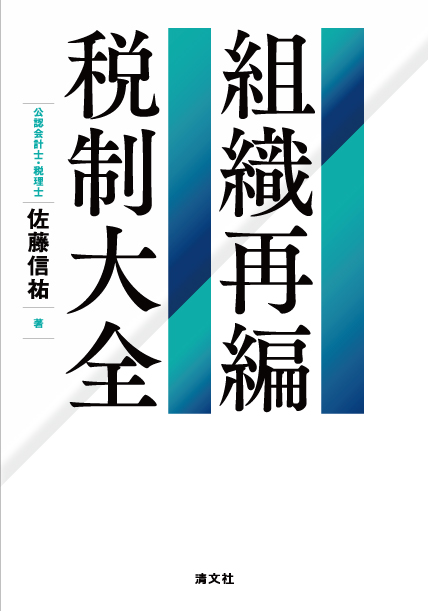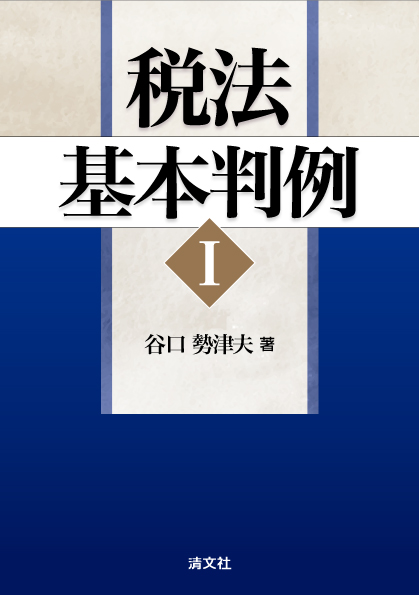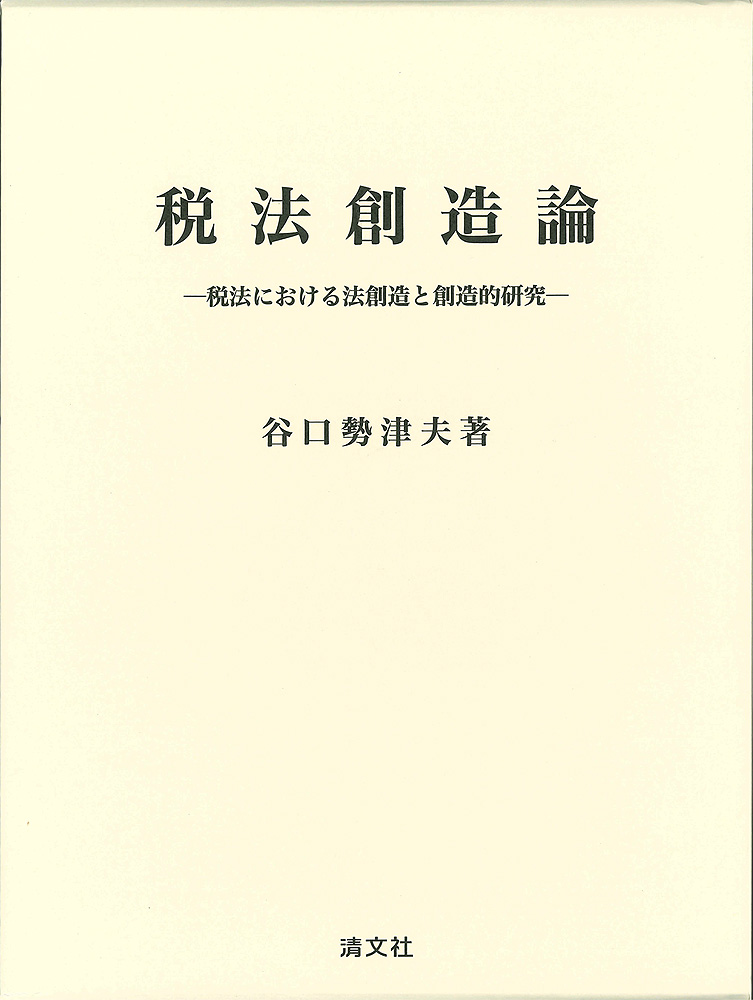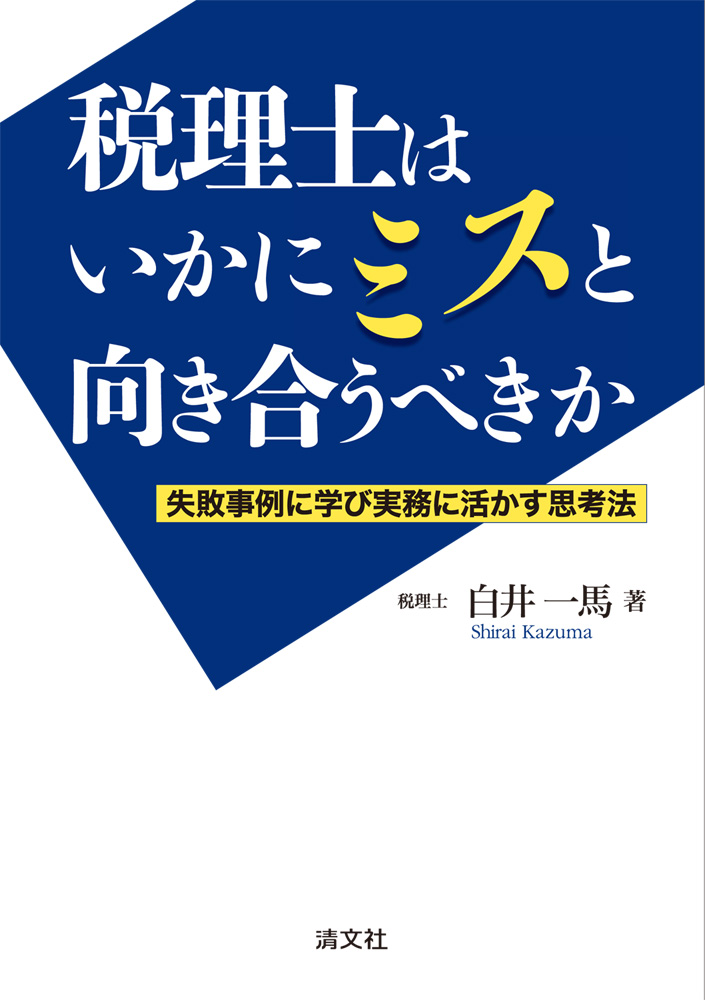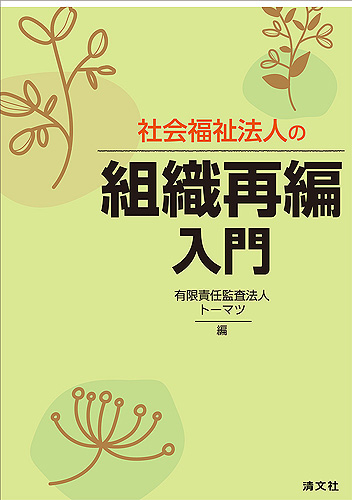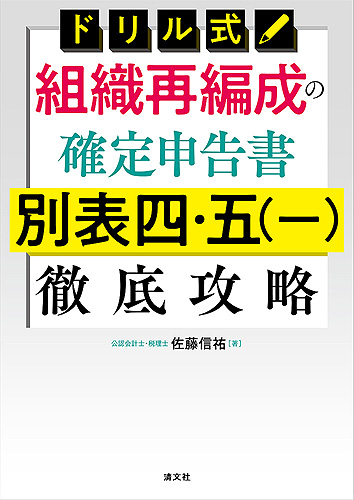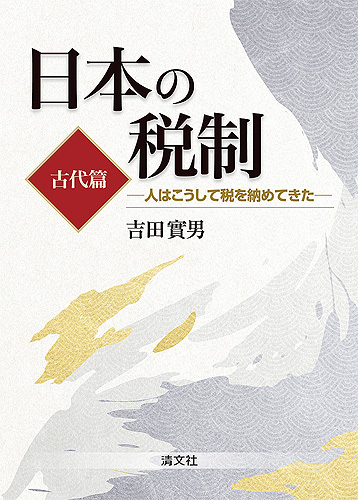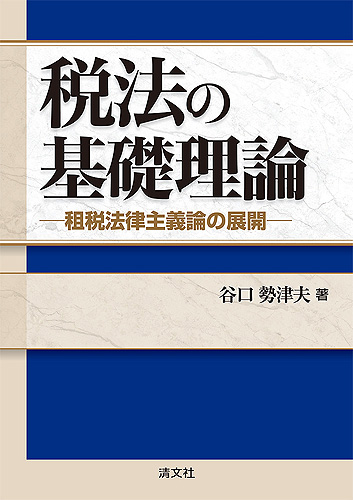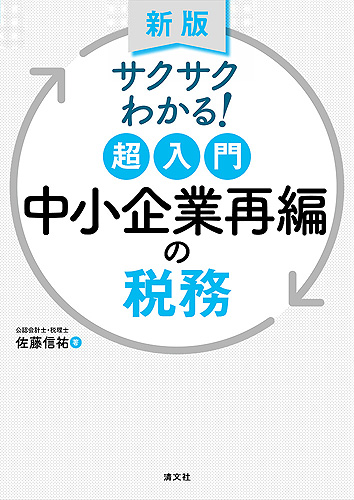組織再編税制における不確定概念
【第1回】
「不確定概念の考え方」
公認会計士 佐藤 信祐
不確定概念とは、「見込まれる」「おおむね」「これらに準ずる」といったものであり、抽象的概念、多義的概念と評されることもある。
租税法においては、このような不確定概念が多々存在しており、組織再編税制以外においても、「不相当に高額」「不適当であると認められる」「相当の理由」「必要があるとき」「正当な理由」というものも存在する。
本連載の第1回目においては、不確定概念の基本的な考え方についての解説を行う。
1 不確定概念の概要
租税法律主義については、日本国憲法84条において、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定されている。
すなわち、租税の賦課・徴収は国家権力によって行われるものであるため、国民の財産を保護するためには、恣意的に行われるものではなく、法律又は法律の定めるところによって行われなければならないという基本原則である。
また、租税法律主義の内容として、金子宏教授は『第17版 租税法』(金子宏著、弘文堂)73頁において、「課税要件法定主義」「課税要件明確主義」「合法性原則」「手続的保障原則」の4つを挙げられているが、本稿で取り上げる「不確定概念」は「課税要件明確主義」と対立する概念である。
すなわち、金子宏教授は前掲書76頁において、「不確定概念(抽象的・多義的概念)を用いることにも十分に慎重でなければならない。」としたうえで、「もっとも、法の執行に際して具体的事情を考慮し、税負担の公平を図るためには、不確定概念を用いることは、ある程度は不可避であり、また必要でもある。」と述べられている。
実務家の立場としても、上記の論述については、同意しやすいものであり、やはり租税法の解釈として、条文に沿った形で解釈を行う必要があることから、あまりに不明確な条文構成というのは、実務上の弊害が大きいと言わざるを得ない。
その一方で、条文の文言で明確化しにくいものがあるというのも理解できるものであり、その条文が適用される時代背景や環境を考えたうえで、柔軟に解釈すべき場面が存在するというのも理解できるものである。
また、山本守之氏は、『検証 税法上の不確定概念』(日本税理士会連合会編、山本守之・守之会著、中央経済社)において、不確定概念の特徴として、抽象性、社会通念、多義性の3つを挙げられており、具体的には、「不確定概念の特徴の1つは、その文言の抽象性である。抽象的であるが故に具体的事実への適用に当たっては、その具体的事実の個別諸条件が反映され多義性をもってくる。」(前掲書27頁)「たとえば、「著しく低い価額」といっても時価に比しどの程度低いものが著しいというかは、その判断者の認めるところの社会通念とも関係してこよう。そして、判断要素となる社会通念は、時と場所によって異なるものである。」(前掲書27頁)と述べられている。
すなわち、不確定概念はその抽象性が故に、複数の解釈が可能となってくるが、それは常に社会通念によるべきであり、納税者が行った取引だけでなく、事業を取り巻く環境、その時代背景などを総合的に判断する必要があると言える。
そういう意味では、答えのない分野ではあるものの、幸いにして、国税局、税務署の職員の方々と、我々、公認会計士、税理士は、同じ「会計・税務」の分野に属していることから、共通のバックグランドを有するが故の暗黙知というものが存在し、それほど大きな差異が生じることは多くない。
無論、細部における解釈の違いについては、それぞれの専門分野や経験値が異なるが故の誤解というものは存在するため、実務上は、慎重な対応が必要になってくるが、制度趣旨を正しく理解していれば、一応の判断が可能な分野であることも事実である。
組織再編税制にも、多くの不確定概念が存在する。
「見込まれる」「おおむね」「これらに準ずる」というものはその典型例であるが、その最たるものとして、法人税法第132条の2に規定する包括的租税回避防止規定が存在し、本連載の第4回目から第10回目までは包括的租税回避防止規定について解説する。
包括的租税回避防止規定については、租税回避に対応するために、「不当に減少させる」という不確定概念が設けられている。それ以外の不確定概念については、租税回避を防止するためという側面もあるが、制度趣旨に反しない限り、納税者に有利なように解釈すべき場面も存在することから、不確定概念の存在は租税回避を防ぐためだけのものとは言い難い。
例えば、第3回目でも解説するが、従業者引継要件の判定において、「おおむね百分の八十以上」と規定されているが、制度趣旨に反しないのであれば、従業者のうち100分の75を引き継いだ場合であっても、従業者引継要件を満たすものと解する余地もあるのではなかろうか。
2 不確定概念に対する実務上の対応
このように、不確定概念については、ある程度の実務家における統一見解があるものの、その性質上、実務においては、やはり専門家の間でも見解が分かれる内容があるというのもやむを得ない。納税者側に立って積極的に解釈する専門家も存在するし、リスクを防ぐために消極的(保守的)に解釈する専門家も存在する。
これは、それぞれの専門家の立ち位置であり、それを他の専門家が批評すべきものではない。
しかしながら、実務においては、クライアントに応じて、柔軟に対応する必要があるというのもまた事実である。
一般的に日本企業は保守的に解釈するクライアントが多いことから、あまり積極的に解釈する必要はないように思えるが、ほとんど問題がないような取引についても、さらにリスクを軽減するための証拠資料を作ることが求められることも少なくない。
税務調査で見られるであろう稟議書や社内検討資料を精査し、税務調査官が異なる解釈を行わないような慎重な対応というものを望むクライアントも存在すれば、コストを考えたうえで、そのような対応を望まないクライアントも存在する。
さらに、時期に応じても、柔軟に対応する必要があるというのもまた事実である。
ストラクチャーを実行する前においては、不確定概念について慎重な判断をする必要があるであろう。解釈に幅があるのであれば、なるべく否認されにくい事実関係を作っていくということもあるべき対応といえよう。
例えば、前述の従業者引継要件の判定において、たとえ、100分の75の従業者を引き継げば、「おおむね百分の八十以上」の従業者を引き継いだと解釈することができるような場面があったとしても、やはりストラクチャーの検討段階においては、100分の80以上の従業者を引き継ぐようにすべきであるし、「おおむね」と規定されていることから、100分の90の従業者を引き継いだとしても、制度趣旨に反している場合には従業者引継要件に抵触するリスクもないわけではないため、制度趣旨に反していないかどうかを慎重に検討したうえで、なるべく100分の100に近い数字に持っていくということも、実務上の対応として求められることであろう。
これに対し、ストラクチャーの実行後は、事実関係を変えることはできないことから、どうやって税務調査で勝てるのかという対応になってくる。
もちろん、勝ち目がないのであれば、税務調査が来る前に修正申告を行うべきであろうが、不確定概念の解釈によって、否認されるリスクがどれくらいあるのか、否認されないように意見書を出すことが可能であるのかどうかなどの検討を行うことになるが、あまりにも納税者に不利な解釈を採るというのは、逆に納税者にとって望ましくないことも少なくない。
さらに、税務調査の段階になってしまえば、もはや証拠資料すら作ることも難しくなってくることから、税務調査において国税当局に説明できるかどうかということになるため、若干は、積極的な解釈というものも求められるであろうが、あまりに積極的な解釈を行った場合には、税務調査における心証を害し、税務調査が長期化する恐れもあることから、積極的な解釈というものも程度問題ということもいえよう。
また、国税不服審判所、裁判所に持ち込まれた場合には、ある意味、訴訟に勝てばよいため、さらなる積極的な解釈というものも検討すべきなのかもしれない。
このように、実務においては、クライアントに応じて、また、その時期において、不確定概念に対する対応を変化させていく必要もあるであろうが、組織再編税制が導入されてから10年を超える期間が経過したことから、税務専門家の間でのある程度の統一見解というものもないわけではない。
第2回目以降においては、組織再編税制における不確定概念について検討するとともに、それぞれの解釈についての基本的な考え方と、グレーな部分についての個人的な見解について解説を行う。
なお、本連載のラインナップは、以下のようになっている。
第1回 不確定概念の考え方(本稿)
第2回 支配関係継続要件等における「見込まれていること」とは
第3回 従業者引継要件等における「おおむね」とは
第4回 包括的租税回避防止規定における「不当に」とは
第5回 みなし配当と株式譲渡損の両建て
第6回 意図的な含み損の実現
第7回 適格合併における繰越欠損金の利用①
第8回 適格合併における繰越欠損金の利用②
第9回 損失の二重利用①
第10回 損失の二重利用②
(了)
「組織再編税制における不確定概念」は、隔週の掲載となります。