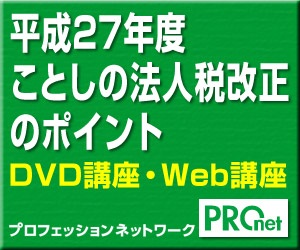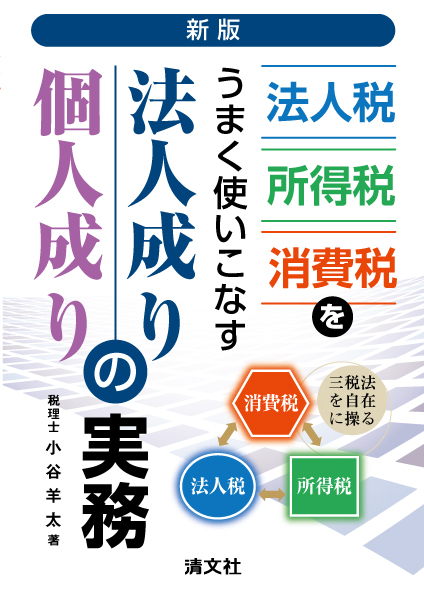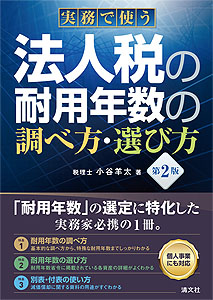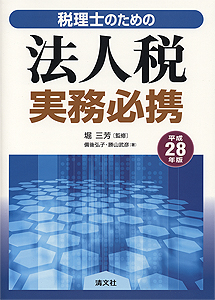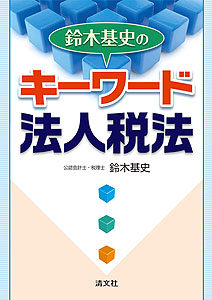法人税改革の行方
【第3回】
「受取配当の益金不算入と租税特別措置」
慶應義塾大学経済学部教授
土居 丈朗
※本連載において意見にわたる部分は、あくまで筆者の個人的見解であって、筆者が関わる組織や会議等を代表するものではない。
本連載で取り上げる今般の法人税改革における課税ベースの見直しに関して、今回は、受取配当の益金不算入と租税特別措置を取り上げる。
《受取配当の益金不算入制度~保有目的による線引きは可能か?》
まず、受取配当の益金不算入については、現行では持株割合が25%以上の株式の配当等の場合はその全額を、25%未満の場合はその50%を益金不算入としている(図1参照)。
そもそもこの仕組みは、法人間での受取配当に法人段階で益金算入すると二重課税になることに配慮して設けられた。政府税制調査会の「法人税の改革について」において、受取配当の益金不算入制度については、
企業の株式保有は、支配関係を目的とする場合と、資産運用を目的とする場合がある。支配関係を目的とする場合は、経営形態の選択や企業グループの構成に税制が影響を及ぼすことがないよう、配当収益を課税対象から外すべきである。他方、資産運用の場合は、現金、債券などによる他の資産運用手段との間で選択が歪められないよう、適切な課税が必要である。
とされた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。