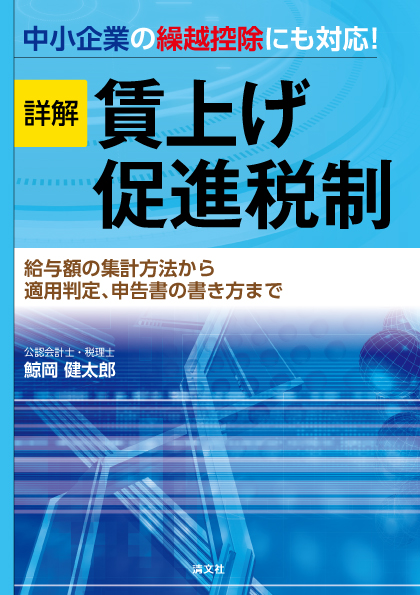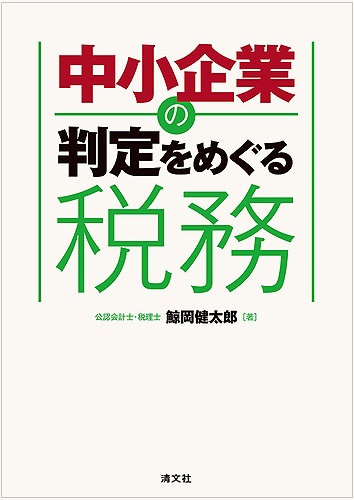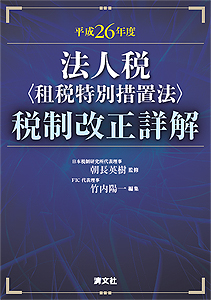雇用促進税制・
所得拡大促進税制の実務
~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~
【第1回】
「雇用促進税制の適用要件」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
最近の雇用失業情勢を概観すると、新規求人倍率、有効求人倍率、完全失業率などの指標については平成21年度から平成23年度にかけて改善がみられ、平成24年度は比較的安定している状況にあると見受けられる(『最近の雇用失業情勢(平成25年2月分)』東京都労働局)。
雇用対策は経済成長戦略上も重要な課題である。税制上の措置としても、平成23年度税制改正において「雇用促進税制」が創設され、平成25年度税制改正においては「所得拡大促進税制」が創設されたほか、「雇用促進税制」の拡充が図られている。
そこでこの連載では、雇用対策のための2つの税制である「雇用促進税制」及び「所得拡大促進税制」の実務について取り上げることとし、まずは雇用促進税制の概要及び適用要件についての解説を行う。なお、内国法人以外の法人及び連結納税に係る部分は対象外とし、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることを予め申し添える。
2 雇用促進税制の概要(平成25年度税制改正後)
青色申告法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「適用年度」という)において、雇用者を5人以上(中小企業者※においては2人以上)増加させ、かつ、雇用者増加割合が10%以上である等の一定の要件を満たす場合には、増加雇用者1名当たり20万円(平成25年4月1日以後開始事業年度については、1名当たり40万円)を法人税額から控除することができる(措法42の12)。ただし控除税額は法人税額の10%(中小企業者は20%)を限度とする。
※ここでいう「中小企業者」とは、資本金の額が1億円以下の法人のうち、以下のいずれかに該当する法人以外の法人をいう(措法42の12、措法42の4⑥、⑫五、措令27の4⑩)。
・発行済株式総数の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額が1億円を超える法人)の所有に属している法人
・発行済株式総数の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
なお中小企業者に該当するかどうかは、適用年度終了時の現況によって判定する(措通42の12-1)。
3 雇用促進税制の適用要件
青色申告法人が雇用促進税制の適用を受けるためには、以下の(1)~(5)のすべての要件を満たすことが必要である。
(1) 離職者要件(措法42の12①一)
適用年度及びその前事業年度において離職者がいないこと
離職者とは、その法人の都合により離職した雇用者及び高年齢雇用者をいう。
つまり、事業主都合による離職者がいないことが必要となる。
事業者都合による離職は、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因の「3 事業主の都合による離職」に該当するものであるが、具体的には以下のようなものが該当する。
① 事業主の都合による解雇
ただし、以下のものは該当しない。
・労働者の責めに帰すべき重大な事由によるもの
・天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによるもの
② 事業主の勧奨等による任意退職
ただし、実質的には労働者の都合による任意退職であるのに事業主が退職金等を支給するために勧奨退職の形式を取った場合は該当しない。
(2) 基準雇用者数要件(措法42の12①二イ)
基準雇用者数が5人以上(中小企業者については2人以上)であること
基準雇用者数は、適用年度終了の日における雇用者の数から、前事業年度終了の日における雇用者(適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く)の数を減算した数をいう(改正措法42の12②四)。
基準雇用者数 = 適用年度末の雇用者数 - 適用年度の前事業年度末の雇用者数
つまり、基準年度末における雇用者の数が前事業年度末に比べて5人以上(中小企業者については2人以上)増加していることが必要である。
また、「雇用者」の定義については留意が必要である。
ここでいう「雇用者」とは、法人の使用人※のうち、雇用保険の一般被保険者に該当するものをいい、高年齢雇用者(高年齢継続被保険者)は含まれない(改正措法42の12②二、三)。
このため、基準雇用者数を計算するに当たって、前事業年度末において「雇用者」であった者が当該適用年度末において「高年齢雇用者」に該当する場合には、基準雇用者数の計算から除かれることに留意が必要である。
※「法人の使用人」には、以下の者は含まれない。
・役員
・役員と特殊の関係のある以下の者
(A) 役員の親族
(B) 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(C) (A)(B)以外で役員から生計の支援を受けているもの
(D) (A)(B)と生計を一にするこれらの者の親族
・法人の使用人としての職務を有する役員(使用人兼務役員)
(3) 基準雇用者割合要件(措法42の12①二ロ)
基準雇用者割合が10%以上であること
基準雇用者割合は、基準雇用者数の適用年度開始の日の前日における雇用者の数に対する割合をいう(改正措法42の12②五)。
基準雇用者割合 = 基準雇用者数 ÷ 適用事業年度の前事業年度末の雇用者数
つまり、適用年度における雇用者数の増加割合が10%以上であることが必要である。
なお、適用年度の前事業年度末の雇用者数がゼロである場合には、基準雇用者割合要件については考慮不要である(措法42の12①二)。
(4) 給与等支給額増加要件(措法42の12①二ハ)
給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
① 給与等支給額
給与等支給額は、法人の給与等の支給額のうち、適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額をいう(改正措法42の12②七)。
ここでいう「給与等」とは、所得税法28条1項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る)をいう(改正措法42の12②六)。具体的には、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与をいう(所法28①)。
給与等の支給額については、その給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額※がある場合には、その金額を控除した金額とし、高年齢雇用者に係るものを除く点に留意が必要である。
※「他の者から支払いを受ける金額」とは、例えば次に掲げる金額が含まれる(措通42の12-2)。
・雇用保険法施行規則110条に規定する特定就職困難者雇用開発助成金、雇用対策法施行規則6条の2に規定する特定求職者雇用開発助成金など、労働者の雇入れ人数に応じて国等から支給を受けた助成金の額
・法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(出向者)に対する給与を出向元法人が支給することとしているときに、出向元法人が出向先法人から支払いを受けた給与負担金の額(出向先法人の負担すべき給与に相当する金額に限る)
② 比較給与等支給額
比較給与等支給額は、以下のように計算される(改正措法42の12②八)。
比較給与等支給額 = (A÷B)+(A÷B×C×30%)
A 適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度における給与等支給額
・・・適用前事業年度の月数が適用年度の月数と異なる場合には、月数按分による調整を行う
⇒ 調整後のA=
調整前のA×適用年度の月数
÷適用前事業年度の月数
B 適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の数
・・・適用前事業年度の月数が12ヶ月であれば、Bは必ず1になる。
C 基準雇用者割合
・・・適用年度の前事業年度末における雇用者数がゼロである場合には、Cは考慮不要である
⇒ A÷B×30%となる
雇用者数が増加しても、給与等支給額が増加しなければ雇用環境がむしろ悪化することとなり、雇用対策としての税制措置の恩典を与えることは適当でないという価値判断が含まれているものと考えられる。
そこで、税制措置の恩典を与えるというメルクマールとして、雇用者数の増加割合の3割程度の給与支給額の増加額(比較給与等支給額)を設定しているものと考えられる。
例えば、適用年度前事業年度(12ヶ月)の給与等支給額を3,000万円、基準雇用者割合を15%とした場合の比較給与等支給額は、
3,000万円÷1+(3,000万円÷1×15%×30%)=3,135万円
となる。
(5) 適用事業要件(措法42の12①本文)
雇用保険法5条1項に規定する適用事業(政令で定める事業を除く)を行っていること
雇用保険法5条1項では、「労働者が雇用される事業を適用事業とする」と広く一般的に定めているが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項に規定する風俗営業又は同条5項に規定する性風俗関連特殊営業を適用事業から除くこととされている(措令27の12③)。
つまり、風俗営業又は性風俗関連特殊営業以外の事業を行っていることが必要である。
4 適用手続
この制度の適用を受けるためには、適用事業年度開始後2ヶ月以内に、主たる事業所を所轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用促進計画」の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で上記の(1)~(3)までの要件について確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要がある(措法42の12①、措令27の12①②、措規20の7①)。
次回は、それぞれの適用手続について詳細に確認していくこととする。
・措法・・・租税特別措置法
・措令・・・租税特別措置法施行令
・措規 ・・・租税特別措置法施行規則
(例) 措法42の12①二イ・・・租税特別措置法42条の12第1項2号イ
(了)
「雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務」は、隔週での掲載となります。