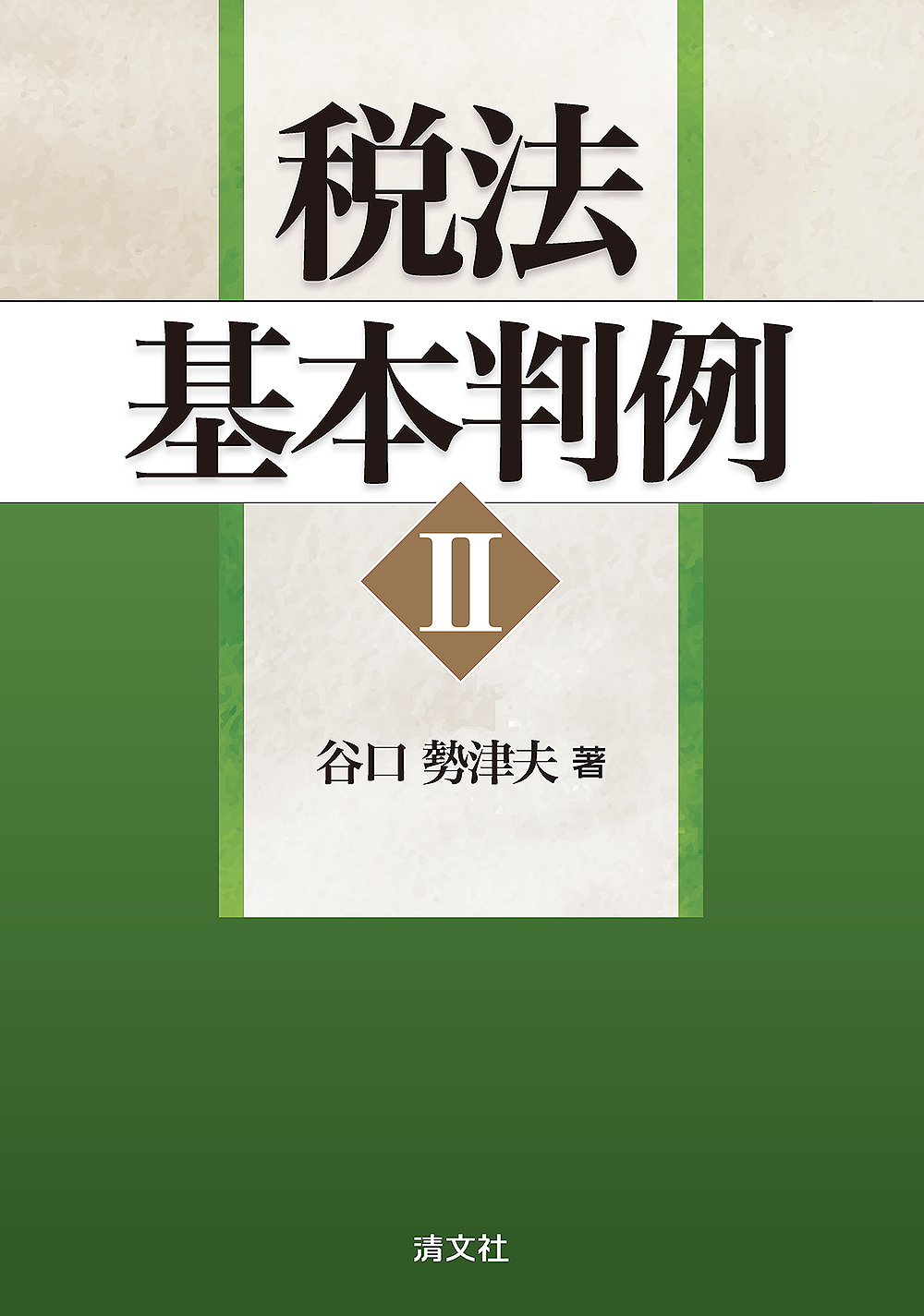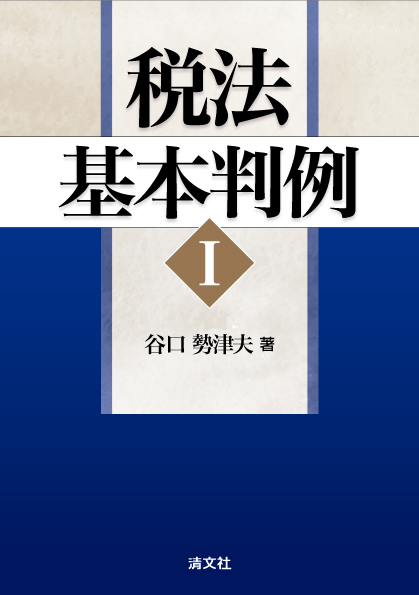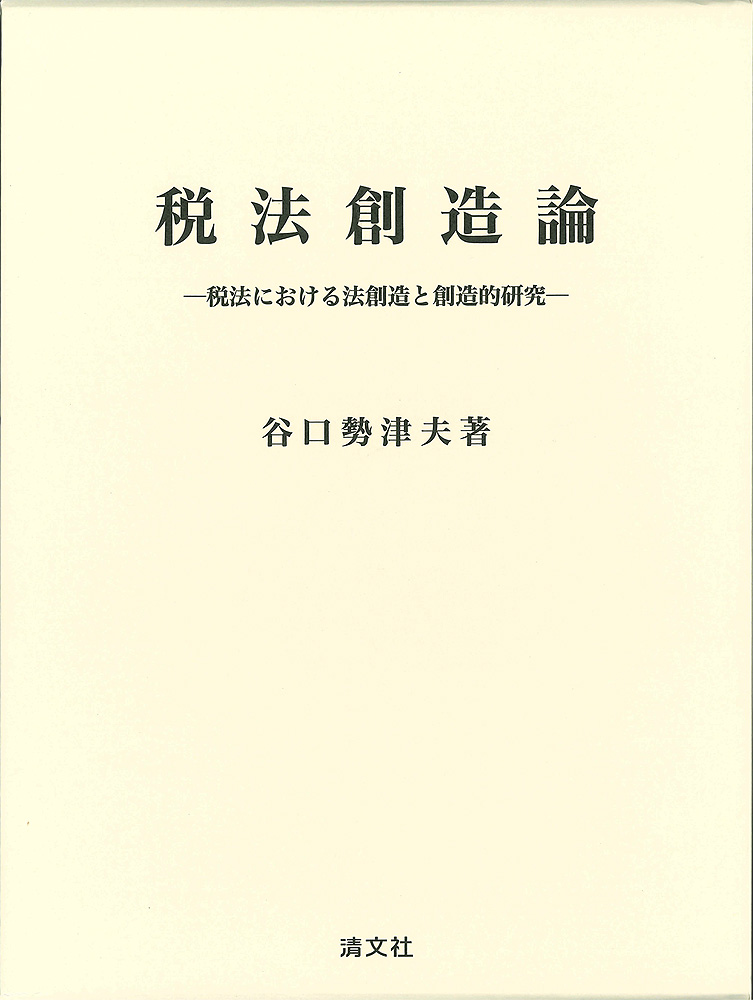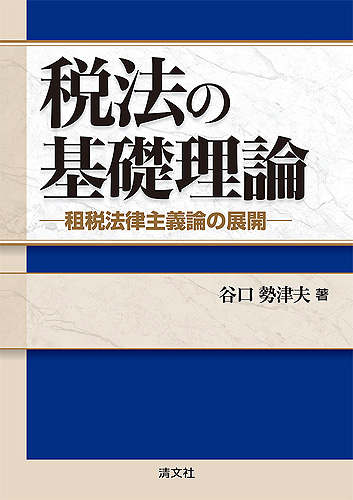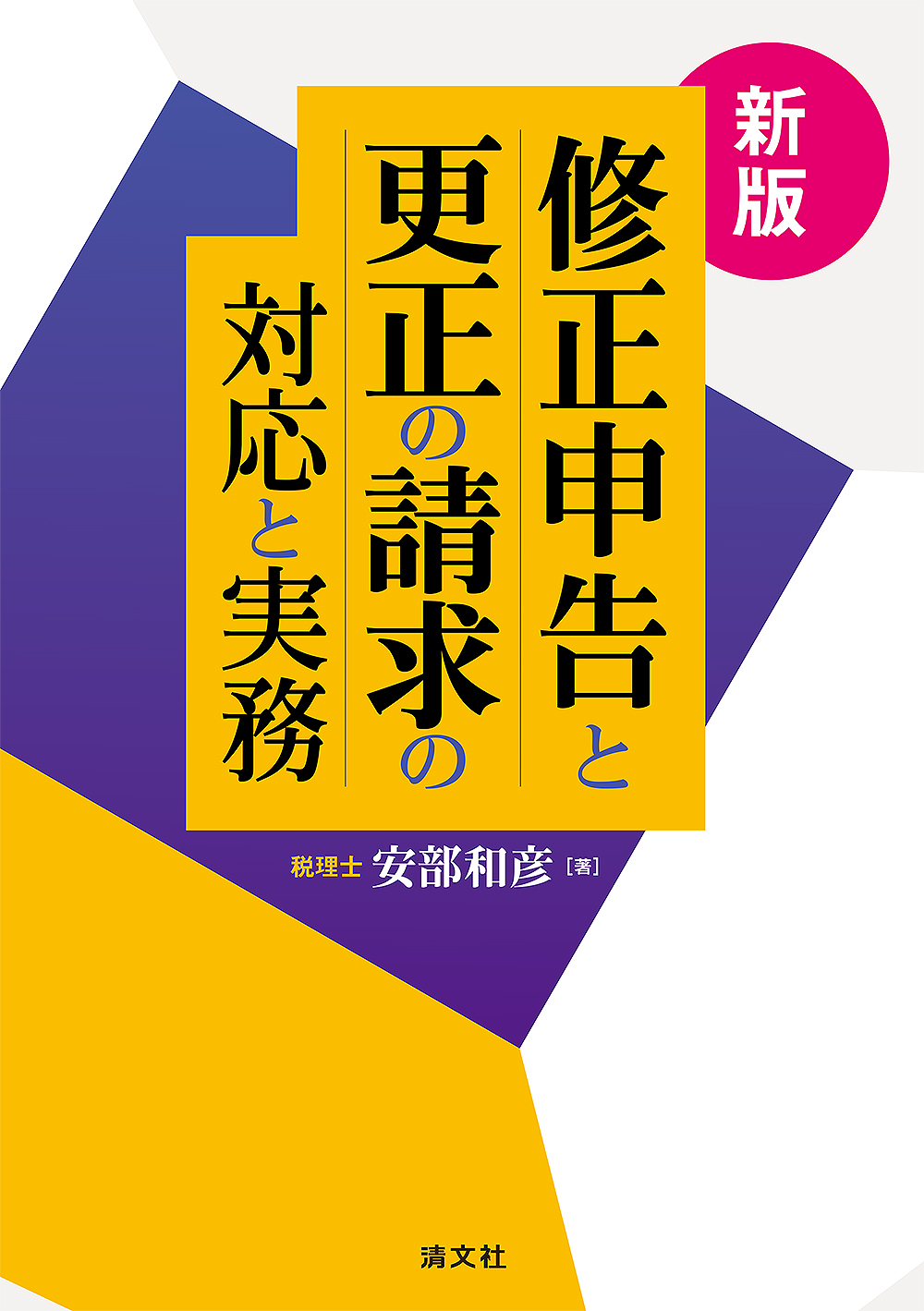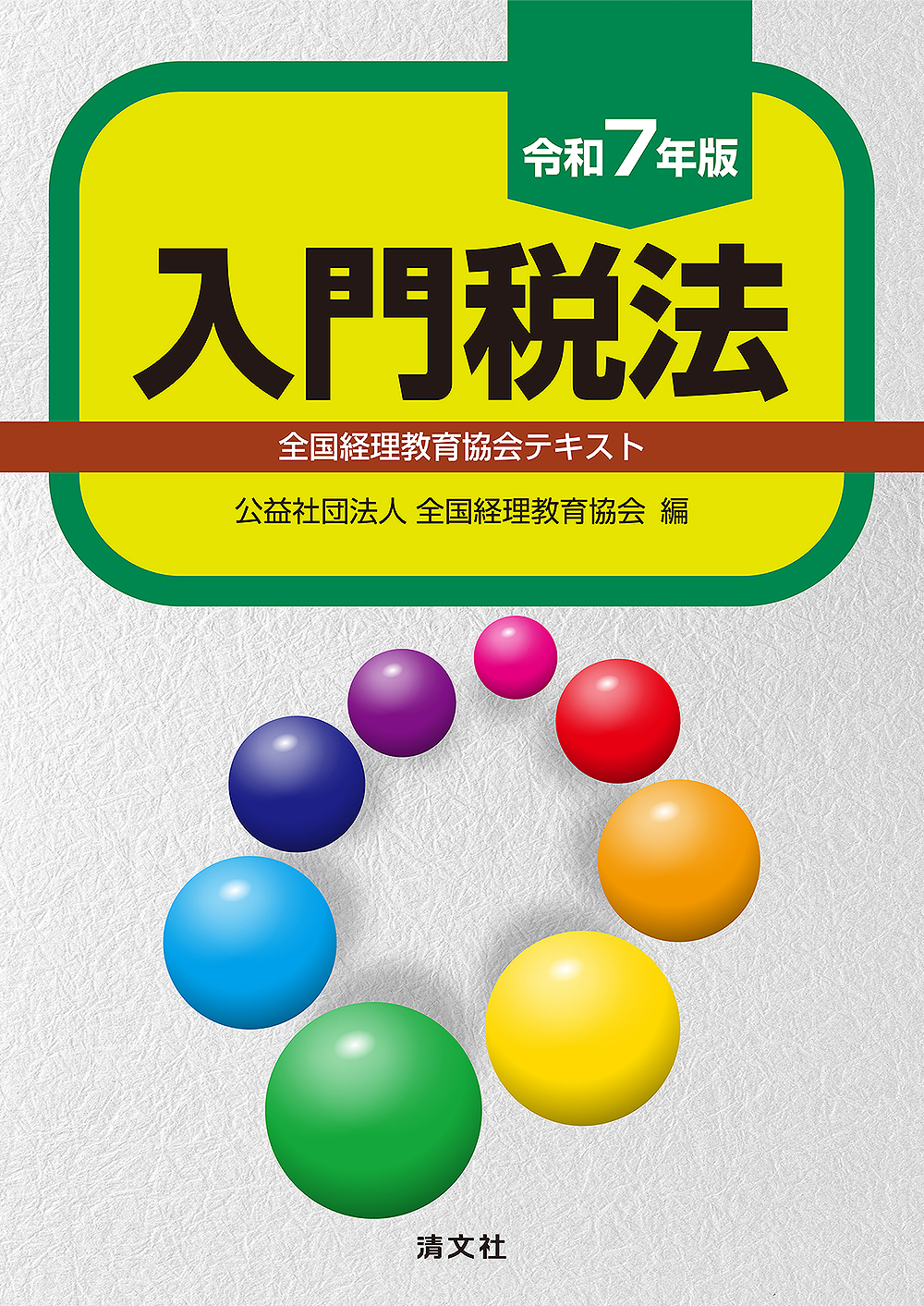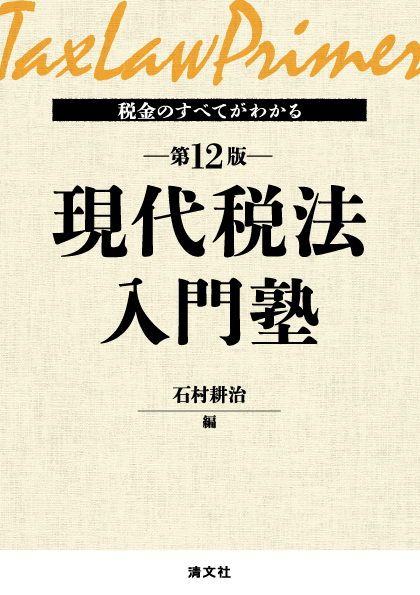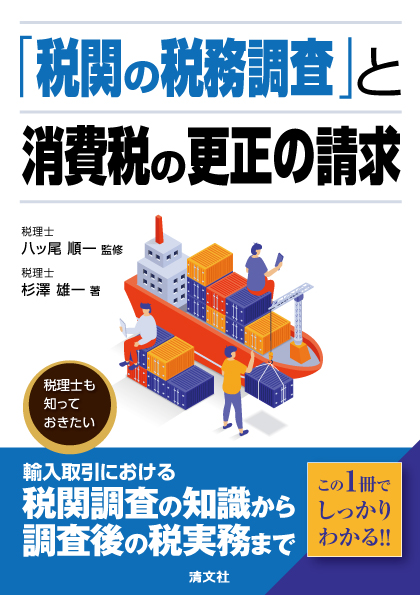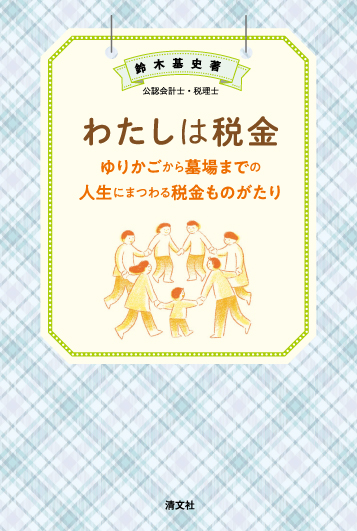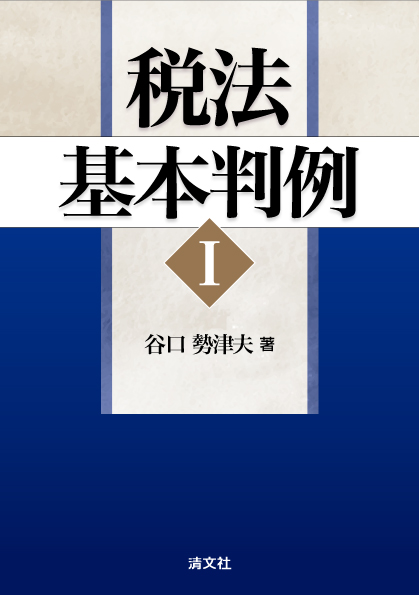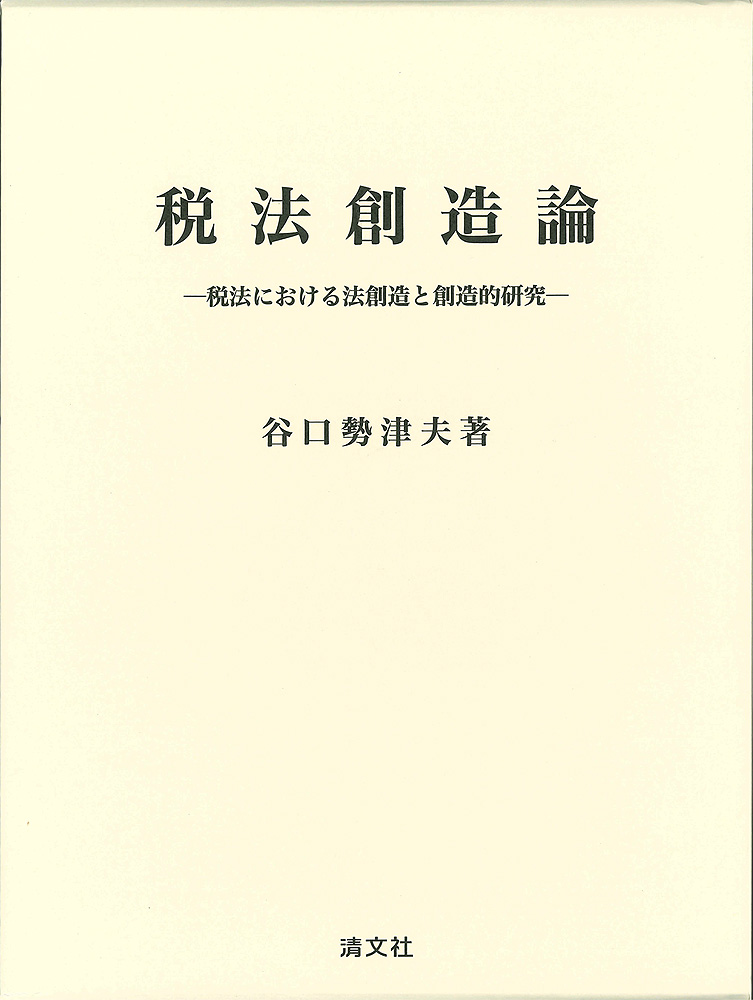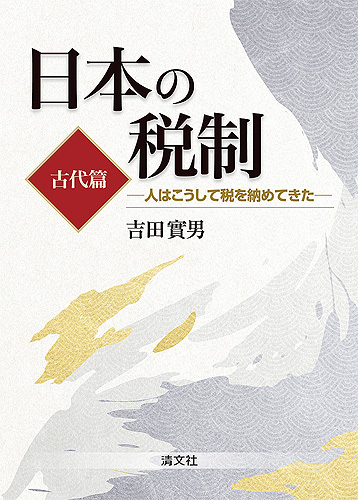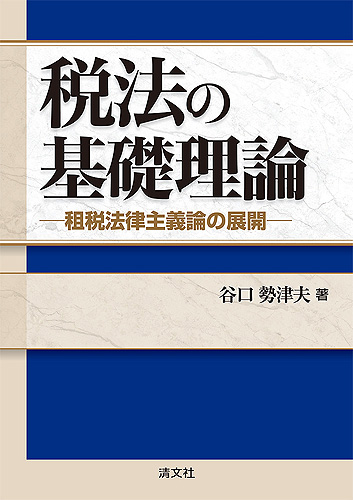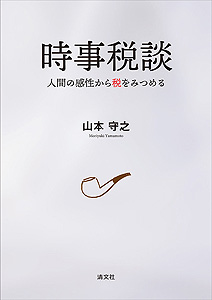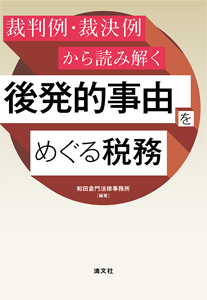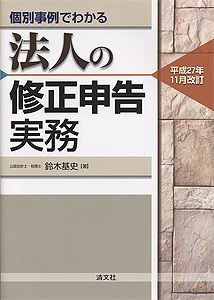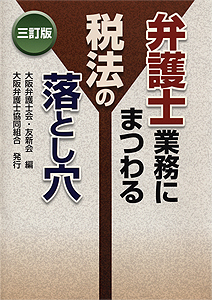谷口教授と学ぶ
国税通則法の構造と手続
【第27回】
「国税通則法第7章の2」
-質問検査総説-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
1 第7章の2の条文構成
国税通則法第7章の2は、以下の各規定によって構成されている。以下では条名とその見出しのみを記しておく。
①第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
②第74条の3(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)
③第74条の4(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)
④第74条の5(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
⑤第74条の6(当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)
⑥第74条の7(提出物件の留置き)
⑦第74条の7の2(特定事業者等への報告の求め)
⑧第74条の8(権限の解釈)
⑨第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)
⑩第74条の10(事前通知を要しない場合)
⑪第74条の11(調査の終了の際の手続)
⑫第74条の12(当該職員の事業者等への協力要請)
⑬第74条の13(身分証明書の携帯等)
⑭第74条の13の2(預貯金者等情報の管理)
⑮第74条の13の3(口座管理機関の加入者情報の管理)
⑯第74条の13の4(振替機関の加入者情報の管理等)
2 第7章の2の沿革と評価
国税通則法第7章の2は平成23年度[11月]税制改正における同法の改正によって創設されたが、その創設は、「昭和36年の国税通則法制定に関する答申では、質問検査権を統一的に同法に盛り込むべきとしたが、質問検査の内容や態様がかなり相違するとして見送られた経緯がある。」(日本弁護士会連合会日弁連税制委員会編『国税通則法コンメンタール 税務調査手続編』(日本法令・2023年)148頁[舘彰男執筆])といわれる、税制調査会「国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)」(昭和36年7月)の答申内容の単なる「復活」ではない。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。