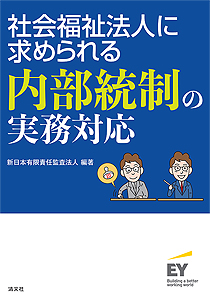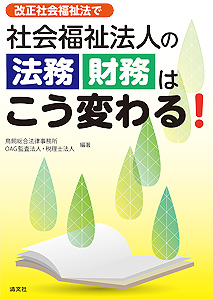[子会社不祥事を未然に防ぐ]
グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ
【第1回】
「子会社不祥事が親会社・親会社役員にもたらすインパクト」
~場合によっては親会社の屋台骨をゆらがしかねない子会社の不祥事~
弁護士 遠藤 元一
1 後を絶たない会計不祥事
本年9月、東芝は、2度の有価証券報告書等の提出の延期を経て「不適切な会計処理」(不正会計・粉飾)を行っていたとして過年度決算訂正等を行った。
【参考】 東芝ホームページ
- 「過年度決算の修正、2014年度決算の概要及び第176期有価証券報告書の提出並びに再発防止策の骨子についてのお知らせ」(2015年9月7日)(PDFファイル)
2011年に資本市場の信頼性を損なうような大規模な会計不祥事・経営者不正が起きたことを契機に、監査基準の改定および監査基準の特別基準として「監査における不正リスク対応基準」が導入され、会社法でも企業統治のための制度改正が行われる等、多方面で公正な資本市場の維持のための努力が続けられている最中、企業統治の優等生としてトップランナーと考えられていた東芝が長期にわたり粉飾を行っていたことが市場関係者に衝撃を与えたことは想像に難くない。
もっとも、東京商工リサーチの調査によると、会計不祥事により過年度決算に影響がでた、あるいは今後、影響がでる可能性があることを開示した上場企業は2012年度(2012年4月1日~2013年3月31日)が26件、2013年度が38件、2014年度が42社となっている。
つまり、上記の事例ほどの大掛かりなものではなくても、上場企業において会計不祥事が間断なく発生している。これらの中には、資本市場の信頼性を担保する目的で適正な企業情報を開示するために会計・監査に関する制度・基準が厳格化され、四半期報告の義務化や会計情報の見積的な要素の増加に伴い、会計基準の選択や見積・評価の誤謬等が原因となって生じた事例も多いが、意図的・故意による粉飾事案も少なくない。
2 会計不祥事が及ぼす企業危機
粉飾決算は、一般に公正妥当と認められる会計基準に反する手続により利益を計上する会計行為である。不正・違法な会計操作の積み重ねは、雪だるま式に飛躍的に大きくなり、財務諸表に対し、定量的ではなく、定性的な影響を及ぼし、当初は、アリの一穴と思われていたものであっても、堤防が崩れ、企業の存亡を左右する大災害を及ぼす。
いったん、会計不祥事が発覚すると、その企業は資本市場での信認が著しく毀損される。その信認を回復するため、企業は第三者委員会を設置して調査を行い、事案の解明、原因分析、役職員の責任の明確化等を内容とした調査報告書が市場に公表され、調査報告書の内容に基づき過年度決算訂正が行われる。
市場規制当局も、証券取引等監視委員会による開示調査・特別調査、勧告を経て金融庁による課徴金納付命令の発出がなされ、特に悪質な場合は検察庁に対して刑事告発され、検察庁による強制捜査が行われることもある。また、金融商品取引所からも、逐次、状況の報告を求められ、改善報告書の提出を求められる等の対応を求められ、上場違約金等の措置のほか、特設市場注意銘柄に指定されたり、悪質な場合には市場からの退出(上場廃止)に至るケースもないではない。
さらに、株主等から、役員が任務を十分に果たさなかった(善管注意義務違反)ために、分配可能限度を超えた金員を支払い、第三者委員会の設置・調査費用や、決算訂正(過去の決算期に遡って訂正する場合もある)に費用を支払うなどの損害を被ったとして役員の対会社責任が追及され、あるいは株価の下落により損害を被ったとして会社法・金融商品取引法上の損害賠償を請求されるなどの事態も発展する。
3 子会社における会計不祥事
ところで、会計不祥事事案の中で、子会社・関係会社が舞台となった事案が2013年度で12件(31・5%)、2014年度で16件(38%)と、本社以外で会計不祥事が行われた事案が目につくが、子会社で生じた会計不祥事は、親会社にどのような影響を与えるだろうか。
現代の企業経営では、国際的に事業展開している大規模なグローバル企業だけでなく、中小企業でも、子会社・関係会社(以下「子会社等」という)から構成されるグループ経営が広く浸透している。
法的観点からは、親会社は、子会社等を通じて事業を行う場合、親会社自らが事業を行う場合に比べてコストを減少させ(親会社が自ら行う場合に負担しなければならない、事業部門に配賦される管理費等の間接費用をコストセーブできる)、子会社等の自律的・独立的な経営に委ねることにより法域や業態を超えて、事業を機動的・効率的に多角化できる点にグループ経営の意義があるが、会計面でも、単体ではなく、連結経営での企業業績評価である連結会計が基軸になっており、株主、投資家・資本市場も、単体ではなく、連結ベースでの企業業績の評価が重視され、企業価値も連結ベースでの評価が通例となっている。
子会社等において会計不祥事が発生すると、連結会計の下では、グループ会社の頂点にある親会社に与える影響は、親会社自身で生じた会計不祥事と質的に差異はない。子会社等の会計不祥事が決算に重要な虚偽記載等と認められる程度に至る場合は、親会社の決算に重要な虚偽をもたらし、親会社の企業価値を毀損し、親会社の屋台骨をゆるがすという深刻な事態にも発展しかねない。
JVCケンウッドは、2010年3月、子会社であるビクターの欧州販売会社で営業関係経費の先送り等の会計不正が発覚し統合初年度の2009年3月の連結業績の営業損益を黒字から赤字に修正し、2010年3月期の業績の最終損益の赤字も拡大したほか、取引金融機関と締結した契約に定める「財務上の特約」(財務制限条項)に抵触し、決算短信に「継続企業の前提に疑義」がある旨の注記がなされた。
【参考】 JVCケンウッドグループ ホームページ
- 「当社および日本ビクターにおける過年度決算の訂正および再発防止策の策定、ならびに平成22年3月期第3四半期の四半期報告書の提出に関するお知らせ」(2010年3月12日)(PDFファイル)
- 「平成22年3月期 決算短信」(2010年5月14日)(PDFファイル)
また、LIXILグループは、本年6月、2014年に買収した中国の子会社が在庫の過大評価、巨額な簿外債務が判明した後、債務超過を理由に破産したことで、連結純利益を大幅に下方修正する事態に追い込まれたこと等の例がみられる。
【参考】 株式会社LIXILグループ ホームページ
- 「過年度に係る有価証券報告書等及び決算短信の訂正に関するお知らせ 」 (2015年6月8日)(PDFファイル)
- 「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」 (2015年6月29日)(PDFファイル)
このように、親会社は、親会社自らにおいて会計不祥事が生じた場合と同様の対応が求められるほか、子会社管理責任が問われる事態も生じ得る。
今回は会計不祥事の事案を取り上げたが、グループ会社の事業・ビジネスには、事業リスク、信用リスク、為替リスク、従業員不祥事やインシデント等、企業価値を左右する様々な事故・事件等が生起する。
グループ会社を統率する親会社にとって、単体のみならず連結の企業業績を重視し、グループ企業全体の企業価値の向上を図るため、どのようなグループ企業管理の基本方針を構築し運用するかが喫緊の課題であることは疑いがないことである。
本連載では、公認会計士の松藤斉先生、公認会計士・公認不正検査士の松澤公貴先生と、弁護士の筆者とがそれぞれの専門的知見の立場から、この課題に関連したテーマを取り扱っていく予定である。しばらく、お付き合いいただきたい。
(了)
「グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ」は、隔週で掲載されます。