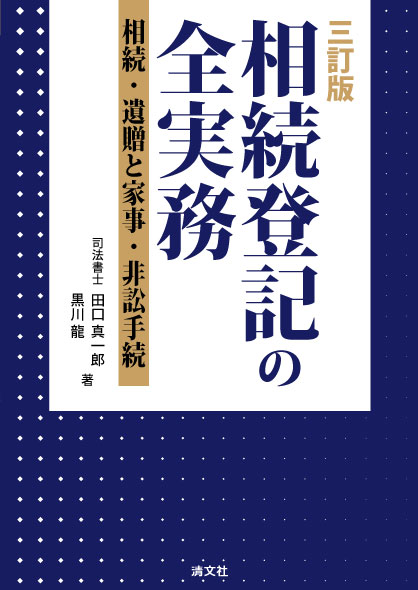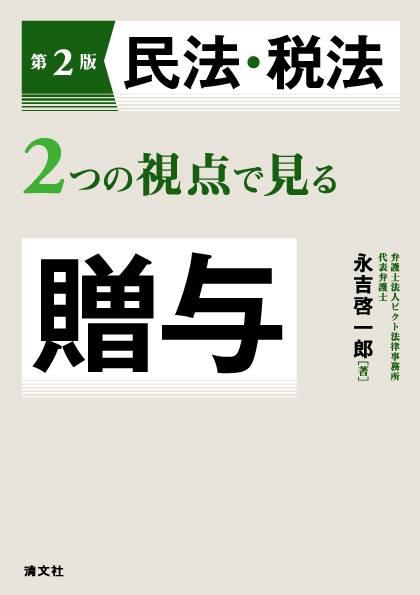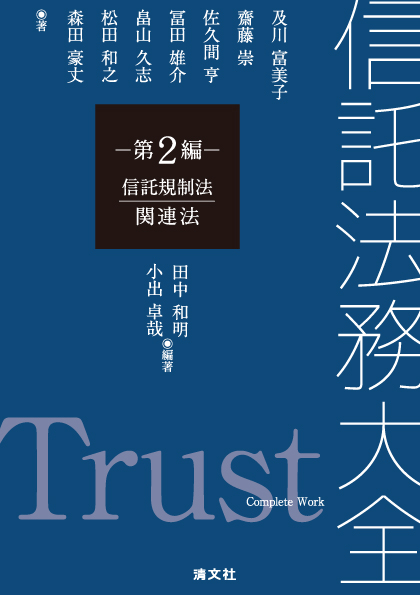税理士が知っておきたい
[認知症]と相続問題
【第4回】
「認知症診断の医学的手順」
クレド法律事務所
駒澤大学法科大学院非常勤講師
弁護士 栗田 祐太郎
1 認知症診断の一般的手順
―「認知症疾患治療ガイドライン」の存在
ある人の判断能力に問題がありそうだ、という疑いが生じた場合、「判断能力が減弱していること」や、ひいては「認知症を発症していること」の判断はどのようにして行うのか。
今回は、この点に関して医学的観点を踏まえて解説したい。
【第2回】で説明したように、ひとくちに認知症といっても、その原因となる疾患は多種多様である。原因疾患が異なれば発生する症状も異なるし、その治療方法も変わってくる。
また、そもそも(狭義の)認知症には該当しないような疾患によっても、認知症と同様の認知機能の低下・障害が発生する場合がある。
そのため、認知症の疑いがある患者の診断手順については、日本神経学会が「認知症疾患治療ガイドライン」を作成し、公開している。
同ガイドラインに基づく一般的な診断手順について、以下、概略を説明する。
2 第1ステップ:認知症であるか否かを診断する
診断手順においては、まず、認知症と誤りやすい「うつ状態」や「せん妄」を除外する必要がある。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。