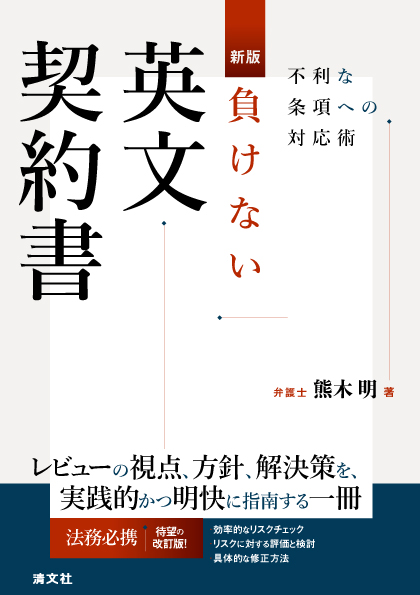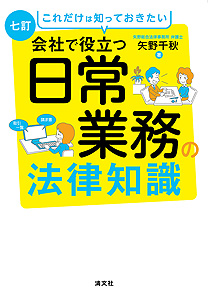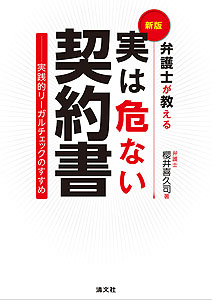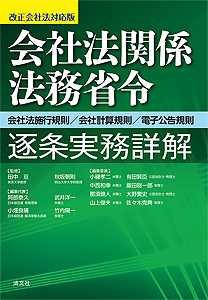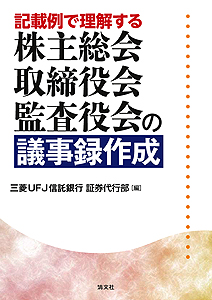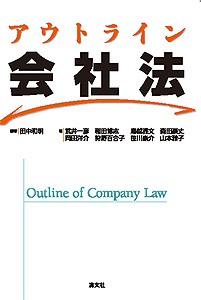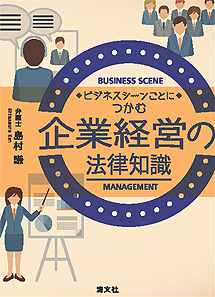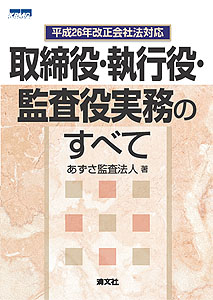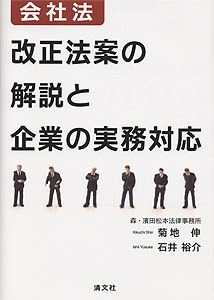常識としてのビジネス法律
【第1回】
「ビジネスと文書(その1)」
弁護士 矢野 千秋
1 ビジネスにはなぜ文書が必要か
ビジネスには文書が必要とされる場合が多く、そのうち権利義務に関するものや、それを証明するものを「法律文書」と呼ぶ。
その代表例は、営業関係でいえば、領収証、請求書、注文書、注文請書、催告書、報告書、契約書、委任状などであるが、その形式について、どのように作るべきかなどの法律上の制約は、原則として存在しない。
これは、もともと私的自治の原則(私法上の大原則)とそれから派生する契約自由の原則(締結の自由、相手方選択の自由、内容決定の自由、方式の自由。この4つの自由が含まれている)に由来する。
「私的自治の原則」とは、簡単に言うと、他人に迷惑をかけない限り私人間のことは自由である、官は余計な規制をしない、という意味であり、歴史上、人民が国家権力から勝ち取ってきたものである。
したがって、方式も内容も規制がなく、書面にするかしないか、どのような内容を盛り込むかも自由なのであるが、実務上は重要なものであれば書面化が望ましいし、内容的にも、最小限「いつ」「誰が」「どのような内容を」「誰宛に」(4W)書いたかを明らかにすることが必要である。
上記のように方式に法律上の制約がないのであれば、文書を作っても作らなくてもよいはずなのに、なぜ文書を作成することが望ましいのか。
それは以下のメリットがあるからである。
① 内容の明確性を担保する(すなわち、誤解、思い違い、忘却等を防ぐ)
書面化することによってお互いの意思を再確認できるし、内容が複雑な場合に忘却等を防ぐことができる。
このメリットを考えれば、担当者の記憶だけに任せておくようなことでは確実な回収は望めないことが明らかであろう。
また内容の明確性は、次の②の前提ともなっている。
② 後日の証拠となる(すなわち、紛争となった場合に、水掛け論を防止し、裁判上の強力な証拠となる)
裁判上の証拠としては、書面のみならず証人の証言も法律上は均しく証拠として同じ扱いなのであるが、人証(証人の証言)と書証(書面による証拠)には実務上証明力の違いがあり、一般に書証の方が強力である。
その理由は、利害が絡むと人間は嘘をつくこともあるので、いきおい裁判官は書証に重きを置くことになるからである。
以上より、たとえ訴訟になった場合にも、勝訴判決が取れる可能性が高い。ということは、相手方は訴訟で争っても敗訴の可能性が高いわけであるから、手間ヒマをかけても無駄になり、それなら争わずに履行することにもつながる。
すなわち、紛争の抑止力にもなるのである。
2 作成が望ましい文書
私的自治の原則から、原則として法律上文書作成が義務づけられているものは少ない。
以下、法律上文書作成が義務づけられているわけではないが、後日の証拠とする意味で作成しておくことが望ましい文書について説明する。
内容としては最小限、前述の4Wは落さないようにする。なお、契約書については稿を改めて説明する。
3 「領収証」の記載ポイント
金銭を支払ったときには領収証を請求できる。これは「相手方が領収証を出さないときには支払いを拒否できる」ということである。
そして領収証の証明力を担保するためには、以下の事項の記載が最少限必要である。
① 領収金額
できるだけタイプ等で印刷したものが望ましい。手書きの場合は算用数字のみならず、漢数字を併記する方がベターである。
もちろん手書きの算用数字は変造が容易だからである。
算用数字は3桁ごとにコンマを入れ、冒頭に¥、末尾にピリオド(.)及びハイフン(-)を記載して終了を示す。
漢数字は冒頭に「金」、末尾に「円也」で終了を示すべきである。
金額の訂正は好ましくない。
できれば金額を誤った領収証は破棄し、新しい領収証用紙を用いるべきである。
どうしても訂正が必要な場合は訂正すべき金額欄全体を2本線で消し、その真上に新しい金額を記載して領収証作成に使用した印章を訂正箇所の上から押捺する。
② 領収文言(領収金額と合わせてWHAT)
金額欄の下に、「上記金額を領収致しました。」との文言を入れるべきである。
通常表題に「領収証」と記載するから、表題のもつ補充的効力から一定金額を領収したものであることが推測できるが、文書作成のメリットの1つが「内容の明確性の担保」にあることから、補充的効力に頼るのは望ましいことではない。
③ 領収年月日(WHEN)
実際に金銭を領収した日を入れるべきである。
実際の日と異なった日を入れると、相手方の帳簿の日付などと相違した場合に領収証自体の信憑性が問われることにもなりかねない。
また、担当者に金銭の受領権限があったか否かなども、一応この記載された日が基準となって判断されるからである。
④ 領収者の記名・捺印(WHO)
領収者の署名(自署)でも構わないのだが、通常取引では記名、すなわち印刷かゴム印が良い。
これは、取引では記名が用いられることが一般的だからである。
捺印は受領担当者のものになることが多い。したがって、真実その者に受領権限があるかどうかに注意する。
(注)署名と記名の違い
「署名」とは一般的には自署、すなわち自己の名称を手書きすることをいい(狭義の署名)、「記名」とはゴム印、PC、印刷等それ以外のすべての方法で名称を表すことをいう。
ただし、署名は広義では記名捺印を含んだ意味で用いられることもあるが、これは法律(例えば手形法82条)や当事者などが特に明記した場合に限られる。
⑤ 宛名(支払った者。会社間取引では会社名になる)(WHOM)
できるだけ「上様」はやめる。
支払いをした会社名を完全に記載して交付すべきである。
「上様」は税務署が偽造を疑う場合の一つであり、取引先に迷惑をかけることにもなる。
⑥ 「領収したのが何の代金か」も記載した方が望ましい(望ましいもう1WのWHY)
単発的な取引においても金銭を受け取った原因、理由は書くべきであるし、また文書化のメリットから考えて、多数取引があるときや、継続取引などでは、個々の請求権との対応関係を明らかにするために必須ともいえる。
⑦ 領収金額に応じた収入印紙の貼付
3万円未満は非課税、3万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円等となる(くわしくは「印紙税額一覧表」17号文書を参照のこと)。
消費税額は必ず別記載する。
【例:525万円(消費税額25万円を含む)等】
この場合、記載金額は500万円となり、印紙税額は1,000円である。合計額525万円だけを書いていると合計額が記載金額となり、印紙税額は2,000円となる。
金銭を領収したもの、すなわち領収証作成者が印紙代を負担する。
なお、消印は領収者が領収証作成に用いた印章を用いて消すのが無難である。
ボールペンでのバツ(×)印などでは、税務署は消印と認めない。
⑧ 領収証用紙など
市販の領収証用紙などを用いるのは好ましくない。
領収者の属する会社特有のものを使用すべきである。
市販の領収証用紙などは、やはり税務署が脱税を疑う場合の一つだからである。
それ以外にも、日付、領収者の住所・電話番号などが入っていないもの、捺印に三文判が用いられているもの、金額が妙に丸いもの(10万円などのようにキリのいい数字)なども疑惑を持たれやすい。
* * *
次回も引き続き「作成が望ましい文書」のうち、「請求書」「注文書」などの記載上の留意点について紹介する。
(了)
「常識としてのビジネス法律」は、毎月第1週・3週の掲載となります。