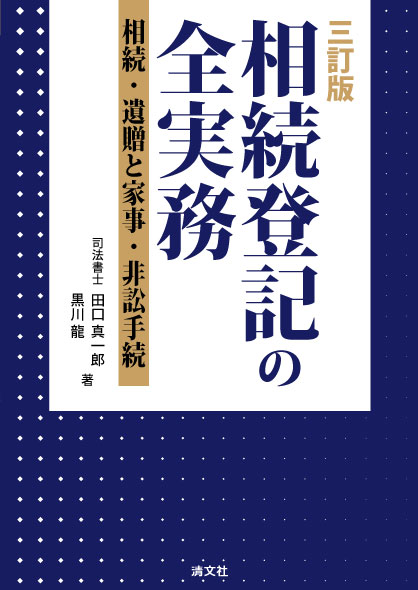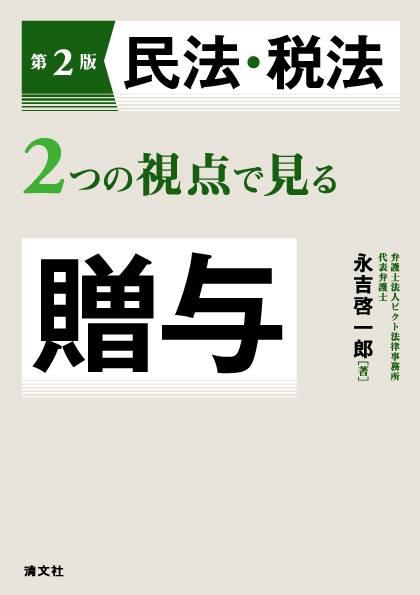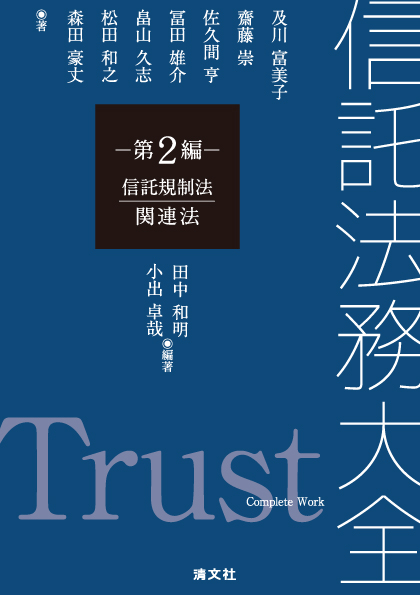税理士が知っておきたい
[認知症]と相続問題
【第3回】
「『判断能力』・『意思能力』とは?」
-その具体的な意味内容-
クレド法律事務所
駒澤大学法科大学院非常勤講師
弁護士 栗田 祐太郎
【第2回】では、認知症の進行により記憶や判断能力等に深刻な問題が生じることを説明した。
ここでも示されているように、「認知症により判断能力を失っている」というような言い方がよくなされるが、ではこの「判断能力」とは、法律学的にはどのように位置づけられ、具体的にはどの程度の能力を意味する概念なのであろうか。
今回はこの点につき説明したい。
1 いわゆる「判断能力」という言葉の意味するもの
「判断能力」という用語そのものは、一般的に広く用いられているものであるにもかかわらず、実は主だった法令には登場しない用語である。
代わりに、民法の教科書を読むと、「意思能力」という概念が登場する。
これもまた民法の条文上は直接には登場しない概念なのであるが、いわゆる「判断能力」とは、この「意思能力」の概念とおおむね重なりあうものとして理解されている。
その具体的な意味内容は、次のとおりである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。