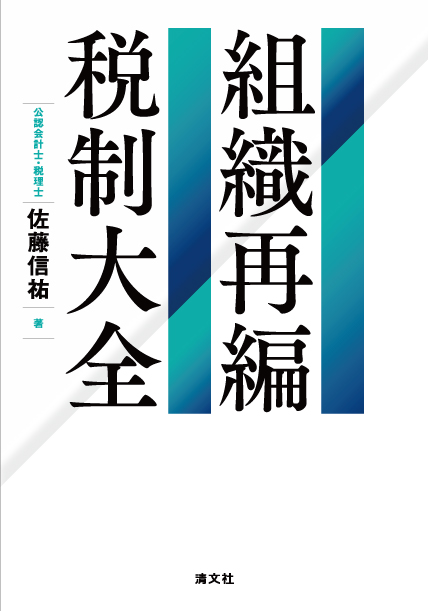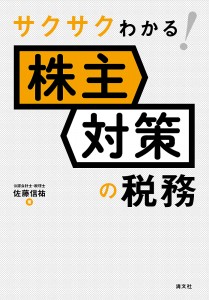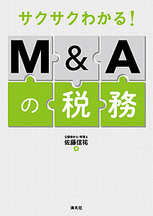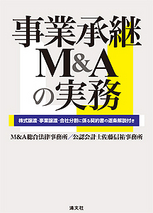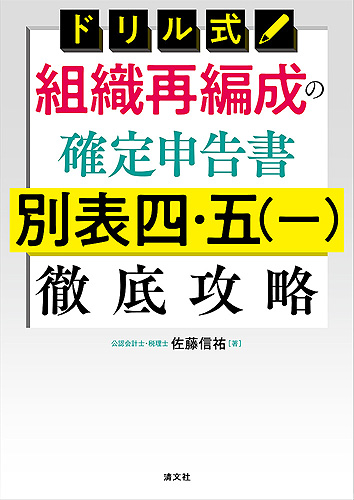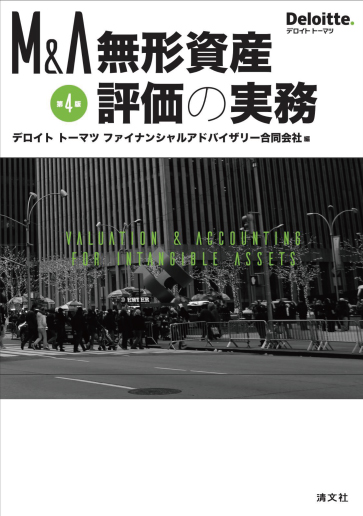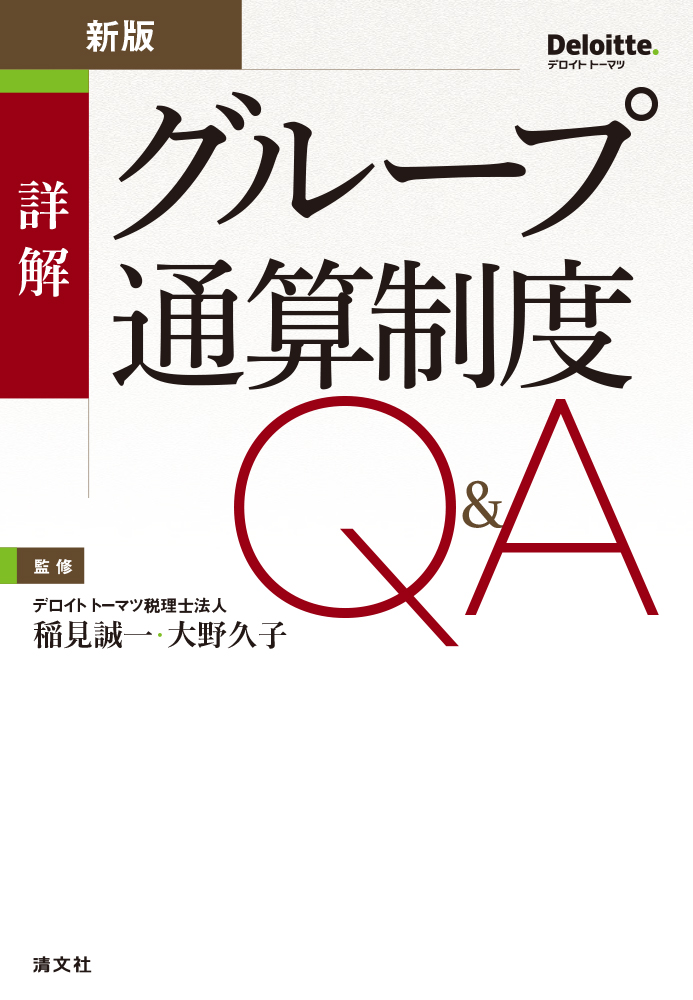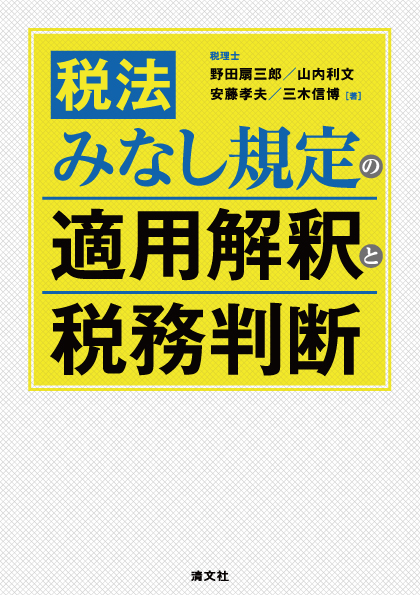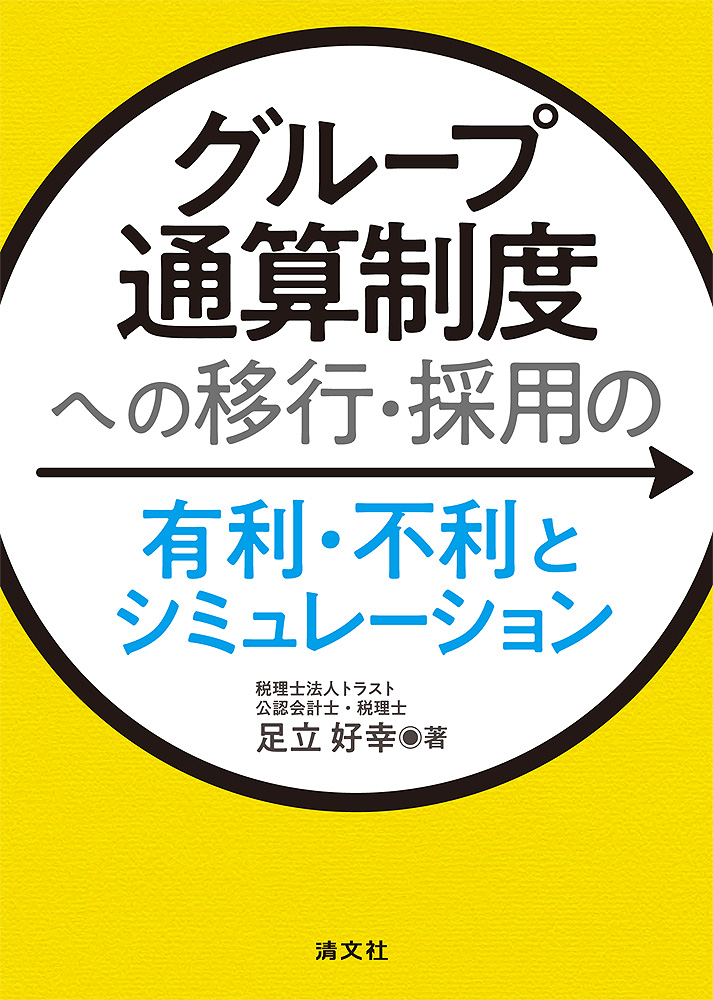組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項
【第1回】
「特定関係子法人から受けた配当等の額に係る特例」
公認会計士 佐藤 信祐
1 基本的な取扱い
内国法人が特定関係子法人から受ける配当等の額(以下、「対象配当等の額」という)及び同一事業年度内配当等の額(※1)の合計額が基準時の直前における当該特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額の100分の10に相当する金額を超える場合(※2)には、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のうち、受取配当等の益金不算入(法法23①)、外国子会社から受ける配当等の額の益金不算入(法法23の2①)又は適格現物分配による益金不算入(法法62の5④)の規定により益金の額に算入されない金額に相当する金額を当該基準時の直前における特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額から減算する必要がある(法令119の3⑦、119の4①)(※3)。これは、みなし配当(法法24)に該当したことにより、受取配当等の益金不算入又は外国子会社から受ける配当等の額の益金不算入が適用される場合であっても同様である(※4)。
(※1) 当該対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日(同日後に特定支配日が生じた場合には、当該特定支配日)からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該特定関係子法人から配当等の額を受けた場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該特定関係子法人との間に特定支配関係があった場合に限る)におけるその受けた配当等の額をいう。
(※2) 2以上の種類の株式を発行している場合には、すべての種類の株式の帳簿価額の合計額により100分の10に相当する金額を超えるか否かの判定を行い、かつ、すべての種類の株式の帳簿価額から減算することになる(法基通2-3-22、瀧村晴人ほか『令和2年度税制改正の解説』476頁)。
(※3) 「減算」と規定されていることから、特定関係子法人から受けた配当等の額に係る規定の適用を受けた後の帳簿価額がマイナスになることもあり得る(瀧村晴人ほか『令和2年度税制改正の解説』476頁)。
(※4) ただし、グループ法人税制(法法61の2⑰、2十六、法令8①二十二)の適用により、株式譲渡損益に相当する金額が資本金等の額として取り扱われる場合には、株式譲渡損益が生じないことから、帳簿価額を引き下げるという本規定は適用されない(法令119の3⑦)。
このように、本規定の適用により、株式の帳簿価額の引下げを通じて、株式譲渡益が引き上げられることから、受取配当等と株式譲渡損の両建てによる租税回避を防止するための規定であるということがいえる。
しかし、内国普通法人である特定関係子法人の設立の時から特定支配日までの期間を通じて、その発行済株式又は出資の総数又は総額のうち100分の90以上の数又は金額の株式又は出資を内国普通法人若しくは協同組合等又は居住者が有している場合(以下、「内国株主割合要件」という)(※5)には、この制度の対象から除外されている(法令119の3⑦一)。その結果、外国法人、非居住者又は公益法人等が株主等になったことがない場合には、この制度は適用されない。さらに、①特定支配日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が10年を超えている場合(法令119の3⑦三、以下、「10年超支配要件」という)、②特定支配日以後に生じた利益剰余金の額から支払われたものと認められる場合(法令119の3⑦二)(※6)、③対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が20百万円を超えない場合(法令119の3⑦四)にも、この制度は適用されない。
(※5) 納税者に書類保存要件が課されていることから、立証責任は納税者にあるということがいえる。
(※6) 前事業年度末の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額と特定支配日の直前事業年度末の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を比較するため、期中に増加した利益剰余金を考慮することはできない。
そのため、実務上、この制度が適用されない事案のほうが多いと思われる。
2 特定関係子法人
特定関係子法人とは、対象配当等の額に係る決議日等において、当該対象配当等の額を受ける内国法人との間に特定支配関係のある他の法人のことをいう(法令119の3⑦)。そして、特定支配関係とは、以下のうち100分の50を超える数若しくは金額の株式、議決権若しくは出資を保有する関係をいい(法令119の3⑨二、法法2十二の七の五)、当該特定支配関係が生じた日を特定支配日という。
① 発行済株式若しくは出資
② 剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配等に関する決議に係る議決権(※7)
③ 役員の選任に関する決議に係る議決権
(※7) 法人税法24条1項に掲げる事由に関する決議に係る議決権を含む。
3 特定支配日以後に増加した利益剰余金の特例
前述のように、対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のうち益金の額に算入されない金額に相当する金額を、特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額から減算する必要がある。ただし、確定申告書に特定支配後増加利益剰余金額超過額及びその計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合には、帳簿価額から減算する金額を特定支配後増加利益剰余金額超過額までとする特例が認められている(法令119の3⑧)。
なお、特定支配後増加利益剰余金額超過額とは、特定支配日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に特定関係子法人から受ける配当等の額の合計額(当該対象配当等の額を受ける前に特定関係子法人から受けた配当等の額に係る規定の適用を受けた金額を除く)が特定支配後増加利益剰余金額を超える部分の金額に相当する金額をいい、特定支配後増加利益剰余金額とは、下記①及び②に掲げる金額から③に掲げる金額を減算した金額をいう。
① 前事業年度末の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額
② 特定支配日から対象配当等の額に係る決議日等の属する特定関係子法人の事業年度開始の日の前日までの間に当該特定関係子法人の株主等が当該特定関係子法人から受けた配当等の額に対応して減少した当該特定関係子法人の利益剰余金の額の合計額
③ 特定支配日の直前事業年度末の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額
4 適格合併、適格分割又は適格現物出資による特定支配日の引継ぎ
対象配当等の額を受ける内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下、「適格合併等」という)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下、「被合併法人等」という)から特定関係子法人の株式又は出資の移転を受けた場合において、当該適格合併等の直前に当該被合併法人等と当該特定関係子法人との間に特定支配関係があり、かつ、当該適格合併等の直後に当該内国法人と当該特定関係子法人との間に特定支配関係があるときは、被合併法人等と特定関係子法人との間の特定支配日を引き継ぐこととされている(法令119の3⑩)。
ただし、当該適格合併等の直前に当該内国法人と当該特定関係子法人との間に特定支配関係があった場合において、その特定支配日が当該被合併法人等と当該特定関係子法人との間の特定支配日以前であるときは、上記の規定は適用されない。
5 合併又は分割型分割による調整計算
(1) 関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割を行った場合
特定関係子法人が、対象配当等の額を受ける内国法人との間に特定支配関係がある他の法人(以下、「関係法人」という)を被合併法人又は分割法人とする金銭等不交付合併又は金銭等不交付分割型分割を行った場合には、(イ)当該関係法人の設立の時から当該関係法人に係る特定支配日までの期間を通じて、当該関係法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうち100分の90以上の数又は金額の株式又は出資を内国普通法人若しくは協同組合等又は居住者が有している場合、(ロ)当該関係法人に係る特定支配日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が10年を超えている場合のいずれかに該当する場合を除き、合併法人又は分割承継法人が内国株主割合要件又は10年超支配要件を満たしたとしても、特定関係子法人から受けた配当等の額に係る規定を適用する必要がある(法令119の3⑪一イ)。
さらに、前述のように、特定支配日以後に増加した利益剰余金の額から支払われた配当等の額については、特定関係子法人から受けた配当等の額に係る規定が適用されないこととされているが(法令119の3⑦二)、合併又は分割型分割に対応して増加した利益剰余金の額のうち関係法人に係る特定支配日前に生じた利益剰余金の額に相当する金額を特定支配日の直前事業年度末の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額に加算することにより、特定支配日以後に増加した利益剰余金の額から除外するという規定が設けられている(法令119の3⑪一ロ)。
ただし、合併法人又は分割承継法人が内国株主割合要件又は10年超支配要件を満たしている場合には、合併又は分割型分割の日を特定支配日とし、特定支配日の直前事業年度末の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を0円とすることが認められている(法令119の3⑪一ハ)。
(2) 関係法人を分割承継法人とする分割型分割を行った場合
特定関係子法人が関係法人を分割承継法人とする分割型分割を行った場合には、分割型分割に対応して減少した利益剰余金の額のうち特定関係子法人に係る特定支配日前に生じた利益剰余金の額に相当する金額を特定支配日の直前事業年度末の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額から減算するという特例が設けられている(法令119の3⑫一)。
ただし、非適格分割型分割を行った場合には、分割型分割に対応して減少した利益剰余金の額はないものとして取り扱われる(法令119の3⑫二)。
6 関係法人からの配当
関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割を行った場合と同様に、特定関係子法人が関係法人から配当等の額を受けた場合についても同様の特例が設けられている(法令119の3⑪二)(※8)。
(※8) 合併又は分割型分割の日を特定支配日とする特例と同様に、「当該特定関係子法人が当該関係法人から特定支配日等以後最初に配当等の額を受けた日」を特定支配日とする特例が設けられている。なお、「特定支配日等」とは、以下のうち最も遅い日をいう。
・特定関係子法人に係る特定支配日
・特定関係子法人から配当等の額を受ける内国法人が(イ)関係法人又は(ロ)関係法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の関係法人との間に特定支配日が生じた日のうち最も早い日
ただし、上記の特例の適用は、以下の要件を満たす場合に限定されている。
① 当該配当等の額及び当該特定関係子法人が当該配当等の額を受けた日の属する事業年度において当該関係法人から受けた他の配当等の額の合計額が20百万円を超え、かつ、当該合計額が基準時の直前における当該特定関係子法人の有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額の100分の10に相当する金額を超えていること。
② 当該特定関係子法人の当該配当等の額を受けた日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める基準時の直前において当該特定関係子法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額が100分の50を超えていること(※9)。
(※9) 「前事業年度の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額」は会計上の帳簿価額により計算し、「当該特定関係子法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額」は税務上の帳簿価額により計算することになる(瀧村晴人ほか『令和2年度税制改正の解説』491頁)。
7 基準時事業年度後に対象配当等の額を受ける場合
対象配当等の額に係る基準時の属する事業年度(以下、「基準時事業年度」という)終了の日後に対象配当等の額を受ける場合には、その受ける対象配当等の額に基づき当該基準時事業年度に遡って特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額から減算する必要がある。
ただし、当該対象配当等の額を受けることが確実であると認められる場合には、その受けることが確実であると認められる対象配当等の額に基づき当該基準時事業年度の確定申告において特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額から減算することも認められている(法基通2-3-22の5)。
〔凡例〕
法法・・・法人税法
法令・・・法人税法施行令
法基通・・・法人税基本通達
(例)法法23の2①・・・法人税法第23条の2第1項
(了)
「組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項」は、毎月第4週に掲載されます。