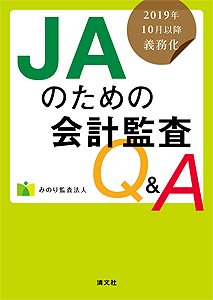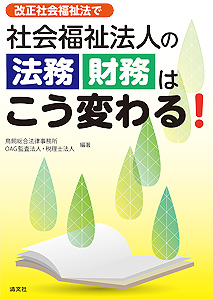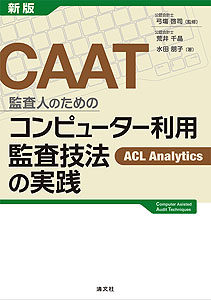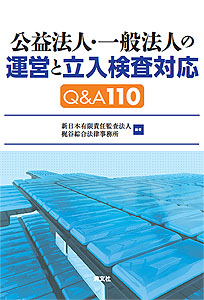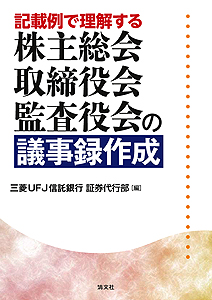〈業種別〉
会計不正の傾向と防止策
【第1回】
「自動車部品製造業」
公認会計士・税理士 中谷 敏久
-本連載の趣旨-
昨年の東芝事件をはじめ、企業における会計上の不正事例には枚挙にいとまがない。
ただし特定の取引形態や法規制、商慣習等によって「会計不正が起こりやすい業種」というものが存在し、その事例から一定の傾向を把握することは可能である。
そこで本連載では、これら会計不正が起こりやすい業種を毎回ピックアップし、その傾向と原因、防止策について紹介したい。
第1回で取り上げるのは「自動車部品製造業」である。
どのような業種業態か?
自動車部品製造業は自動車産業の中では“サプライヤー”と呼ばれ、トヨタ、日産、ホンダなど日本を代表するメーカーに部品を供給している。
メーカーは国内外の競争に打ち勝つため徹底したコスト管理をしており、サプライヤーも当然のごとく毎年コスト削減が求められる。それに対応すべく生産設備の新規導入や生産体制の見直し改善が実施され、また、国外に安い労働力を求めて、東南アジア等に現地子会社を設立し、当該工場から現地のメーカーに部品を供給する体制を敷いているサプライヤーは多い。
ただし、このような生産効率が優先されるあまり、間接コストとしての経理事務作業は軽視され、対応が後手に回るケースが多いのも現状である。
どのような不正が起こりやすいか?
メーカーから絶えず品質面及びコスト面で高いレベルを要求されるため、必然的に生産管理体制の構築は社内の優先目標のひとつとなる。また、計数管理手法として管理会計が重要視され、原価計算及び損益管理に関する会計情報には関心を持つが、逆に過去情報としての財務会計には無関心である経営者は少なくない。
そのため、業容拡大によって事務量が増加しているにもかかわらず、生産活動に支障をきたさないということでその対策を怠り、旧態依然として手作業によって会計情報を集計しているケースが見受けられる。
ここに会計不正が発生する原因がある。
不正が発生する項目は会社によってまちまちであるが、一般的に生産ラインと結びついた会計情報からは発生しにくい。なぜなら、これらの会計情報に不正情報が含まれるとすると、生産活動が混乱する可能性があるからである。
例えば、売上高、材料仕入高、外注加工費、棚卸資産といった項目は不正が発生しにくい。それに対して、固定資産の取得、移動、除却、売却に関する処理は不正リスクが高くなる。なぜなら、生産に必要な固定資産が実在し現実に稼働していれば、たとえそれらに関して不正な会計処理がなされていたとしても、生産活動には全く影響がないからである。
事例検証
平成21年3月10日に公表されたフタバ産業(株)(東証1部)の不正事例を紹介する。
社内調査委員会の調査報告書によると、下記に示すような固定資産に関する不正な会計処理が長期間にわたって行われていた。
① 建設仮勘定の本勘定への振替漏れとそれに伴う減価償却費の計上不足(144億円)
② 仕掛品の売上原価への振替漏れ(192億円)
③ 据付調整費の資産性の根拠不足とそれに伴う期間費用の一括計上(451億円)
①については、量産開始後は国内生産用金型・設備等について建設仮勘定から本勘定へ振替すべきところ、量産開始後も建設仮勘定のまま計上し、減価償却を失念したというものである。
金型・設備等の製作については外製の場合と内製の場合とがあるが、どちらの場合においても発注段階でオーダーナンバーを設定し、そのナンバーをキーにして検収処理、建設仮勘定への計上、本勘定への振替を行うケースが実務上多い。
調査報告書によると、オーダーナンバーの付け方の要領書が難解で、誰にでも容易に間違いなく付番できるものではなかったとされている。
②については、一見すると仕掛品の処理であり、固定資産に関するものではないように見られるが、そうではない。海外子会社に売却する金型・設備等ということで仕掛品勘定を用いただけであり、実態は金型・設備等という固定資産そのものである。
海外子会社に金型・設備等を輸出する場合、実務上は輸出手続としてパッキングリストが作成され、船積みされるまでの間、海運業者の倉庫に保管される。したがって、一般的には輸出売上に対応する売上原価の把握はそれほど難しいものではないが、調査報告書によると、仕掛品から売上原価に振り替えるために必要な作番(設備ごとの材料・部品の通し番号)の付け方の要領書が難解で、誰にでも容易に間違いなく付番できるものではなかったとされている。
③の「据付調整費」とは、金型・設備等の性能確認・調整等の費用であり、機械装置の取得原価に加算するか、あるいは「生産能率の向上又は生産計画の変更等により、設備の大規模な配置替を行った場合等の費用」(財務諸表等規則ガイドライン36項5号)として、繰延資産である開発費に計上する。
しかし、今回のケースは、その処理を裏付ける会計証憑が保存されていないにもかかわらず、建設仮勘定に計上するという不正な会計処理がなされたものである。
* * *
これらの不正会計が発生した原因として、調査報告書では、国内需要の急速な拡大、海外への急速な進出、工場改革計画の遂行による急速な投資の実行により、従来の業務フローでは対応できないほど業務量が拡大したにもかかわらず、経理部等の管理部門の効率化が思うように進まず、金型製造部門及び購買部門との連絡体制に不備が生じたためとしており、今回の不正な会計処理が意図的に行われたものではないとしている。
ただし、意図的でないにしても、総額700億円を超える不正会計が長い間修正されることなく放置されてきたことは不思議でならない。
【参考】
「社内調査委員会調査報告書」(H21.3.10)
「過年度決算訂正調査報告書」(H21.3.10)
不正の防止策
前半で述べたように、この業種では、業容拡大によって事務量が増加しているにもかかわらず、生産活動に支障をきたさないということでその対策を怠り、旧態依然として手作業によって会計情報を集計している場合に、会計不正が発生しやすい。固定資産の取得、移動、除却、売却に関する会計情報の集計には、システム化されてはいるものの、売上高等の生産ラインと結びついた会計情報のそれと比べると、手作業の感が否めないケースが少なくない。
このような手作業に起因する会計不正を防止するためには、内部統制を強化することが必要である。ただし、単にチェック人員を増加させるだけでは不十分であり、社内でどのような取引が発生しているのか、実務担当者が取引実態を正確に把握すべきであろう。
そして、その取引実態の把握に基づいて会計情報の集計手続を標準化することが求められる。
同様の不正が起こりうる業種業態は?
製造業は、製品を生産するために金型・設備等に多額の投資を必要とする。特に、需要の変化に対応するために絶えず生産体制の見直しを求められる業界にあっては、金型・設備等の動きが激しい。ある意味で固定資産が流動資産化しており、同様の不正が起こりうる可能性が高いと言える。
(了)
「〈業種別〉会計不正の傾向と防止策」は、毎月最終週に掲載されます。