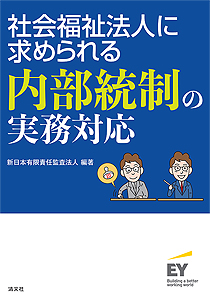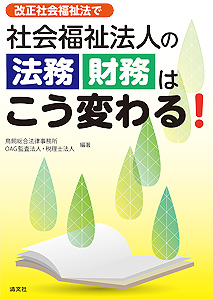〔具体事例から読み取る〕
“強い"会社の仕組みづくりQ&A
【第1回】
「なぜ内部統制報告制度を導入しても
不正や会計上の誤りはなくならないのか」
米国公認会計士・公認内部監査人
打田 昌行
【Q】
日本のものづくりの信頼性が揺らぐ事件として、三菱電機株式会社において30年以上にわたり品質検査不正やねつ造の行為が組織的に繰り返されていたことが先般報道されました。日本には内部統制報告制度があるにもかかわらず、なぜこうした品質の不正や不祥事を見破り、未然に防止することができないのでしょうか。
【A】
まず、内部統制報告制度の目的は、上場企業の「財務報告の信頼性」を実現することにある。「財務報告の信頼性」とは、信頼性のある、正しい財務諸表を作ることであり、そのために必要な社内の仕組みづくりを進めることだ。したがって制度自体は、社内の不正や不祥事を炙り出す、いわゆるあら探しを直接の目的とするものではない。
しかし、正しい決算書の作成を妨げる不正や不祥事、企業の信頼性を著しく毀損する品質検査不正などコンプライアンスを侵す行為は、内部統制が取り組むべき重要な課題の1つとなり得る。そこでこれらの行為を早期に見破り、予防をするには、次に示すことを適切に実施することが求められる。
◆◇ 解 説 ◇◆
次の3つの問いかけに対し、自社としてどこまで自信を以て応ずることができるだろうか。他社の多くの失敗や躓きに隠された教訓から学びを得ることが大切である。
1 その①:「直訴」の実践的な仕組みが、使いやすく正しく機能しているか
ここでいう「直訴」とは、組織上の権限と責任を持つ窓口に、違法あるいは反倫理的な行為について知り得たことを直接通報することをいう。内部統制の仕組みでいえば、内部通報制度がその典型といえる。よく似た仕組みとして、ほかにも経営者(社長)に対し、全社員が電子メールで直接に、相談や通報をできるよう工夫をしている会社もある。
実際に、通報制度によって不正や不祥事が早期に把握され、効果を上げる場面も数多く見聞きする。正しく使えば、誠実な従業員の通報によって早期に不正や不祥事の芽を摘み取ることができる。しかし他方で、せっかく経営者に直接実情を訴えられる仕組みがあっても、実際には使い勝手が良くないために、運用されずお飾りとなってしまっているケースも耳にする。
冒頭の品質検査不正事件に関し、三菱電機株式会社の杉山社長(発覚当時)は、記者会見で社員の通報による情報の迅速な収集について問われ、記者に次のように応じている。
Q.情報が出てくるかは社員の自主性に任せるということか。
A.社内には情報収集の窓口を準備しているが、今回、結果として機能していなかった。社内と社外に窓口があり、情報提供者がわからないような仕組みは作られてはいるが、まだまだ従業員の皆さんに理解が不足している面がある。もっと使いやすく、もっと提案しやすくなるよう改善が必要だと考えている。(以下略)
(※) 三菱電機株式会社「鉄道車両用空調装置等の不適切検査/当社の品質風土改革に向けた取り組みに関する会見 質疑応答(報道機関)」7頁より一部引用。
制度を作っただけで安心せず、使い手の使いやすさをしっかりと考慮することが大切だ。次のことを十分加味し、制度の実践をしなければ、効果が半減してしまうことに注意すべきである。
(1) 制度利用の目的を周知して心理的な壁を取り除く
通報すると会社の利益が損なわれ、上司にも迷惑が及ぶと考え、通報をためらう従業員がいる。これではせっかくの制度の趣旨を活かすことはできない。通報制度の趣旨を十分に社内に周知することが肝要である。それに加え、通報には匿名を認め、制度を使う社員の心理的な抵抗感を取り除く工夫も求められる。
(2) 通報の秘匿性を確保する
メールによる通報時は、システム上で発信者の特定ができないようにして通報者の秘匿性を確保し、使いやすさを考慮することも大切である。
(3) 通報者の利益を必ず守る約束をする
顕名による通報の場合、会社が通報者に対し不利益を与えないことを約する必要がある。せっかくの制度も社員からの信頼がなければ、いきなり外部のマスコミや監査法人に通報され、会社のリスク管理責任が問われかねない。通報内容が会社の方針等に反することを理由に不利益を与えれば、通報する者はなくなり、制度は形骸化するばかりとなる。
(4) 通報に基づき改善結果をフィードバックする
正しい通報の結果、改善を施した場合はその成果を社内全体に、あるいは通報者(顕名の場合のみ)に必ずフィードバックして制度自体の信頼性を高める努力をすべきである。
(5) 制度の悪用者を厳しく処罰する
他方、偽りの通報で他者を陥れようと企む者は、厳しく処罰する必要がある。内部通報制度は、ナチスや旧社会主義の東欧諸国が用いた密告とは性格を全く異にする。通報制度では、通報内容の真実性が求められ、他者を悪意により陥れる手段では決してない。
(6) リニエンシー制度を併用する
リニエンシー制度を用い、複数による不正にも効果的に対応することができる。自らが関わった(複数人による)不正を自主的に通報した者には、懲戒処分などの社内処分の減免をする仕組みをリニエンシー制度といい、これを通報制度と併設して使うことも望ましいと考えられる。
2 その②:教育こそ内部統制報告制度運用のための礎と考えているか
内部統制に関する社員教育を継続することは、口にするのは簡単だが実際に行うとなると難しい。なぜなら教育に対する投資は、一定のコストを要する反面、数値など客観的な物差しによって成果が計りにくいからである。とはいえ、経営者はじめ従業員の意識や日頃の行動に強い影響をもたらし、不正や不祥事を許さない企業風土を培うために、やはり教育の継続を欠かすことができない。
現状を追認するコトナカレ主義、不正や不祥事を見て見ぬふりをする意識や行動様式は、長年にわたり繰り返される因習や行動パターンによって形成されてゆくものである。こうした組織の垢を新陳代謝によって取り払うには、根気強い教育研修に頼らざるを得ない。実際に会社が取り組む次の事例を参考に挙げることができる。
(1) 経営層が自分の言葉でコンプライアンスの大切さを伝える
コンプライアンスに関する社内研修は、経営層が直接従業員に訴える場とする。年度初め、期中、期末、予算・決算の発表、節目に応じて定期的に経営層が従業員に向けてコンプライアンスに関するメッセージを送る機会を確保する。メッセージは、経営層自らの言葉で、分かりやすく伝える。間違ってもマスコミや報道が伝える、ありきたりな標語を使うことは避けるべきである。
(2) 感染症の流行を制度定着のチャンスと考える
コスト、時間、機会のどれを考慮しても、コロナ禍の今こそ、教育研修に取り組む絶好のチャンスとなり得る。感染症の流行に端を発したテレワークが浸透するにつれて、オンラインによる教育研修を充実させる会社が増えている。物理的な身体の移動はなく、海外や地方などいかに遠方でも旅費等のコストを要せず、研修室や会議室のイスの数に制約されずに多くの参加者が一度に研修を行うことができる。
(3) 研修内容は自社や他社の失敗事例を大いに活用する
研修の内容は、マスコミで報道された他社の事例はもちろんのこと、自社の監査で指摘された案件、場合によっては社内の社内調査委員会や第三者委員会で公知となった不正や不適切事例でも研修材料として用いることが非常に有効である。
3 その③:常に第三者の眼に晒される機会を作っているか
昨今、会社の不正や不適切な会計処理を巡り、調査のために第三者委員会を設ける件数が増大している。モノ言う株主が増加し、ますます企業経営に対する説明責任が厳しく問われている証拠でもある。内部統制上で不備や問題があれば、改善に加え社会に対する説明責任が厳しく求められる。そのため、企業活動を第三者の眼に晒す努力をすれば、広く公平性や客観性、信頼性を得ることができるのも確かである。
例えば、前述の通報制度も、通報窓口を社内に設置し、社外の弁護士事務所にその運用を委託することで、通報する者が持つ心理的なプレッシャーを和らげる効果が得られ、かつ制度の客観性や信頼性も確保できる。
品質管理問題の場合でいえば、品質に関する外部専門家による検証や検査を定期的に実施し、社内ルールが遵守されていることを客観的に検証することが重要となる。ただし検証や検査は各グループ会社単位では行わず、必ず本社主導でグループの壁を越えて徹底的に実施することが、ものづくりのプライドを守る意識の醸成に繋がるはずである。
* * *
前述した三菱電機株式会社の社長が引責辞任にあたり、報道機関に次のように応じた。あらためて、内部統制が取り組むべき問題の根深さを実感する。
Q.辞任の経緯について。これまでもガバナンス、コンプライアンス問題を複数起こしてきたが、それらとの比較において、今回の事の重大さをどの部分で痛感したのか。
A.30年以上に亘って不正が行われた、それも特定の個人ではなく組織的、行為が何代にも亘って受け継がれてきたことは極めて厳しい状態だと捉えている。非常に重要なことが欠落していると言わざるを得ないと考えており、これに対してしっかり取り組む必要がある。(以下略)
(了)
「〔具体事例から読み取る〕“強い"会社の仕組みづくりQ&A」は、毎月最終週に掲載されます。