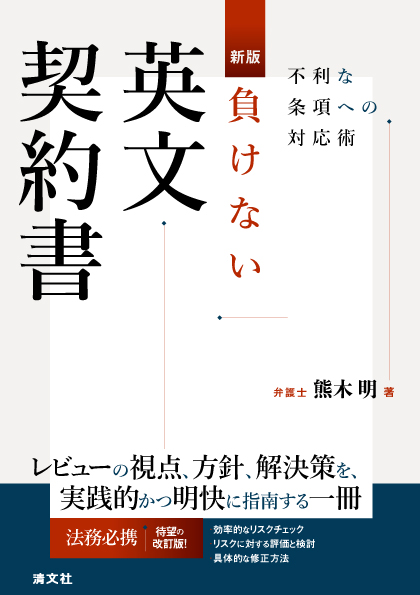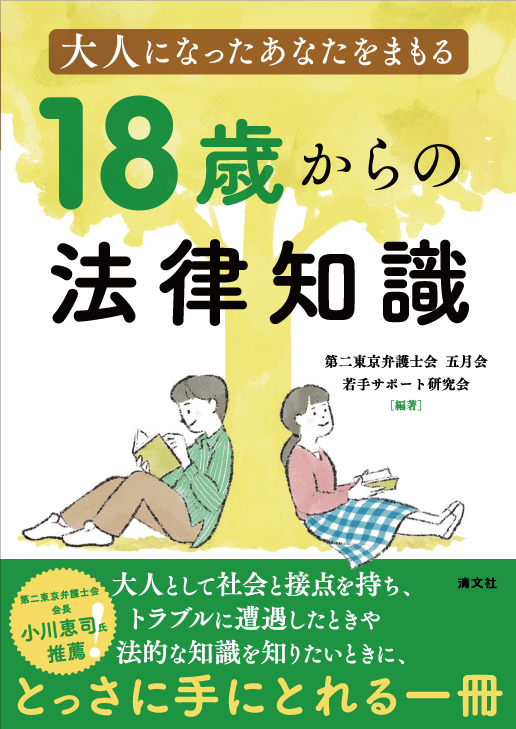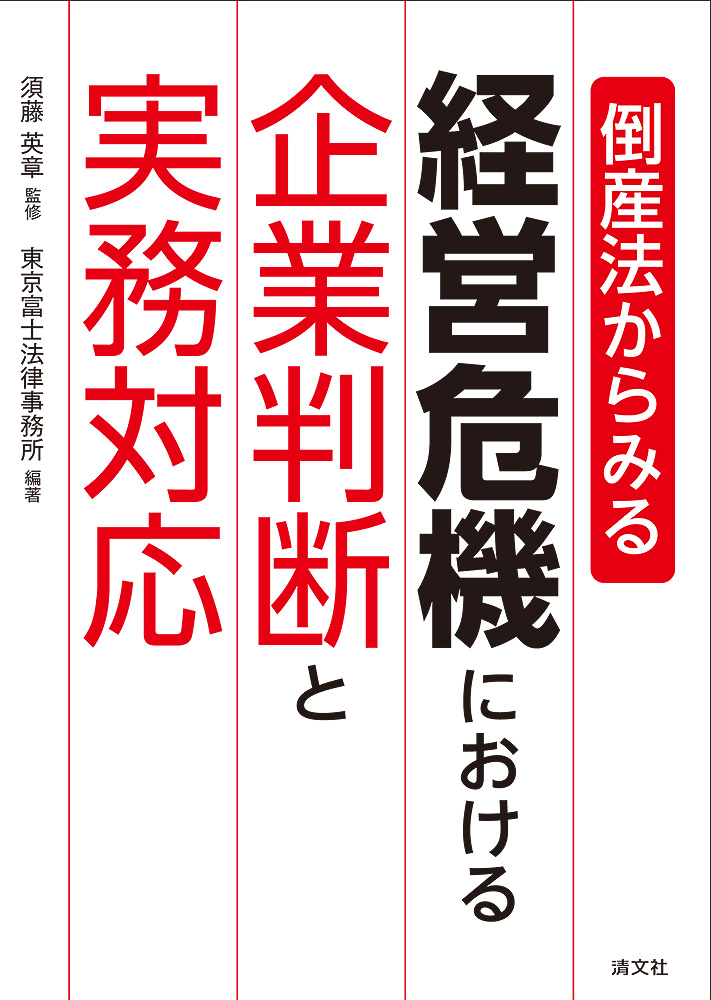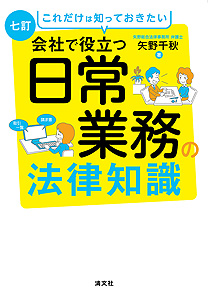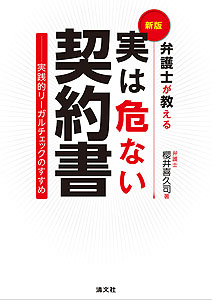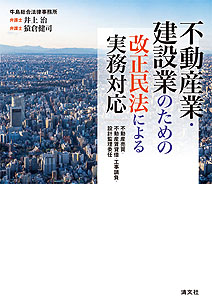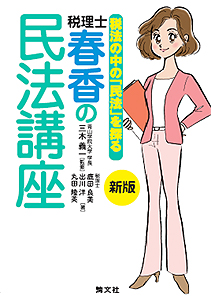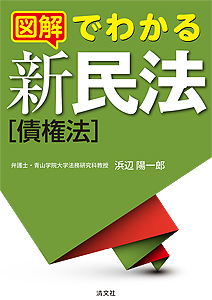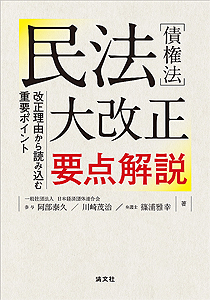常識としてのビジネス法律
【第6回】
「契約に関する法律知識(その2)」
弁護士 矢野 千秋
1 契約書の形式
私的自治の原則と、それから派生する契約自由の原則中の方式の自由から、契約書の方式には原則として、何の決まりもない(例外として有価証券、遺言、定款、寄付行為、建築請負契約、小作契約、労働協約、保証契約等がある。これらは種々の理由から法が方式を決めていたり、書面を要求しているものである)。
したがって、文書の内容から何らかの合意が読み取れるものなら、すべて「契約書」と言える。このため、注文書と注文請書を併せて合意が読み取れる場合でも、併せて契約書と呼べるし、注文請書をとれないような場合には、注文書コピーの余白に相手方の確認の記載(最低限署名のみでも)をとっておけば、それをもって契約書、すなわち後日契約成立の強力な証拠となる。
2 契約書の表題・内容
(1) 表題
「契約書」「念書」「覚書」「協定書」「確認書」等、どのような表題でも、内容から合意が読みとれれば契約書である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。