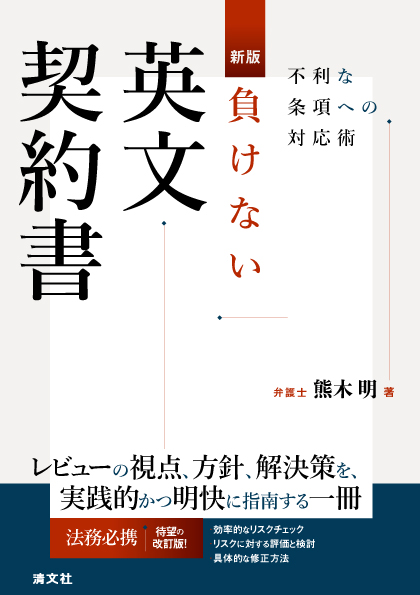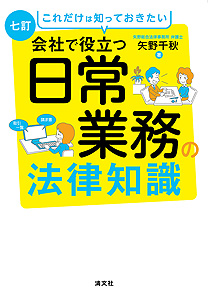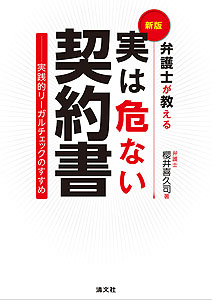社外取締役と〇〇
【第1回】
「社外取締役の存在意義」
西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子
1 はじめに
本稿は、「社外取締役と〇〇」と題する連載の第1回目である。
社外取締役に関しては、2019年12月4日に成立した「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)(以下「改正法」という)により、監査役会設置会社であっても、公開会社かつ大会社であり、有価証券報告書の提出義務を負う会社(以下「上場会社」という)において、その選任が義務化される等(なお、社外取締役の選任義務については次稿にて取り上げる)、その果たす役割は、一層重視されている。
このような近時の社外取締役への期待を背景に、本連載では、実務に根ざした多様な観点から、各回毎に異なるテーマを定め、社外取締役に関する諸論点を検証することとしたい。
2 社外取締役の導入状況
本稿のテーマとする「社外取締役の存在意義」を検討するにあたり、社外取締役の導入状況について簡潔に記載すると、2014年会社法改正及びそれに係る法務省令改正(※1)により、上場会社につき「社外取締役を置くことが相当でない理由」を定時株主総会において説明し(会社法327条の2)、かつ、事業報告及び株主総会参考書類に記載すること(会社法施行規則74条の2第1条、124条2項)が求められることとなる「前」である2013年においては、1名以上の社外取締役を選任する企業は、東証の全上場企業中、54.2%(2名以上は30.6%)であった。
(※1) これらの改正の施行日は2015年5月1日である。また、同年6月1日には、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という)によるコーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」という)が施行され、東証第一部及び第二部上場企業を対象として、最低2名の独立社外取締役を選任することが推奨され、かつ、企業の実態に鑑み必要と考える場合には3分の1以上の独立社外取締役の選任を検討すべきことが求められることとなった(CGコード原則4-8)。
しかし、2017年においては96.9%(2名以上は91.9%)に至っている。また、東証の全上場企業のうち、取締役の1/3が社外取締役である企業は2017年において32.7%を占め、取締役の過半数が社外取締役である企業も、同年では4.4%存する(※2)。このように、現在の実務においては、社外取締役を複数名選任することが通例であり、かつ、取締役の1/3以上を社外取締役が占める企業も珍しくない状況にあるといえる。
(※2) 東証「東証上場会社における社外取締役の選任状況及び社外取締役を置くことが相当でない理由の開示状況について」法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会(以下「部会」という)第5回会議(2017年9月6日開催)参考資料19(3頁、7頁)。
3 社外取締役の効用
上記2のとおり、社外取締役の選任が広く普及する現状において、社外取締役の効用として、一般的には、取締役会や委員会を通じた監督や助言、社内向け講演会やリーダー研修の講師、個別案件・分野における助言、CEOの相談相手、将来のトップ候補との面談・会食、外部の人材や会社等の紹介等が指摘されている(※3)。
(※3) 江川雅子「コーポレートガバナンス・コード導入後の取締役会の実態」旬刊商事法務2196号(2019)36頁。
もっとも、少なくとも現時点において、社外取締役の導入により会社の業績が向上するという分析結果は示されていない。かえって、CGコード導入後の2事業年度に限定したものではあるが、東証第一部上場企業では社外取締役の選任によって特に優位な(統計学上意味のある)業績変化は見出せないが、東証第二部上場会社の場合には、むしろ業績が有意に悪化するという統計分析が示されている(※4)。
(※4) 齋藤卓爾「取締役会に関する実証分析」部会第5回会議参考資料23(22~23頁)。もっとも、上述のとおり、当該統計分析は、CGコード導入後の2事業年度に限定したものであり、かつ、部会資料として用いられることのみを目的としたものであることに留意する必要があるが、社外取締役の効用について検証しきれていないことを示す資料として有益と考えられる(田中亘「コーポレートガバナンス改革の本質を問い直す〔上〕-I 社外役員の意義と職責」旬刊商事法務2215号(2019)6頁)。
このように、社外取締役の選任による可視的な効果は見出しにくいにもかかわらず、その選任が推奨され、ひいては義務化されることとなった現状に鑑みると、取締役の存在意義について、導入企業及び社外取締役自身の双方が主体的に認識していることが重要といえる。
4 社外取締役の存在意義
それでは、社外取締役の存在意義はどのような点に見出すことができるだろうか。特に重要なものとして、以下の2点を挙げることができる。
(1) 利益相反における判断
まず、業務執行取締役等において利益相反が生じる場面において、利益相反のない取締役として対象事項の決定を行うという存在意義がある。
利益相反が生じる典型的な場面は、取締役候補の決定(指名)及び取締役の報酬の決定である。これらの「指名」及び「報酬」は、その利益相反性に鑑み、指名委員会等設置会社においては、社外取締役が過半数を占める指名委員会及び報酬委員会において決定することが会社法上の義務とされている。
指名委員会等設置会社以外のガバナンス体制をとる会社においては、このような会社法上の義務はないが、CGコードでは、これらの会社においても、独立社外取締役が取締役の過半数に達していない場合には、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会の設置が求められている(CGコード補充原則4-10①)(なお、社外取締役と役員報酬については本シリーズの後掲の論稿にて取り上げる)。
(2) 内部統制システムの機能強化
次に、内部統制システムの機能強化という存在意義を挙げることができる。
そもそも、会社法上、内部統制システムの整備は、取締役会の責務とされている(会社法348条3項4号、362条4項6号、399条の13第1項ハ及び416条1項1号ホ)。もっとも、社内に必ずしも精通してはいない社外取締役が、各企業において、どのような内部統制システムが適しているか、その制度設計や運営状況の監督において主導的な役割を果たすことは難しいことが多いと考えられる。
しかし、内部統制システムが、代表取締役、業務執行取締役、(指名委員会等設置会社における)執行役等への報告ラインとしてのみ構築されている場合には、監督の対象となる本人にしか報告がなされないため、職務執行の適正確保という内部統制システムの本来の機能を果たすことはできない。これに対し、社外取締役(を含む取締役会)、監査委員会又は監査役会が、内部統制システムにおける直接の報告先とされていれば、その本来の機能を維持しうる(※5)。
(※5) 金融庁及び東証により設置された「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」による「「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書(4)」(2019年4月24日)4頁。
また、近時においては、監査役会設置会社における監査役監査の実効確保のため、監査役等による内部統制部門の「連携」よりも、さらに一歩踏み込んだ「活用」が提唱されている(※6)。「活用」には、監査役等による内部統制部門に対する指示等が含まれると解される(※7)。
(※6) 経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(2019年6月28日)4.5(72頁)。
(※7) 前掲(※4)田中11頁。
このように、社外取締役は、その本来の職責として、内部統制システムの整備状況を監督するにあたり、その報告先が代表取締役等に限定されていないか(社外取締役や監査役等が含まれているか)、また、監査役等による内部統制部門への連携又は活用が確保されているかを検証することで、適切な内部統制部門の構築に効果的に貢献することができる(なお、社外取締役と内部統制システムについては本シリーズの後掲の論稿にて詳述する)。
5 おわりに
以上、本稿においては、社外取締役の存在意義につき概説した。次稿以降、その存在意義を構成する要素を含む様々な観点から、社外取締役に関する諸論点を検証することとしたい。
(了)
「社外取締役と〇〇」は、毎月最終週に掲載されます。