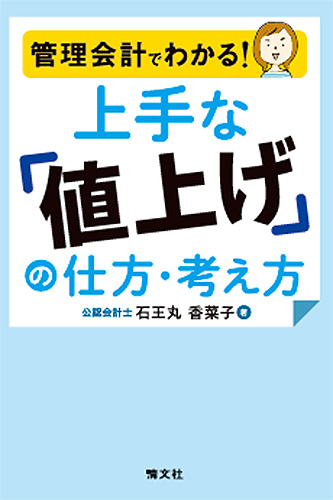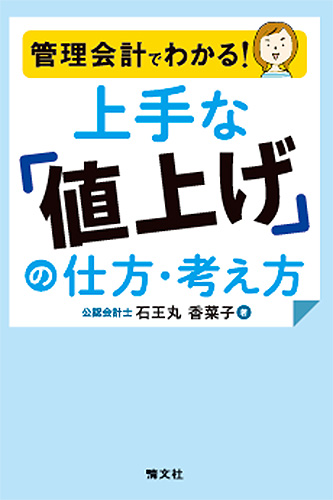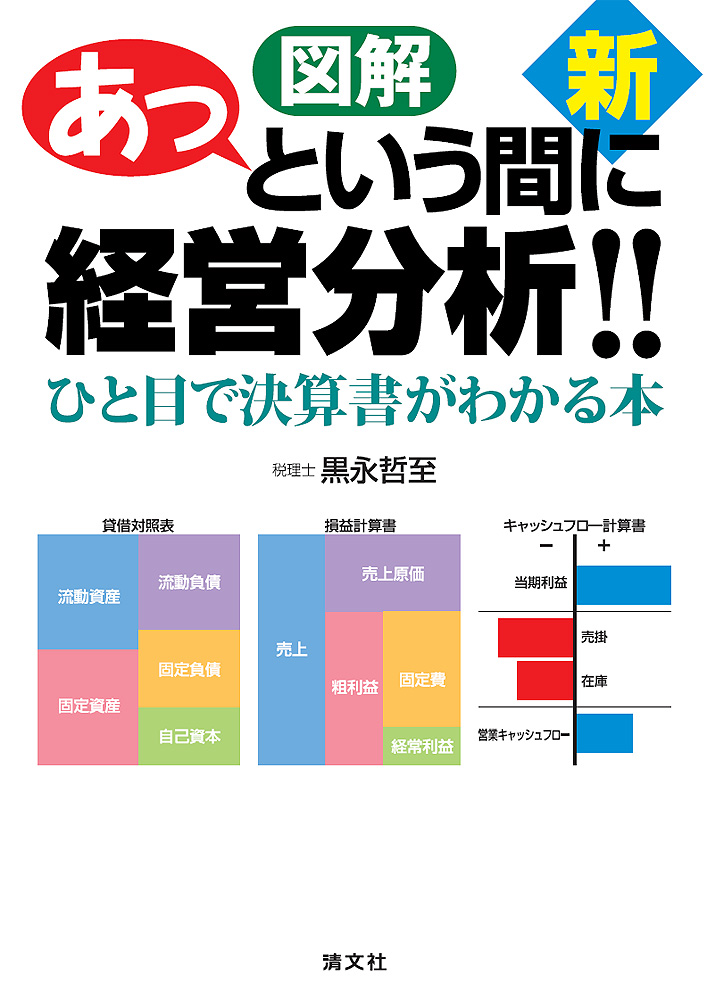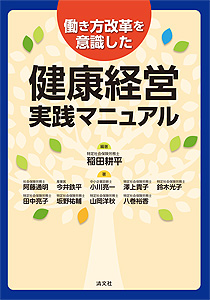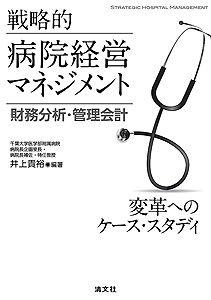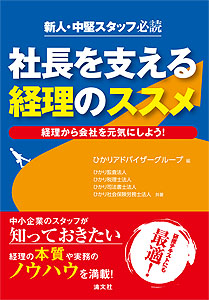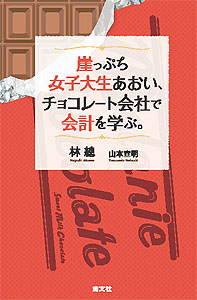ファーストステップ
管理会計
【第17回】
(最終回)
「大切なのは将来とバランス感覚」

公認会計士 石王丸 香菜子
前回まで16回にわたって、管理会計の基礎について勉強してきました。最終回となる今回は、これをどのように実務に活かすかを考えます。
◆こんな管理会計システムがあったら?
管理会計の基礎を理解したみなさんのところに、あるシステム会社から、管理会計システムの案内が届いたとしましょう。その名も「ゴールデン・パーフェクト・システム(GPS)」という管理会計システムです。案内には、こんなことが書いてあります。
① 管理会計に関するあらゆる数値を完璧かつ緻密に計算できます!
② 過年度の数値を詳細に集計・分類することにこだわります!
③ あらゆる会社に対応可能なマルチシステムです!
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。