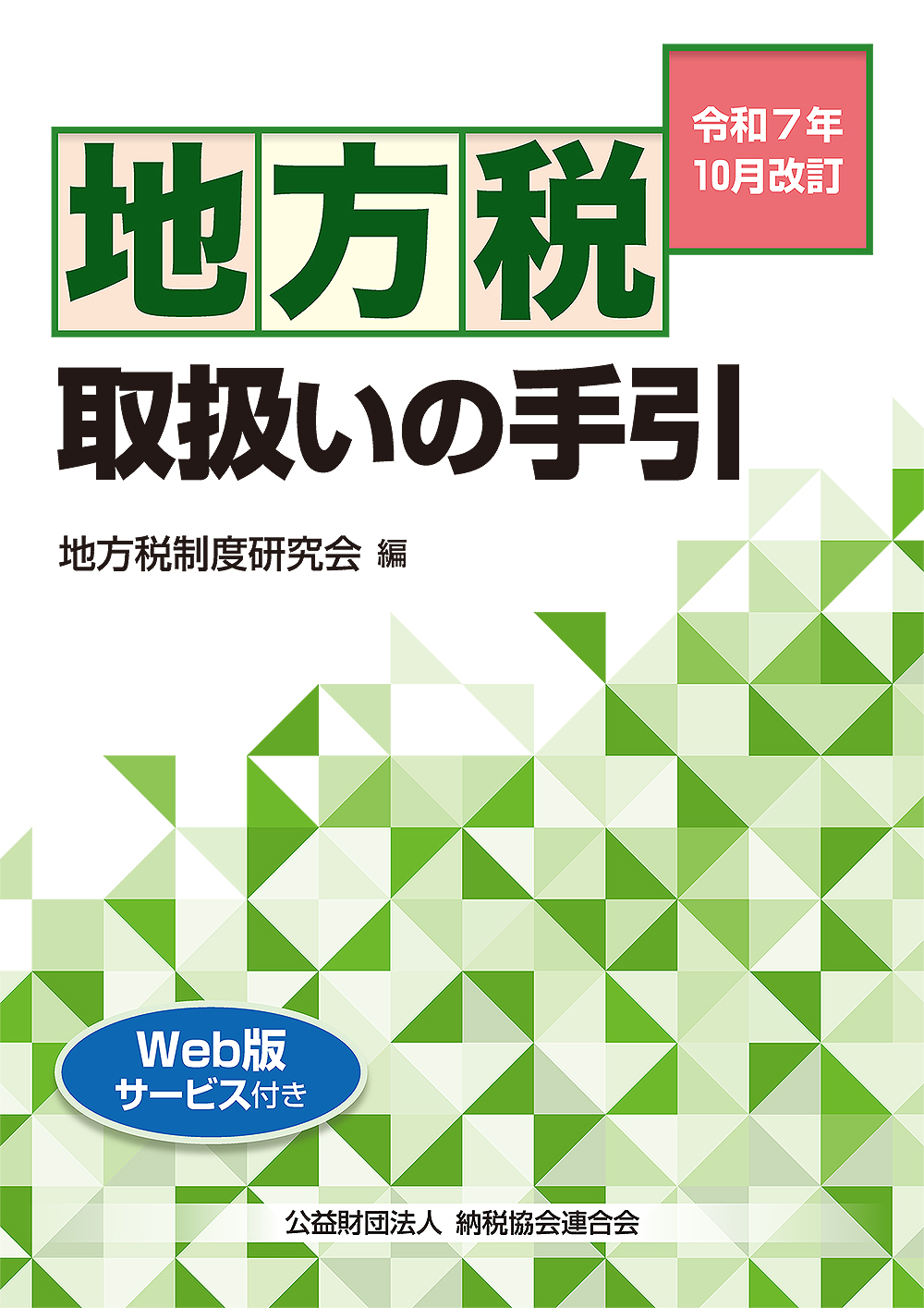固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第1回】
「5年超前の過誤納固定資産税の還付が認められた判例」
税理士 菅野 真美
▷固定資産税の課税
固定資産税は、その年1月1日に土地、家屋、償却資産を有する者について、市町村(東京都特別区においては東京都)がこれらの価額に基づいて課税するものである。所得税等は納税者の申告に基づいて課税される制度であるが、固定資産税は賦課決定という課税主体(市町村)が課税標準や納付すべき税額を決める制度である。課税標準となる固定資産の価格は、固定資産評価基準によって決定しなければならない(地方税法403条1項)。どのようにして決めていくかというと、市町村の職員が、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって、公正な評価をするように努めなければならないとされている(地方税法403条2項)。
固定資産税の課税標準については減額制度がいくつか設けられているが、住宅地については課税標準となるべき価格の3分の1の額とされ、小規模住宅用地については6分の1の額とされる。軽減措置の適用を受けるために市町村は納税者に必要事項を申告させることができ(地方税法384条1項)、もし、納税者が正当な事由がなくて申告しなかった場合は、条例で10万円以下の過料を課す規定を設けることができる(地方税法386条)。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、期間制限があるが、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができ、価格以外の課税の内容について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。市町村は、過誤納金がある場合は速やかに還付しなければならないが(地方税法17条)、過去にさかのぼって還付できる期間は通常5年とされている。それでは、5年を超えた過去の過誤納部分の還付を受けることは可能だろうか。
本件は、国家賠償法1条(国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる)に基づく還付(ただし過失相殺による2割減額)が認められた事案である。
【東京地方裁判所平成28年10月26日判決・平成○○年(●●)第○○号国家賠償請求事件(一部認容)(確定)】(TAINSコード:Z999-8381)
▷どのような事案か
- Aが平成14年に相続により取得した土地に、平成16年に建物を建築して、介護付き優良老人ホームとして賃貸した。
- 平成16年3月又は4月に都税事務所職員が、建物完成後、建築工事請負契約書等を受け取った。
- 納税者は、固定資産税の住宅用地等申告書を提出しなかった。
- 平成17年分以降の固定資産税として、土地について非住宅用地又は一般住宅用地として賦課決定した。
- 平成20年6月にAが死亡。Bが土地、家屋を相続により取得した。
- 納税者は平成26年に都税事務所職員から指摘を受けて、初めて固定資産税課税に誤りがあったことを知った。
- 平成27年2月に納税者に対し、平成22年度分から平成26年度分までの過誤納固定資産税を還付した。
- 平成27年10月27日付の遺産分割協議により、過納付した固定資産税に関する損害賠償請求権をBが取得した。
▷争点は何か
主たる争点として下記3点があった。
① 国家賠償法上の違法性があるか
② 消滅時効は完成しているか
③ 過失相殺はあるか
① 国家賠償法上の違法性があるか
納税者は、東京都が小規模住宅用地及び市街化区域農地として賦課決定すべき職務上の義務を負っていたにもかかわらず、非住宅用地及び一般住宅用地として課税し、過大な固定資産税等を賦課したことは国家賠償法1条1項の違法があると主張した。
東京都は、納税者が申告義務を履行していないから、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく認定を誤ったとはいえないから違法性はないと主張した。
② 消滅時効は完成しているか
国家賠償法に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅するとされている(国家賠償法4条、民法724条1号)。
納税者は、平成26年10月頃に指摘されて初めて誤りを知ったが、同時点においても具体的にどのような損害があったのか認識できておらず、平成27年2月に過去5年分の過納付金の還付を受けて初めて具体的な損害の発生を認識した。そのため消滅時効の起算点は、平成27年2月、又は早くとも平成26年10月頃であると主張した。
東京都は、毎年度送られる課税明細書等には「全部非住宅用地」と記載されており、住宅用地の特例の案内や住宅用地所有者の申告義務について注意を喚起する文言が記載された文書を同封していたことから、請求が事実上可能であったのは平成17年分から平成21年分の納税の時点からである。既に3年以上経過しているから、消滅時効は完成していると主張した。
③ 過失相殺はあるか
納税者は、口頭の説明の形式で申告することも認められるべきであり、平成16年3月又は4月に都の職員が訪問した時に資料を交付して、固定資産税等の評価のために必要な説明をしているから住宅用地の申告をしているし、職員から申告書の提出も求められなかった。また、市街化区域農地について一般住宅用地又は非住宅用地と認定したことは、申告書の提出と無関係の誤った課税であるから、申告書の提出は過失相殺にならないと主張した。
東京都は、住宅地の所有者として申告義務を負っているのに義務を履行しなかったから過失相殺するのが相当と主張した。
▷裁判所の判断
① 国家賠償法上の違法性があるか
これは違法性があるとした。固定資産税は賦課決定制度であり、小規模住宅用地や市街化区域農地の所有者の申告要件で軽減が認められるものではない。建物の外観から、多数の住居からなる居住用建物であることがわかり小規模住宅用地に該当することが明らかであり、農地であることの判別が外観上困難である事情もなかった。つまり、職員が、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことがなく特例を適用せずに評価・認定したから違法性があるとした。
② 消滅時効は完成しているか
消滅時効は、平成26年10月頃に職員から連絡が来るまで何らの対応をしていないことから、同月以前に過誤納付による損害を知っていたものと認めることはできないとした。
③ 過失相殺はあるか
過失相殺として2割控除するとした。納税者の不申告が損害の発生及びその増大に一定程度寄与しているから過失相殺は考慮すべきであるが、申告したとしても、非住宅用地又は一般住宅用地と認定するような誤りが是正されず残った可能性もある。本件は東京都側の複数のミスが重なった結果というべきだから、納税者の過失を過大に評価することはできないとした。
* * *
このように、5年を超えた固定資産税の過誤納の還付は可能であるが、本ケースにおいて納税者が無申告でも過失相殺が2割であったのは、明らかに手抜きであったと疑われるようなミスが原因の過誤納であったからと考える。それでは、納税者が税理士の場合でも過失相殺2割が認められただろうか。
(了)
「固定資産をめぐる判例概説」は、毎月第4週に掲載されます。