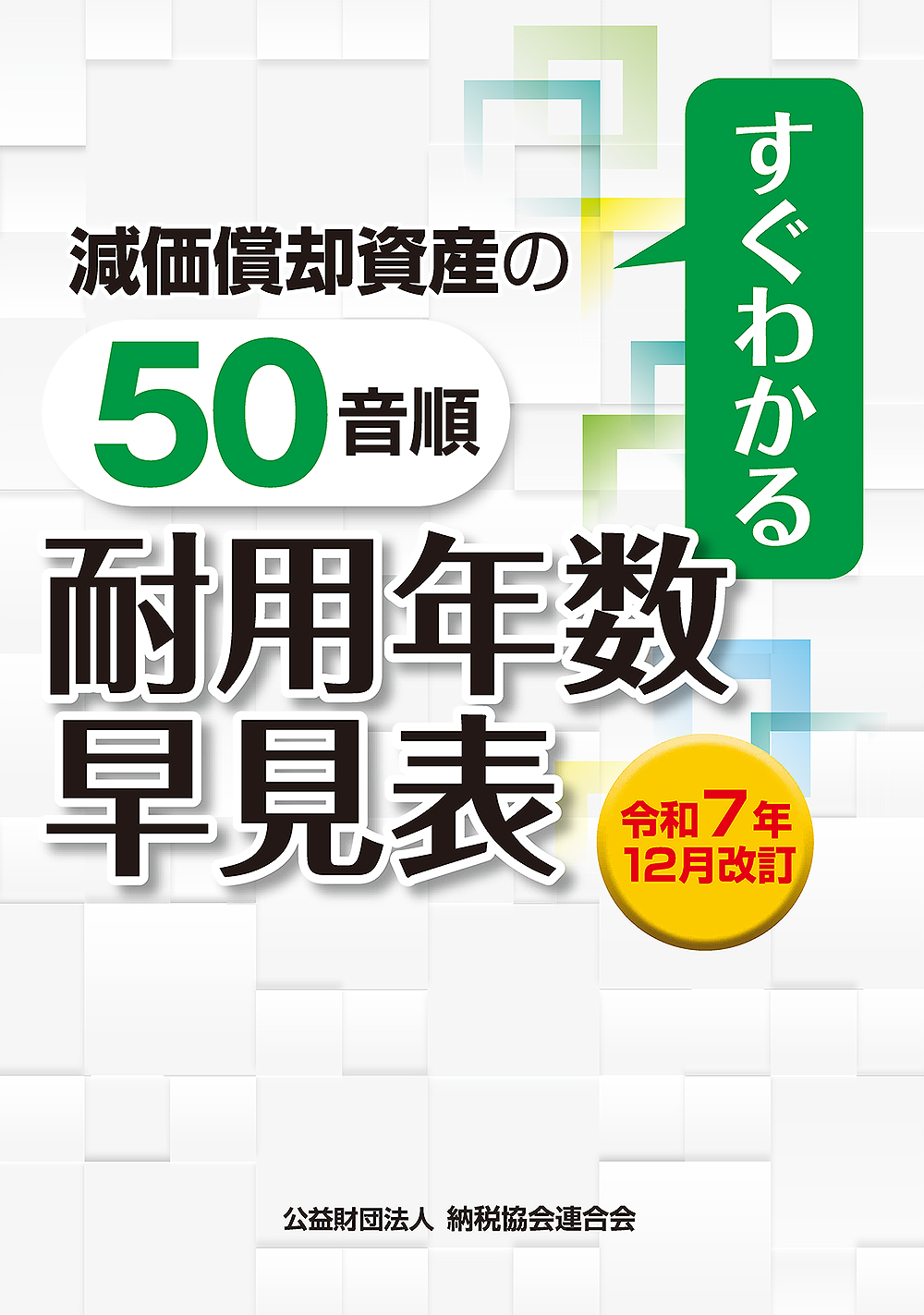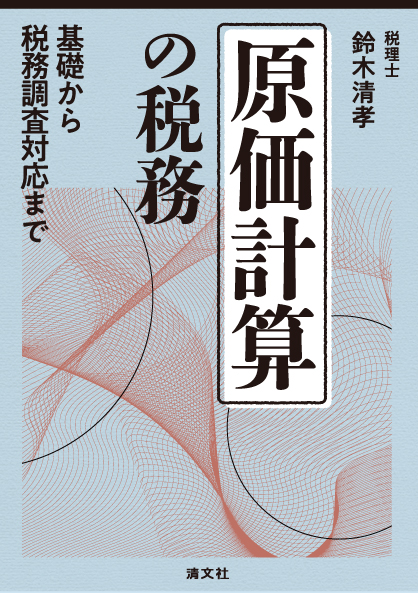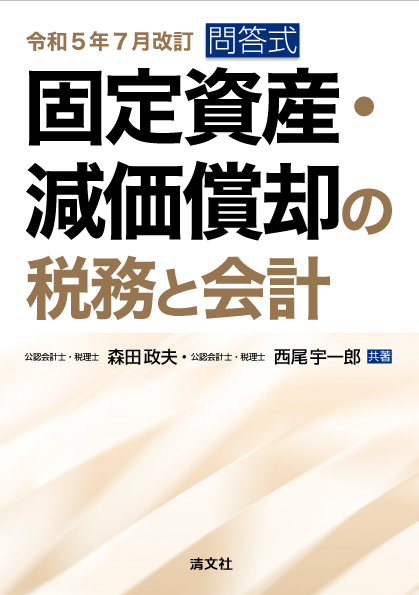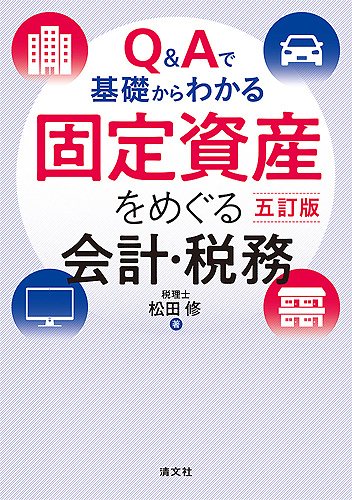固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第51回】
「食堂の冷房のために設置されたクーラーは簡単に取り外すことができ、7組の室内機と室外機が各々稼働又は休止しているから建物附属設備ではなく、単体の冷房用機器(器具及び備品)の集合体とされた事例」
税理士 菅野 真美
▷建物附属設備と器具及び備品
建物附属設備とは、暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備(法令13一)と法人税法上定義されている。この中の冷暖房設備であるが、耐用年数省令の別表によると冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)の耐用年数は13年であり、その他のものは15年とされている。
他方、工具、器具及び備品の中においても冷房用又は暖房用機器があり、この耐用年数は6年である。
冷暖房設備と冷房用又は暖房用機器の違いについて耐用年数通達では「冷却装置、冷風装置等が1つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当する(耐用年数通達2-2-4)とされている。
では、大きなスペースを冷房するためにいくつもの冷房装置があり、室内機は天吊り式であり、配管が天井内を伝わっているものは建物附属設備に該当するのか、それとも、器具及び備品となるのか。この件で争われた事案を検討する。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。