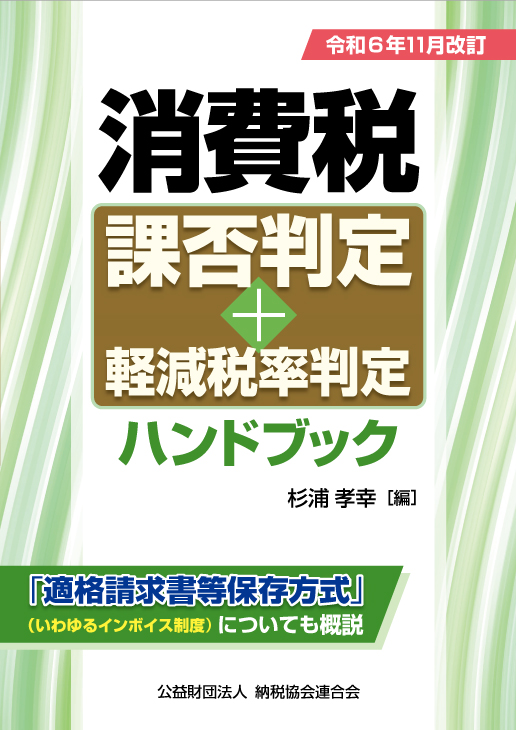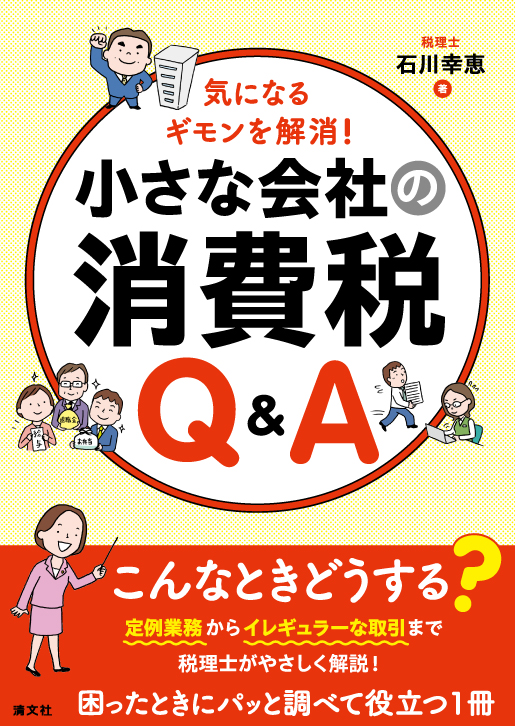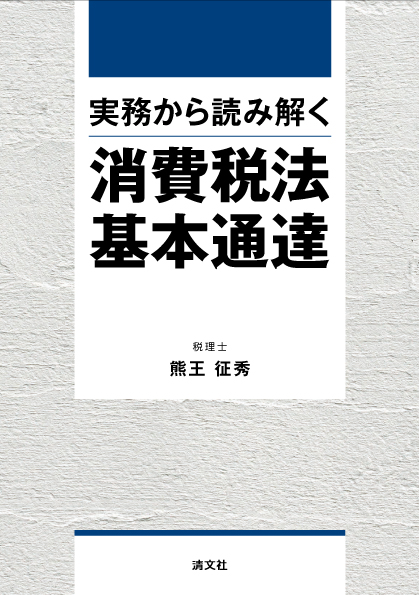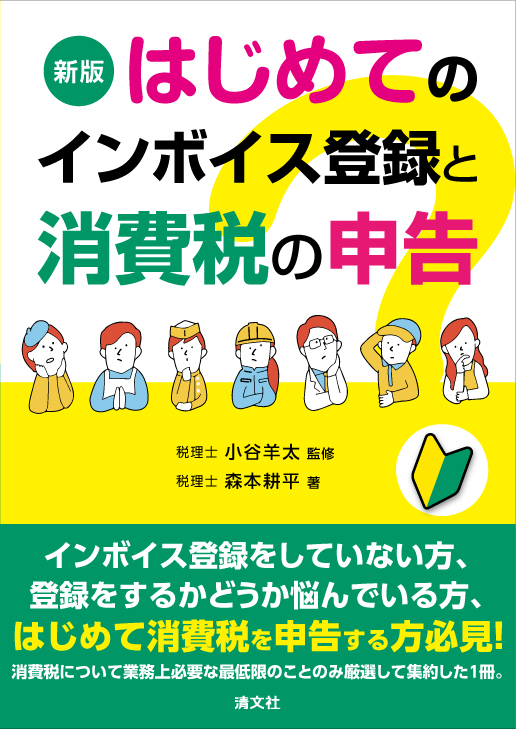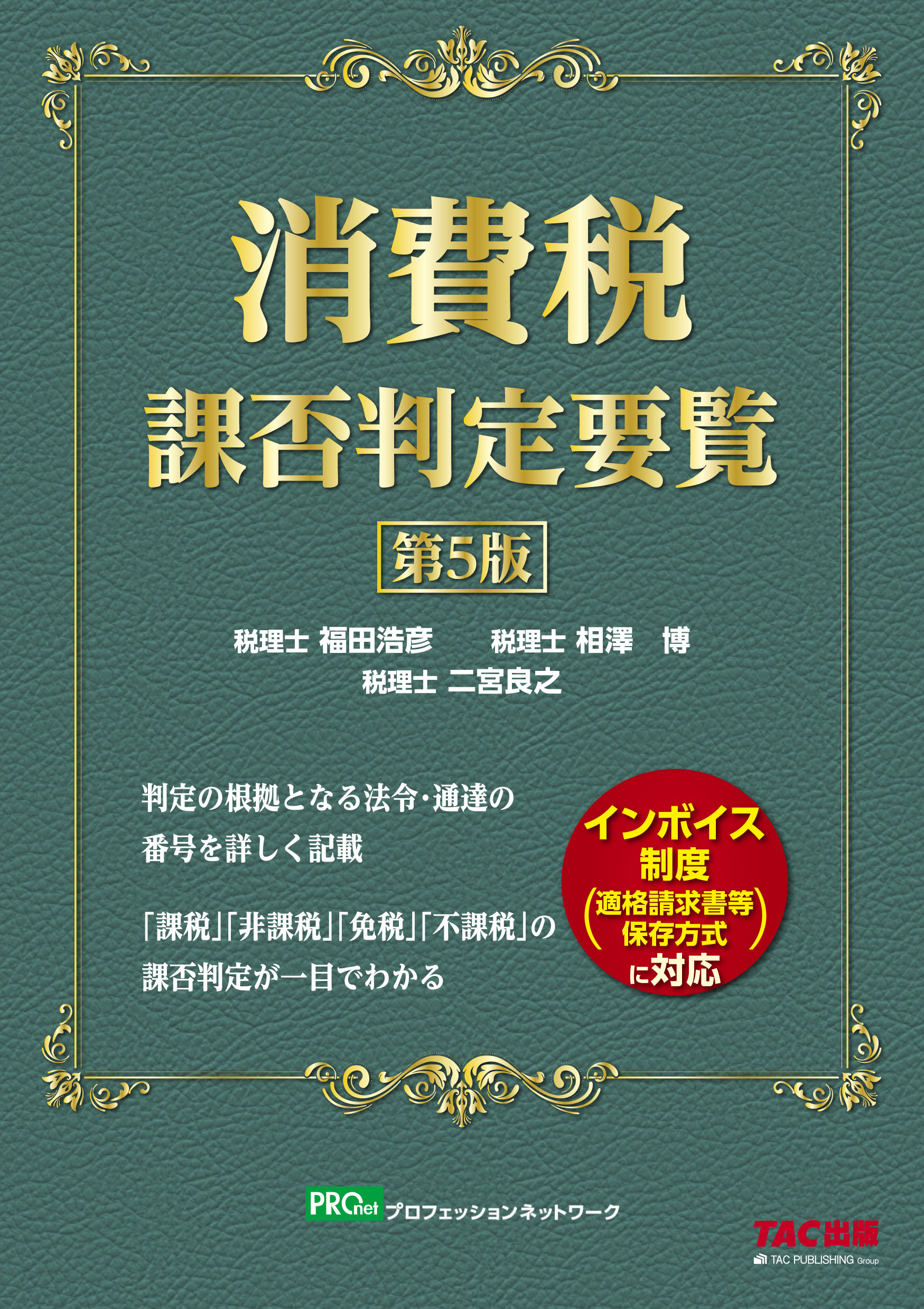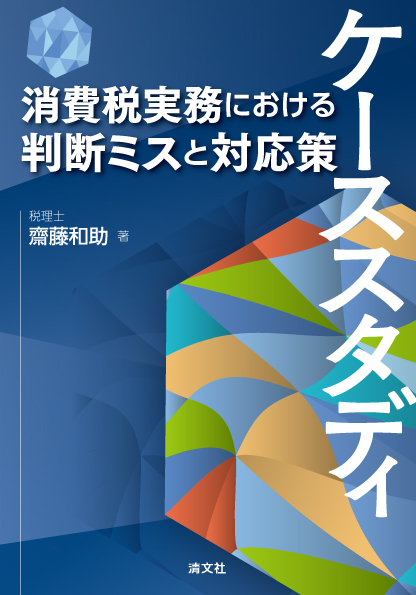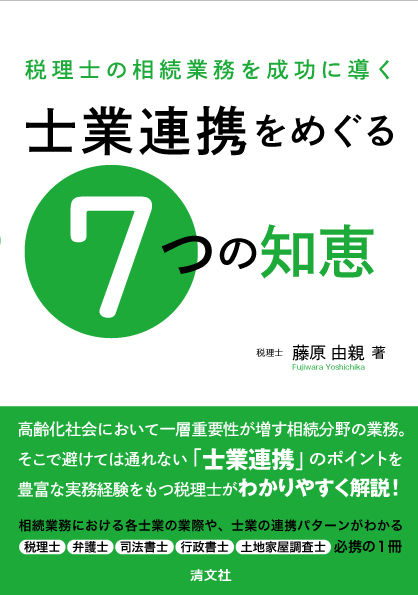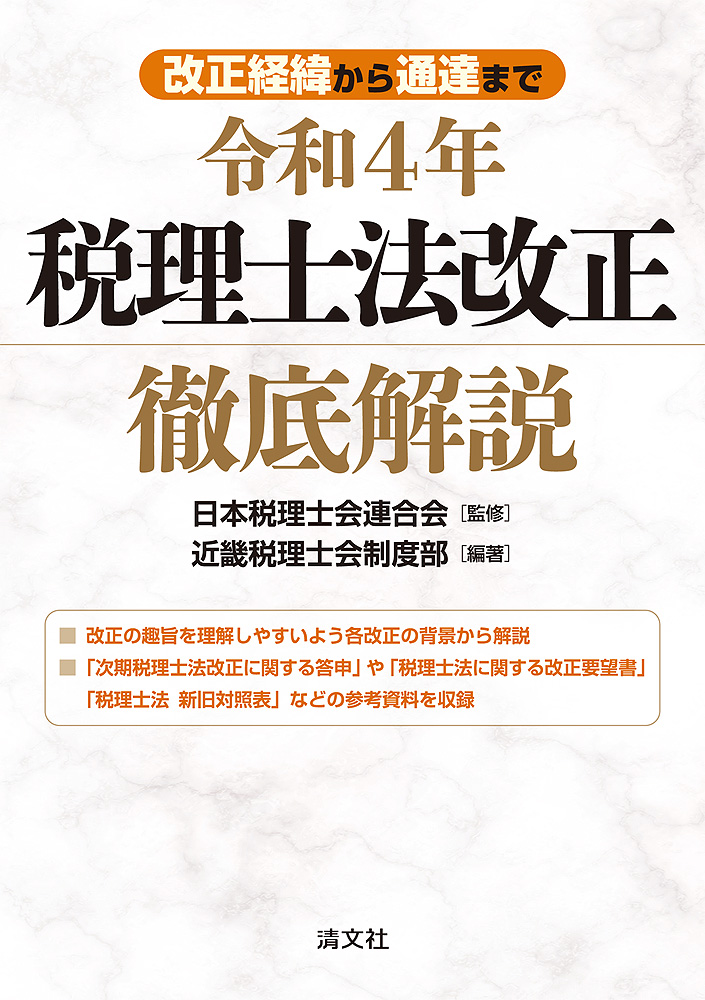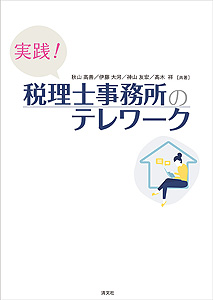税理士のための
〈リスクを回避する〉
顧問契約・委託契約Q&A
【第1回】
「顧問契約の範囲と助言義務」
弁護士・税理士
米倉 裕樹
弁護士・ 関西大学法科大学院教授
元氏 成保
弁護士・税理士
橋森 正樹
-連載開始に当たって-
税理士業務を行っていくに当たり、意図せずトラブルに巻きこまれるなどし、依頼者から損害賠償等を請求される法的リスクにさらされる機会はますます増加傾向にある。
そこで本連載では、税理士がこれらリスクを回避するために、依頼者と初期の段階で締結することとなる委任契約や顧問契約をどのように改善すべきか、その他留意点等につき、以後、全12回にわたってQ&A方式により解説を行う。
Q
顧問先であるA社は、第1期(平成16年4月1日~同17年3月31日)、第2期とも消費税免税事業者であったが、第3期において、売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額の方が多く、かつ第1期における課税売上高が1,000万円未満であったため、第2期末までに消費税課税事業者選択届出書を提出するように助言を受けていれば、約3,700万円の還付を受けることができるはずであったのに、私(税理士B)がそのような助言を怠ったとして、同額の損害賠償を請求すると言われている。
顧問契約は、概要、以下の内容にて締結している。
顧問料として月額2万円。決算報酬として年額合計30万円。
委嘱事務の範囲として①税理士法に定める業務及び会計業務、②前項の業務遂行のため必要とする関連業務。
定期訪問なし。税務上の問題につきましてはお電話にてお問い合わせください。問題解決のため、資料作成、調査等が必要となる場合には、別途料金が発生します。
A社からは、今回の課税事業者選択の件に関して、特段、問い合わせを受けていないが、A社からは「問い合わせや相談を受けなくても、委嘱事務の範囲として、今回の課税事業者選択に関する制度を説明し、または注意喚起すべき義務があった」と主張されている。
実際のところ、私(税理士B)は、A社から第3期に多額の広告宣伝費を支出する可能性があることは聞いてはいたが、具体的な金額については当時、認識していなかった。
仮に、裁判となった場合、どのような判決が見込まれるのか。
また今後、類似のトラブルを回避するには、何に注意すればよいか。
A
本件では、本件顧問契約における「委嘱事務の範囲」が問題となる。
委嘱事務の範囲を確定するに当たり考慮される事情としては、①顧問契約書の文言、②契約締結に至るまでの経緯、③報酬金額の多寡、④契約締結後の実際の役務提供内容等が挙げられる。
類似の事案が問題となった東京地裁平成20年11月17日判決においても上記事情を考慮した上、以下のとおり、顧問税理士の責任を否定した。
本件契約書には「定期訪問なし。税務上の問題につきましては、お電話にてお問い合わせください。」と記載されているところ、この文言は、本件契約は、税理士が顧客を定期訪問せず、顧客から税務相談があった場合には電話で対応するという内容のものであるから、税理士としては、顧客から相談がない限り、助言ないしそのための情報収集をすることはないことが定められているものと解するのが素直である(註:上記①顧問契約書の文言)。
平成17年7月ころ、税理士が顧客に対し、月次訪問監査あり、担当者有り(2名体制)、報酬月額10万円という案を提示したのに対し、顧客は報酬が高すぎると言って断り、次に税理士は、同年秋ころ、月次訪問監査あり、担当者有り(1名体制)、報酬月額5万円という案を提示したがこれも断り、そこで、税理士は同年12月末ころ、月次の訪問なし、税務上の問題は電話で問い合わせをする、報酬月額2万円という内容の案を提示し、その内容で本件契約が締結されていることに照らすと、税理士は、税務顧問契約締結交渉において、報酬額を下げるに伴いその対応を明確に下げており、そのことを顧客も十分に理解していたはずであり、最終的には、一般的な報酬の平均額より極めて低額で本件契約を締結するに至ったものである(註:上記②契約締結に至るまでの経緯)。
以上のような本件契約書に記載されている文言及び本件契約の締結経緯に照らすと、本件契約の内容としては、原則として、顧客が税理士に問い合わせ等をしない限り、税理士が積極的に調査して顧客に助言等をする義務を負うことはないと解するのが相当である。本件では問い合わせがあったことを認めるに足りる証拠はない。
もっとも、同裁判例では、問い合わせや相談を受けなくても、税理士が顧客に対し、本件制度について説明し、または注意喚起等を行う義務が生じる場合がありうるとし、具体的には、⑤顧客が税制を知らないことを税理士において認識している場合や容易に認識しえた場合、もしくは顧客にとって税制上有利となることを税理士が認識している場合や容易に認識しえた場合を挙げているが、同裁判例ではいずれにも該当しないと判断し、税理士の責任を否定している。
今後、類似のトラブルを回避するに当たっては、顧問契約書等において委嘱事項の範囲に明確化しておくとともに、委嘱範囲が争われる場合の上記事情を念頭に、日頃の業務経過、打ち合わせ内容等を業務日誌等において継続的に記録しておくことが重要といえる。
例えば、次のような規定を設けることで、顧問契約の範囲、助言義務の存否、顧問料の範囲内外をより明確化することができる。
依頼者から税務上のご質問(前項記載の委嘱事務の範囲内のものに限る)がなされた場合には、特に調査等を要しないご質問については顧問料の範囲内にて口頭、電話による回答を行い、回答するに当たり調査や資料作成等が必要なご質問については、別途、1時間当たり〇〇〇円(税別)のタイムチャージによる料金が発生します。なお、いずれの場合であっても、ご質問ない限り、当方から積極的に調査や助言等を行うことはございません。
ただし、このような規定を設けても、上記⑤に該当する事情が存在する場合には責任を問われることはありえるため注意が必要である。
(了)
「税理士のための〈リスクを回避する〉顧問契約・委託契約Q&A」は、毎月第2週に掲載されます。