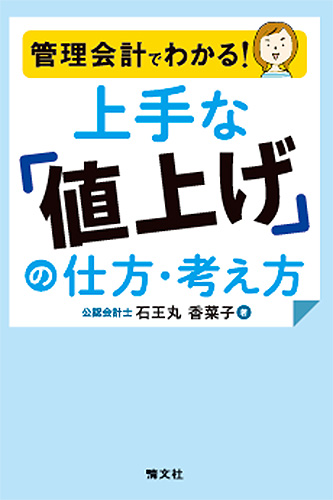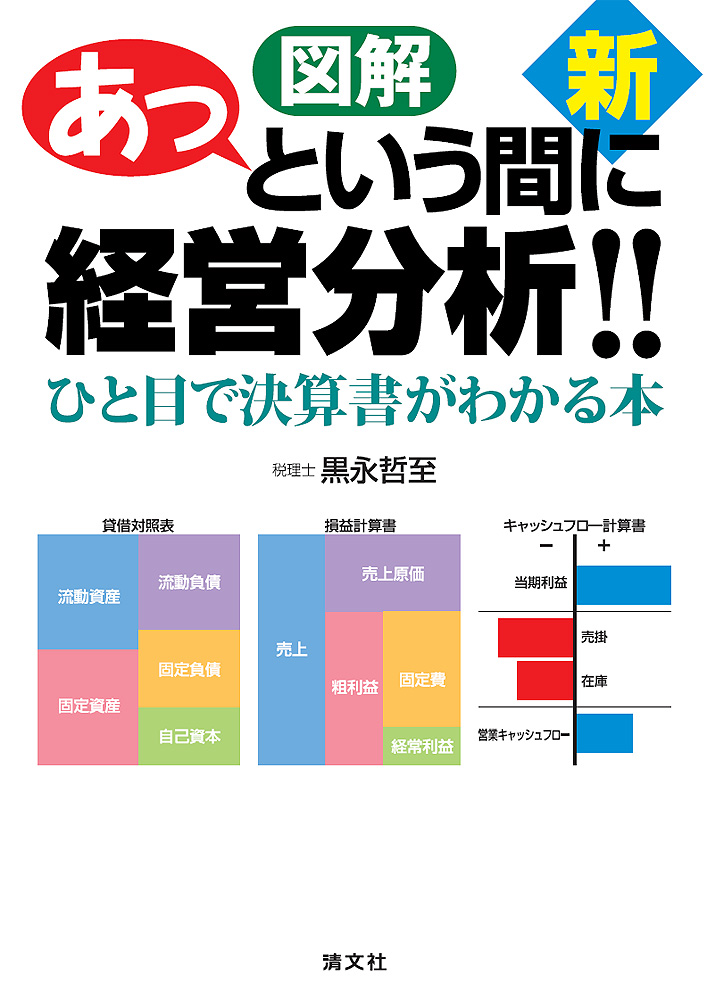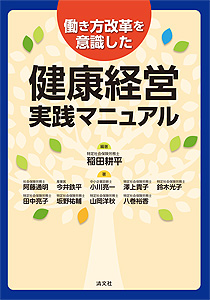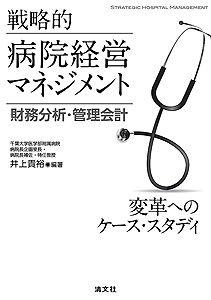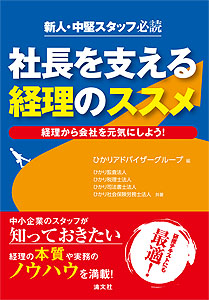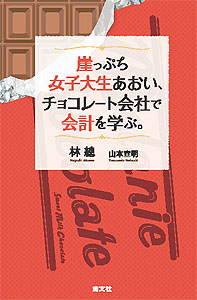林總の
管理会計[超]入門講座
【第15回】
「個別原価計算への誤解」
公認会計士 林 總
特定の製品・作業に対する集計方式ではない
林 製品別計算の最後が個別原価計算だ。何度も繰り返してきたように、製品別に原価を集計できるのは個別原価計算しかない。
それでは、原価計算基準(以下、基準)がどのように個別原価計算を考えているか、じっくり見ていくことにしよう。
まず基準には、
個別原価計算は、種類を異にする製品を個別的に生産する生産形態に適用する。個別原価計算にあっては、特定製造指図書について個別的に直接費および間接費を集計し、製品原価は、これを当該指図書に含まれる製品の生産完了時に算定する。
林 と書かれていて、その適用例として
経営の目的とする製品の生産に際してのみでなく、自家用の建物、機械、工具等の製作又は修繕、試験研究、試作、仕損品の補修、仕損による代品の製作等に際しても、これを特定指図書を発行して行なう場合は、個別原価計算の方法によってその原価を算定する。
林 とある。君に、イメージがつかめるかな。
Q そうですね。例えば大きな船を造るとか、建物を建設するとかだったら、それ毎に原価を集計すればいいんですよね。
でも、「修繕、試験研究、試作、仕損品の補修」となると、漠然としてイメージがつかめません。
林 そうだよね。修繕とか試験研究には形がないからね。でも、原価はかかっている。
Q 先生、もったいぶらないで教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。