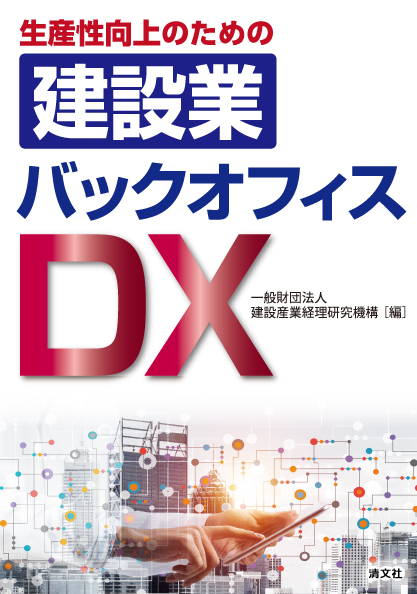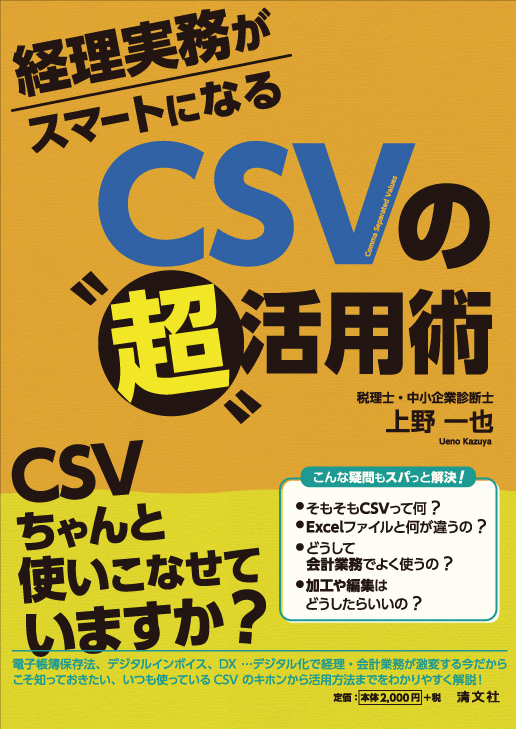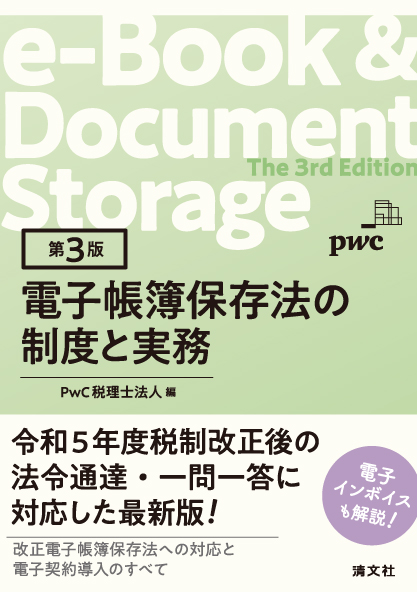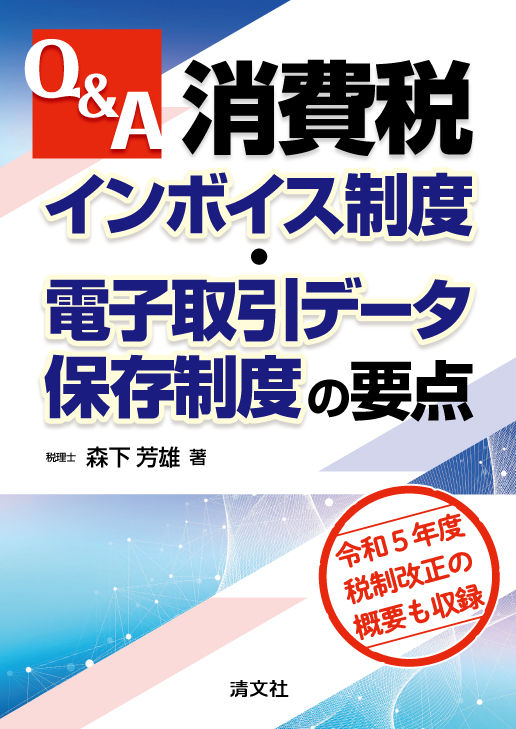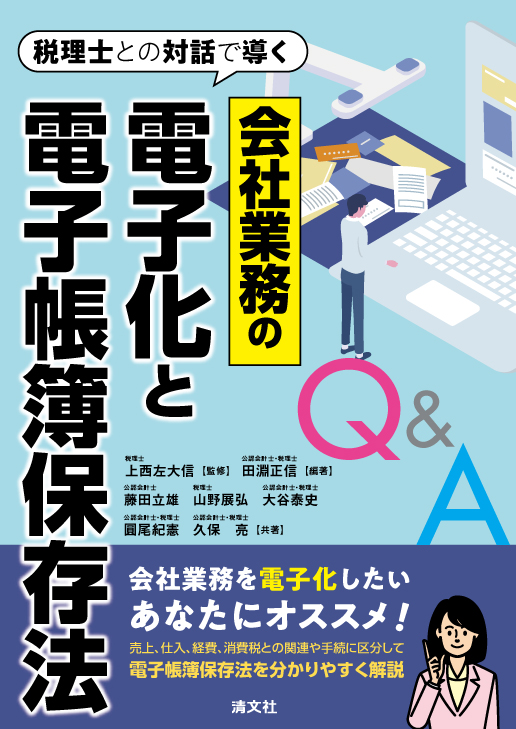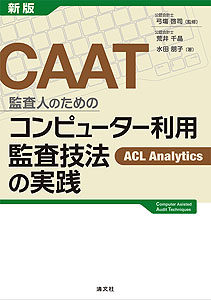〈IT会計士が教える〉
『情報システム』導入のヒント (!)
【第12回】
(最終回)
「導入ベンダーの賢い選び方、使い方」
公認会計士 五島 伸二
-連載の目的-
この連載は、「日本IT会計士連盟」に所属する者が有志により、企業がさまざまな形態の『情報システム』を導入する際に遭遇し抱え込んでしまう“ありがちな疑問・問題”について取り上げ、その解決の糸口を示すことで、企業がスムーズにそのシステムを導入・運営できるよう手助けすることを目的とする。
はじめに
基幹システムや会計システムはパッケージ製品を導入することが多い。わざわざ、企業独自で新規開発することは少なくなってきた。
そのため、基幹システムや会計システムの導入に際しては、まずは導入するパッケージ製品を選択することになる。
しかし、忘れてならないのは、パッケージを選択すると同時に、そのパッケージの導入を支援する導入ベンダーも選択する必要があるということである。
パッケージ製品によっては、必ず製品ベンダーが販売し導入する形態(直接販売)を採る製品もあるが、多くの製品は、製品ベンダー以外のITベンダーが、製品ベンダーとパートナー契約を結び、その製品の販売と導入を行う形態(間接販売)を採っている。
▼とても重要な導入ベンダー選び▼
導入ベンダーは、その製品の導入に際して、ユーザー企業のプロジェクトメンバーに対するトレーニング、テスト環境の構築、製品とユーザー企業業務のフィット&ギャップ、ギャップを解消するソリューションの提案など、ユーザー企業側のプロジェクトを全面的に支援し、そのシステム導入プロジェクトを成功に導くために重要な役割を果たす。
したがって、どんなに良いパッケージ製品を選定できたとしても、導入ベンダーの選択を間違えると、スムーズなシステム導入が実現できないことになる。
場合によっては、導入ベンダーの力不足で導入プロジェクト自体が頓挫することもありえるのである。
それくらい、導入ベンダーの役割は重要といえよう。
基幹システムや会計システムの導入というと、どうしても製品選択に重点がおかれがちであるが、今回は、導入ベンダーの選択に焦点を絞って、いくつかの切り口でそのポイントを解説する。
▼なにはともあれ製品知識▼
導入ベンダー選定にあたっては、まずは、どれだけそのパッケージ製品に精通しているかという観点が重要となる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。