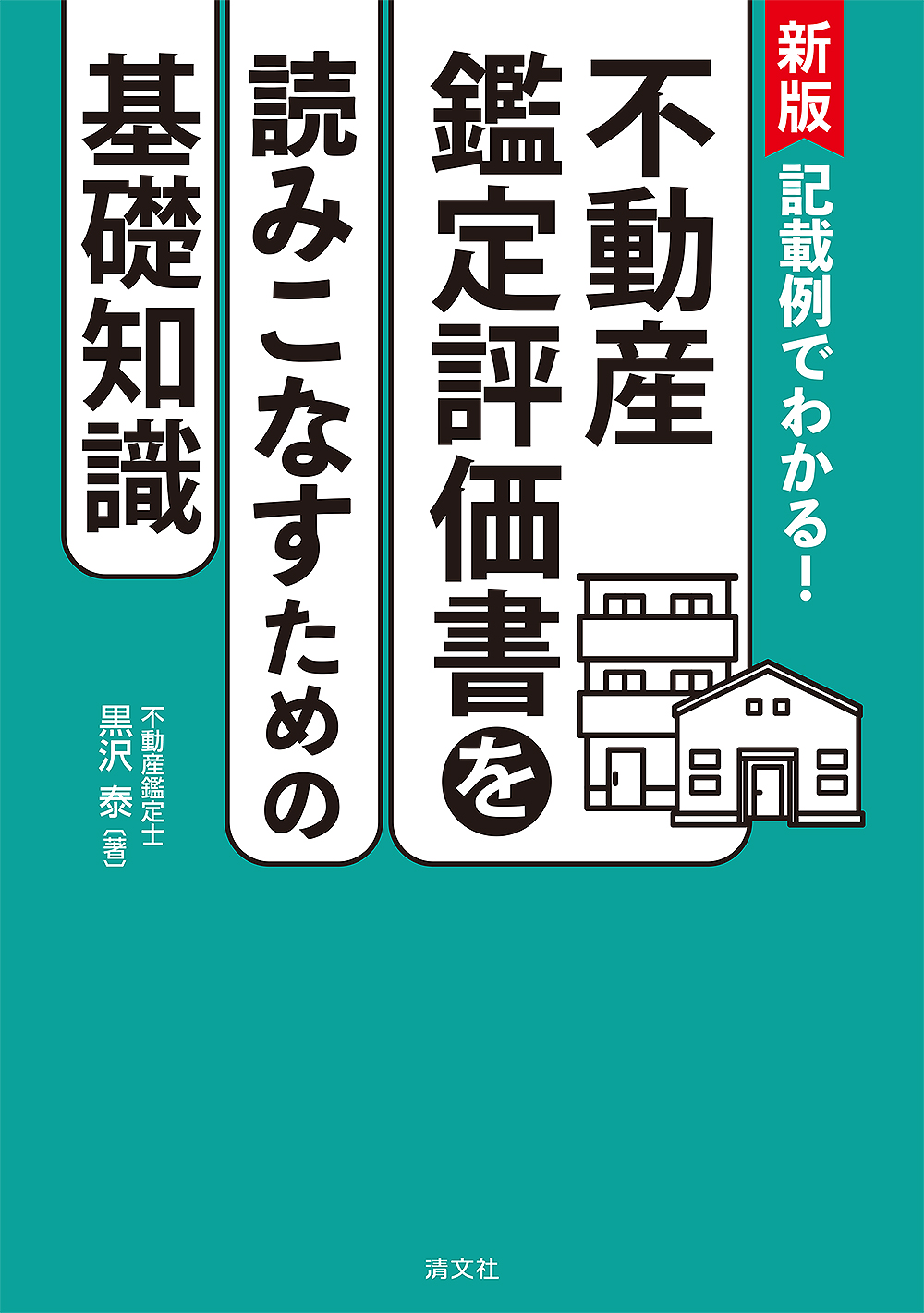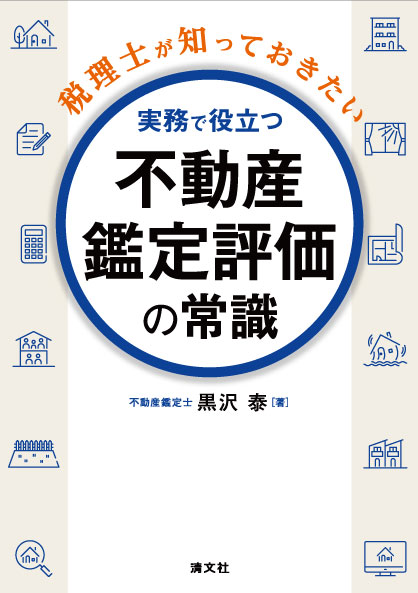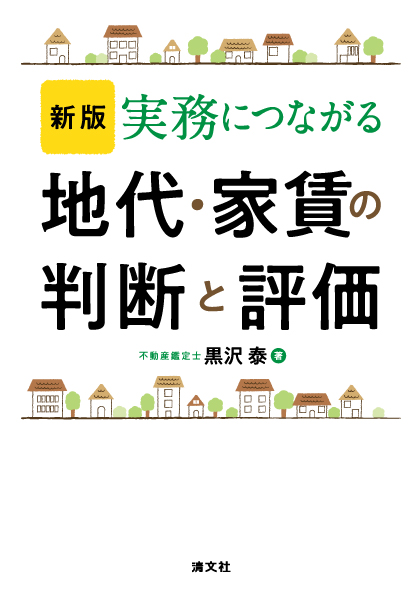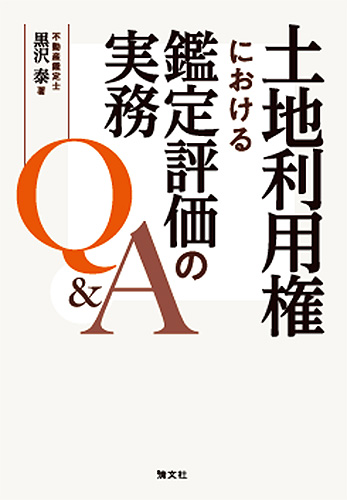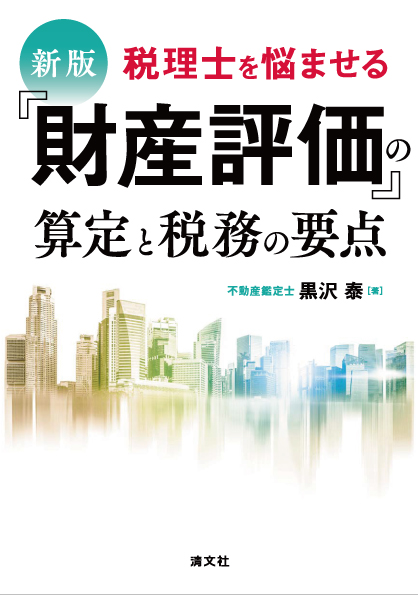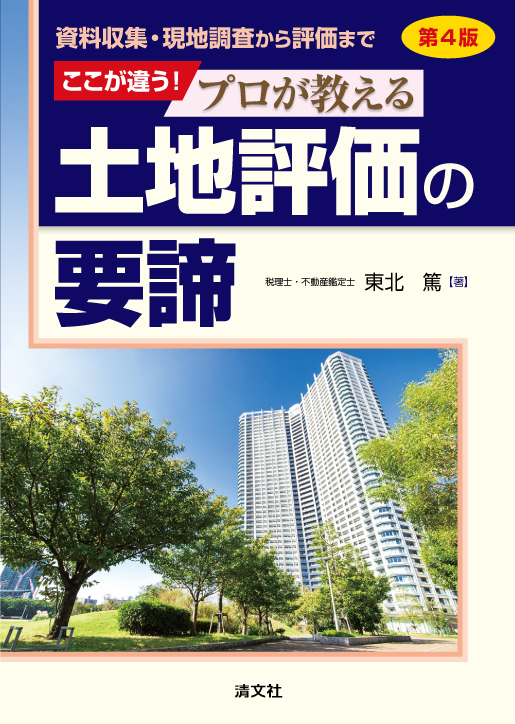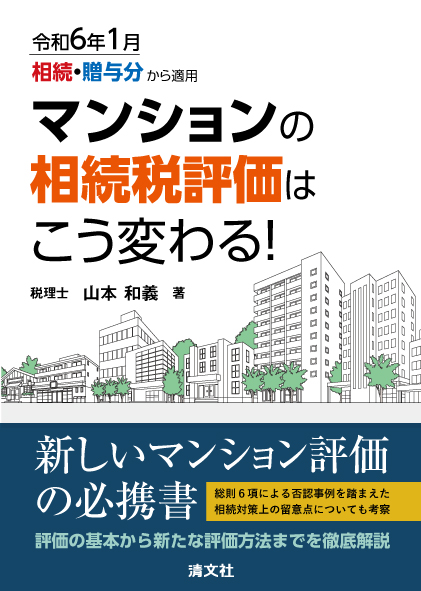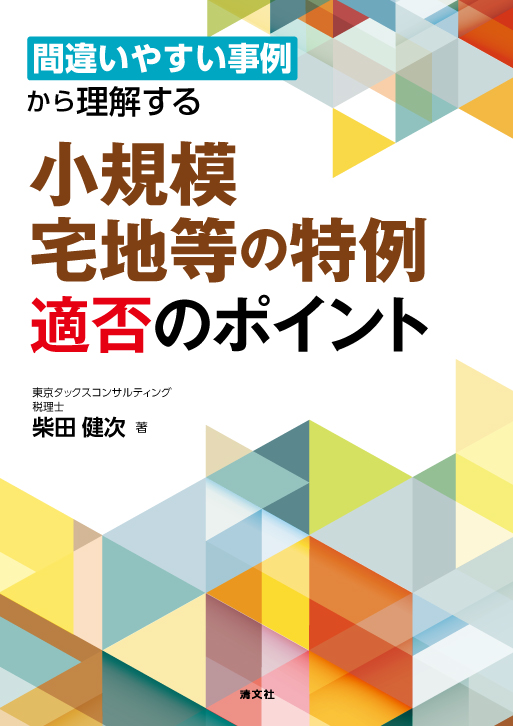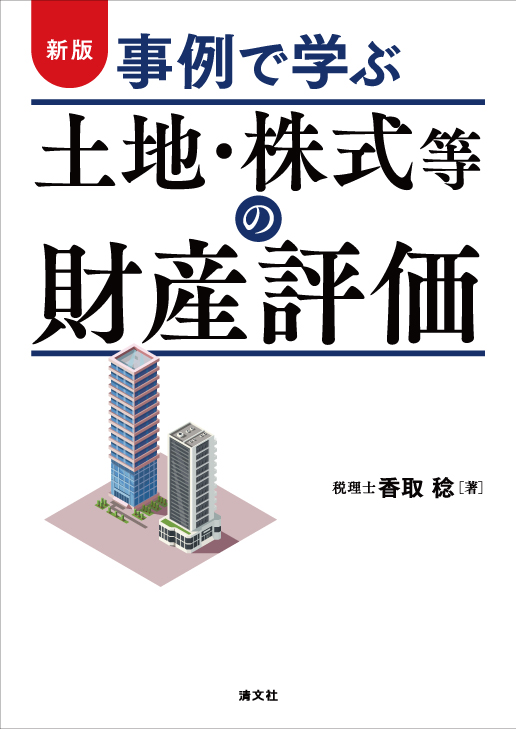税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第57回】
「不動産の鑑定評価に潜む「人間的要素」」
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
今回は、前回までの連載の内容とは趣きを変え、不動産の鑑定評価という行為には、自然的要素だけでなく人間的要素も大いに含まれているということを、不動産鑑定評価基準の起草者の言を引用しつつ改めて振り返ってみます。
これにより、筆者は、課税の公平性という観点から画一的な評価基準を設けている相続税の財産評価や固定資産税の評価と、不動産の経済価値の追究に当たり様々な判断要素の介入を避けて通ることのできない鑑定評価との本質的な相違を読み取ることができるものと考えています。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。