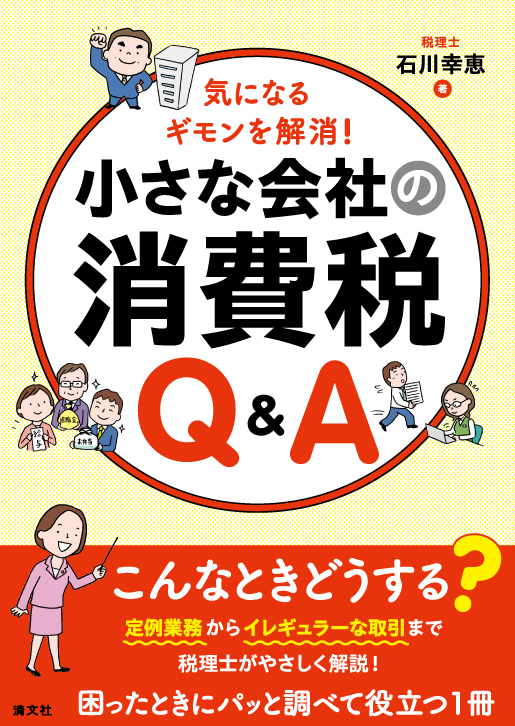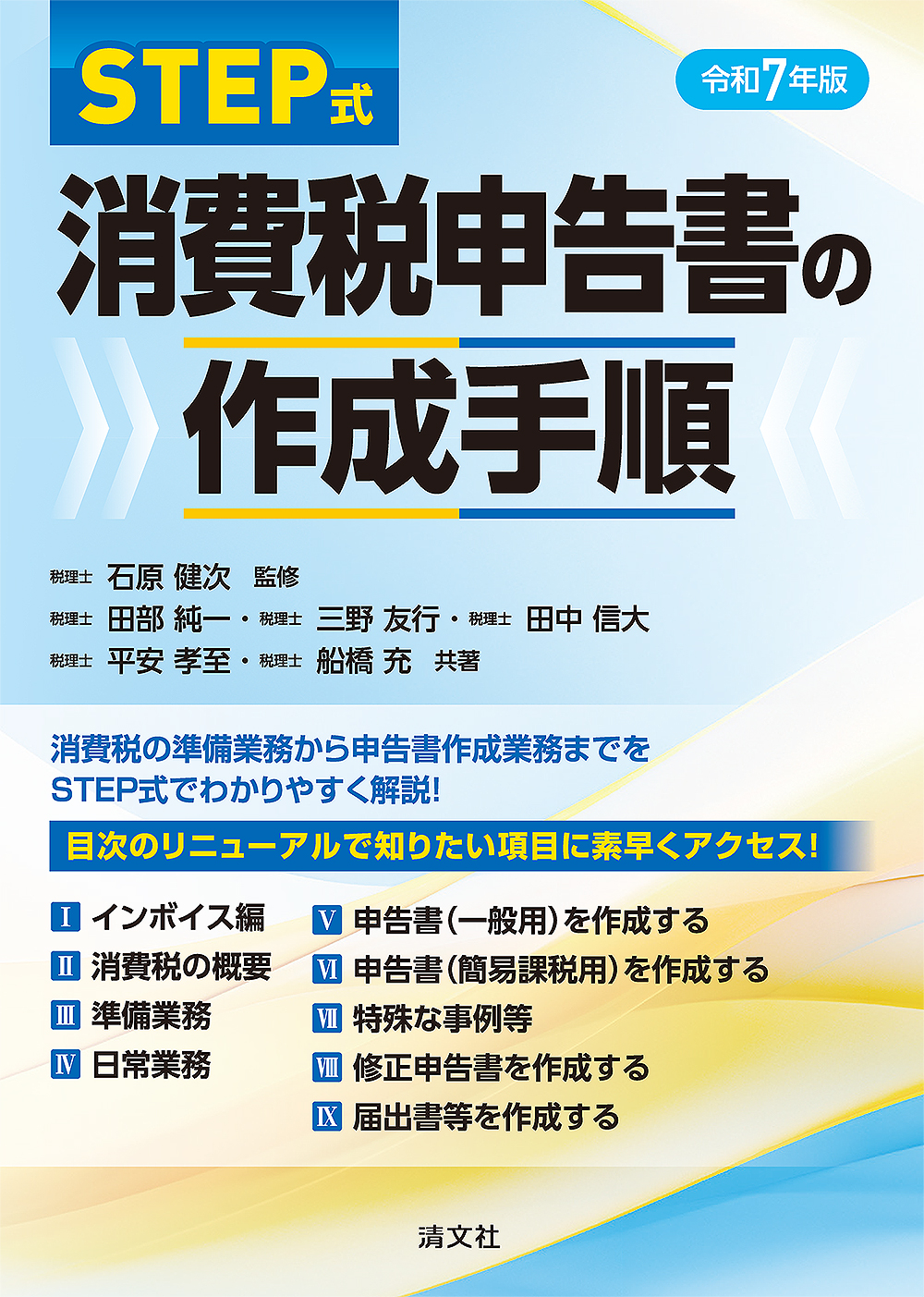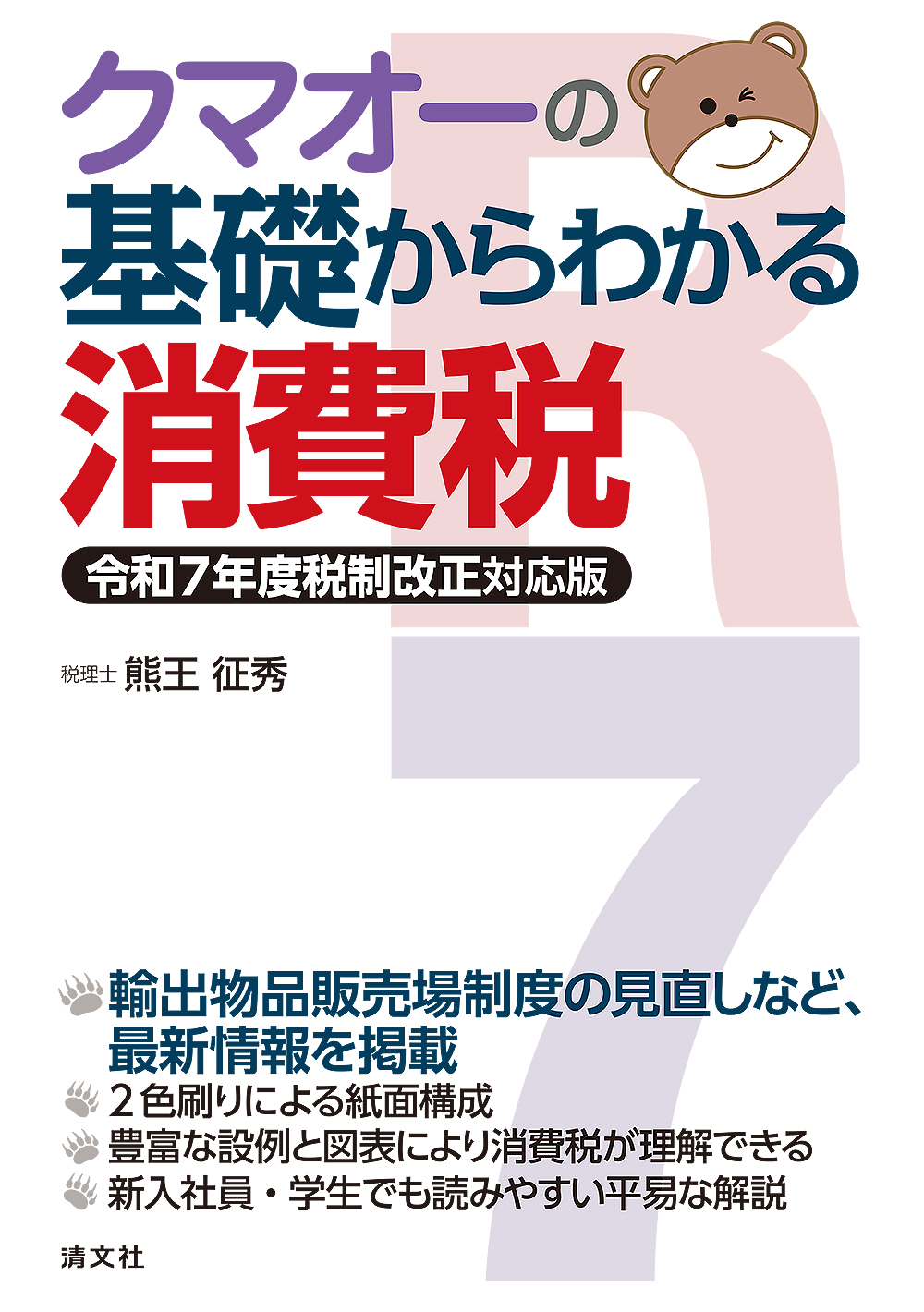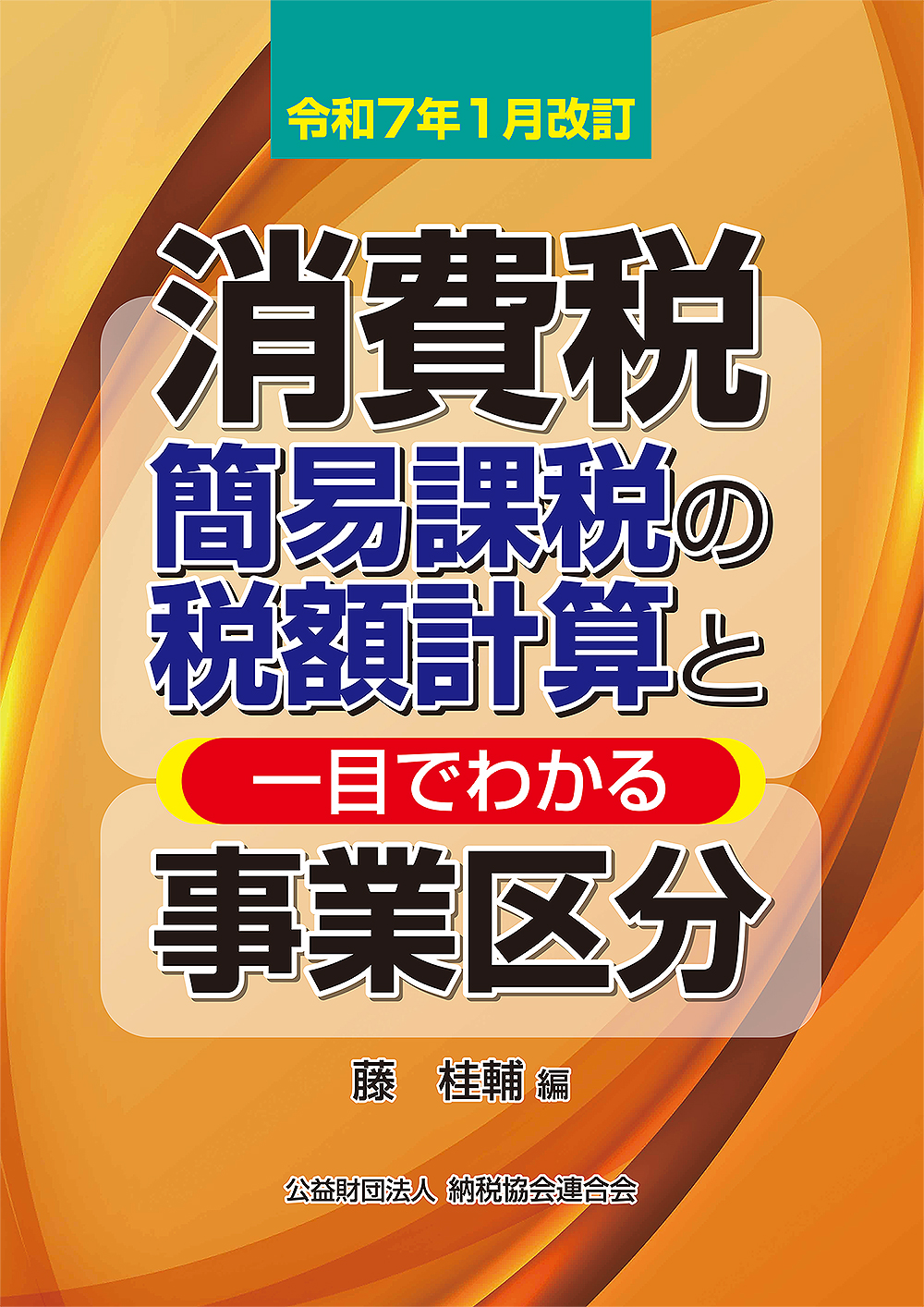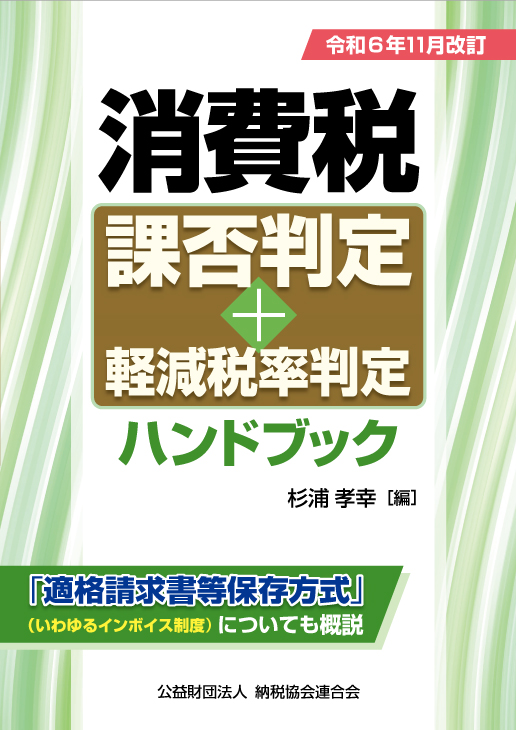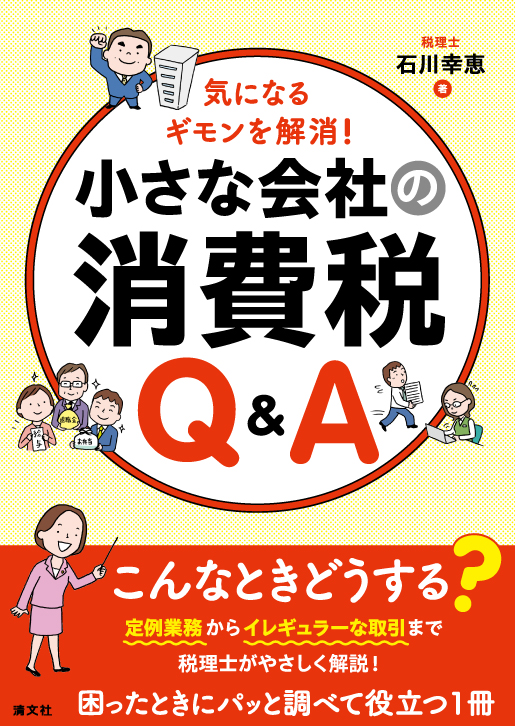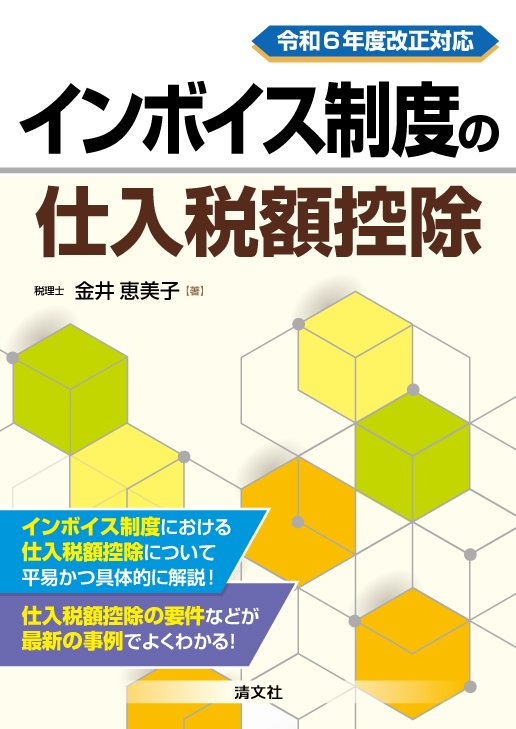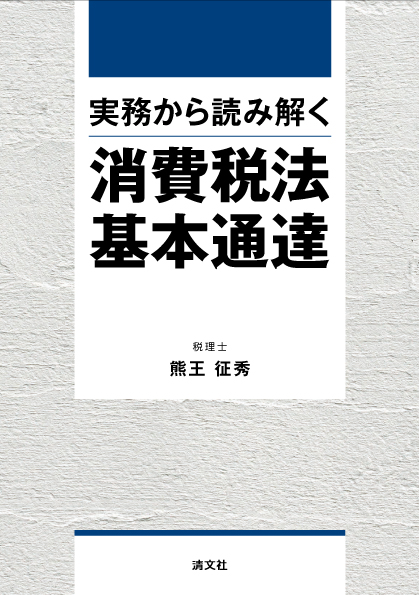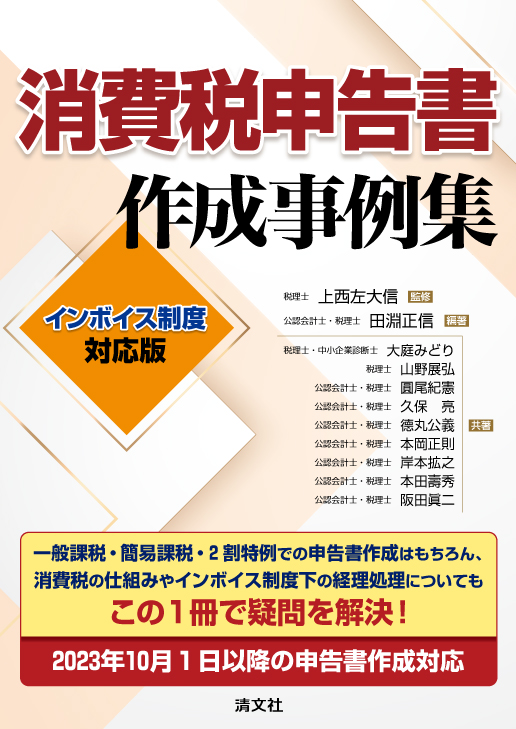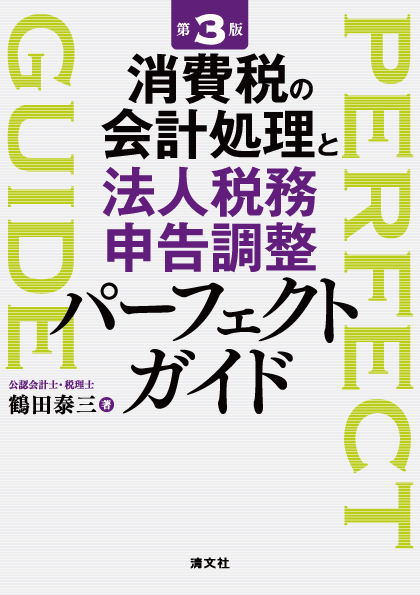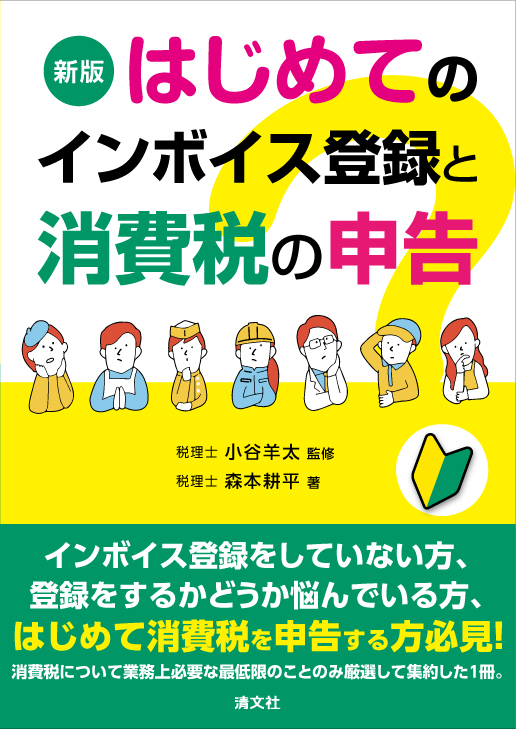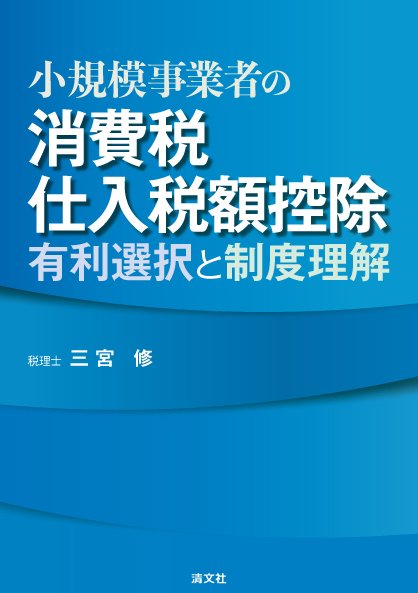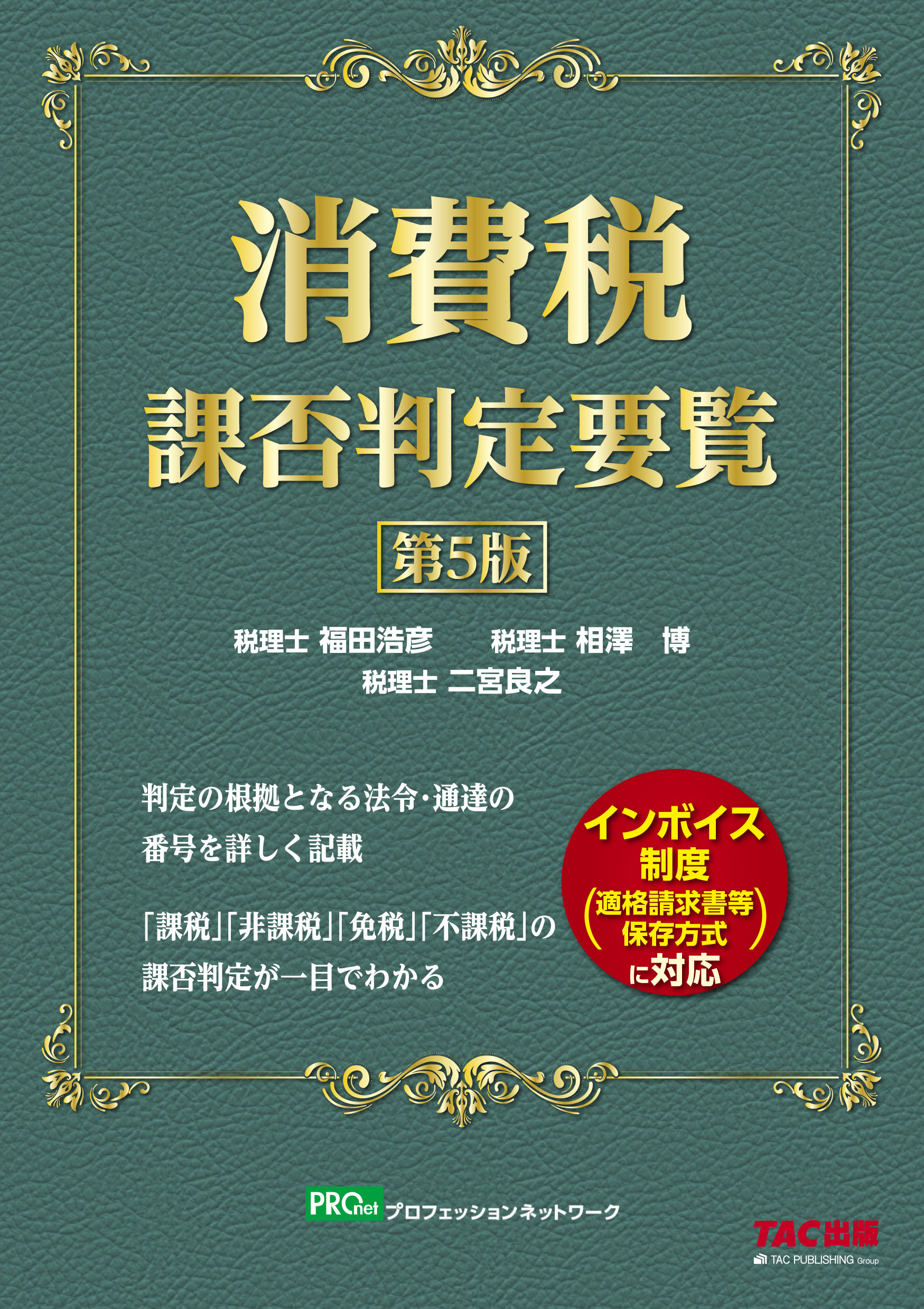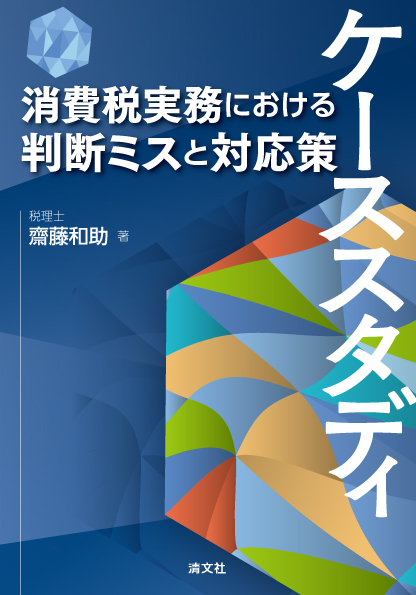〔疑問点を紐解く〕
インボイス制度Q&A
【第1回】
「課税事業者が適格請求書発行事業者登録をする判断ポイント」
税理士 石川 幸恵
【Q】
私は飲食店を経営しています。開業当初の一定期間を除いて消費税の課税事業者です。令和5年10月1日を含む課税期間も消費税の課税事業者であることが既に確定しています。
プライベートで来店されるお客様が多いですが、接待、職場の親睦会などビジネスで利用するお客様もいらっしゃいます。ビジネス利用のお客様からは「(経費精算するので)領収書をください」と言われます。私たちのようなお店は、適格請求書発行事業者の登録をすべきなのでしょうか。その判断のポイントを教えてください。
※本文中に特に記載がない限り、法人・個人事業者共通です。
〔ポイント〕
(1) 適格請求書発行事業者か否かで売上先から選別される恐れがある。
(2) 適格請求書発行事業者の登録申請、領収書の記載事項の見直し等の準備が必要。
(3) 登録事項が国税庁のホームページに公開される。
(4) 登録するかしないかは任意である。
* * *
【A】
(1) 適格請求書発行事業者か否かで売上先から選別される恐れ
① 適格請求書等保存方式への変更
令和5年10月1日から仕入税額控除の要件が「適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)」に変わります。【Q】のように飲食店をビジネスで利用したお客様は、飲食代に含まれる消費税額等について仕入税額控除をするため、適格請求書等に該当する領収書の交付を求めると思われます。
② 適格請求書等を交付できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者のみ
適格請求書等は税務署長に登録を受けた適格請求書発行事業者にしか交付できません。課税事業者であっても登録を受けない限り、適格請求書等は交付できないのです(インボイスQ&A問1)。
【Q】のような飲食代は比較的少額と考えられますが、より高額な仕入や外注の取引先の選定にあたっては、仕入税額控除ができない取引先(一定の経過措置あり。インボイスQ&A問110)よりも、適格請求書発行事業者である取引先が優先される可能性は否定できません(※)。
(※) 適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者に対して、転嫁拒否等をすることは、独占禁止法や下請法の規制対象となる恐れがあります。
【参考】 公正取引委員会ホームページ
(2) 適格請求書発行事業者の登録申請、領収書の記載事項の見直し等準備が必要
① 登録の申請
適格請求書等を交付しようとする課税事業者は納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります(インボイスQ&A問1)。手続きの詳細は次回以降で取り上げます。
② 領収書の記載事項の見直し
飲食店は適格簡易請求書という適格請求書よりも記載事項が簡易なものの交付が認められています(インボイスQ&A問25)が、現在の区分記載請求書等よりも記載事項が増えます。記載事項は以下のとおりです。なお、下線部分が新たに追加されます(インボイスQ&A問56)。
イ.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
ロ.課税資産の譲渡等を行った年月日
ハ.課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減税率対象資産の譲渡等である旨)
ニ.課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
ホ.税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
(3) 登録事項が国税庁のホームページに公開
① 公表の目的
適格請求書発行事業者の登録事項はインターネットを通じて国税庁のホームページにおいて公表されますので、特に個人事業主の方などで、公表に抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。公表の目的は、公表事項の閲覧を通じて、適格請求書等の作成者が適格請求書発行事業者に該当するかを確認するためです(インボイスQ&A問1、問20)。
② 公表事項
公表事項については次のとおりです(国外事業者に関するものは省略)。個人事業者については住所地を公表しないなど一定の配慮がされています。
イ.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
ロ.登録年月日
ハ.登録取消年月日、登録失効年月日
ニ.法人(人格のない社団を除く)については、本店又は主たる事務所の所在地
ホ.主たる屋号や主たる事務所の所在地(個人事業者等で公表の申出があった場合)
主たる屋号や主たる事務所の所在地を公表するにあたっての申出は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」によることとなっていますが、本稿執筆時点で、申出書の書式を含め申出の方法は明らかになっていません。また、適格請求書発行事業者の氏名に関して、旧姓や通称の使用の可否についても明らかになっていません。
インボイスQ&A(令和3年7月改訂)で、適格請求書発行事業者の氏名に関して、旧姓や通称を氏名として公表、又はこれらを氏名と併記して公表する方法が明らかになりました(インボイスQ&A問2)。
旧姓や通称の登録は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」によって行います。「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」の様式もインボイスQ&Aの改訂と同時に公表されました。
詳細は連載【第6回】以降で解説します。
〔追記:2021/8/17〕
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和3年7月改訂)」の公表に伴い、上記赤文字部分の追記を行いました。
(4) 登録するかしないかは任意
適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは任意です(インボイスQ&A問11)が、飲食店のような消費者が主たる売上先である事業者も登録することをお勧めします。上の(2)、(3)で示したような準備の手間や公開への抵抗感もありますが、ビジネス利用のお客様から適格請求書等を求められたときに交付できるメリットの方が大きいと思われます。
〔凡例〕
・インボイスQ&A・・・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和5年4月改訂)
(了)
「〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A」は、毎月第2週に掲載されます。