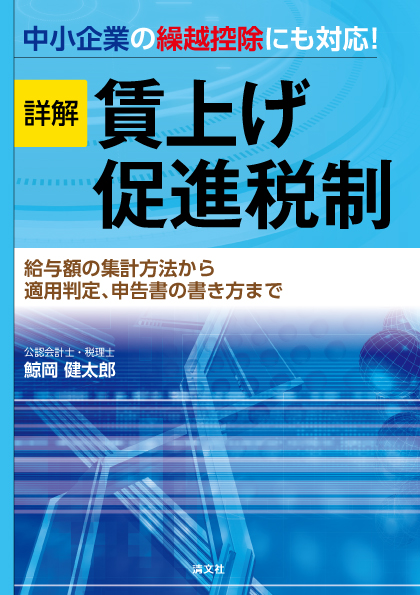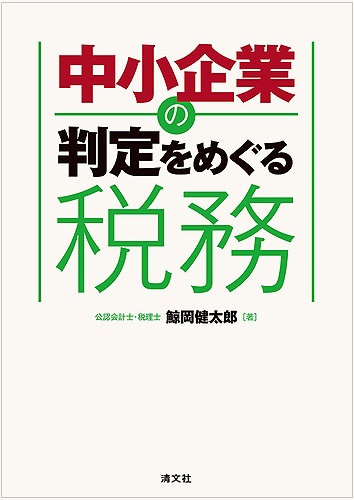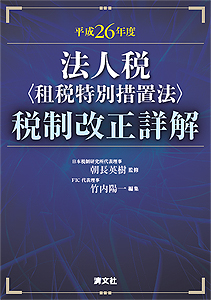《速報解説》
賃上げ促進税制・所得拡大促進税制の抜本改正について
~令和4年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
令和3年12月10日、与党(自由民主党及び公明党)より令和4年度税制改正大綱が公表された。
岸田内閣は、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期しつつ、未来を見据え、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした、新しい資本主義の実現に取り組むこととしている。
これに関連したところでは、令和3年11月8日に公表された「新しい資本主義実現会議」緊急提言の中でも『民間企業において人的資本など未来への投資を強化させることで、中長期的に稼ぐ力を高め、その収益を賃上げ等の分配や更なる未来投資へ循環させることで持続的な成長を実現する。そして、現場で働く従業員や下請企業も含めて、広く関係者の幸せにつながる、多様なステークホルダーを重視した、持続可能な資本主義を構築していく。』と謳われているように、「分配」を通じたマルチステークホルダーへの配慮まで言及されている。
そのような背景をふまえ、今回の税制改正大綱においては「成長と分配の好循環の実現」が主要項目の第一に掲げられ、そのための第一の措置として積極的な賃上げ等を促すための措置が含まれている。これは、『成長と分配の好循環』の実現に向けて、長期的な視点に立って一人ひとりの積極的な賃上げを促すとともに、株主だけでなく従業員、取引先などの多様なステークホルダーへの還元を後押しする観点から措置されるものである。
そこで本稿では、令和4年度税制改正大綱において示された、賃上げ促進税制(所得拡大促進税制)の改正項目について紹介する。なお、文中の意見にわたる記述は筆者の私見であり、所属する団体・組織の公式見解ではないことを申し添える。
2 「賃上げ促進税制」への再改組(大企業向け)
大企業(中小企業者等以外の企業)向けの税制については、令和3年度税制改正において「賃上げ・投資促進税制」から「人材確保等促進税制」に抜本改組されたばかりであるが、わずか1年で再び抜本的に改組されることとなった。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。