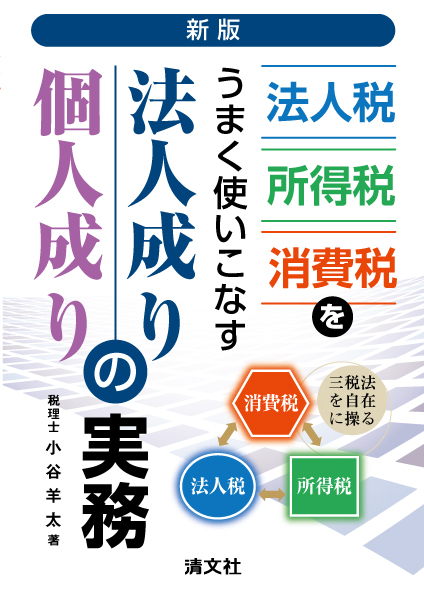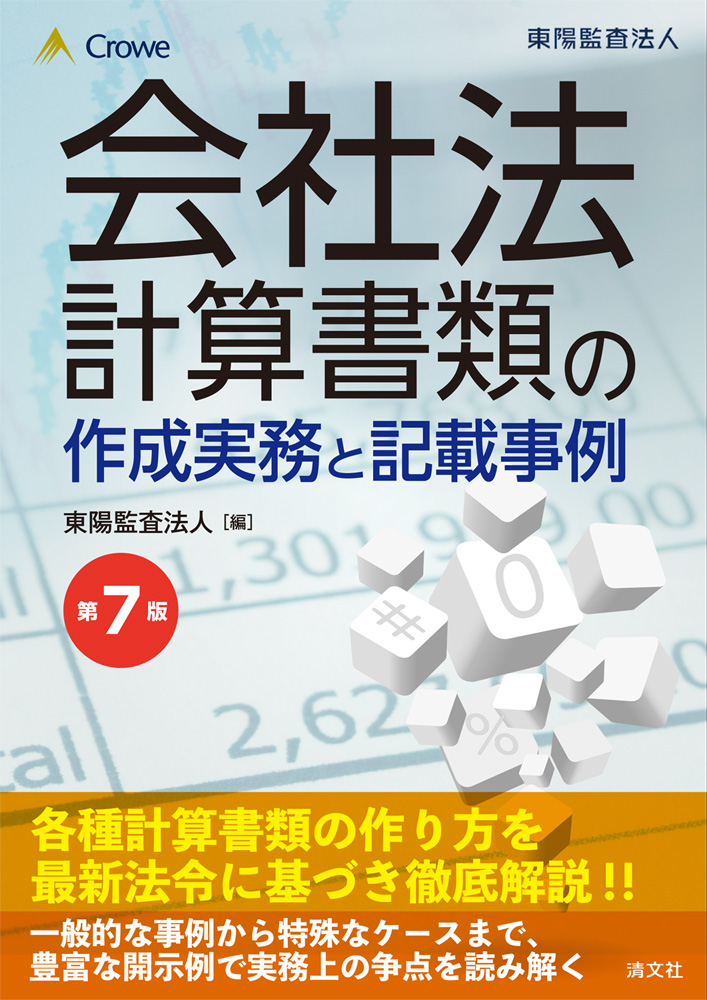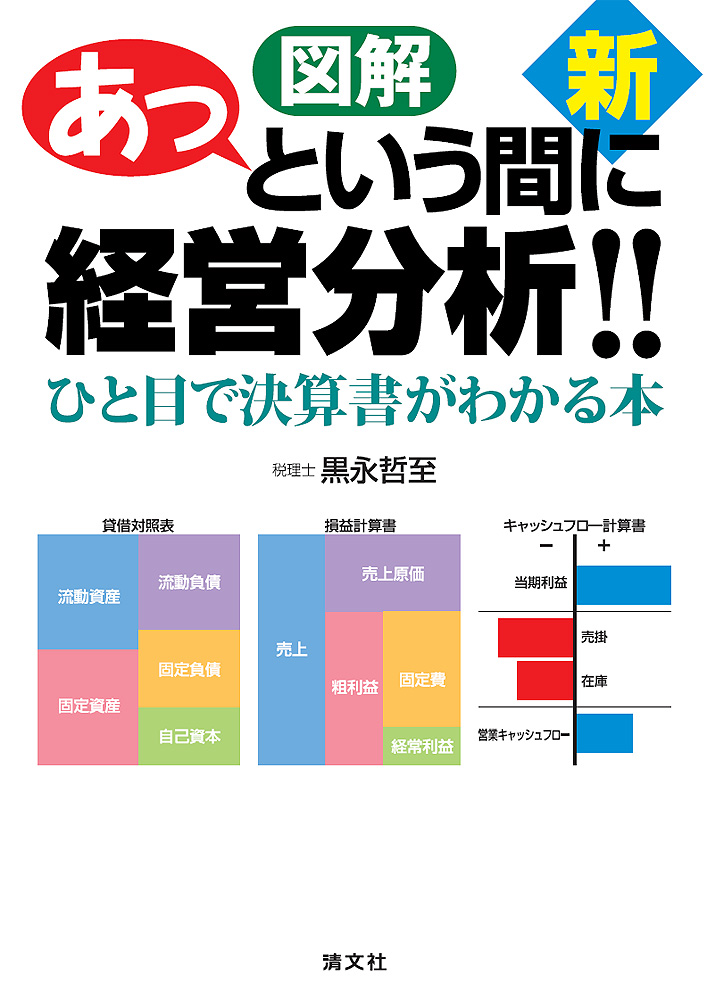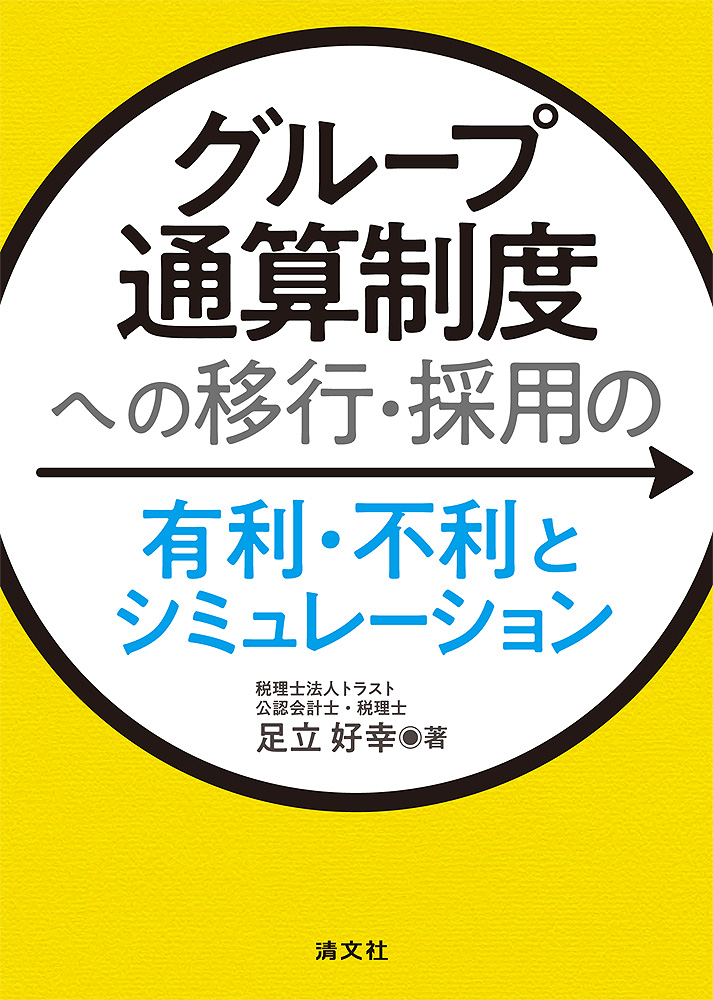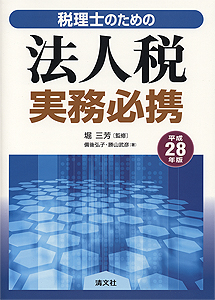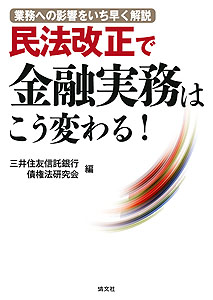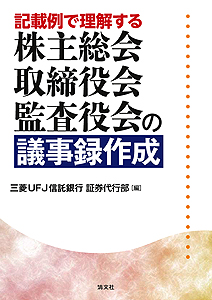Ⅶ 「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等
1 グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い
2023年3月28日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)(以下、「改正法人税法」という)が成立し、国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税のルールのうち所得合算ルール(IIR)に係る取扱いが定められ、2024年4月1日以後開始する対象会計年度から適用されている。
改正法人税法では、一定の要件を満たす多国籍企業グループ等の国別の利益に対して最低15%の法人税を負担させ、当該課税の源泉となる純所得(利益)が生じる企業と納税義務が生じる企業が相違する。
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等及び税効果会計についてどのように取り扱うかが明らかでなかったことから、2024年3月22日に、ASBJより以下の会計基準の改正が公表された。
- 実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(以下、「課税取扱い」という)
- 補足文書「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等に関する見積りについて」(以下、「補足文書」という)
補足文書は、課税取扱いを適用する場合に実務に資するための情報を適用することを目的としている。
(1) 連結財務諸表及び個別財務諸表における取扱い
① 会計処理
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、対象会計年度(※)となる連結会計年度及び事業年度において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積り計上する(課税取扱い6)。
(※) 「対象会計年度」とは、法人税法第15条の2に規定する多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表(法人税法82①)の作成に係る期間をいう(課税取扱い5)。
② 特に見積りが困難な場合
(ⅰ) 適用初年度
適用初年度は特に見積りが困難な状況が考えられるが、「財務諸表作成時に入手可能な情報」に基づき見積ることとなる。
《適用初年度において情報の入手が困難な場合の会計上の見積りの例》
グローバル・ミニマム課税制度の適用初年度については、通常の法人税等とは異なるグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を算定するための新たな調整項目の把握や、各構成会社等からの情報を入手する体制の構築等が必要となる。しかし、関連する法令等の公表からグローバル・ミニマム課税制度の適用開始までの期間が短く、従来情報を入手していない各構成会社等からの情報や国別報告事項等の必要な情報を適時かつ適切に入手する体制の構築等が困難な場合がある(補足文書11)。例えば、在外子会社A社の支店がA社とは異なる国にある場合に当該支店や、在外子会社B社に孫会社がある場合の当該孫会社について、情報を適時かつ適切に入手できない場合もあると考えられる。
グローバル・ミニマム課税制度の適用初年度では、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づく当該制度に係る法人税等の合理的な金額の見積りについて、例えば、以下のように限定的な情報に基づいて見積ることがあり得る(補足文書12)。なお、以下は例示であり、この方法に限られるものではない(補足文書13)。
(ア) 対象範囲の判定において、従来の連結財務諸表の作成にあたって入手していない国別報告事項に関する情報や恒久的施設等及び特殊な会社等からの情報を適時に入手することができない場合には、従来の連結財務諸表の作成にあたって入手している子会社等の情報のみに基づき国別実効税率を算定する等の方法により対象範囲の判定を行う。
(イ) 子会社等におけるグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の算定に際して、個別計算所得等の金額、調整後対象租税額、給与適用除外額及び有形資産適用除外額の算定において必要な情報について、従来の連結財務諸表の作成にあたって入手しておらず対象会計年度となる連結会計年度及び事業年度の決算時において適時に入手することができない場合には、従来の連結財務諸表の作成にあたって入手している子会社等の会計数値に基づき当該金額を見積る。
(ⅱ) 適用初年度の翌年度以降
適用初年度の翌年度以降は、適用初年度に比べればグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の申告に向けて情報を入手する体制がより強化され、実績値の把握等によって、入手可能となる情報が増加することがあると考えられる。しかし、グローバル・ミニマム課税制度においては、対象範囲の判定や個別計算所得等の金額等の算定にあたって必要な情報を適時かつ適切に入手することが困難な場合があると考えられる。このような場合には、適用初年度の翌年度以降においても、上記(ⅰ)の(ア)(イ)に示した例を参考とすることが考えられる(補足文書14)。
③ 見積金額と確定額の差額
上記①(又は②)により入手可能な情報に基づき見積もった金額と翌事業年度の見積金額又は確定額との間に差額が生じる場合がある。しかし、各事業年度において財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積もっている限り、当該差額は誤謬にはあたらず、当期の損益として処理する。
また、会計上の見積りの変更にあたって、当該差額に重要性がある場合には、会計上の見積りの変更注記(企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下、「遡及基準」という)18)を行う(課税取扱いBC11)。
(2) 四半期及び中間における取扱い
当面の間、当四半期連結会計期間及び当四半期会計期間並びに当中間連結会計期間及び当中間会計期間を含む対象会計年度に関するグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しないことができる(課税取扱い7)。
(3) 表示
貸借対照表及び損益計算書における表示は、以下のとおりである。
〔連結BS/個別BS〕
グローバル・ミニマム課税制度に係る未払法人税等は、以下のとおりBS上、表示する(課税取扱い8、BC15、BC16)。
・1年内:流動負債に「未払法人税等」で表示
・1年超:固定負債の区分に「長期未払法人税等」などの科目で表示
〔連結PL〕
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、「法人税、住民税及び事業税」等の科目で表示する(課税取扱い9)。
重要な場合は、当該金額を注記する(課税取扱い10)。
〔個別PL〕
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、
① 「法人税、住民税及び事業税」等の科目の次に「国際最低課税額に対する法人税等」の科目で表示するか、
② 「法人税、住民税及び事業税」等に含めて表示した上で、当該金額を注記する(課税取扱い11、財務諸表等規則95の5、会社計算規則93②)。
ただし、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の金額の重要性が乏しい場合は、「法人税、住民税及び事業税」等の科目に含めて表示し、注記は要しない(課税取扱い12)。
(4) 適用時期
2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する(課税取扱い14)。
四半期財務諸表及び中間財務諸表における注記(上記(2)参照)については、上記の適用時期に関わらず、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する(課税取扱い15)。
(5) 会計方針の変更注記
課税取扱いの適用については、以下の見解に分かれると考えられる。四半期又は中間の注記事例から考えると、会計方針の変更注記の会社もあったが、会計方針の変更注記を記載していない会社の事例の方が多いと推測される。
① グローバル・ミニマム課税は、新たな課税制度ではあるものの、新たな会計基準等の設定による「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更」とし、会計方針の変更注記を行う。
② 従前はグローバル・ミニマム課税がないことから、「新事実の発生に伴う新たな会計処理の採用」と捉えて、会計方針の変更とは扱わない。なお、この場合でも、重要性に応じて追加情報として注記することは考えられる。
2 グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い
グローバル・ミニマム課税制度を導入するための法人税法の改正は数年にわたって行われ、令和6年度の税制改正において所得合算ルール(IIR)が導入され、令和7年度税制改正大綱で、軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)の導入が予定されている(前回参照)。
そこで、ASBJにおいてグローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の取扱いが検討され、2023年3月31日に以下の実務対応報告が公表され、2024年3月22日に改正が行われた。
- 実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(以下、「課税税効果取扱い」という)
(1) 会計処理
課税税効果取扱いの適用を終了するまでの間、連結会計年度及び事業年度の決算における税効果会計の適用にあたっては、「税効果適用指針」の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しない(課税税効果取扱い3)。
四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表並びに中間連結財務諸表及び中間個別財務諸表においても同様である(課税税効果取扱い3-2)。
したがって、法定実効税率もグローバル・ミニマム課税に係る法人税等を含まない税率を使用すると考えられる。
(2) 適用時期
課税税効果取扱いの公表日以後適用する(課税税効果取扱い4-2)。
(3) 注記
課税税効果取扱いを適用した旨の注記は必要ない(課税税効果取扱い16)。