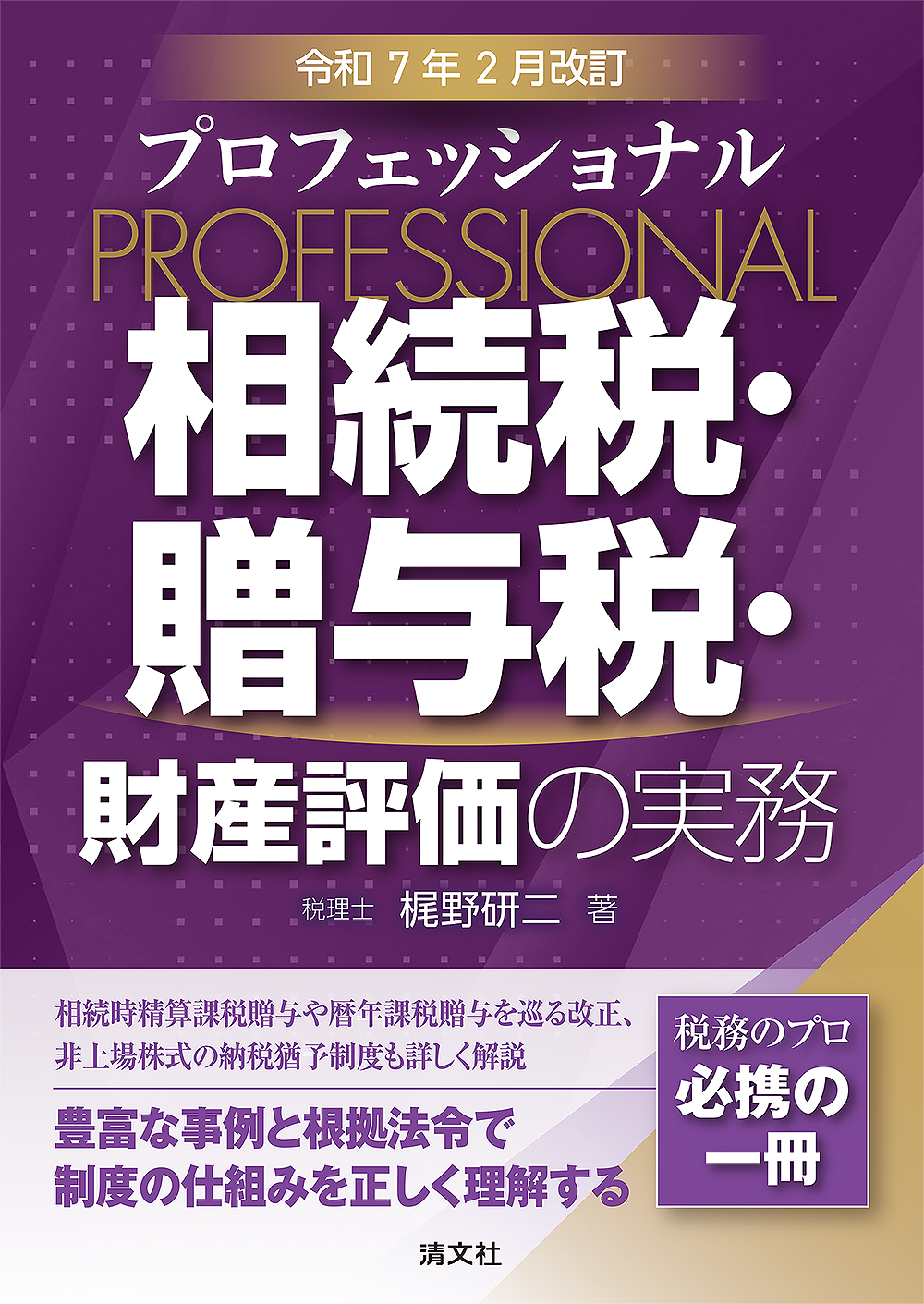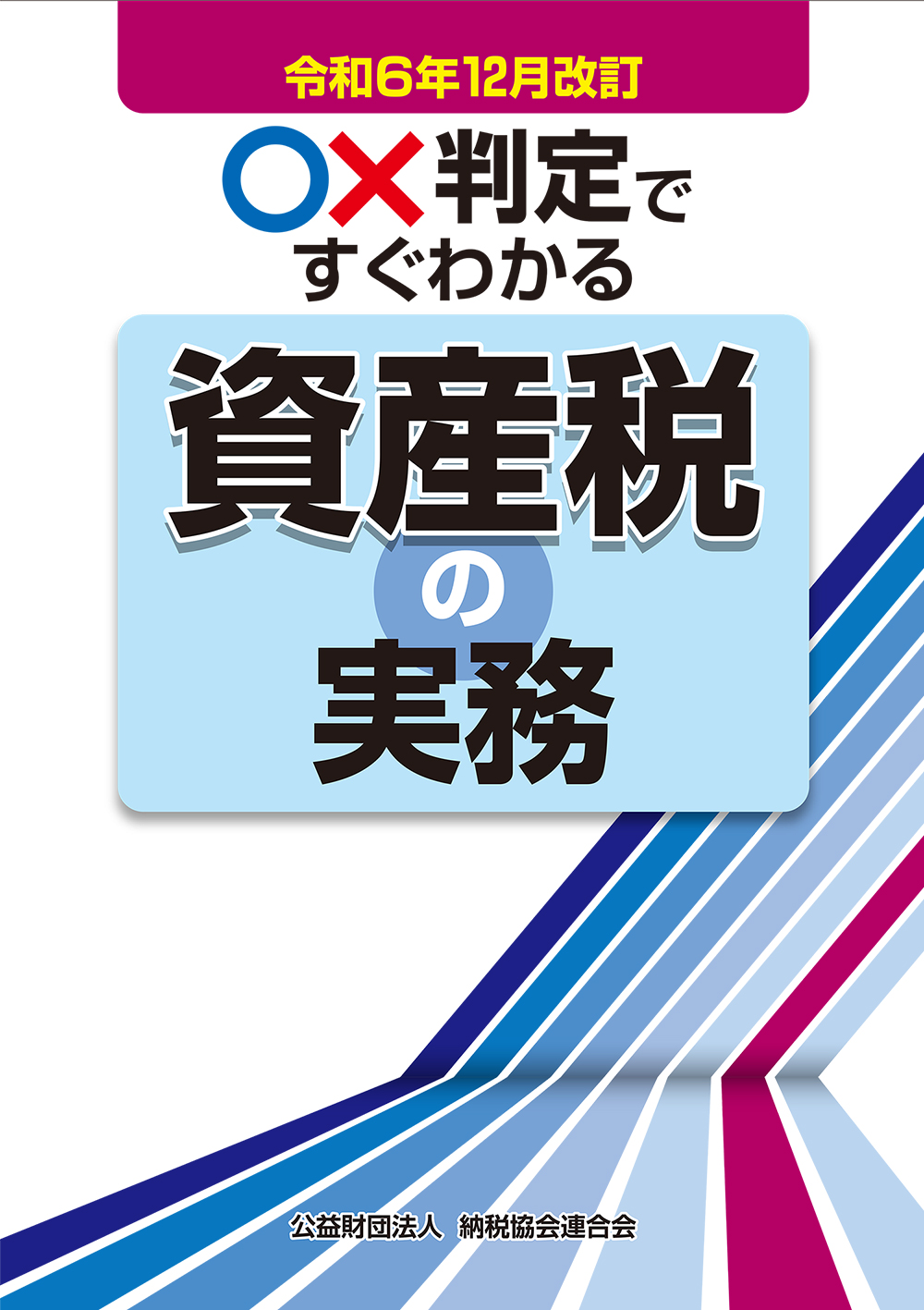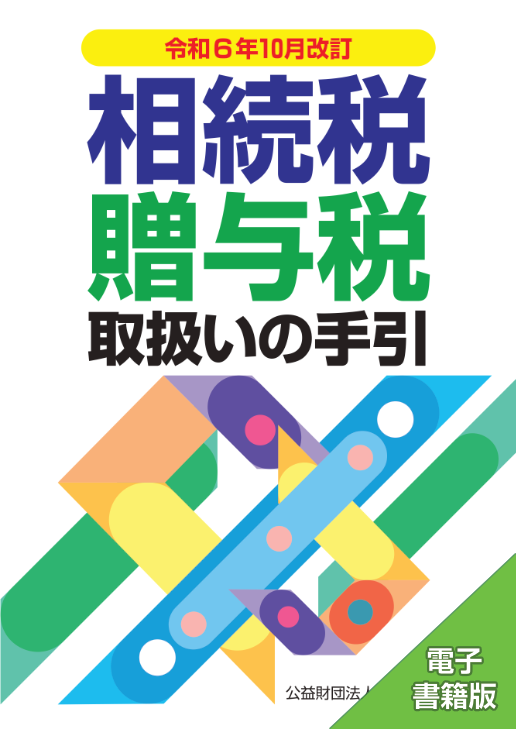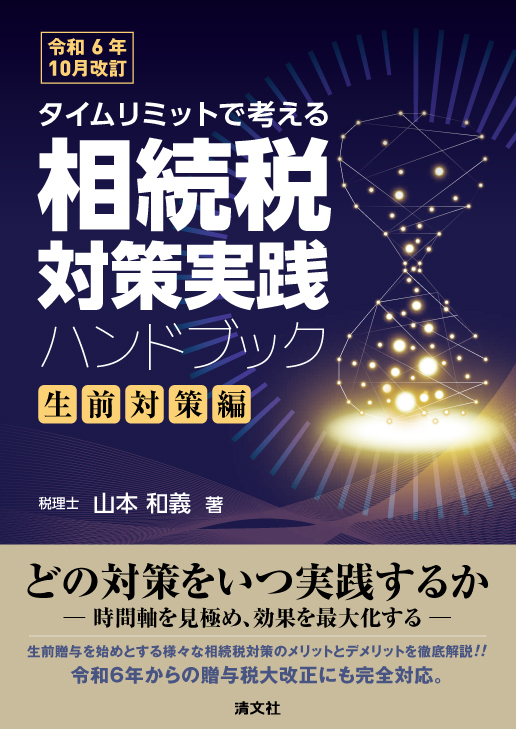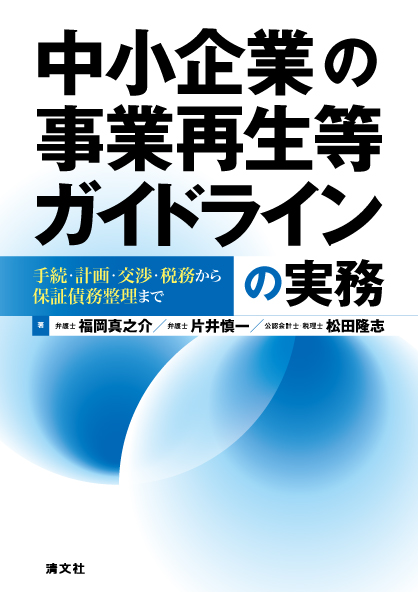〔一問一答〕
税理士業務に必要な契約の知識
【第23回】
「遺留分侵害額請求権と事業承継」
虎ノ門第一法律事務所
弁護士 枝廣 恭子
〔質 問〕
2018年の民法改正で相続法が改正され、それまでの「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」へと変わりました。制度としてどのような違いがあるのでしょうか。また、事業承継を促進することが期待されるとのことですが、具体的にどのような影響が考えられるのでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。